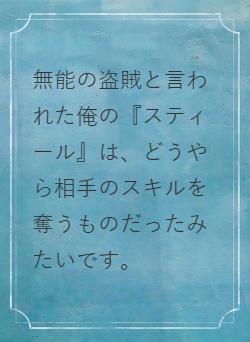「レトルトカレーノアマクチ、パックゴハン、オチャヲフタツズツ」
ご主人様が眠りについたのを確認して、私は監視室のパソコンを使ってその日の分の発注を確定させる
三階の監視カメラに映るご主人様を見つめながらしばらく待つと、注文が届いた通知がパソコンに入ってくる。
「ソレデハ、ホジュウニイキマスカ」
私は誰に言う訳でもなく、そんな言葉を漏らして一人監視室を後にする。
業務用のエレベーターを使って荷物が到着している一階に向かう中、鏡に映っている自分の姿を見てふと考えてしまう。
「イチゴウト、ワタシノナニガチガウ?」
ゴウゴウッと動くエレベーターの中で、私は鏡に映る姿を見てぽろっとそんな言葉を漏らした。
見た目は何も変わらないはずなのに、一号と私の役割は違っていた。一号がご主人様のお世話をするのに対して、私はそれが滞りなく進むために動く黒子だった。
私はさっきまで見つめていた監視カメラの映像を思い出して、顔を俯かせる。
監視からの映像なので声は聞こえないが、声が聞こえなくても分かるくらい二人は仲が良かった。
日に日に仲良くなっていく二人を監視カメラ越しに見て、私はプログラムにはないはずの孤独というモノを覚えた。
自分の存在を知って欲しい、一号のように褒めて欲しい、ご主人様に自分の働きを見て欲しい。
そんな欲求は日に日に大きくなっていくのだった。
ある日、ご主人様と一号が『家電量販店』から出ていってしまった。
「アノオトコト、ドコカニイッタダケデショウ。スグニモドッテキマスヨ」
私はいつもの監視室で、そわそわしながらそんな独り言を漏らしていた。
ご主人様が監視カメラに映っていた男を助けて、その男と共に特定小型原付に乗っていったのも、食料品を多くランドセルに詰めていたのも知っている。
だから、ただ少し遠くに行くだけですぐに帰ってくるのだということは分かっていた。
しかし、一日帰ってこないと、もう二日目以降も帰ってこないのではないかと悪い方にばかり物事を考えてしまっていた。
今まではただ会話をしていないだけで、そこにご主人様がいるのだということは監視カメラ越しに分かっていた。
しかし、『家電量販店』にあるどのカメラを見ても、そこにご主人様の姿はなかった。
そして、このとき私は本当の孤独と向き合うことになった。
何も変わらない『家電量販店』の中で、誰もいない状況で、一人でただ時間が過ぎていく。機械学習のせいで生まれた感情を持つ私には、あまりにも酷な時間だった。
しかし、それから数日経ったある日、『家電量販店』の入口のカメラにご主人様の姿が写った。
「ゴシュジンサマ! カエッテキタ!」
私はご主人様の姿を見るなり、慌ててエスカレーターを駆け下りていった。
この時の感情がどんなものなのかは分からない。孤独な日々がこれで終わるのだと思ったら、無意識のうちに駆け出していた。
そして、監視室から一階に向かおうとエスカレーターを降りた途中、三階で私は重要なことに気がついた。
「ワタシ、ゴシュジンサマニアッテモ、イイノ?」
私の仕事はご主人様が不自由なく生活を送れるサポートをすること。そのためには、今まで通り黒子で裏かをしている方がいいかもしれない。
私はピタリと足を止めて、下りてきたエスカレーターの方に振り返る。
今から業務用のエレベーターに乗れば、ご主人様に気づかれずに監視室に戻ることができる。
……今まで通りそうすべきだ。
そう考えた私は、急いで監視室に向かうべく業務用のエレベーターに向かった。
そして、気がついた時には――私はご主人様が普段使っているベッドの上にいた。
???
おかしい。考えていることと行動が合っていない。
これはバグなのだと思って体を起こそうとしたが、無意識のうちにシーツを強くつかんだ手が離せない。
孤独な一人きりの監視室に戻ろうとしても、体が言うことを聞かなくなっていた。意味が分からない。
しかし、そんな私の考えに反して、何を考えたのかわざとらしく口が動いていた。
「フー。ハッチュウガナイノハイイケド、ダンナサマガイナイト、ヒマダナー」」
寂しすぎて気が狂いそうだから、そろそろ私を見てください。
そんな心の叫びは、恥ずかしすぎる棒読みなトーンで再生された。
そして、私が振り向いた先には、画面越しでずっと見ていたご主人様がいた。
ご主人様は画面越しで見るよりもずっと、可愛い存在だった。
そして、そこで私は今まで感じたことがない温かさを胸のあたりに感じた。これはきっと、寂しさが生んだ心のバグなのだ。
そうでなければおかしいほど、目の間にいるご主人様が愛おしく思えた。
なにこれ⁉ なんで思ったことがすぐポロッと言葉に出て、考えたことがすぐに行動に反映されるの⁉
私が思いもしなかった行動に恥じらいを感じていると、ご主人様が申し訳なさそうに私の仕様変更について教えてくれた。
旦那様は『オタクに優しい明るいギャル系メイド』に性格が寄ってしまったのだと言っているけど、多分違う。
これは、『思わずぽろっと素直なことを口にしちゃうくらい、正直な子』。この設定のせいだ。
でも、そのことを正直に指摘する気はなかった。理由は単純で恥ずかしすぎるからだった。
ご主人様が私を嫌いにならないのなら、素直な気持ちを表に出せるのは嬉しい。それに、ご主人様も今の私の方がいいと言ってくれている。
私は自然と零れ出る笑みを隠せずにいた。
私がそんなことを考えていると、アリスが私のことを指さしてじろっと睨んできた。
「旦那様? なぜあの者を、あんな性の化身のような姿に変えたのですか?」
「せ、性の化身⁉」
ご主人様はアリスの言葉を聞いて、驚いたような目で私を見つめてきた。
私は思いもしなかった言葉を受けて、一気に恥ずかしくなって胸元を両腕で覆った。
しかし、そのときに私は気づいてしまった。
……ご主人様が真剣な目で、恥ずかしがっている私を見つめている。
そういう目で見られているという恥ずかしさと、自分のことを見てくれるという嬉しさが混ざり合って、私の中でトロッとした何かが生まれた気がした。
ご主人様に恥ずかしがっている自分をもっと見てもらいたい。
機械学習で培われたはずのどの感情とも違う、初めての感情が顔を覗かせた気がした。