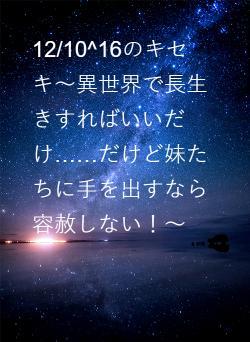やがて甲高い横笛と太鼓の音《ね》が鳴り響くと、それに合わせて烏帽子《えぼし》を被り狩衣《かりぎぬ》を纏った人たちが入ってきた。
そしてそれに続くのは、蛍。
「ほぅ……」
思わず溜息が漏れる。
金色の、シャラシャラした飾りの付いた冠を被り、白粉《おしろい》と紅で化粧を施した蛍は、想像以上に綺麗だった。その身に纏う色とりどりで豪華な着物に着られるような事は無く、高貴さすら感じられる。半端な人間がアレを着ていたとしたら、ただ派手々々しく下品に映っていたかもしれない。
蛍が所定位置につくと、祝詞が捧げられ、儀式が始まった。
粛々と儀式が進められていく。俺はその間、教えられた通りの動作をしながらただ、蛍を見つめていた。
そして、その時が来た。
彼女の身体に神様が降りた瞬間は、全くの部外者である俺にもすぐに分かった。目の前に見えるのは蛍なのに、そこにいるのは全く知らない、別の誰かに思えた。
雰囲気が一変した蛍が口を開く。その声も、俺の知っている蛍の声ではなかった。蛍とは別の意味で美しく、そして力強い声だった。
それからはあっという間に時間が過ぎた。予言の内容はイマイチ覚えていない。だけど、この時の蛍の姿だけは、何年も経った今でもハッキリ思い出せる。
この日の夕食は蛍の家でご馳走になって、そのまま最終便で村まで帰った。蛍も一緒だ。
バスに乗っている間に何か話せればとは思ったが、蛍は疲れて眠ってしまっていた。
翌日、蛍は珍しく昼前まで起きてこなかった。
最終日で少し豪華だった昼食を終えると、蛍は村のみんなに挨拶しに行った。俺もついていこうかと思ったが、断られてしまった。
結局、蛍は夕食の時間まで帰ってこなかった。
夕食を終え、寝る準備をしてから屋根の上に登った。既に空は星に覆われている。
視線の先には、真っ黒な海。見えるものは何もなかった。
そのままぼんやりしていると、すぐ下の窓が開く音がした。蛍だ。
蛍の顔を出した窓のすぐ下には一階部分の屋根がある。そこから俺のいる二階部分の屋根に登って来ようとしていたので、手を貸してやった。
「ふぅ。お婆さんが、祐介が考え事をする時はここだろうって言ってたから」
なんでここに来たのか聞こうとしたら、先に言われた。
「ちょっと、話したいなって思って」
そう言う蛍の体からは少し湯気が立ち昇り、髪も艶っぽい。
「そんな格好じゃ湯冷めするぞ。これでも羽織っとけ」
俺は自分の着ていた上着を蛍に渡してやった。夏とはいえ、海風は冷える。
「ありがとう。……それにしても、ビックリしたよ。急に来るから」
「……悪りぃ」
「全然怒ってないよ! 寧ろ、嬉しかった」
上着は貸してしまった筈なのに、何故か、体はさっきよりも暑い。
「その、なんだ……綺麗だった」
ボソボソとした声で、それだけ言った。
「そ、そりゃあ、神様の衣装だからね!」
「あ、あぁ、そうか。そうだな!」
「……」
「……」
暫くの間沈黙が降りる。
「……私ね、普通に結婚して、普通に子どもを産んで、普通にお婆ちゃんなるのが夢だったんだ」
俺は、蛍の言葉をただ聞いていることしか出来なかった。
「それなのにさ……ねぇ、なんで私だったんだろうね?」
「……」
「……神様って、酷いね」
「……あぁ」
「……祐介、私、死にたくない」
この時初めて俺は、蛍の顔を見た。
泣いていた。
「死にたくないよぉ……!」
ただの高校二年生に過ぎなかったこの時の俺に出来たのは、泣きじゃくる彼女に無言で胸を貸すことだけだった。
暫くすると、すぐ下から寝息が聞こえてきた。泣き疲れてしまったらしい。俺は彼女を部屋まで運んで布団に寝かせると、そのまま部屋へ帰った。
翌朝、俺の家の客間には時間がとれた何人かの村人が集まっていた。蛍を見送るためだ。
少し早めの昼食ということで簡単な宴会を開き、今回の企画の全行程が終わりとなる。その間、俺は蛍と一言も話していない。
そしていよいよ、帰りのバスの時間となった。
「以上を持ちまして、私のどもの提供する全てのプランを終了とさせていただきます。幸見《さきみ》様、ご利用ありがとうございました」
案内役だった俺が代表して告げる。
「……こちらこそ、楽しかったです。ありがとうございました」
彼女が、玄関を出て歩いて行く。これでもう、彼女とは会えない……。
「……良かったのか?」
少ししてから客間に戻ると、祖父がそう聞いてきた。
「……爺ちゃん、片付け任せていいか?」
「おぅ、行ってこい」
俺は慌てて靴を履き、駆け出す。丘の下の方、海岸近くに、白いワンピースと水色のキャリーケースが見えた。
少しショートカットをして、転けそうになりながらも一気に坂を駆け下りる。
バス停に着いた時、ちょうどバスが来たところだった。
良かった。なんとか間に合った。
「待って!」
彼女が乗り込もうとした足を止めて、振り返る。
「はぁはぁ…………俺、ほたるが好きだ。また、見に行こう!」
彼女が微笑んだ。
「うん、私もよ」
そう言って彼女は、バスに乗り込んでいった。
この日以来、俺は彼女と話していない。