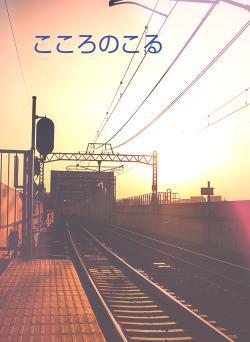三人の共通の話題といえば、やはり高校時代のことだった。
「今さらながら。リクはなんで放課後練習の時いつも、運動部ちゃうのに、ジャージを着てきてたんや」
ミウも自然とリクに目を向けてくる。あのころと変わらない、大きめの黒目が二つ、そこにあって、リクは言葉に詰まった。
「ボーカリストは、あれだよ、ある意味アスリートだからさ」
「そやな。リクは速い曲になると、歌いながら謎の激しいダンスをしてたもんな」
おぼえているのだろう、ミウは目を細めて、うんうんと頷く。
リクは、首と片手を横に振った。
「いや、そういうことじゃなくて。その方がリズム取りやすかったんだよ」
「でもな、最後のステージで、あれはないやろ。K高のジャージでアレ歌われても説得力ないで」
「うう、たしかに」
ミウが弾けたように笑い声を立てた。
「ほな、そのくせ、土日は普通に制服着てきて、あれは何やったん」
ソラが横目でリクを見てから、うまそうにパスタをほおばった。
リクは遠い日のことでも今でも愛着があるのだろう、難なく鮮明に記憶を引き出せる。
「お袋が勝手に洗濯してしまってな。何べん言っても、休みの日はいらんのちゃうのって」
ソラが思わず吹き出す。
「そら、きついな!」
「今さらながら。リクはなんで放課後練習の時いつも、運動部ちゃうのに、ジャージを着てきてたんや」
ミウも自然とリクに目を向けてくる。あのころと変わらない、大きめの黒目が二つ、そこにあって、リクは言葉に詰まった。
「ボーカリストは、あれだよ、ある意味アスリートだからさ」
「そやな。リクは速い曲になると、歌いながら謎の激しいダンスをしてたもんな」
おぼえているのだろう、ミウは目を細めて、うんうんと頷く。
リクは、首と片手を横に振った。
「いや、そういうことじゃなくて。その方がリズム取りやすかったんだよ」
「でもな、最後のステージで、あれはないやろ。K高のジャージでアレ歌われても説得力ないで」
「うう、たしかに」
ミウが弾けたように笑い声を立てた。
「ほな、そのくせ、土日は普通に制服着てきて、あれは何やったん」
ソラが横目でリクを見てから、うまそうにパスタをほおばった。
リクは遠い日のことでも今でも愛着があるのだろう、難なく鮮明に記憶を引き出せる。
「お袋が勝手に洗濯してしまってな。何べん言っても、休みの日はいらんのちゃうのって」
ソラが思わず吹き出す。
「そら、きついな!」