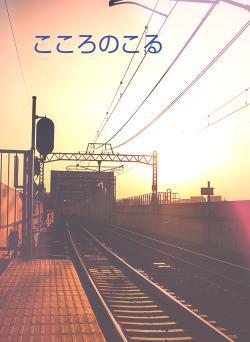地下一階、80平米くらいの小さなライブハウス。
薄暗いステージにスポットライトが当たる。
リクがボーカルマイクのスタンドに両手をあてがい、高さと角度を決め直すと小さく振り向いた。
ドラムのテツが、ゆっくり「ワーン、ツー、スリ」とカウントを取り、「フォー」のタイミングでクロベエのベースが絡んでゆく。そして、さらにソラのギターアルペジオが乗っかった。
イントロがやや長い、ミディアムテンポの曲。
もう四人で何度もやってきた曲だった。
音に寸分のよどみもない。
ステージ中央でマイクスタンドに凭れるようにして立っているリクが、額にかかる前髪の下で瞳を閉じたまま、かすれた声でささやくように歌い始めた。
『明けない夜はないけれど
止まない雨ならあるでしょう
キミのその凍えそうな身体を
温める太陽みたくボクがなれたなら
きっといいな
たとえば一人ぼっちになって
高く冷たい壁に囲まれて
そんなときはボクのこの歌を
キミが思い出してくれたなら
もっといいな
壁の上から伸ばす
ボクの手が見えると思うんだ
時は 片時も止まらないから
ボクはいつまでも
この歌を歌いつづけてる
キミがいつかボクの前から消えてしまうまで
キミのために そう
ボクだけの SONG』
リクが胸に描く景色にはいつも、笑い声を立てながら背中にかかる長い髪を揺らすミウの端正な横顔があった。
そのミウが今日ここへ来ているはずだが、スポットの光を顔に浴びているリクからかろうじて見える客席は、誰を誰とも特定できない人影の集まりでしかない。
最後のフレーズをリクがため息のようにささやき声で歌い上げたあと、まもなくテツは徐々にリズムをスローダウンさせた。
それに合わせてソラが、ギターのネックをゆっくりと起こしていき、やがて垂直になると、音を溜めたハイトーンのリフを紡いだ。
曲は、その残響音で終わった。
薄暗いステージにスポットライトが当たる。
リクがボーカルマイクのスタンドに両手をあてがい、高さと角度を決め直すと小さく振り向いた。
ドラムのテツが、ゆっくり「ワーン、ツー、スリ」とカウントを取り、「フォー」のタイミングでクロベエのベースが絡んでゆく。そして、さらにソラのギターアルペジオが乗っかった。
イントロがやや長い、ミディアムテンポの曲。
もう四人で何度もやってきた曲だった。
音に寸分のよどみもない。
ステージ中央でマイクスタンドに凭れるようにして立っているリクが、額にかかる前髪の下で瞳を閉じたまま、かすれた声でささやくように歌い始めた。
『明けない夜はないけれど
止まない雨ならあるでしょう
キミのその凍えそうな身体を
温める太陽みたくボクがなれたなら
きっといいな
たとえば一人ぼっちになって
高く冷たい壁に囲まれて
そんなときはボクのこの歌を
キミが思い出してくれたなら
もっといいな
壁の上から伸ばす
ボクの手が見えると思うんだ
時は 片時も止まらないから
ボクはいつまでも
この歌を歌いつづけてる
キミがいつかボクの前から消えてしまうまで
キミのために そう
ボクだけの SONG』
リクが胸に描く景色にはいつも、笑い声を立てながら背中にかかる長い髪を揺らすミウの端正な横顔があった。
そのミウが今日ここへ来ているはずだが、スポットの光を顔に浴びているリクからかろうじて見える客席は、誰を誰とも特定できない人影の集まりでしかない。
最後のフレーズをリクがため息のようにささやき声で歌い上げたあと、まもなくテツは徐々にリズムをスローダウンさせた。
それに合わせてソラが、ギターのネックをゆっくりと起こしていき、やがて垂直になると、音を溜めたハイトーンのリフを紡いだ。
曲は、その残響音で終わった。