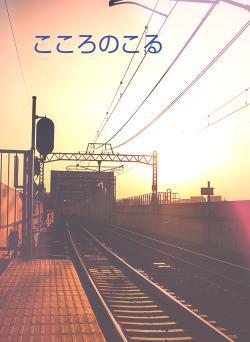新天地でも一週間もすると、だんだんその店特有の仕事の流れや、取り巻く人間の人柄が見えてきたりもするものだ。
精肉課には、正社員は片倉の他に、鵜川と大橋の二人がいる。
鵜川は、身体が丸々とした猫背気味の五十代とおぼしき男だった。
寡黙で、いつも作業台の横幅一メートルほどの大きなまな板に向かい、肉に包丁を入れている。
時々、作業場の角にあるスライスの機械を操り、薄切り肉や切り落とし肉をバットに切り置き、それがいっぱいになるごとにトレイにきれいに詰めて三段カートに並べるまでが彼の通常業務だった。
大橋は、今春の新卒入社で、ちょうど三か月目だった。
円いフレームの黒縁眼鏡を掛けて愛嬌のある顔立ちの青年だったが、鵜川とは対称的に身体の線はひょろっとしていて、まだ学生の気分が抜けないのか、何事にも気後れしているような態度だった。
蚊の鳴くような話し声で、まるで騒ぐようにやり取りをしている片倉やパートらと作業場にいると、必ず壁際に突っ立って、自分の存在感を消そうとしているようにさえ見えた。
あくまでソラの主観だが、おっとりした大橋には、スピーディで荒っぽく刃物がそこらできらめく典型的な3Kの生鮮職場よりも、上階のアパレルや文具売り場の方が、似合っていそうだった。
精肉課には、正社員は片倉の他に、鵜川と大橋の二人がいる。
鵜川は、身体が丸々とした猫背気味の五十代とおぼしき男だった。
寡黙で、いつも作業台の横幅一メートルほどの大きなまな板に向かい、肉に包丁を入れている。
時々、作業場の角にあるスライスの機械を操り、薄切り肉や切り落とし肉をバットに切り置き、それがいっぱいになるごとにトレイにきれいに詰めて三段カートに並べるまでが彼の通常業務だった。
大橋は、今春の新卒入社で、ちょうど三か月目だった。
円いフレームの黒縁眼鏡を掛けて愛嬌のある顔立ちの青年だったが、鵜川とは対称的に身体の線はひょろっとしていて、まだ学生の気分が抜けないのか、何事にも気後れしているような態度だった。
蚊の鳴くような話し声で、まるで騒ぐようにやり取りをしている片倉やパートらと作業場にいると、必ず壁際に突っ立って、自分の存在感を消そうとしているようにさえ見えた。
あくまでソラの主観だが、おっとりした大橋には、スピーディで荒っぽく刃物がそこらできらめく典型的な3Kの生鮮職場よりも、上階のアパレルや文具売り場の方が、似合っていそうだった。