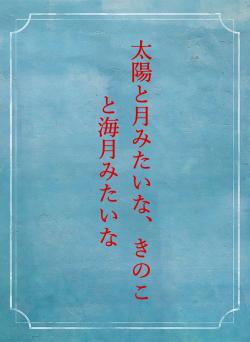5.
美月は嫌がったらしいが、その日の夜に、陽菜は帰宅した俊明さんに今日のことを伝えた。
俊明さんは、陽菜の話を聞くと、わかったと一言いい、それから、八月になったら行う予定だった検査を一週間繰り上げてまた今週の土曜日に行なおうと美月に提案した。
僕は陽菜から、そのことを夜に電話で聞かされ、土曜日の再検査は奏も付き添ってほしいと頼まれた。
僕は「あたりまえだろ」と陽菜に返した。
***
土曜日。僕たちは再び俊明さんが待つ病院に三人で向かった。
美月は着くなり、すぐに脳波測定の検査に入った。またお決まりのMRI、CT、脳波測定などだった。
僕と陽菜は検査を待つあいだに俊明さんの診察室に呼ばれた。
僕は美月のいないところで俊明さんと話すのに嫌な思い出が蘇った。美月の最初の入院検査のときに俊明さんと僕でナースステーション横のプレイルームで話したときのことを僕は思い出していた。
俊明さんは僕たちが診察室に入るとすぐにカルテや資料を出して説明した。
「先週の美月の検査結果だ」
僕は俊明さんから美月の脳波図を渡された。
「きちんといおう。美月の脳波図からピーク時ほどではないが、入院時に観測されていた波形と同じ波形が検出されている」
俊明さんは感情を交えずに言う。
「つまり、美月の脳で、扁桃体と海馬を中心に、微弱だが例の第六の波形が再び観測されているんだ。このことが感情や記憶の異常となりその症候を引き起こしていると考えられる。今美月の脳は感情と記憶を結びつける機能の過剰な活発化が再び始まろうとしているんだ」
奏くん、俊明さんは僕にそう呼びかけた。
「美月に現れている第六の波形を観測した症例はこれまで世界的に三例だと言ったね。そして一度心停止してその一時間後に蘇った美月は、もはやこの三例の症例ケースを越えて独自の領域に入っていると」
「はい」
僕は俊樹さんの言葉に答えた。
俊明さんは僕の返事を確認して続けた。
「症例ケース1は脳のなかでも、匂い、つまり嗅覚を司る第一脳神経から内嗅皮質において最も特徴的にこの特異な波形が観測されている。そして第二の症例ケースにおいては視床下部、ここは感情と関係の深い箇所だが、そこが中心となって第六の波形が観測された」
隣りの陽菜は部屋に入ってからなにも言わずにただ黙っていた。
「繰り返すが、第四症例となる美月の症例はもはや他の三つの症例とは、大幅に異なる状況となっている。けれど、前例となる三例のうち、一例だけ異常脳波が観測されている脳部位が極めて酷似している例があるんだ」
僕は俊明さんの説明を理解していることを示すために言った。
「三例目ですね? 今回の美月の脳波と類似しているのが、その三つ目の症例なんですね」
俊明さんは頷く。
唇をギュッと引き結び、手元の紙束を握る手は少し緊張したように強まっていた。
「そのとおりだ。三つ目の症例では、扁桃体を中心とした系、つまり記憶だ。記憶を司る脳部位を中心とした箇所から第六の波形が主だって観測された。この症例患者では、主症状として記憶力の異常な発達が見られた。そしてそれに付随するように情動の混乱、自己認識の不安定化などが発生した。そして……」
俊明さんは手元の紙をめくりながら話した。髪の擦れる不協和音が耳に響くたびに僕は頭蓋骨の奥の柔らかな部分に直接触れられ、そして心臓が鼓動とともに傷つけられるような気がした。
「そして最終的に最初の二症例と同様に、この第三の症例も異常波形が神経ネットワーク全体に伝播し、脳の各部位が互いに異常な信号を送り合い始めた。まるで自己崩壊のように、脳全体がオーバーフローに陥り、最終的には機能不全に至ったんだ」
俊明さんは第三の症例をそんなふうに説明した。隣りでずっと顔を上げずに俯いていた陽菜が口元だけ動かして小さく囁いた。
「お母さん」
俊明さんはその小さな声に気がついて、話すのを一瞬やめた。それから陽菜は相変わらず顔を床に向けたまま言った。
「お母さんは最後はなにも忘れられなくなっていた」
俊明さんは頷いた。そして最後に手元の紙を診察台のうえに置くと、僕の方に向き直って言った。
「そうだ、この美月の症例に最も近いケースは、わたしの妻……」
それはつまり……、僕は俊明さんの話す言葉を聞きながら、声に出さず当たり前のことをなぜかぼんやりと頭で確認しようとした。
しかし俊明さんがはっきりとそれを口にした。
「それはつまり、美月の母親だ」
***
俊明さんの話を診察室で聞いていると、診察室の内線が鳴った。俊明さんは看護師からの連絡を聞くと、美月の検査が終わったらしい、と僕らに告げた。
「美月は今、どこですか?」
俊明さんは答えた。
「美月は今、寝ているよ。たぶん、今週はあまり寝れていなかったんだろう。検査が終わって緊張の糸が切れたんだ、心配しなくても大丈夫だ。看護師長が空いているベッドを使わせてくれているようだ、病室を教えるよ」
俊明さんは僕と陽菜に病室の部屋番号を告げた。
「すまないが検査結果を早く確認したいから、中座させてもらうよ。先に美月の病室で待っていてくれ、本人のいるところでこの続きは話そう」
俊明さんと僕たちはそういって診察室を出て、別れた。
僕たちは俊明さんから告げられた番号の病室に向かった。診察室がある棟から離れた場所で以前入院していた棟とも異なって三階だった。
僕と陽菜は病室に向かうまで会話はなく、エレベータのなかではシャフトを上がるわずかな音が間延びしたように響いた。
それからフロアの廊下を進んで、美月のいる病室に辿りついた。
俊明さんがいったように美月はベッドの上で横になって寝ていた。
陽菜は声をかけようとしたが、僕は彼女の腕をひいて、それを制した。いまは美月を安らかにさせておくべきだと思ったのだ。
陽菜は僕の意図を理解すると検査のまえに姉から預かっていたライトグリーンのハンドバッグを棚のうえの置いた。それからそっと起こさないように両手でベッドのサイドレールを握ってその表情を覗き込んだ。
美月はただ意識を深く落として、その寝顔には不安も苦痛もなく穏やかそのものだった。
「わたしたちが小学生のときにママが病気で死んじゃったのは聞いてるよね」
陽菜は静かに眠っている美月には届かないように小さな声で話した。
「ああ。陽菜は美月がお母さんと同じ症状だって知っていたのか?」
陽菜は僕の質問に首を振った。
「ううん。お父さんからその話は今日初めて聞いた。でも、お姉ちゃんみてたら、なんとなく近いなっていうか、思わせるようなところはあったから、なるほどなって思った。たぶん、お姉ちゃんもおんなじような感じだと思う」
陽菜はベッドの姉から目線を逸さなかった。
「ママが病気だってわかったとき、最初はそんな深刻なことだと思ってなかったの……。ママが仕事でずーっと集中して曲を作っているときも同じようなことってよくあったから」
陽菜はそう切り出して自分の記憶を辿っているようだった。
「ママの症状が出始めたときもちょうどこの前のお姉ちゃんみたいにすごく細かいことを覚えていたり、なのにすごく当たり前のことを逆に忘れたり、全然思い出せなかったり、頭のなかの記憶がグチャグチャになってるみたいだった。最初はママのいつもの天然なのかなって思ってたんだ」
陽菜は思い出すように目を細め、苦笑いを浮かべた。
「でも、そのときママが一晩かけて作った曲を聴かせてもらったんだ。そうしたら、その曲、どこかで聴いたことがあるなと思ったら、二十年前にママがデビューしたときに作った曲と一音も違わずに同じだったの。でも、ママ自身は全然それに気づいてないみたいで、お姉ちゃんと二人でおかしいなって」
陽菜は当時の不安が蘇ったのかベッドのサイドレールを強く握った。
「そのときは、まあ、ママも昔作った曲を忘れちゃってるのかなって……。でもね、だんだん様子が変わっていったの。ママが突然、記譜の方法や楽譜の読み方を忘れて、私たちに聞いてきた。ママは音楽のすごい基本的なことをすっかり忘れちゃったの。それでも、なぜか曲だけは作れるみたいで、でも、その曲もやっぱり昔の作品とまったく同じだったり、同じフレーズを何度も繰り返したり、ひどいものだと無秩序でなんの調性もない音符の羅列が何小節も続いたりしていた」
はっきりいって、あの頃のママはちょっと不安定なところもあって怖かった。
陽菜は記憶の狭間にそう付け加えた。
異常波形が神経ネットワーク全体に伝播し、脳の各部位が互いに異常な信号を送り合い始めた。まるで自己崩壊のように、脳全体がオーバーフローに陥り、最終的には機能不全に至った。僕は俊明さんのさっきの説明を反芻していた。
「そのうち、ママは参考にしたいからって私たちに過去の演奏を頼むようになったの。あのときの何年何月のあの演奏のあの一音をもう一度鍵盤で押してみてくれない? って、すごく具体的に頼まれた。私たちが楽譜を見てその一音を弾いても、ママは、それじゃない、もっとこうだったって……。私たちは何度も何度も弾くんだけど、何が違うのかわからなくて、でもママはすごく必死に、あのときの音を再現してほしいのって、どうしても譲らなくて……」
陽菜は言葉を詰まらせて、一度唇を噛んだ。
僕は母さんに父と全く同じ演奏をするように怒鳴りつけられた日々が脳裏に蘇った。
母さんは最後には何もかも忘れて、自分を喪った。
けれど美月の母は何もかも忘れられずに、自分を喪っていったのだ。
僕はそこにとても嫌な皮肉を感じた。それはとてもとても嫌な皮肉だった。
「それでパパがママを病院で診て、ママの入院が決まったの。ママはそれから忘れられなくなっていった。大事なことも、どうでもいいことも、全部が頭に詰め込まれて……忘れることができなくなっちゃったの。だんだん記憶に支配されていって、たくさんの思い出や過去が押し寄せて、それを思い出している自分というのが定まらなくて、わからなくなっちゃうことが頻繁に起きた。ママは押し寄せる記憶のなかである日は二〇年前の二十歳の自分、でも別の日には子どもの時の六歳の自分になったりした」
陽菜は母親の最後の様子を話した。
僕は陽菜の話を聞きながら、美月の母親に生じた感覚を想像してみた。
それはまるで目や耳が自分に無数に増えたようだった。あらゆる楽器で鳴らした音が一斉に一つしかない脳に流れ込む。どれが自分が聴いている音か、鳴らしている音がなにもわからなくなって、やがて聴いている自分が誰かもわからなくなってしまう、そんな感覚。
「最後に死んじゃうまえには、これまでの感じた記憶の感覚も全部思い出して忘れられなくなって、今自分が聴いている音が、過去にかつて聴いていた記憶の音と区別がつけられなくなって、自分がいまいつどこで生きてるかわからなくっなっちゃった」
やがて記憶のなかで現在も過去も、時間が喪われる。最後には未来すらも。
陽菜は最後に僕にこう問いかけた。
「お姉ちゃんはいまなにか夢を見ているのかな」
美月はいま暗闇のなかで何をみているのだろうか。
僕は美月の寝顔を見て、彼女がいまいる場所のことを想像した。
美月はいまなにか夢でもみているのだろうか。
それとも何もみずにただ真っ黒な光景を見ているのだろうか。
あるいはハレーションを起こしたような真っ白。
真っ白な闇を。
その白い光で埋め尽くされた景色ではどんな音が響いているのだろうか。
土曜日の午後の病室はほとんど見舞客もいなくて、静かで風が吹く音も聴こえなかった。そしてようやく僕らの話し声に気がついて美月は目を覚ました。
目覚めたばかりの美月の目は虚ろでただ外界を写すだけの鏡のようだった。
美月は嫌がったらしいが、その日の夜に、陽菜は帰宅した俊明さんに今日のことを伝えた。
俊明さんは、陽菜の話を聞くと、わかったと一言いい、それから、八月になったら行う予定だった検査を一週間繰り上げてまた今週の土曜日に行なおうと美月に提案した。
僕は陽菜から、そのことを夜に電話で聞かされ、土曜日の再検査は奏も付き添ってほしいと頼まれた。
僕は「あたりまえだろ」と陽菜に返した。
***
土曜日。僕たちは再び俊明さんが待つ病院に三人で向かった。
美月は着くなり、すぐに脳波測定の検査に入った。またお決まりのMRI、CT、脳波測定などだった。
僕と陽菜は検査を待つあいだに俊明さんの診察室に呼ばれた。
僕は美月のいないところで俊明さんと話すのに嫌な思い出が蘇った。美月の最初の入院検査のときに俊明さんと僕でナースステーション横のプレイルームで話したときのことを僕は思い出していた。
俊明さんは僕たちが診察室に入るとすぐにカルテや資料を出して説明した。
「先週の美月の検査結果だ」
僕は俊明さんから美月の脳波図を渡された。
「きちんといおう。美月の脳波図からピーク時ほどではないが、入院時に観測されていた波形と同じ波形が検出されている」
俊明さんは感情を交えずに言う。
「つまり、美月の脳で、扁桃体と海馬を中心に、微弱だが例の第六の波形が再び観測されているんだ。このことが感情や記憶の異常となりその症候を引き起こしていると考えられる。今美月の脳は感情と記憶を結びつける機能の過剰な活発化が再び始まろうとしているんだ」
奏くん、俊明さんは僕にそう呼びかけた。
「美月に現れている第六の波形を観測した症例はこれまで世界的に三例だと言ったね。そして一度心停止してその一時間後に蘇った美月は、もはやこの三例の症例ケースを越えて独自の領域に入っていると」
「はい」
僕は俊樹さんの言葉に答えた。
俊明さんは僕の返事を確認して続けた。
「症例ケース1は脳のなかでも、匂い、つまり嗅覚を司る第一脳神経から内嗅皮質において最も特徴的にこの特異な波形が観測されている。そして第二の症例ケースにおいては視床下部、ここは感情と関係の深い箇所だが、そこが中心となって第六の波形が観測された」
隣りの陽菜は部屋に入ってからなにも言わずにただ黙っていた。
「繰り返すが、第四症例となる美月の症例はもはや他の三つの症例とは、大幅に異なる状況となっている。けれど、前例となる三例のうち、一例だけ異常脳波が観測されている脳部位が極めて酷似している例があるんだ」
僕は俊明さんの説明を理解していることを示すために言った。
「三例目ですね? 今回の美月の脳波と類似しているのが、その三つ目の症例なんですね」
俊明さんは頷く。
唇をギュッと引き結び、手元の紙束を握る手は少し緊張したように強まっていた。
「そのとおりだ。三つ目の症例では、扁桃体を中心とした系、つまり記憶だ。記憶を司る脳部位を中心とした箇所から第六の波形が主だって観測された。この症例患者では、主症状として記憶力の異常な発達が見られた。そしてそれに付随するように情動の混乱、自己認識の不安定化などが発生した。そして……」
俊明さんは手元の紙をめくりながら話した。髪の擦れる不協和音が耳に響くたびに僕は頭蓋骨の奥の柔らかな部分に直接触れられ、そして心臓が鼓動とともに傷つけられるような気がした。
「そして最終的に最初の二症例と同様に、この第三の症例も異常波形が神経ネットワーク全体に伝播し、脳の各部位が互いに異常な信号を送り合い始めた。まるで自己崩壊のように、脳全体がオーバーフローに陥り、最終的には機能不全に至ったんだ」
俊明さんは第三の症例をそんなふうに説明した。隣りでずっと顔を上げずに俯いていた陽菜が口元だけ動かして小さく囁いた。
「お母さん」
俊明さんはその小さな声に気がついて、話すのを一瞬やめた。それから陽菜は相変わらず顔を床に向けたまま言った。
「お母さんは最後はなにも忘れられなくなっていた」
俊明さんは頷いた。そして最後に手元の紙を診察台のうえに置くと、僕の方に向き直って言った。
「そうだ、この美月の症例に最も近いケースは、わたしの妻……」
それはつまり……、僕は俊明さんの話す言葉を聞きながら、声に出さず当たり前のことをなぜかぼんやりと頭で確認しようとした。
しかし俊明さんがはっきりとそれを口にした。
「それはつまり、美月の母親だ」
***
俊明さんの話を診察室で聞いていると、診察室の内線が鳴った。俊明さんは看護師からの連絡を聞くと、美月の検査が終わったらしい、と僕らに告げた。
「美月は今、どこですか?」
俊明さんは答えた。
「美月は今、寝ているよ。たぶん、今週はあまり寝れていなかったんだろう。検査が終わって緊張の糸が切れたんだ、心配しなくても大丈夫だ。看護師長が空いているベッドを使わせてくれているようだ、病室を教えるよ」
俊明さんは僕と陽菜に病室の部屋番号を告げた。
「すまないが検査結果を早く確認したいから、中座させてもらうよ。先に美月の病室で待っていてくれ、本人のいるところでこの続きは話そう」
俊明さんと僕たちはそういって診察室を出て、別れた。
僕たちは俊明さんから告げられた番号の病室に向かった。診察室がある棟から離れた場所で以前入院していた棟とも異なって三階だった。
僕と陽菜は病室に向かうまで会話はなく、エレベータのなかではシャフトを上がるわずかな音が間延びしたように響いた。
それからフロアの廊下を進んで、美月のいる病室に辿りついた。
俊明さんがいったように美月はベッドの上で横になって寝ていた。
陽菜は声をかけようとしたが、僕は彼女の腕をひいて、それを制した。いまは美月を安らかにさせておくべきだと思ったのだ。
陽菜は僕の意図を理解すると検査のまえに姉から預かっていたライトグリーンのハンドバッグを棚のうえの置いた。それからそっと起こさないように両手でベッドのサイドレールを握ってその表情を覗き込んだ。
美月はただ意識を深く落として、その寝顔には不安も苦痛もなく穏やかそのものだった。
「わたしたちが小学生のときにママが病気で死んじゃったのは聞いてるよね」
陽菜は静かに眠っている美月には届かないように小さな声で話した。
「ああ。陽菜は美月がお母さんと同じ症状だって知っていたのか?」
陽菜は僕の質問に首を振った。
「ううん。お父さんからその話は今日初めて聞いた。でも、お姉ちゃんみてたら、なんとなく近いなっていうか、思わせるようなところはあったから、なるほどなって思った。たぶん、お姉ちゃんもおんなじような感じだと思う」
陽菜はベッドの姉から目線を逸さなかった。
「ママが病気だってわかったとき、最初はそんな深刻なことだと思ってなかったの……。ママが仕事でずーっと集中して曲を作っているときも同じようなことってよくあったから」
陽菜はそう切り出して自分の記憶を辿っているようだった。
「ママの症状が出始めたときもちょうどこの前のお姉ちゃんみたいにすごく細かいことを覚えていたり、なのにすごく当たり前のことを逆に忘れたり、全然思い出せなかったり、頭のなかの記憶がグチャグチャになってるみたいだった。最初はママのいつもの天然なのかなって思ってたんだ」
陽菜は思い出すように目を細め、苦笑いを浮かべた。
「でも、そのときママが一晩かけて作った曲を聴かせてもらったんだ。そうしたら、その曲、どこかで聴いたことがあるなと思ったら、二十年前にママがデビューしたときに作った曲と一音も違わずに同じだったの。でも、ママ自身は全然それに気づいてないみたいで、お姉ちゃんと二人でおかしいなって」
陽菜は当時の不安が蘇ったのかベッドのサイドレールを強く握った。
「そのときは、まあ、ママも昔作った曲を忘れちゃってるのかなって……。でもね、だんだん様子が変わっていったの。ママが突然、記譜の方法や楽譜の読み方を忘れて、私たちに聞いてきた。ママは音楽のすごい基本的なことをすっかり忘れちゃったの。それでも、なぜか曲だけは作れるみたいで、でも、その曲もやっぱり昔の作品とまったく同じだったり、同じフレーズを何度も繰り返したり、ひどいものだと無秩序でなんの調性もない音符の羅列が何小節も続いたりしていた」
はっきりいって、あの頃のママはちょっと不安定なところもあって怖かった。
陽菜は記憶の狭間にそう付け加えた。
異常波形が神経ネットワーク全体に伝播し、脳の各部位が互いに異常な信号を送り合い始めた。まるで自己崩壊のように、脳全体がオーバーフローに陥り、最終的には機能不全に至った。僕は俊明さんのさっきの説明を反芻していた。
「そのうち、ママは参考にしたいからって私たちに過去の演奏を頼むようになったの。あのときの何年何月のあの演奏のあの一音をもう一度鍵盤で押してみてくれない? って、すごく具体的に頼まれた。私たちが楽譜を見てその一音を弾いても、ママは、それじゃない、もっとこうだったって……。私たちは何度も何度も弾くんだけど、何が違うのかわからなくて、でもママはすごく必死に、あのときの音を再現してほしいのって、どうしても譲らなくて……」
陽菜は言葉を詰まらせて、一度唇を噛んだ。
僕は母さんに父と全く同じ演奏をするように怒鳴りつけられた日々が脳裏に蘇った。
母さんは最後には何もかも忘れて、自分を喪った。
けれど美月の母は何もかも忘れられずに、自分を喪っていったのだ。
僕はそこにとても嫌な皮肉を感じた。それはとてもとても嫌な皮肉だった。
「それでパパがママを病院で診て、ママの入院が決まったの。ママはそれから忘れられなくなっていった。大事なことも、どうでもいいことも、全部が頭に詰め込まれて……忘れることができなくなっちゃったの。だんだん記憶に支配されていって、たくさんの思い出や過去が押し寄せて、それを思い出している自分というのが定まらなくて、わからなくなっちゃうことが頻繁に起きた。ママは押し寄せる記憶のなかである日は二〇年前の二十歳の自分、でも別の日には子どもの時の六歳の自分になったりした」
陽菜は母親の最後の様子を話した。
僕は陽菜の話を聞きながら、美月の母親に生じた感覚を想像してみた。
それはまるで目や耳が自分に無数に増えたようだった。あらゆる楽器で鳴らした音が一斉に一つしかない脳に流れ込む。どれが自分が聴いている音か、鳴らしている音がなにもわからなくなって、やがて聴いている自分が誰かもわからなくなってしまう、そんな感覚。
「最後に死んじゃうまえには、これまでの感じた記憶の感覚も全部思い出して忘れられなくなって、今自分が聴いている音が、過去にかつて聴いていた記憶の音と区別がつけられなくなって、自分がいまいつどこで生きてるかわからなくっなっちゃった」
やがて記憶のなかで現在も過去も、時間が喪われる。最後には未来すらも。
陽菜は最後に僕にこう問いかけた。
「お姉ちゃんはいまなにか夢を見ているのかな」
美月はいま暗闇のなかで何をみているのだろうか。
僕は美月の寝顔を見て、彼女がいまいる場所のことを想像した。
美月はいまなにか夢でもみているのだろうか。
それとも何もみずにただ真っ黒な光景を見ているのだろうか。
あるいはハレーションを起こしたような真っ白。
真っ白な闇を。
その白い光で埋め尽くされた景色ではどんな音が響いているのだろうか。
土曜日の午後の病室はほとんど見舞客もいなくて、静かで風が吹く音も聴こえなかった。そしてようやく僕らの話し声に気がついて美月は目を覚ました。
目覚めたばかりの美月の目は虚ろでただ外界を写すだけの鏡のようだった。