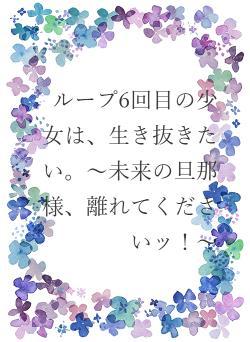涼しい家で過ごしたかった土曜日。
なのに、暑い炎天下の下を歩いている。
本当に世の中は理不尽だ。
姉ちゃんにアイスを買ってこいと、パシられる。
そして、アイスを買った帰りにクラスメイトと出会ってしまう。
いや、出会うと言っても一方的な『出会う』。
大きな川に架かる橋の下で本を読む男子に話しかける女子。
しかも、女子も男子も学校内で有名な美形の持ち主だ。
女子が、渦島(うずしま)。
男子が、秋下(あきした)。
渦島は、男子の中で・・・いや、女子の中でも相当モテているはずだ。
モテる理由が、誰にでも優しく笑顔が可愛いという理由。
誰にでも、というのは女子にも男子にも優しいせいか女子にもキャーキャー騒がれいる。
秋下は、本当にクールで誰とも絡まない奴だった。
だから、秋下と渦島が一緒にいるところを見たとき、見てはいけないものをいたような気分だった。
「何、読んでるの?」
「えっと、『僕は、君へ恋を想う』」
「それって面白い?」
「さあ?」
「さあって」
秋下は、最低限の言葉しか言っていない。
だけど、渦島のおかげで会話のキャッチボールができているのだ。
「ちょっと、読まして」
そう言って、渦島は秋下が持っている本をのぞき込む。
秋下は、思っていた以上に渦島と近かったせいか顔が赤に染まる。
読み終わったのか、渦島は秋下の顔を見て目を見開く。
「へぇー、君でもそんな顔をするのか~」
そう言って、頬杖をし秋下をジーと見つめる。
秋下は、いたたまれなくなったのか目線を本へ移していた。
「・・・なんだこの青春の一ページみたいな感じは」
誰にも聞こえないようにボソっと呟く。
「確かにそうだね」
俺の呟きに答えてくれる相手はいないはずなのに。
「おっ、びっくりしてるびっくりしてるね~」
何か面白いものを見るみたいにニヤニヤと見つめてくる誰か。
「・・・あのさ、顔に何かついてる?」
「ついてないよ」
「じゃあ、なんで・・・」
まずまず、なんでここにいる?
「あっ、アイス溶けちゃうよ?」
そうだ。姉ちゃんにアイス頼まれてたんだ。
「じゃあね~」
誰か知らないのに、タメ口でしかも普通に話しかけてきた。
「あいつ・・・、ダレ?」
本当に誰なんだろうか。
――――この誰かさんが誰なのかが翌日わかることになるなんて知るよしもしなかった。
なのに、暑い炎天下の下を歩いている。
本当に世の中は理不尽だ。
姉ちゃんにアイスを買ってこいと、パシられる。
そして、アイスを買った帰りにクラスメイトと出会ってしまう。
いや、出会うと言っても一方的な『出会う』。
大きな川に架かる橋の下で本を読む男子に話しかける女子。
しかも、女子も男子も学校内で有名な美形の持ち主だ。
女子が、渦島(うずしま)。
男子が、秋下(あきした)。
渦島は、男子の中で・・・いや、女子の中でも相当モテているはずだ。
モテる理由が、誰にでも優しく笑顔が可愛いという理由。
誰にでも、というのは女子にも男子にも優しいせいか女子にもキャーキャー騒がれいる。
秋下は、本当にクールで誰とも絡まない奴だった。
だから、秋下と渦島が一緒にいるところを見たとき、見てはいけないものをいたような気分だった。
「何、読んでるの?」
「えっと、『僕は、君へ恋を想う』」
「それって面白い?」
「さあ?」
「さあって」
秋下は、最低限の言葉しか言っていない。
だけど、渦島のおかげで会話のキャッチボールができているのだ。
「ちょっと、読まして」
そう言って、渦島は秋下が持っている本をのぞき込む。
秋下は、思っていた以上に渦島と近かったせいか顔が赤に染まる。
読み終わったのか、渦島は秋下の顔を見て目を見開く。
「へぇー、君でもそんな顔をするのか~」
そう言って、頬杖をし秋下をジーと見つめる。
秋下は、いたたまれなくなったのか目線を本へ移していた。
「・・・なんだこの青春の一ページみたいな感じは」
誰にも聞こえないようにボソっと呟く。
「確かにそうだね」
俺の呟きに答えてくれる相手はいないはずなのに。
「おっ、びっくりしてるびっくりしてるね~」
何か面白いものを見るみたいにニヤニヤと見つめてくる誰か。
「・・・あのさ、顔に何かついてる?」
「ついてないよ」
「じゃあ、なんで・・・」
まずまず、なんでここにいる?
「あっ、アイス溶けちゃうよ?」
そうだ。姉ちゃんにアイス頼まれてたんだ。
「じゃあね~」
誰か知らないのに、タメ口でしかも普通に話しかけてきた。
「あいつ・・・、ダレ?」
本当に誰なんだろうか。
――――この誰かさんが誰なのかが翌日わかることになるなんて知るよしもしなかった。