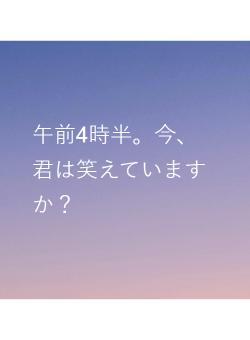「ただいま戻りました」
僕が初めて担当する人と挨拶した日。
「おかえり。初めての仕事はどうだった?」
僕と暮らしている先輩死神。仕事ができるのに昇格しようとしない。謎めいた人。
「まだ何もしてないです。ただ話しただけ。でも、何故だか心地よかったです」
感じたことを並べ、伝える。
「そうか。頑張れよ」
「ありがとうございます。精進してまいります」
冷たい人。暮らし始めてすぐはそう思っていたのに心の底は熱く、優しい人。人間を強引に死に導こうとはしない、その姿は死神の鑑であった。
僕は彼の秘密を唯一知っている。
『この世界に来る前は人間界で人間として生きていた』
過去の記憶を持った死神は知らない、と彼は言っていた。
きっと過去の記憶を持った死神は彼、と僕だけ。その事実を彼は知らないが。
僕は胎内記憶と呼ばれるものが過去の記憶と残っている。
これは、僕の過去の記憶
僕だけの隠れ家で育った。
幸せだった。
僕の見えないどこかで聞こえる音。
微かに差し込むほのかな光。
優しく、温かいその場所での暮らしは――一瞬だった。
すべての感覚が消え、厳しく、冷たいその空間で過ごすのはとても酷なものだった。
早く僕を何処かへ消してくれ。
誰も聞いていない。
此処は僕だけの隠れ家。誰一人いない。
寂しい。早く迎えに来てほしい。
少しの日が経った頃、僕は初めて通る道を歩いた。
いつの間にか体が大きくなっていて、重さを感じた。
真っ暗で、光が見えない道。あの光は何処へ行ってしまったのだろう。
「怖いよ……」
目の中に透明なものが溜まって、瞬きすると垂直に落ちて、溶けていった。
これは涙だというものだと後に教えてもらった。
それまでは宿されたときから持った言葉を紡ぐだけだった。
学びというものを知らなかった。
「小さな坊や。ここにいても誰も来ない。俺の家に来い。居候させてやる」
僕の小さな、小さな体を軽々と持ち上げ、肩に乗っけた。
黒色のコートを羽織り、靡かせながらこちらにやってきた姿は逞しく、これが大人というものなのかと初めて知った。
「坊や。君は何処から来たんだ?」
低く、重い声が体にまで伝わり、響く。
「知らない」
僕は知らなかった。あの場所がどこなのか。
「そうか。俺は毎日君が座り込んでいた場所に行く。あそこで待っている子供がたくさんいるからな」
僕だけではない。ここに迷い込んだのは。
世界の隅で誰かが迎えに来ることを望んでいる子供がたくさんいるのか。
何も見えない場所を見るために振り返った。
誰もいない。
安心してしまった僕を強く恨んだ。
「自己嫌悪。この言葉知ってるか?」
「知らない」
「簡単に言えば自分に嫌気がさすこと。君は自分のことを嫌いになるなよ。ここで俺が君を見つけられたのはきっと、――奇跡だから」
奇跡。聞いたことのあるような言葉だが、意味は、
知らない。
わからない言葉が耳元を打つのに若干の苛立ちを覚えてしまう。――自己嫌悪。
常に広がる暗闇に小さな光が見えた。
「そろそろ着く」
急に体が思い切り揺さぶられ、気付けば夜の風を切っていた。
「気持ちいいだろ。こうやって走るのだけでも案外楽しいんだ」
「降りてもいい?」
ゆっくりと速度を落とし、止まってくれる。
「なら競争だ。ここから真っ直ぐいくと俺の家の入口の門がある。あそこがゴール」
スタートラインに並び、顔を見合わす。
「よーい、ドン」
合図で足を大きく踏みだした。
僕はこの日から僕の正体を探していた。
僕が初めて担当する人と挨拶した日。
「おかえり。初めての仕事はどうだった?」
僕と暮らしている先輩死神。仕事ができるのに昇格しようとしない。謎めいた人。
「まだ何もしてないです。ただ話しただけ。でも、何故だか心地よかったです」
感じたことを並べ、伝える。
「そうか。頑張れよ」
「ありがとうございます。精進してまいります」
冷たい人。暮らし始めてすぐはそう思っていたのに心の底は熱く、優しい人。人間を強引に死に導こうとはしない、その姿は死神の鑑であった。
僕は彼の秘密を唯一知っている。
『この世界に来る前は人間界で人間として生きていた』
過去の記憶を持った死神は知らない、と彼は言っていた。
きっと過去の記憶を持った死神は彼、と僕だけ。その事実を彼は知らないが。
僕は胎内記憶と呼ばれるものが過去の記憶と残っている。
これは、僕の過去の記憶
僕だけの隠れ家で育った。
幸せだった。
僕の見えないどこかで聞こえる音。
微かに差し込むほのかな光。
優しく、温かいその場所での暮らしは――一瞬だった。
すべての感覚が消え、厳しく、冷たいその空間で過ごすのはとても酷なものだった。
早く僕を何処かへ消してくれ。
誰も聞いていない。
此処は僕だけの隠れ家。誰一人いない。
寂しい。早く迎えに来てほしい。
少しの日が経った頃、僕は初めて通る道を歩いた。
いつの間にか体が大きくなっていて、重さを感じた。
真っ暗で、光が見えない道。あの光は何処へ行ってしまったのだろう。
「怖いよ……」
目の中に透明なものが溜まって、瞬きすると垂直に落ちて、溶けていった。
これは涙だというものだと後に教えてもらった。
それまでは宿されたときから持った言葉を紡ぐだけだった。
学びというものを知らなかった。
「小さな坊や。ここにいても誰も来ない。俺の家に来い。居候させてやる」
僕の小さな、小さな体を軽々と持ち上げ、肩に乗っけた。
黒色のコートを羽織り、靡かせながらこちらにやってきた姿は逞しく、これが大人というものなのかと初めて知った。
「坊や。君は何処から来たんだ?」
低く、重い声が体にまで伝わり、響く。
「知らない」
僕は知らなかった。あの場所がどこなのか。
「そうか。俺は毎日君が座り込んでいた場所に行く。あそこで待っている子供がたくさんいるからな」
僕だけではない。ここに迷い込んだのは。
世界の隅で誰かが迎えに来ることを望んでいる子供がたくさんいるのか。
何も見えない場所を見るために振り返った。
誰もいない。
安心してしまった僕を強く恨んだ。
「自己嫌悪。この言葉知ってるか?」
「知らない」
「簡単に言えば自分に嫌気がさすこと。君は自分のことを嫌いになるなよ。ここで俺が君を見つけられたのはきっと、――奇跡だから」
奇跡。聞いたことのあるような言葉だが、意味は、
知らない。
わからない言葉が耳元を打つのに若干の苛立ちを覚えてしまう。――自己嫌悪。
常に広がる暗闇に小さな光が見えた。
「そろそろ着く」
急に体が思い切り揺さぶられ、気付けば夜の風を切っていた。
「気持ちいいだろ。こうやって走るのだけでも案外楽しいんだ」
「降りてもいい?」
ゆっくりと速度を落とし、止まってくれる。
「なら競争だ。ここから真っ直ぐいくと俺の家の入口の門がある。あそこがゴール」
スタートラインに並び、顔を見合わす。
「よーい、ドン」
合図で足を大きく踏みだした。
僕はこの日から僕の正体を探していた。