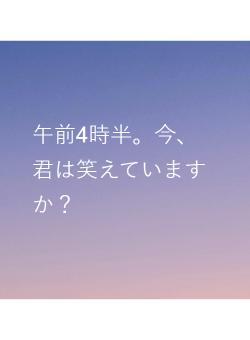目いっぱい差し込む朝の光。
あの後眠ってしまったようだ。隣にあった母の姿はもうなかった。
一日中寝ていたようで新しい朝が訪れていた。
秋風に舞うカーテン。
その隙間から見える町はとても活気に溢れていた。
別世界のようだ。
「またマイナスなこと考えてた?」
窓から顔を出してやってきた絃月。彼は死神だからと脳内に刻み込んだら違和感など吹き飛んでいった。
「別に。街を眺めてただけ」
「寝ている間だったらなー、全部聞けるのに」
「死神さんの事情は私に関係ないですけど」
そっか、あの夜声を掛けられたときは私の思考を盗み聞きしていたのか。
人は常に思考を巡らせるのだろうか。絃月が指しているのは意識不明の状態の時のことだろうか。
「僕はね、姉ねが寝ている間に考えていることが聞こえるの。不思議な話だけど」
よく分からないから話を逸らしてしまおう。
「絃月。君が私のもとに来た目的は?」
言わなきゃダメかと目で訴えかけてくる姿がなかなかに可愛らしい。そこまでして言いたくないのだろうか。
「……言ったら姉ね死んじゃうよ」
聞き取るのが困難なほどに小声だった。
「言って。知りたいよ」
躊躇いながらも言葉を紡いでくれていることがありがたかった。早く知りたかったから。
「姉ねは昨日から数えて、七日で死ぬの。それを伝えに来た。そして、最期を見送るために……」
潤っているその瞳からは涙というものは零れてこない。苦しそうな顔を浮かべているだけ。
「私が死ぬのはこの、事故のせい?」
包帯の巻かれた足を指して問い掛けてみる。
「違うよ。詳しいことは、何も言えない」
でも、違うよ。
一拍ためて、絃月はそう言った。
「そっか。じゃあ、入院中に抱いた夢がついに叶うのか」
笑いながら口にしてみたが、ぎこちなくなった。
死にたいはずなのに、その考えと比例しない感情。
「本当に死にたいの?」
心の奥底に問い掛けられた言葉が生きる道を開こうとしたが、一瞬にして閉じた。
「死にたい」と口にしてしまったから。
「僕はね、姉ねの最期を幸せにしたくて来たの」
「そっか、幸せか……。感じたことないな……」
絃月には届かぬよう、心の声を零してみた。
不幸な人生だった。
あの頃の負のループのせいで私の人生は一変した。とにかく不幸な人生だった。
「じゃあさ、私のことを幸せにしてみてよ」
「姉ねは幸せになったことないの?」
やはり、数十秒前に零した心の声は届いていなかった。
安堵しながら「うん」と頷いてみた。
「僕もね、幸せを知らないよ。でも、僕の先輩がね、『人間が幸せを感じられてこそ一人前の死神だ。最期が綺麗でも、残酷であっても関係ない。ただ仕事を全うしろ』って言って僕をここに送り届けてくれたの」
小さな死神の先輩か。そちらの方が頼りがいがあった気がするという考えが過ぎり、急いでかき消した。聞こえていないとはいえ、申し訳ないから。
「だから、僕は姉ねを幸せにするよ。そうしたら僕も幸せを感じられるかもしれないし」
私が幸せになれば絃月も幸せを感じられる。
それならば、幸せにしてもらおう。
私には存在しない弟のような絃月を幸せにしてもらおう。
「じゃあ、幸せにさせて。この七日間で、一生分の幸せを感じさせてよね」
「もちろん!」
上から目線の偉そうな口調で発された言葉にも嬉しそうに返事をする絃月。
彼の心の底は終わりのない海のように、広く、深く、透き通っているのだろう。
あの後眠ってしまったようだ。隣にあった母の姿はもうなかった。
一日中寝ていたようで新しい朝が訪れていた。
秋風に舞うカーテン。
その隙間から見える町はとても活気に溢れていた。
別世界のようだ。
「またマイナスなこと考えてた?」
窓から顔を出してやってきた絃月。彼は死神だからと脳内に刻み込んだら違和感など吹き飛んでいった。
「別に。街を眺めてただけ」
「寝ている間だったらなー、全部聞けるのに」
「死神さんの事情は私に関係ないですけど」
そっか、あの夜声を掛けられたときは私の思考を盗み聞きしていたのか。
人は常に思考を巡らせるのだろうか。絃月が指しているのは意識不明の状態の時のことだろうか。
「僕はね、姉ねが寝ている間に考えていることが聞こえるの。不思議な話だけど」
よく分からないから話を逸らしてしまおう。
「絃月。君が私のもとに来た目的は?」
言わなきゃダメかと目で訴えかけてくる姿がなかなかに可愛らしい。そこまでして言いたくないのだろうか。
「……言ったら姉ね死んじゃうよ」
聞き取るのが困難なほどに小声だった。
「言って。知りたいよ」
躊躇いながらも言葉を紡いでくれていることがありがたかった。早く知りたかったから。
「姉ねは昨日から数えて、七日で死ぬの。それを伝えに来た。そして、最期を見送るために……」
潤っているその瞳からは涙というものは零れてこない。苦しそうな顔を浮かべているだけ。
「私が死ぬのはこの、事故のせい?」
包帯の巻かれた足を指して問い掛けてみる。
「違うよ。詳しいことは、何も言えない」
でも、違うよ。
一拍ためて、絃月はそう言った。
「そっか。じゃあ、入院中に抱いた夢がついに叶うのか」
笑いながら口にしてみたが、ぎこちなくなった。
死にたいはずなのに、その考えと比例しない感情。
「本当に死にたいの?」
心の奥底に問い掛けられた言葉が生きる道を開こうとしたが、一瞬にして閉じた。
「死にたい」と口にしてしまったから。
「僕はね、姉ねの最期を幸せにしたくて来たの」
「そっか、幸せか……。感じたことないな……」
絃月には届かぬよう、心の声を零してみた。
不幸な人生だった。
あの頃の負のループのせいで私の人生は一変した。とにかく不幸な人生だった。
「じゃあさ、私のことを幸せにしてみてよ」
「姉ねは幸せになったことないの?」
やはり、数十秒前に零した心の声は届いていなかった。
安堵しながら「うん」と頷いてみた。
「僕もね、幸せを知らないよ。でも、僕の先輩がね、『人間が幸せを感じられてこそ一人前の死神だ。最期が綺麗でも、残酷であっても関係ない。ただ仕事を全うしろ』って言って僕をここに送り届けてくれたの」
小さな死神の先輩か。そちらの方が頼りがいがあった気がするという考えが過ぎり、急いでかき消した。聞こえていないとはいえ、申し訳ないから。
「だから、僕は姉ねを幸せにするよ。そうしたら僕も幸せを感じられるかもしれないし」
私が幸せになれば絃月も幸せを感じられる。
それならば、幸せにしてもらおう。
私には存在しない弟のような絃月を幸せにしてもらおう。
「じゃあ、幸せにさせて。この七日間で、一生分の幸せを感じさせてよね」
「もちろん!」
上から目線の偉そうな口調で発された言葉にも嬉しそうに返事をする絃月。
彼の心の底は終わりのない海のように、広く、深く、透き通っているのだろう。