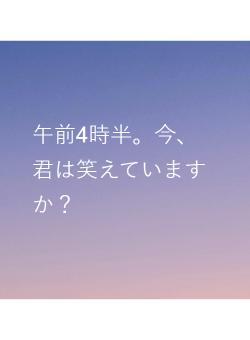「死神さん。私を、早く空の上へ連れて行ってよ」
現実にいるかも分からないその存在は私にとって希望であった。
実際にいれば、だけど。
意識不明の状態。
早く死んでしまいたいと何度望んだことか。
ベットにくっつけれて治療を受ける日々は意味があるのだろうか。
大量の管には繋がれて視線を常に感じる。
真暗闇の視界にも確かに光があって、それは私が生きられる希望なのだろうが、ただ、身を苦しめる絶望であった。
死にたい。
「なーに悲しいこと考えてるの? 死んでしまいたいなんてもったいないよ」
幼い声が耳元で聞こえる。幼児の声のようだ。でも、この病棟に、真夜中に子供がいるとは考えれない。
「姉ねさ、二週間目覚めれないからって落ち込まないでよ。まだ生きれるよ」
血の繋がった姉のように接する子供は声質の割に大人びたことを言う。
視界が綺麗な色で染まった。目の前に飛び込んできたのは小さな男の子。黒いパーカーのフードを深く被っている。正直、彼の姿と不釣り合いだ。
「おはよう」
「おはよう、?」
つい、身を引いてしまう。
「怖がらなくていいよ。そんな恐ろしい存在じゃないから」
「君は誰? 私の周りの病室には子供はいなかったはずだよ」
「だって、僕はここで入院していないもの」
なら、何故この病院の中にいるの? はてなを浮かべた私の顔を見た彼は思い切り吹き出した。
「そうだよね。自己紹介しなきゃだね」
ベットの横に置かれた椅子に座り、足を組んでいる。
初対面なのに緊張の色を見せず、話を淡々と進める彼についていけない。それなのに、また話が動き出す。
「横見沙弥さん。初めまして。僕は、死神です」
子供らしさをすべて消し去ったかのように、改まって自己紹介をする彼から出てきた言葉。
死神
確かに私が望んでいた存在。でも、全く現実味がない。とても幼すぎる。
眠っている間に考えていた死神では無い。
私が想像していたのは小説の登場人物であるような死神で、少し大人びた、優しい死神。
ただの少年として話したかった気もした。
「……何で、名前知っているの?」
「だって、僕は君のことなんでも知っているから」
話が噛み合わない。幼い子はこんな感じなのだろうか。十六年間、一人っ子として生きてきた私にはよく分からない。
「君は、何歳なの?」
もう一度、質問を投げかける。これで話のキャッチボールが出来なかったら彼のことをただの少年と思っていよう。
「僕にはね、年齢なんてないよ。姉ね達にはある誕生日も僕にはない。急に生まれて、ある程度大きくなったら仕事するの」
思っていたよりも大人な返事が返ってきて困惑した。
彼はどこにでもいる少年ではない。
――死神、なんだろう。
「じゃあ、最後の質問ね。君のこと、何って呼べばいい?」
咄嗟に口から出てきた質問。私は彼の名前を呼びたいと思っているようだ。
「うーん」
よりフードを深く被って考え込んでいる。少しの隙間から見える口元は若干歪んでいた。
「あのね、僕には名前がないの。だから、呼び方を聞かれても、答えれないんだよね」
悲しそうな顔をして話す姿に心苦しくなった。
思いついた一つの考え。
「私が君の名前を付けてもいい?」
「えっ、でも、僕まだ見習い死神だから名前持てない……」
「私が付けたいだけ。君は名前を持っているとは思わなくていい。私が君を呼ぶためだから」
「じゃあ、欲しい」
脳内に浮かんだ幾つもの名前。彼にぴったりの名前を見つける。
その間は幾分かの沈黙が流れた。
サイドテーブルに置かれた紙とペンを持ち、思いついた名前を書く。
「絃月、って名前はどう?」
彼にその紙を見せる。
この名前に沢山の意味を持たせたけど、今は言わないでおく。
いつの日かに、――別れが来るってことだから。
「絃月、か。素敵な響き。僕が貰っていいの?」
「うん。よろしくね。絃月」
心の中が幸せで溢れていく感覚がした。
虚しかったこの日々が急に感情でいっぱいになり、色付いていく。
涙。
いつから流していなかっただろう。頬を濡らしていく水滴が力を奪っていくよう。
あの日から止まっていた心と体が緩んでいく。
「大丈夫? ほら」
小さな手で差し出してくるハンカチ。受け取ろうと触れたら手が通り過ぎて行った。
「ごめん。忘れてた。姉ね達は僕のものに触れないんだよね」
「そうなんだ」
触れようとしたあのハンカチの影はとても冷たかった。そして、彼の体からも冷たさが伝わってくる。
生温い手のひらで涙を払い、必死で笑顔を作る。
「もう大丈夫。もう泣いていない」
「頬がまだ濡れてる」
私の頬で感じられる冷たさに棘は無かった。温かい。
頬を濡らしたものはもういなかった。
「じゃあ、帰るね。また来るから」
私の枕元に置かれたナースコールを押し、そのまま扉を開けて何処かへ帰る彼。
背中を最後まで見つめてみたけど、名乗り直ぐに消えてしまった。
突然現れて死神と、一瞬のように何処かへ帰ってしまった。
そんな謎秘めた彼の顔がずっと離れなかった。
とても愛おしい。
私に弟という存在がいたらこんな感情を常に抱いていられたのだろう。
会いたかった。会ったことの無いあの人に会いたかった。
もう二度と会うことのないあの人と重なる彼。顔も知らないのに。
会いたい。
早く会いたい。
死神と名乗っただけで目的を言い残さないまま消えた彼。
きっと、会えるよね。
君が死神なら、また。
「横見さん! 目、覚ましたんですね……」
若い女性の看護師さんが部屋に入ってきた。
眠っている間何度も聞いた声。まだ若いのに、疲れ切った顔をしている。私のせいでも、あるのかな。
眠っていた間は何も出来なかった。ずっと固まっていた。それなのに、今は硬直していた体が事故以前と同じように動く。当たり前のように。
「ご家族呼んできますね」
また一人。
心がすり減っていくような感じがした。
大きく開いているカーテン。目に留まる美しい朝月夜。必死に顔を見せる繊月が朝を彩っている。
空の様子だと時刻は六時前ぐらいだろうか。
秋の夜明けは夏よりも少しばかり遅い。今日この日に見られたのが少しばかり嬉しかった。
家族はまだ起きていないだろうからしばらく一人きり。起きていても来てくれないかもしれない。
椅子に座って空を眺めていようかと、起き上がる。
固定された右足。包帯が巻かれた左腕。体中に残る傷。
椅子に座ることは諦めた。ベットから眺める空も十分綺麗だ。
「沙弥!」
勢いよく開いたドアから呆れるほど聞いてきたその声が聞こえた。
「お母さん」
「良かった……。目覚めてくれて」
強く抱きしめられて胸が痛む。
「……ごめんなさい」
胸の奥から飛び出してきた謝罪の言葉。耳元で小さく呟いた。この言葉が本心か本心じゃないのかは私にもわからない。
大きく首を振る振動が体に流れた。
体温が強く身に染みて、暑苦しい。
自ら身を引き、優しさという名の鎖を断ち切った。
「ずっと待ってた。沙弥が起きてくれることを」
どんな顔をしていればいいのだろう。合わせる顔がない。
「勝手に家飛び出してごめんなさい」
「謝らなくていいの。私もごめんなさい」
***
些細なことだった。
毎日部屋で引きこもっていた。毎朝、私を高校に連れていくために起こしに来る。毎晩、晩御飯を部屋の前に置きに来る。
菓子で腹が膨れているから手は付けない。
あの日の晩御飯の置かれたお盆の上に置かれた一枚のメモ用紙。
『ちゃんとご飯食べてね』
……余計なお世話。
朝昼はきちんと食べているのだから。
小さな紙切れに苛立ちを覚え、気付いたら自室の窓から飛び降りていた。二階から、一階に。
床に平行につけた足に強い衝撃が流れたが、痛みなどどうでも良かった。
せっかくの機会だ。
手ぶらで身軽な体のままどこかで消えよう。誰かに見られながらいなくなるのは勘弁。
全力疾走。痛む足をかばいながらでも、何とか走れた。ただ、鈍っていた体には莫大な負担。
それでも走り続けた。
何もかも私には関係ない。
周りにいる人々も遠くにいる人々もすべてを包み込むこの世界ももう、味方ではないから。
隣接市に着いた。見慣れないその景色はあの場所より何倍も安心できた。
呼吸を整えるために散策してみた。
暖かな街灯は本来であれば優しいのだろうが、私には棘のように感じられた。
大きな家。あんな家で暮らせたらさぞ幸せなのだろう。
古びた小さな一軒家。こんな真新しい大きな一軒家は別世界だ。
大きな庭。ところどころに転がっているもの。
あんなに裕福そうな生活でも散らかっている箇所があるのに不謹慎ながら笑ってしまった。
まあ、いいや。私には関係ない。
すべてを振り切ろう。
もう終わりなんだから。
もう一回全力で風を切った。
流れる意味が分からない涙が止まらぬまま。
誰もいない夜の街に溶けていく私の涙。
口元に流れたその水は塩辛くて仕方がない。
この冷たい風よ、私の心を空っぽにしてくれ。
思い出を蘇らさせるこの涙を乾かしてくれないか。
これが最後だから。もう消えるのだから。
最期だけは楽にいたい。
消え去らない思いと涙。
また生きるなんてもう無理だ。
早く、早く。
信号機の無い横断歩道。白線を一つずつ踏みしめる。
辺りの光が私のことを包み込み、何処かへと誘おうとしている。
耳の中で強く反響するブレーキ音に足を止めた。
こちらへと向かってくる真っ白な光が視界を奪っていく。
白く染まった私の世界ではなすがままとなった。
鈍い衝突音が体中を巡り、痛みを引き起こした。
どこも動かせない。言葉が出ない。
微かに触れる生温い血液。気持ち悪くなって吐き出したくなる。
上手く呼吸ができない。苦しい。
目が自然と閉じて、やがて、鼓動が止まっていた。
それから大量の管に繋げて、固定して、人々は私のことを助けようとする。
助けられたんだ。拒みたくても、拒めなかった。
***