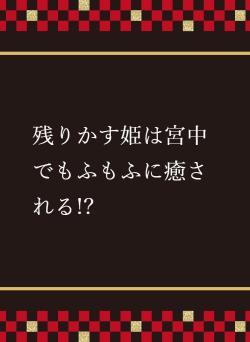深夜ということもあり、ゆうべは結局、伊月とあれ以上話ができなかった。
翌朝。目が覚めた俺は、真っ先に耳と尻尾が生えてきてやしないか確認した。
「あ、大丈夫っぽいな」
どうやら伊月が注いでくれた気の効果は、まだ続いているようだ。ひとまず安堵したところで制服に着替え、自室を出る。
ちんたらリビングに向かっていると、廊下の途中に皿の乗ったトレイが置かれていた。すぐ脇にあるのは、兄貴の部屋のドアだ。
皿には、昨日の晩飯……カレーが半分ほど残っていた。サラダは手つかずで、半分萎びている。俺はそれをトレイごと持ってリビングに行き、流しまで運ぶ。
キッチンではおふくろがコーヒーを淹れていた。やってきた俺を見て「おはよう」と僅かに口角を上げたが、手にしていたトレイを見てすぐに表情を暗くする。
「一哉、ゆうべもあまり食べてくれなかったのね……。そろそろ部屋の掃除もしてあげたいけど……いつ、中に入れてくれるかしら」
トレイを渡しながら、おふくろってこんなに小さかったっけ、と思った。
一哉っていうのは、四歳上の俺の兄貴だ。
ごく普通の大学生だった兄貴は、半年前、突然部屋から出てこなくなった。
それから、うちの中が一変した。家族揃って飯を食うことはなくなったし、キャッチボールもしていない。
昼夜逆転の生活をしている兄貴が寝ているこの時間は、比較的平和だった。俺はそそくさと朝飯をかきこんで、玄関から外に飛び出す。
俺たちの住まいは、四階建てのビルの最上階。一階は、親父とおふくろが経営する薬局だ。その薬局の看板の横をすり抜けて通りに出たところで、箒を持ったおばちゃんに声をかけられた。
「幸太郎ちゃん。行ってらっしゃーい」
このおばちゃんは、うちの向かいで煎餅屋をやっている。朝はこうやって、店の前を掃除してることが多い。
俺は口の端っこを無理やり持ち上げて「はよーっす」と返し、停めてある自転車に跨った。
風を顔に受けながら走り出すと、目に映るのはいわゆる商店街の光景だ。
通称、麻布十番と呼ばれるこの界隈は、一応、セレブの住む港区に属しているものの、漂っている空気は完全に下町のそれだった。俺が生まれる前は交通の便が悪くて、陸の孤島だったという。昭和の香りがするとか言われているのは、開発が遅かったせいだろう。
そんな麻布十番に軒を連ねる『朝見薬局』はわりと老舗で、親父は四代目の店主。薬局と住居を兼ねる四階建ての細長いビルは、俺ん家の持ち物だ。
二階と三階を他人に貸しているお陰で、港区の地価が爆上がりした今でもなんとか税金を払える……と親父が言ってた。
ちなみに、俺が通う都立狸穴高校も港区にある。校名は江戸時代の地名からきてると前に誰かから聞いたが、詳しいことは忘れた。
俺、歴史は苦手だからな。まぁ、英語も国語も得意じゃねーし、理系科目に至っては吐き気がするけどさ……。
そうこうしているうちに学校につき、俺は「うぃーっす!」と周囲に挨拶しつつ教室へ向かう。
二年B組の戸を開けたとき、真っ先に目に飛び込んできたのは、出入り口の一番近くに座る伊月の顔だった。
「……あ、伊月。おはよう」
俺は軽く手を挙げてみせた。だが伊月はちらりと視線を投げてきただけで、すぐに机上の教科書と向かい合う。
あまりの不愛想ぶりに驚いた。
まぁ、伊月ってもともとこんなタイプだったわ。でも、ゆうべはちゃんと口をきいてくれたじゃん。あんなに密着もしたし。……っていうか、くっつきすぎだったよな。仕方ねぇけどさ。
俺は昨夜のことをぼんやり思い出しながら自分の席に座った。
授業中、居眠りの合間にこっそり様子を窺うと、伊月はいつもしゃんと背を伸ばしていた。
うーん、よく見ると顔はそこそこ整ってる。目は大きくて鼻筋は通ってるし、短く切り揃えられた髪は天パ気味でふわふわだ。
身長は俺より七、八センチ低かったから、百六十五ってとこか。弟系っていうか、小型犬系? これで愛想がよけりゃ、女子にモテそうなのに。
なんかこう、近寄りがたい雰囲気があるんだよなぁ。伊月と同じクラスになって半年だが、ろくに話したことがなかったのはそのせいだ。
……と、まぁこんな感じで、午前中は伊月の観察(と居眠り)に時間を割いた。
昼休みのチャイムが鳴ると、その伊月が自分の席から立ち上がった。机と椅子の間を器用にすり抜け、最短ルートで俺のところまでやってくる。
「朝見幸太郎くん。職員室で先生が呼んでるよ」
「……え、マジ?」
前の席の矢田吹と昼飯を調達しに行こうとしていた俺は、その場でズッこけそうになった。伊月はそんな俺に、冷めた目を向ける。
「とにかく、僕と一緒に来てくれ」
「あ……ああ、分かった」