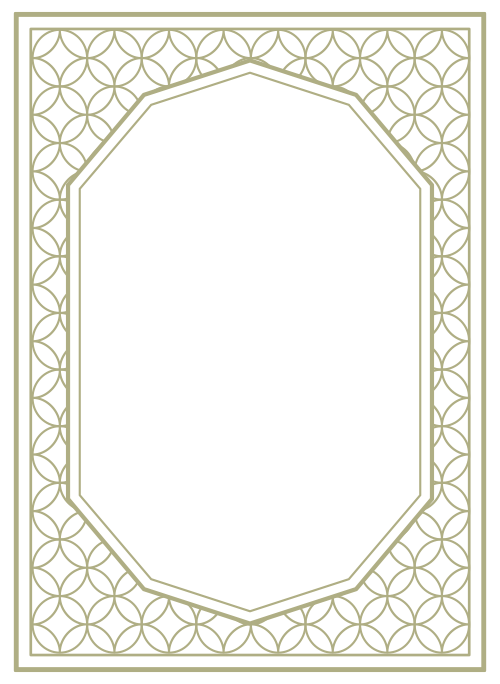二年が経ち、私たちは卒業式を迎えた。高校生活が終わるその日に、三人そろって千里ちゃんの家を訪れる。
「おじゃましまーす」
「いらっしゃい、みんな久しぶりね。千里も待っているわよ」
久々に会うおばさんは寂しそうだったけれど、かつてと変わらない笑顔を私たちに見せてくれた。
仏壇が置かれているのは千里ちゃんの部屋だ。飾られた額縁の中の千里ちゃんはまぶたを閉じた穏やかな笑顔で、まるで私たち三人を見守ってくれているみたい。
並んで千里ちゃんの前に正座をし、そろって両手を合わせる。
おばさんは四人分のチーズケーキを出してくれた。ひとつを千里の仏壇に供える。それから、ごゆっくりどうぞ、と言ってそっと扉を閉めた。千里ちゃんが元気だった頃と同じように接してくれることに胸がじんと熱くなる。
卒業した私たちはこれから別々の道に進むから、ひとつはその報告をしにきたのだ。
まずは葉山くんから。
「千里たん、俺さ、高校生活をサッカーに捧げてきたつもりだぜ。全国では負けちまったが、スカウトを受けたんだ。まあ、下位リーグからのスタートだけど、プロの世界での戦いだから、いよいよ伝説が幕を開けるんだ。楽しみにしてくれよな」
「葉山くん、二年前にも幕が上がったようなこと言ってなかった?」
「うるさい有紗、あのときはプロローグにすぎなかったんだ。というわけで千里たん、サッカーは屋外競技だから雲の上から見られるだろ? 応援してくれよな」
京本くんがうんうんとおおきくうなずいた。
次は京本くんの番。彼は真剣な表情で千里ちゃんの遺影に語りかける。
「千里、僕は大学に進むよ。社会学を学ぶつもりだ。
千里と会って考えたんだけどさ、不自由を抱えているせいで、持っている才能を発揮できない人って、世の中にたくさんいると思う。だから、不自由を抱えた人が活躍できるような社会を作りたいっていうのが、僕が見据えた目標なんだよ。
そのためには、日本中のいろんな地域の現状も知らないといけないし、北欧の福祉モデルを学んだりしたいとも思っている。そうなったらなかなか会いに来られなくなると思うけれど許してくれよな」
京本くんはほんとうに真面目な人だ。そんなところが彼のいいところで、同時に自分自身を苦しめていた理由だとも思う。でも、千里ちゃんと出会って、彼は苦しみながら自分の未来を見つけられたんだ。
最後に私の番。今日は進路の報告だけでなく、もうひとつ、どうしても千里ちゃんに伝えたいことがあったのだ。
「千里ちゃん、私は文系の大学に進むけれど、みんなみたいなやりたいことを、まだ見つけられずにいるんだ。だから、これから自分のやりたいことを探すために、いろんなことに挑戦してみようと思っている。勉強もするし、でもフルートは続けたいし、それになにかスポーツもやってみようと思う。せっかく光のある世界でできることをやらなかったらもったいないもんね。それから――」
カバンの中から本を一冊取りだす。私はそれを仏壇の前にそっと置いた。
「あと、物語を書いてみるのもいいかな、って思っている。――じつはこの本ね、京本くんと私で一緒に書いたものなんだ。千里ちゃんのことが書かれた物語なんだよ」
千里ちゃんからのメッセージを受け取った後、私は京本くんとふたりで、千里ちゃんと出会ってからのことを書き記した。京本くんからの提案で、理由は古本さんから「本は著者が抱いた思いを、ありのままの姿でとどめておくことができる」と聞いたかららしい。
私たちは、それぞれふたりの想いを込めた文章を組み合わせて、ひとつの物語を完成させた。
物語はそれぞれの視点で書かれているので、ふたりの胸中が克明に記されている。だから私は――京本くんが背負っていた罪の十字架を、彼が書いた物語の中から知ることになった。
その十字架の重さこそ、水曜日の彼が喋らない理由だった。
今日はそんな私たちの気持ちを全部、千里ちゃんに届けたいと思って、完成した本を持ってきた。
すかさず葉山くんが提案する。
「おい京本、せっかくだから千里たんに朗読してやったらどうだ」
「あっ、それいい考えね。絶対、京本くんの声を聴きたがっていると思う」
「ええっ、みんなに聴かれるのはさすがに照れるな。でも、それもいいかもね」
京本くんは本を手に取り感慨深そうに表紙を眺める。私たちはその物語に、こんな題名をつけていた。
『水曜日のライト・フレンズ』
著 京本和也
高円寺有紗
表紙をめくると、最初に書かれている言葉は――。
『この物語を、楠千里に捧げる』
「千里たん、聴いていてくれよ。いよいよ公開するぜ、ヒャッホー!」
「なんか騒がしくなりそうだ。やっぱりふたりきりにしてもらおうかな」
「えーやだよ、私だって聴きたいもん。千里ちゃんばっかりずるーい」
千里ちゃん、私たちは相も変わらず好き勝手なことを言っている。そんな気軽な関係は、これからも続きそうな気がしているんだ。
ほんとうにでこぼこな友達だよ。みんなすこしずつ違っているけれど、それでいいんだと思う。
千里ちゃんと私たちの間にも違いがあって、でもみんな、その違いを飛び越える勇気を持っていた。私たちはそんな勇気をたくさんの人に広げて、もっと自由な世界を作らなくちゃいけないと思っている。
だって、これから私たちは広い世界でさまざまな人たちと出会い、誰かが誰かを照らしたり、支えたり、励ましたり、そして――好きになったりすると思うのだから。
私たちはみんな、そんなふうにたくさんのありがとうを抱えて生きてゆくんだ。
それから京本くんは、ゆったりとした口調で私たちの本を読み始める。
穏やかな声調で紡がれる物語が、千里ちゃんの部屋に広がってゆく。
額縁の中できらめく笑顔が、やわらかな青陽の風になって、私たちの心の穂先をそっと揺らしてゆくようだった。
【了】
「おじゃましまーす」
「いらっしゃい、みんな久しぶりね。千里も待っているわよ」
久々に会うおばさんは寂しそうだったけれど、かつてと変わらない笑顔を私たちに見せてくれた。
仏壇が置かれているのは千里ちゃんの部屋だ。飾られた額縁の中の千里ちゃんはまぶたを閉じた穏やかな笑顔で、まるで私たち三人を見守ってくれているみたい。
並んで千里ちゃんの前に正座をし、そろって両手を合わせる。
おばさんは四人分のチーズケーキを出してくれた。ひとつを千里の仏壇に供える。それから、ごゆっくりどうぞ、と言ってそっと扉を閉めた。千里ちゃんが元気だった頃と同じように接してくれることに胸がじんと熱くなる。
卒業した私たちはこれから別々の道に進むから、ひとつはその報告をしにきたのだ。
まずは葉山くんから。
「千里たん、俺さ、高校生活をサッカーに捧げてきたつもりだぜ。全国では負けちまったが、スカウトを受けたんだ。まあ、下位リーグからのスタートだけど、プロの世界での戦いだから、いよいよ伝説が幕を開けるんだ。楽しみにしてくれよな」
「葉山くん、二年前にも幕が上がったようなこと言ってなかった?」
「うるさい有紗、あのときはプロローグにすぎなかったんだ。というわけで千里たん、サッカーは屋外競技だから雲の上から見られるだろ? 応援してくれよな」
京本くんがうんうんとおおきくうなずいた。
次は京本くんの番。彼は真剣な表情で千里ちゃんの遺影に語りかける。
「千里、僕は大学に進むよ。社会学を学ぶつもりだ。
千里と会って考えたんだけどさ、不自由を抱えているせいで、持っている才能を発揮できない人って、世の中にたくさんいると思う。だから、不自由を抱えた人が活躍できるような社会を作りたいっていうのが、僕が見据えた目標なんだよ。
そのためには、日本中のいろんな地域の現状も知らないといけないし、北欧の福祉モデルを学んだりしたいとも思っている。そうなったらなかなか会いに来られなくなると思うけれど許してくれよな」
京本くんはほんとうに真面目な人だ。そんなところが彼のいいところで、同時に自分自身を苦しめていた理由だとも思う。でも、千里ちゃんと出会って、彼は苦しみながら自分の未来を見つけられたんだ。
最後に私の番。今日は進路の報告だけでなく、もうひとつ、どうしても千里ちゃんに伝えたいことがあったのだ。
「千里ちゃん、私は文系の大学に進むけれど、みんなみたいなやりたいことを、まだ見つけられずにいるんだ。だから、これから自分のやりたいことを探すために、いろんなことに挑戦してみようと思っている。勉強もするし、でもフルートは続けたいし、それになにかスポーツもやってみようと思う。せっかく光のある世界でできることをやらなかったらもったいないもんね。それから――」
カバンの中から本を一冊取りだす。私はそれを仏壇の前にそっと置いた。
「あと、物語を書いてみるのもいいかな、って思っている。――じつはこの本ね、京本くんと私で一緒に書いたものなんだ。千里ちゃんのことが書かれた物語なんだよ」
千里ちゃんからのメッセージを受け取った後、私は京本くんとふたりで、千里ちゃんと出会ってからのことを書き記した。京本くんからの提案で、理由は古本さんから「本は著者が抱いた思いを、ありのままの姿でとどめておくことができる」と聞いたかららしい。
私たちは、それぞれふたりの想いを込めた文章を組み合わせて、ひとつの物語を完成させた。
物語はそれぞれの視点で書かれているので、ふたりの胸中が克明に記されている。だから私は――京本くんが背負っていた罪の十字架を、彼が書いた物語の中から知ることになった。
その十字架の重さこそ、水曜日の彼が喋らない理由だった。
今日はそんな私たちの気持ちを全部、千里ちゃんに届けたいと思って、完成した本を持ってきた。
すかさず葉山くんが提案する。
「おい京本、せっかくだから千里たんに朗読してやったらどうだ」
「あっ、それいい考えね。絶対、京本くんの声を聴きたがっていると思う」
「ええっ、みんなに聴かれるのはさすがに照れるな。でも、それもいいかもね」
京本くんは本を手に取り感慨深そうに表紙を眺める。私たちはその物語に、こんな題名をつけていた。
『水曜日のライト・フレンズ』
著 京本和也
高円寺有紗
表紙をめくると、最初に書かれている言葉は――。
『この物語を、楠千里に捧げる』
「千里たん、聴いていてくれよ。いよいよ公開するぜ、ヒャッホー!」
「なんか騒がしくなりそうだ。やっぱりふたりきりにしてもらおうかな」
「えーやだよ、私だって聴きたいもん。千里ちゃんばっかりずるーい」
千里ちゃん、私たちは相も変わらず好き勝手なことを言っている。そんな気軽な関係は、これからも続きそうな気がしているんだ。
ほんとうにでこぼこな友達だよ。みんなすこしずつ違っているけれど、それでいいんだと思う。
千里ちゃんと私たちの間にも違いがあって、でもみんな、その違いを飛び越える勇気を持っていた。私たちはそんな勇気をたくさんの人に広げて、もっと自由な世界を作らなくちゃいけないと思っている。
だって、これから私たちは広い世界でさまざまな人たちと出会い、誰かが誰かを照らしたり、支えたり、励ましたり、そして――好きになったりすると思うのだから。
私たちはみんな、そんなふうにたくさんのありがとうを抱えて生きてゆくんだ。
それから京本くんは、ゆったりとした口調で私たちの本を読み始める。
穏やかな声調で紡がれる物語が、千里ちゃんの部屋に広がってゆく。
額縁の中できらめく笑顔が、やわらかな青陽の風になって、私たちの心の穂先をそっと揺らしてゆくようだった。
【了】