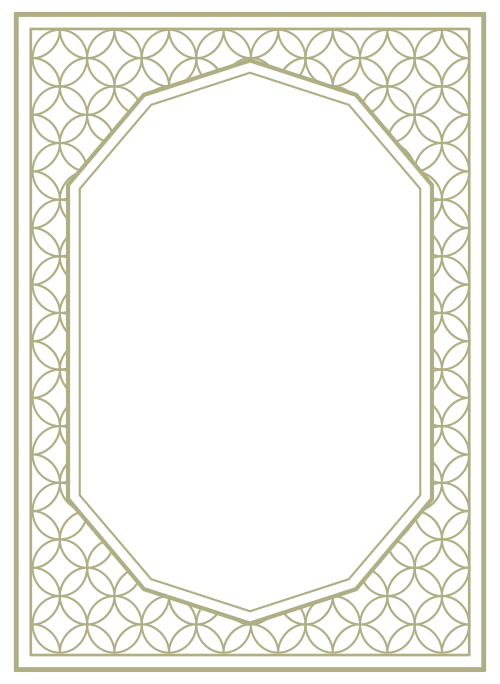みんなが、あたしの光になってくれた。和也くんも、有紗ちゃんも、陽一くんも、あたしの大切なライト・フレンズだよ!
あたしの世界が広がっていく。大切な友達が増えていく。幸せな水曜日が必ず訪れる。別れを覚悟しているのに、すごく嬉しくて、すごく楽しくて、そのぶん、きっと――みんなを悲しませてしまう。
友達はみんな最高で、それなのにあたしだけが最低だった……。
それでも、みんなと離れたくない。その一心であたしは病気を隠し続けた。病気が再発したと気づいても、みんなを遠ざけることができず、結局はみんなの前で具合が悪くなって倒れてしまった。
きっと、あたしが一番ずるい人間なんだよ。薄れていく意識の中で、そう思っていた。
だからあたしは、みんなにごめんねの気持ちがたくさん。
でもね、最後にもうすこしだけ、身勝手を許してほしいの。
それは――あたしのことを忘れないでいてほしいっていう、一方的なお願いなんだ。
あたしは空気になっても、世界のどこかには必ず存在している。あたしの光になってくれた、ライト・フレンズのみんなを見ていたいの。
それから和也くん、あたしの一番の心配はきみなんだよ。和也くんは義理堅くて頑固だから、あたしがいなくなってもおんなじ水曜日をえんえんと続けていそうなんだもん。だからね、このメッセージを残す一番の理由はそれなんだよ。
どんな物語だって、必ずエンディングが訪れるものよね。
だからね、きみとあたしの物語は、ここでおしまいになるの。
というわけで、これからあたしが和也くんに感謝を込めてエンドロールを贈ります。歌が終わったら、そこから先は和也くんの新しい物語が始まるんだよ』
そう言って千里ちゃんはおおきく息を吸い込んだようだった。かすかな空気の流れが、録音された音の中に感じられた。
千里ちゃんは、京本くんの優しさと誠実さをほんとうによくわかっていた。だから、京本くんを未来に送りだすために、このメッセージを残したんだ。
京本くんは受け入れる覚悟を決めたようで、ぎゅっと目をつぶり両手を握りしめる。ああ、彼の水曜日が終わりを告げるんだ。
ふたりの特別な関係が迎える結末に、私の胸は燃えるように熱くなる。もう、息も吸えないくらいだった。
千里ちゃんの最後の歌が流れる。
それは聴いたことのない曲だった。千里ちゃんが和也くんのために作曲した曲なんだと、私はすぐに気づいた。
どこまでも澄んだ聖歌のような歌声は、そんなふたりのエンディングにとてもふさわしい。
――ちいさなひかりがおちてきた
――あけないよるをともす、あたたかいひかりが
千里ちゃんの透明な声色は、まるで天使の歌声のよう。この曲の神秘的な響きをより引き立たせている。
京本くんは、音の粒子に込められた千里ちゃんの想いをひとつ残らず掬いあげるかのように、真剣に聴き入っていた。
――きみがえがく、いろあざやかなせかいがあふれて
――わたしのうたごえよ、きみのせかいにひびきわたれ
隣にいる私にさえ、ふたりの世界がどんなに美しい聖域だったのか伝わってくる。そして千里ちゃんは、この歌の中にみんなの未来への希望を込めているんだ。
千里ちゃんの魂が、歌に乗ってあふれだす。千里ちゃんが苦しいことも悲しいこともぜんぶ受け止めて、未来に繋がる光の道へと昇華させてゆく。
――みんなのたましいが、そらにまいあがる
――かぜのささやきも、たいようのぬくもりも、ぜんぶつかまえて
――おおきなわになって、わたしをつつんで、てらしだしてくれる
もうとっくに、涙で視界がおぼつかなくなっていた。あふれる涙がこんなにも熱いものだなんて、初めて知った。
千里ちゃんに会えて、ほんとうに嬉しい。みんなを繋げてくれて、心から感謝している。こんな大切な友達のこと、私はずっと忘れたくない。いろんな感情がいっぺんに混ざり合って、ぎゅっとちいさな思い出の塊になって、心の奥に溶け込んでゆく。
――わたしはおもいでのなかの、ちいさなひかりになって
――いつまでも、いつまでも、みんなのなかでいきている
? 風に運ばれるように歌が消えていくと、千里ちゃんは最後にひとこと、そっと囁いた。
『みんな、大好きだったよ――』
ぷつりと、ボイスレコーダーの音が切れた。
部屋が静寂に包まれ、みんな言葉を失っていた。私はただ、心が麻酔をかけられたように熱くじーんと痺れていて、両目から静かにこぼれる雫を拭うことしかできないでいた。
ようやっと、葉山くんが嗚咽の混ざる声を発する。
「おい京本……おまえ、千里たんにそこまで想われていたなんて、ほんっとに幸せなやつだよな。永遠の誓い、やってあげてよかったよなぁ……」
京本くんは涙をごしごしと制服の袖で拭い顔をあげた。ぼろぼろの表情だったけれど、その崩れた顔こそ、千里ちゃんに対する想いの証のように思える。
「ああ、僕はなんにも知らなかったんだなぁ。千里が僕を目指して頑張っていたことも、たくさんの苦難を乗り越えていたことも」
「でも、おまえの執拗な水曜日のおかげで、千里たんは幸せに浸れたんだな。千里たんの中では、おまえは間違いなく最高の彼氏だったよな」
「僕だって……大好きだよ、千里……」
ふたりの言葉は、私の胸をさらに熱くさせる。千里ちゃんを心に浮かべて語りかける。
――千里ちゃん、想いはちゃんと届いたからね。
「……なあ、葉山」
「なんだよ京本」
「悪いんだけどさ、死ぬほど泣いても……いいか?」
「そっか。じゃあ俺も付き合ってやるよ……」
「わ……私だって、我慢できるはずがないよぉ」
「いいぞ、有紗……おまえも泣き虫同盟だな」
とめどなくあふれる涙は頬から床へとこぼれ落ち、遠慮のない慟哭が京本くんの部屋に響く。
そう、私たちはみんな同じ人間なんだ。大切な人のために、いくらでも泣くことのできる、幸せな生き物だ。
だから今は、みんなで千里ちゃんのことを想いたい。いっぱい泣いて、涙を流し尽くしたら、すこしだけでも前を向いて、ちいさな一歩を踏みだそう。
そしてちゃんと、千里ちゃんの願う、光ある未来を――。
あたしの世界が広がっていく。大切な友達が増えていく。幸せな水曜日が必ず訪れる。別れを覚悟しているのに、すごく嬉しくて、すごく楽しくて、そのぶん、きっと――みんなを悲しませてしまう。
友達はみんな最高で、それなのにあたしだけが最低だった……。
それでも、みんなと離れたくない。その一心であたしは病気を隠し続けた。病気が再発したと気づいても、みんなを遠ざけることができず、結局はみんなの前で具合が悪くなって倒れてしまった。
きっと、あたしが一番ずるい人間なんだよ。薄れていく意識の中で、そう思っていた。
だからあたしは、みんなにごめんねの気持ちがたくさん。
でもね、最後にもうすこしだけ、身勝手を許してほしいの。
それは――あたしのことを忘れないでいてほしいっていう、一方的なお願いなんだ。
あたしは空気になっても、世界のどこかには必ず存在している。あたしの光になってくれた、ライト・フレンズのみんなを見ていたいの。
それから和也くん、あたしの一番の心配はきみなんだよ。和也くんは義理堅くて頑固だから、あたしがいなくなってもおんなじ水曜日をえんえんと続けていそうなんだもん。だからね、このメッセージを残す一番の理由はそれなんだよ。
どんな物語だって、必ずエンディングが訪れるものよね。
だからね、きみとあたしの物語は、ここでおしまいになるの。
というわけで、これからあたしが和也くんに感謝を込めてエンドロールを贈ります。歌が終わったら、そこから先は和也くんの新しい物語が始まるんだよ』
そう言って千里ちゃんはおおきく息を吸い込んだようだった。かすかな空気の流れが、録音された音の中に感じられた。
千里ちゃんは、京本くんの優しさと誠実さをほんとうによくわかっていた。だから、京本くんを未来に送りだすために、このメッセージを残したんだ。
京本くんは受け入れる覚悟を決めたようで、ぎゅっと目をつぶり両手を握りしめる。ああ、彼の水曜日が終わりを告げるんだ。
ふたりの特別な関係が迎える結末に、私の胸は燃えるように熱くなる。もう、息も吸えないくらいだった。
千里ちゃんの最後の歌が流れる。
それは聴いたことのない曲だった。千里ちゃんが和也くんのために作曲した曲なんだと、私はすぐに気づいた。
どこまでも澄んだ聖歌のような歌声は、そんなふたりのエンディングにとてもふさわしい。
――ちいさなひかりがおちてきた
――あけないよるをともす、あたたかいひかりが
千里ちゃんの透明な声色は、まるで天使の歌声のよう。この曲の神秘的な響きをより引き立たせている。
京本くんは、音の粒子に込められた千里ちゃんの想いをひとつ残らず掬いあげるかのように、真剣に聴き入っていた。
――きみがえがく、いろあざやかなせかいがあふれて
――わたしのうたごえよ、きみのせかいにひびきわたれ
隣にいる私にさえ、ふたりの世界がどんなに美しい聖域だったのか伝わってくる。そして千里ちゃんは、この歌の中にみんなの未来への希望を込めているんだ。
千里ちゃんの魂が、歌に乗ってあふれだす。千里ちゃんが苦しいことも悲しいこともぜんぶ受け止めて、未来に繋がる光の道へと昇華させてゆく。
――みんなのたましいが、そらにまいあがる
――かぜのささやきも、たいようのぬくもりも、ぜんぶつかまえて
――おおきなわになって、わたしをつつんで、てらしだしてくれる
もうとっくに、涙で視界がおぼつかなくなっていた。あふれる涙がこんなにも熱いものだなんて、初めて知った。
千里ちゃんに会えて、ほんとうに嬉しい。みんなを繋げてくれて、心から感謝している。こんな大切な友達のこと、私はずっと忘れたくない。いろんな感情がいっぺんに混ざり合って、ぎゅっとちいさな思い出の塊になって、心の奥に溶け込んでゆく。
――わたしはおもいでのなかの、ちいさなひかりになって
――いつまでも、いつまでも、みんなのなかでいきている
? 風に運ばれるように歌が消えていくと、千里ちゃんは最後にひとこと、そっと囁いた。
『みんな、大好きだったよ――』
ぷつりと、ボイスレコーダーの音が切れた。
部屋が静寂に包まれ、みんな言葉を失っていた。私はただ、心が麻酔をかけられたように熱くじーんと痺れていて、両目から静かにこぼれる雫を拭うことしかできないでいた。
ようやっと、葉山くんが嗚咽の混ざる声を発する。
「おい京本……おまえ、千里たんにそこまで想われていたなんて、ほんっとに幸せなやつだよな。永遠の誓い、やってあげてよかったよなぁ……」
京本くんは涙をごしごしと制服の袖で拭い顔をあげた。ぼろぼろの表情だったけれど、その崩れた顔こそ、千里ちゃんに対する想いの証のように思える。
「ああ、僕はなんにも知らなかったんだなぁ。千里が僕を目指して頑張っていたことも、たくさんの苦難を乗り越えていたことも」
「でも、おまえの執拗な水曜日のおかげで、千里たんは幸せに浸れたんだな。千里たんの中では、おまえは間違いなく最高の彼氏だったよな」
「僕だって……大好きだよ、千里……」
ふたりの言葉は、私の胸をさらに熱くさせる。千里ちゃんを心に浮かべて語りかける。
――千里ちゃん、想いはちゃんと届いたからね。
「……なあ、葉山」
「なんだよ京本」
「悪いんだけどさ、死ぬほど泣いても……いいか?」
「そっか。じゃあ俺も付き合ってやるよ……」
「わ……私だって、我慢できるはずがないよぉ」
「いいぞ、有紗……おまえも泣き虫同盟だな」
とめどなくあふれる涙は頬から床へとこぼれ落ち、遠慮のない慟哭が京本くんの部屋に響く。
そう、私たちはみんな同じ人間なんだ。大切な人のために、いくらでも泣くことのできる、幸せな生き物だ。
だから今は、みんなで千里ちゃんのことを想いたい。いっぱい泣いて、涙を流し尽くしたら、すこしだけでも前を向いて、ちいさな一歩を踏みだそう。
そしてちゃんと、千里ちゃんの願う、光ある未来を――。