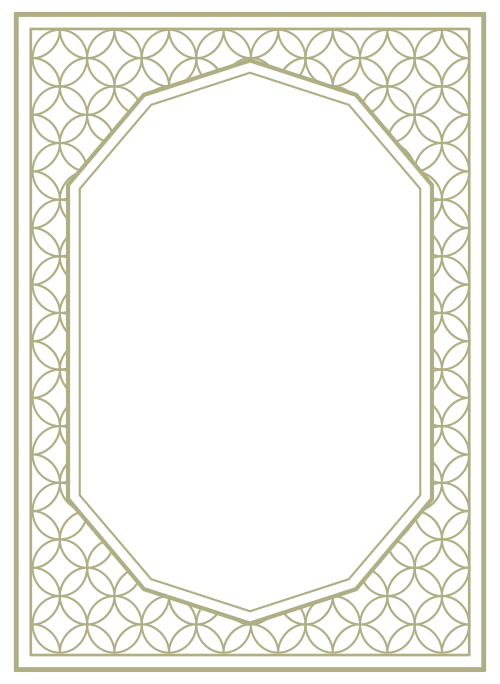「京本、おまえのはなんて書いてあるんだ」
私もはやる気持ちでつい、前のめりになってしまう。京本くんの顔と便箋を交互に見ていると、彼は声を振り絞るようにこう言った。
「僕のは――『さがして』だった」
――捜して……?
繋げて読むと、「みんなで・わたしを・さがして」だ。意味が理解できず困惑しているとまずは葉山くんが意見を口にする。
「もしかするとあのとき、千里たんはこれを俺たちに残して、ひとりで出かけたっていうのか? 鬼ごっこかなにかのつもりで」
あのとき、というのは千里ちゃんが姿を消したときのことだ。その目的は結局、わからずじまいだった。
「じゃあ、私たちはこの手紙に気づかなくて、千里ちゃんは無駄足だったっていうこと?」
「うーん、どうだろう……」
私たちが腑に落ちないでいると、京本くんははっきりと反論した。
「でも、僕がこれをもらったのは、千里が行方不明になった日よりも後のことだよ」
「えっ、どうしてそう言い切れるの?」
「だってこれ、ジャンパーのポケットに入っていたんだ。屋上で会ったとき、千里が僕のポケットに忍ばせたはずなんだ」
私と葉山くんの便箋はたぶん、お見舞いのときに隙を見てカバンの中に忍び込ませたのだと思う。千里ちゃんなら耳と手探りで可能なことだ。
でも、京本くんは千里ちゃんと会っていなかったから、それまで便箋を渡す機会はなかったはずだ。
もしそうなら、この「捜して」が意味するのは、いなくなった千里ちゃんのことではない。
ふと、千里ちゃんが眠りにつく前、京本くんの腕の中で囁いた言葉が脳裏をよぎる。ずっと引っかかっていた、意味のよくわからなかった言葉だ。
『これからも、友達とは仲良く、だよ。そうすればまた、あたしに会えるかもね』
そのときは朦朧としていたからだと思っていたけれど、もしもその言葉に意味があるとしたら――。
『友達とは仲良く』というのは、私たちが繋がっていなければ解けない『マインド・コネクト・ゲーム』を出題したということ。
そして、『また、あたしに会えるかも』というのは、自分自身のなにかを、どこかに残したということ。
だからこのメッセージの意味するところは――。
「これさ、千里ちゃんが私たちになにかを残していて、それを捜すように、っていう意味のはずだよ!」
「まっ、まじかよ! でもそうだとすると、千里たんがいなくなったのは――」
「うん、京本くんの住んでいる街のどこかに、重要なものを忍ばせに行っていたはずよ」
「そうだったのか!」
心が鐘を打ちつけたかのように震える。隠されたほんとうの意図は、絶対に解かなくちゃいけない。
それができるのは――きっと、彼しかいない。
「ねえ、その場所は京本くんには心当たりがあると思う。それも絶対、千里ちゃんとの時間の中にヒントがあるはずよ」
「僕が……知っているはず……?」
京本くんは頭を抱え込み黙考する。絡まる記憶の糸の中から真実の一本をつかもうとしているようで、頭を掻きむしり何度も首を横に振る。
その動きが突然、ぴたりと止まった。ぽろっとひとこと、低い声でもらす。
「……きっとあそこだ」
そしてゆらりと立ち上がった。
★
私たちは千里ちゃんの足取りを追うために学校を抜けだして電車に乗り込んだ。
向かった先は――京本くんがアルバイトをしていた古本屋。駅から出て商店街に入り、すぐのところにあった。
皆で雑談をしていたとき、千里ちゃんは京本くんにアルバイト先をそれとなく尋ねていた。千里ちゃんの本心は、京本くんが働いていたこの本屋、「エルシド」を訪れてみたかったということなのだろう。
「ほへー、やけに閑散としているな」
「ほら、そこ声がおおきい! 学校をさぼっているの自覚してよね」
「すみません古本さん、ご無沙汰しております」
京本くんはカウンターに鎮座する初老の男性に挨拶をする。古本さんと呼ばれたその男性はうなずき、のっそりと立ち上がり歩みよってきて、京本くんと向かいあった。
「ようやっと来おったな。気づいていないのかと心配したぞ」
京本くんの肩にしわの刻まれた手を軽く乗せる。
「……古本さん、千里はここに来ていたんですね」
「ああ。千里ちゃんというのだな」
やっぱり京本くんの考えは的を射ていた。千里ちゃんは京本くんの働くこの本屋さんを訪れていたんだ。
「ところでその子、目が見えないようだが、歩く足元もおぼつかなかった。目以外にどこか具合が悪いのか?」
「……じつは重い病気を患っていて、先日他界しました」
「むぅ、そうだったのか。お若いのに……」
古本さんは目がしらを押さえて顔を伏せる。
それから私たちに背を向け、店の奥へと足を進めていく。ついてゆくと、天井まで続くおおきな本棚があり、その前で足を止めた。棚の最上段を仰いでこう言う。
「ほんとうに、目が見えないのによくきたものだ。その子は、この場所に立って本棚を見上げていた」
私は本棚の前にたたずむ千里ちゃんの姿を想像した。この場所を目指すのはすごく勇気が必要だったろう。それに命懸けだったはず。でも、どうしてそこまで無理をして、って思う。
古本さんがさらに言葉を綴る。
「京本少年、この場所は、きみの持ってくる本と同じ匂いがすると言っていたぞ」
「同じ匂い、ですか」
ああ、そうだったのか。千里ちゃんは、京本くんとふたりでいられる本の世界をたどっていたんだ。その源泉が、京本くんの働いていたこの本屋なのか。それほどまでに、千里ちゃんにとっては京本くんとの時間がかけがえのないものだったんだ。
古本さんはふたたび足を運び、レジに戻ってカウンターの下に手を差し込む。取りだしたのはちいさな巾着袋だった。
「あの子はこう言っていた。『大切な友達が必ずこれを取りに来ます。そのときまで預かっていてもらえますか』とな。もちろん、それが京本少年のことだとも、な」
「千里が……僕のために……」
「だから俺はこの巾着袋を受け取り、『その願いは必ず叶えるから、安心して帰りなさい』と伝えたよ。その子はすこぶる安心した顔をして、よろよろと店を出て行ったのだ」
古本さんは京本くんの目の前に巾着袋を差しだす。京本くんは両手で包み込むように、その巾着袋を受け取った。袋の外から感触を確かめ、はっとした顔になった。
すぐさま縛られた巾着袋の紐を解き中身を探る。出てきたものを見て、私は唖然とした。
それは――私たちがプレゼントした、あのボイスレコーダーだった。
京本くんは目がふわふわと浮いていて、夢か現実かわからないみたいな顔だった。
私もはやる気持ちでつい、前のめりになってしまう。京本くんの顔と便箋を交互に見ていると、彼は声を振り絞るようにこう言った。
「僕のは――『さがして』だった」
――捜して……?
繋げて読むと、「みんなで・わたしを・さがして」だ。意味が理解できず困惑しているとまずは葉山くんが意見を口にする。
「もしかするとあのとき、千里たんはこれを俺たちに残して、ひとりで出かけたっていうのか? 鬼ごっこかなにかのつもりで」
あのとき、というのは千里ちゃんが姿を消したときのことだ。その目的は結局、わからずじまいだった。
「じゃあ、私たちはこの手紙に気づかなくて、千里ちゃんは無駄足だったっていうこと?」
「うーん、どうだろう……」
私たちが腑に落ちないでいると、京本くんははっきりと反論した。
「でも、僕がこれをもらったのは、千里が行方不明になった日よりも後のことだよ」
「えっ、どうしてそう言い切れるの?」
「だってこれ、ジャンパーのポケットに入っていたんだ。屋上で会ったとき、千里が僕のポケットに忍ばせたはずなんだ」
私と葉山くんの便箋はたぶん、お見舞いのときに隙を見てカバンの中に忍び込ませたのだと思う。千里ちゃんなら耳と手探りで可能なことだ。
でも、京本くんは千里ちゃんと会っていなかったから、それまで便箋を渡す機会はなかったはずだ。
もしそうなら、この「捜して」が意味するのは、いなくなった千里ちゃんのことではない。
ふと、千里ちゃんが眠りにつく前、京本くんの腕の中で囁いた言葉が脳裏をよぎる。ずっと引っかかっていた、意味のよくわからなかった言葉だ。
『これからも、友達とは仲良く、だよ。そうすればまた、あたしに会えるかもね』
そのときは朦朧としていたからだと思っていたけれど、もしもその言葉に意味があるとしたら――。
『友達とは仲良く』というのは、私たちが繋がっていなければ解けない『マインド・コネクト・ゲーム』を出題したということ。
そして、『また、あたしに会えるかも』というのは、自分自身のなにかを、どこかに残したということ。
だからこのメッセージの意味するところは――。
「これさ、千里ちゃんが私たちになにかを残していて、それを捜すように、っていう意味のはずだよ!」
「まっ、まじかよ! でもそうだとすると、千里たんがいなくなったのは――」
「うん、京本くんの住んでいる街のどこかに、重要なものを忍ばせに行っていたはずよ」
「そうだったのか!」
心が鐘を打ちつけたかのように震える。隠されたほんとうの意図は、絶対に解かなくちゃいけない。
それができるのは――きっと、彼しかいない。
「ねえ、その場所は京本くんには心当たりがあると思う。それも絶対、千里ちゃんとの時間の中にヒントがあるはずよ」
「僕が……知っているはず……?」
京本くんは頭を抱え込み黙考する。絡まる記憶の糸の中から真実の一本をつかもうとしているようで、頭を掻きむしり何度も首を横に振る。
その動きが突然、ぴたりと止まった。ぽろっとひとこと、低い声でもらす。
「……きっとあそこだ」
そしてゆらりと立ち上がった。
★
私たちは千里ちゃんの足取りを追うために学校を抜けだして電車に乗り込んだ。
向かった先は――京本くんがアルバイトをしていた古本屋。駅から出て商店街に入り、すぐのところにあった。
皆で雑談をしていたとき、千里ちゃんは京本くんにアルバイト先をそれとなく尋ねていた。千里ちゃんの本心は、京本くんが働いていたこの本屋、「エルシド」を訪れてみたかったということなのだろう。
「ほへー、やけに閑散としているな」
「ほら、そこ声がおおきい! 学校をさぼっているの自覚してよね」
「すみません古本さん、ご無沙汰しております」
京本くんはカウンターに鎮座する初老の男性に挨拶をする。古本さんと呼ばれたその男性はうなずき、のっそりと立ち上がり歩みよってきて、京本くんと向かいあった。
「ようやっと来おったな。気づいていないのかと心配したぞ」
京本くんの肩にしわの刻まれた手を軽く乗せる。
「……古本さん、千里はここに来ていたんですね」
「ああ。千里ちゃんというのだな」
やっぱり京本くんの考えは的を射ていた。千里ちゃんは京本くんの働くこの本屋さんを訪れていたんだ。
「ところでその子、目が見えないようだが、歩く足元もおぼつかなかった。目以外にどこか具合が悪いのか?」
「……じつは重い病気を患っていて、先日他界しました」
「むぅ、そうだったのか。お若いのに……」
古本さんは目がしらを押さえて顔を伏せる。
それから私たちに背を向け、店の奥へと足を進めていく。ついてゆくと、天井まで続くおおきな本棚があり、その前で足を止めた。棚の最上段を仰いでこう言う。
「ほんとうに、目が見えないのによくきたものだ。その子は、この場所に立って本棚を見上げていた」
私は本棚の前にたたずむ千里ちゃんの姿を想像した。この場所を目指すのはすごく勇気が必要だったろう。それに命懸けだったはず。でも、どうしてそこまで無理をして、って思う。
古本さんがさらに言葉を綴る。
「京本少年、この場所は、きみの持ってくる本と同じ匂いがすると言っていたぞ」
「同じ匂い、ですか」
ああ、そうだったのか。千里ちゃんは、京本くんとふたりでいられる本の世界をたどっていたんだ。その源泉が、京本くんの働いていたこの本屋なのか。それほどまでに、千里ちゃんにとっては京本くんとの時間がかけがえのないものだったんだ。
古本さんはふたたび足を運び、レジに戻ってカウンターの下に手を差し込む。取りだしたのはちいさな巾着袋だった。
「あの子はこう言っていた。『大切な友達が必ずこれを取りに来ます。そのときまで預かっていてもらえますか』とな。もちろん、それが京本少年のことだとも、な」
「千里が……僕のために……」
「だから俺はこの巾着袋を受け取り、『その願いは必ず叶えるから、安心して帰りなさい』と伝えたよ。その子はすこぶる安心した顔をして、よろよろと店を出て行ったのだ」
古本さんは京本くんの目の前に巾着袋を差しだす。京本くんは両手で包み込むように、その巾着袋を受け取った。袋の外から感触を確かめ、はっとした顔になった。
すぐさま縛られた巾着袋の紐を解き中身を探る。出てきたものを見て、私は唖然とした。
それは――私たちがプレゼントした、あのボイスレコーダーだった。
京本くんは目がふわふわと浮いていて、夢か現実かわからないみたいな顔だった。