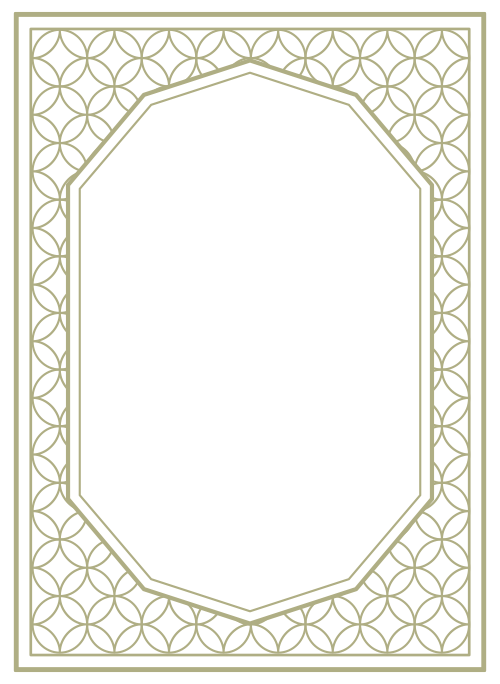千里ちゃんがいなくなってからというもの、私たちは互いに自然と距離を置くようになっていた。三学期の頭に席替えがあって、葉山くんとも離れ離れになった。
でも、そろそろ心配になってきたから、私は自分から葉山くんに声をかけることにした。
「葉山くん、京本くんってだいぶ休んでいたけど、進級は大丈夫そうなの?」
「ああ、有紗か。まあ、京本の母ちゃんと俺で直談判したから、先生は事情を汲むって言っていたけどさ」
「でもぜんぜん、授業に出てないじゃない。また今日も屋上でしょ、こんなに寒いのに」
京本くんは結局、千里ちゃんのお葬式に出席しなかった。お線香をあげに行ったことすらない。それどころかひとことも喋らなくなり、ずっと本を読んでいるばかりだ。
「千里たんは京本と過ごせて幸せだったろうな。それに、最後に京本と会えたから救われたと俺は思う。でも、今度は京本のやつが廃人かよ……」
「京本くんは今、水曜日の中に閉じ込もっていると思うの。千里ちゃんがいた頃の思い出の中にね」
「はぁ、確かにな。あいつらの関係は特別だったからなぁ」
私はうんうんとうなずいて同意するけれど、私だって千里ちゃんの笑顔を思いだすと、寂しさがあふれてきて涙腺がゆるんでしまう。
「京本のやつを思い出から解放するってのは、俺らにできることじゃねえよ」
葉山くんは両腕を組んで眉根をよせた。京本くんはこのままずっと千里ちゃんとの思い出の世界に棲み続けるのかな、とひどく心配になる。
葉山くんは「あーあ、どうすりゃいいんだろうな」と言って足を机の上に投げだした。勢い余って、机に置いた私のカバンが蹴っ飛ばされた。カバンが宙を舞い鈍い音を立てて落ち、中身が床に散乱する。
「あっちゃー。わりぃ、有紗」
「もうっ、相変わらず足癖悪いんだから」
葉山くんはすまなそうに教科書を拾って私に手渡す。
受け取って仕舞おうとすると、ふと、空になったカバンの奥底にちいさな封筒が見えた。なんだろう、底板《ベルポーレン》の裏側に回り込んでいて気づかなかったみたいだ。
記憶にないその封筒を取りだして開くと、桃色の便箋が一枚入っていた。けれど文字が記されているわけではなく、ふっくらと膨らんだちいさなポッティングシールがたくさん貼られている。碁盤のように等間隔だけど、ところどころ抜け落ちている。
なんだろうと思い眺めると、葉山くんがその便箋を指さし唖然としていた。
「それ……俺のカバンにも入っていたんだけど」
「えっ?」
葉山くんがせかせかと自分のカバンを開けて中身を漁る。
「最初はラブレターかと思ったんだけどさ。よくわからないけど、気になるものだったから一応、取っておいたんだ」
見せてくれた便箋は私と同じもので、やっぱりポッティングシールが並んで貼られていた。でも、シールの並び方は私のとは違っている。
ふたりが似たものを持っているなんて、なにか重要な意味が隠されているんじゃないかと私は直感した。それに、女子向けのかわいい絵柄だったので、そうなると心当たりはひとつしかない。同時に葉山くんもはっとなった。
「もしかして、これって……」
「俺らが持っているっていうことは、つまり……」
私たちは顔を見合わせ、同時に声をあげる。
「千里ちゃんからだ!」
「千里たんからだ!」
クラスメートがいっぺんに私たちのほうを見たので、すぐに声をひそめる。
「きっとそうだよ」
「じゃあ、なんのためにだよ。シールが並んでいるだけで、あんまり芸術的とはいえねえし」
「そうよね、目が見えないから便箋の使い道がなかったんじゃないかな。だからこの手紙に意味なんて――」
その瞬間、雷光のようなひらめきが降りてきて私は息をのんだ。
そうだ、千里ちゃんは目の見えない子だ。
だから、この便箋の上に並んだシールが意味することは――。
「これ、きっと点字だよ!」
「ああっ、そうだったのか!」
興奮して声を張り上げてしまい、クラスメートがまたもや怪訝そうに視線を向ける。
そのとき授業開始のチャイムが鳴った。もう、授業が始まってしまう。私はいてもたってもいられなくなり、葉山くんの腕をつかんで引っ張る。
「ねえ、京本くんのところに行こうよ」
「ああん、授業はいいのかよ」
「なに言っているのよ、授業よりもずっと重要なことでしょ!」
「おおっ、そうか、そうだよな。いいぞ有紗、これでおまえもちゃらんぽらん同盟だ」
葉山くんは勢いよく立ち上がった。クラスメートが投げかける視線を振り払い、ふたりで教室を駆けだしていく。
たどり着いた屋上の扉を力強く開ける。そこには花壇の縁に座り、本を読みふける京本くんの姿があった。
「京本くん、聞いて!」
下を向いたままの京本くんに駆けよると、京本くんはのっそりと顔を起こす。その目は死んだ魚のように虚ろだった。すぐさま便箋を目の前に差しだす。
「京本くんはこれ、持っている? 千里ちゃんからのメッセージだよ」
京本くんは驚き、目の奥に輝きを宿す。それから手にした本をぱらぱらとめくる。ぴたりと手が止まると、そこには折りたたまれた便箋がはさまっていた。栞のかわりに使っていたみたいだ。
開くと同じ柄の便箋で、ポッティングシールが不揃いに並んでいる。
「ああっ、やっぱりそうだ!」
彼が持っていたことで、私は確信を得た。
京本くんは黙ったままだったけれど、便箋を挟む指先はかすかに震えていた。
「ねえ、このメッセージ、みんなで読んでみようよ」
「メッセージ? ――まさかこれ、点字ってことなのか?」
京本くんは見たことがないほど目を丸くしている。
「たぶんね」
スマホを開き、点字の翻訳サイトを検索するとすぐにヒットした。みんなで画面をのぞき込みながら、それぞれ自分がもらった便箋に記された点字をひとつひとつ文字に変換してゆく。
読むと私の手紙には『みんなで』と書かれていた。伝えると同時に葉山くんも声をあげる。
「俺のは『わたしを』だってさ!」
その繋がりに私は、いや、私たちは皆、心当たりがあった。
「これ、ひょっとして……」
「ああ、きっとそうだ」
全身にぞわりと鳥肌が立った。
そう、これは千里ちゃんが私たちに仕掛けた『マインド・コネクト・ゲーム』としか思えなかった。千里ちゃんはなんらかの理由で私たちを行動させようと誘っているに違いない。
でも、それだけじゃない。自分がいなくなっても、みんなと一緒に楽しんでいたいという思いが込められているように思えた。
葉山くんが京本くんの顔をのぞき込む。
でも、そろそろ心配になってきたから、私は自分から葉山くんに声をかけることにした。
「葉山くん、京本くんってだいぶ休んでいたけど、進級は大丈夫そうなの?」
「ああ、有紗か。まあ、京本の母ちゃんと俺で直談判したから、先生は事情を汲むって言っていたけどさ」
「でもぜんぜん、授業に出てないじゃない。また今日も屋上でしょ、こんなに寒いのに」
京本くんは結局、千里ちゃんのお葬式に出席しなかった。お線香をあげに行ったことすらない。それどころかひとことも喋らなくなり、ずっと本を読んでいるばかりだ。
「千里たんは京本と過ごせて幸せだったろうな。それに、最後に京本と会えたから救われたと俺は思う。でも、今度は京本のやつが廃人かよ……」
「京本くんは今、水曜日の中に閉じ込もっていると思うの。千里ちゃんがいた頃の思い出の中にね」
「はぁ、確かにな。あいつらの関係は特別だったからなぁ」
私はうんうんとうなずいて同意するけれど、私だって千里ちゃんの笑顔を思いだすと、寂しさがあふれてきて涙腺がゆるんでしまう。
「京本のやつを思い出から解放するってのは、俺らにできることじゃねえよ」
葉山くんは両腕を組んで眉根をよせた。京本くんはこのままずっと千里ちゃんとの思い出の世界に棲み続けるのかな、とひどく心配になる。
葉山くんは「あーあ、どうすりゃいいんだろうな」と言って足を机の上に投げだした。勢い余って、机に置いた私のカバンが蹴っ飛ばされた。カバンが宙を舞い鈍い音を立てて落ち、中身が床に散乱する。
「あっちゃー。わりぃ、有紗」
「もうっ、相変わらず足癖悪いんだから」
葉山くんはすまなそうに教科書を拾って私に手渡す。
受け取って仕舞おうとすると、ふと、空になったカバンの奥底にちいさな封筒が見えた。なんだろう、底板《ベルポーレン》の裏側に回り込んでいて気づかなかったみたいだ。
記憶にないその封筒を取りだして開くと、桃色の便箋が一枚入っていた。けれど文字が記されているわけではなく、ふっくらと膨らんだちいさなポッティングシールがたくさん貼られている。碁盤のように等間隔だけど、ところどころ抜け落ちている。
なんだろうと思い眺めると、葉山くんがその便箋を指さし唖然としていた。
「それ……俺のカバンにも入っていたんだけど」
「えっ?」
葉山くんがせかせかと自分のカバンを開けて中身を漁る。
「最初はラブレターかと思ったんだけどさ。よくわからないけど、気になるものだったから一応、取っておいたんだ」
見せてくれた便箋は私と同じもので、やっぱりポッティングシールが並んで貼られていた。でも、シールの並び方は私のとは違っている。
ふたりが似たものを持っているなんて、なにか重要な意味が隠されているんじゃないかと私は直感した。それに、女子向けのかわいい絵柄だったので、そうなると心当たりはひとつしかない。同時に葉山くんもはっとなった。
「もしかして、これって……」
「俺らが持っているっていうことは、つまり……」
私たちは顔を見合わせ、同時に声をあげる。
「千里ちゃんからだ!」
「千里たんからだ!」
クラスメートがいっぺんに私たちのほうを見たので、すぐに声をひそめる。
「きっとそうだよ」
「じゃあ、なんのためにだよ。シールが並んでいるだけで、あんまり芸術的とはいえねえし」
「そうよね、目が見えないから便箋の使い道がなかったんじゃないかな。だからこの手紙に意味なんて――」
その瞬間、雷光のようなひらめきが降りてきて私は息をのんだ。
そうだ、千里ちゃんは目の見えない子だ。
だから、この便箋の上に並んだシールが意味することは――。
「これ、きっと点字だよ!」
「ああっ、そうだったのか!」
興奮して声を張り上げてしまい、クラスメートがまたもや怪訝そうに視線を向ける。
そのとき授業開始のチャイムが鳴った。もう、授業が始まってしまう。私はいてもたってもいられなくなり、葉山くんの腕をつかんで引っ張る。
「ねえ、京本くんのところに行こうよ」
「ああん、授業はいいのかよ」
「なに言っているのよ、授業よりもずっと重要なことでしょ!」
「おおっ、そうか、そうだよな。いいぞ有紗、これでおまえもちゃらんぽらん同盟だ」
葉山くんは勢いよく立ち上がった。クラスメートが投げかける視線を振り払い、ふたりで教室を駆けだしていく。
たどり着いた屋上の扉を力強く開ける。そこには花壇の縁に座り、本を読みふける京本くんの姿があった。
「京本くん、聞いて!」
下を向いたままの京本くんに駆けよると、京本くんはのっそりと顔を起こす。その目は死んだ魚のように虚ろだった。すぐさま便箋を目の前に差しだす。
「京本くんはこれ、持っている? 千里ちゃんからのメッセージだよ」
京本くんは驚き、目の奥に輝きを宿す。それから手にした本をぱらぱらとめくる。ぴたりと手が止まると、そこには折りたたまれた便箋がはさまっていた。栞のかわりに使っていたみたいだ。
開くと同じ柄の便箋で、ポッティングシールが不揃いに並んでいる。
「ああっ、やっぱりそうだ!」
彼が持っていたことで、私は確信を得た。
京本くんは黙ったままだったけれど、便箋を挟む指先はかすかに震えていた。
「ねえ、このメッセージ、みんなで読んでみようよ」
「メッセージ? ――まさかこれ、点字ってことなのか?」
京本くんは見たことがないほど目を丸くしている。
「たぶんね」
スマホを開き、点字の翻訳サイトを検索するとすぐにヒットした。みんなで画面をのぞき込みながら、それぞれ自分がもらった便箋に記された点字をひとつひとつ文字に変換してゆく。
読むと私の手紙には『みんなで』と書かれていた。伝えると同時に葉山くんも声をあげる。
「俺のは『わたしを』だってさ!」
その繋がりに私は、いや、私たちは皆、心当たりがあった。
「これ、ひょっとして……」
「ああ、きっとそうだ」
全身にぞわりと鳥肌が立った。
そう、これは千里ちゃんが私たちに仕掛けた『マインド・コネクト・ゲーム』としか思えなかった。千里ちゃんはなんらかの理由で私たちを行動させようと誘っているに違いない。
でも、それだけじゃない。自分がいなくなっても、みんなと一緒に楽しんでいたいという思いが込められているように思えた。
葉山くんが京本くんの顔をのぞき込む。