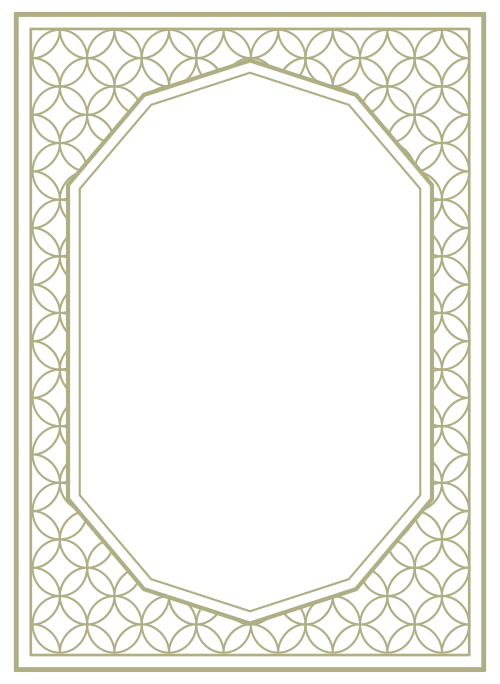でも、この歌は僕らのデュエットだ。僕も歌い手のひとりとして、千里と肩を並べている。
曲は男性パートへと移り、僕が歌う番となった。千里への言葉にできない想いを歌に乗せてゆく。
――che sei con me con me(きみが僕と一緒にいること)
千里は閉じたまぶたの顔で僕を見上げてちいさく微笑んだ。あふれた幸せが心からこぼれ落ちたかのような表情だった。
僕は今になってようやっと気づいた。僕たちはお互いの足りないものを求め合うように生きていたんだ。
――tu mia luna tu sei qui con me(きみは僕の月、僕とともにある)
千里が空虚だった僕の、生きる目的になってくれた。僕が千里に、たくさんの違った世界を見せてあげた。
僕たちは、まるで引力を宿しているかのように、互いを必要とし、必要とされて、同じ空間で同じ時間を過ごしてきた。
デュエットのパートに入ると、僕らは歌の中で出会い、互いの声を紡ぎ合わせてハーモニーを昇華させる。千里と僕の、最初で最後の共演だ。
ふたりでしっかりと手を繋ぎ、無限のリングを空に掲げる。
――con te io li rivivr?(あなたとともにまた生きて)
声が重なり、風になる。
空に溶けて永遠になる。
――con te partir?(あなたとともに旅立とう)
僕たちは、きっといつまでも繋がっている。
そうだ、千里と僕の友情は、永遠に続くんだ――。
歌が終焉を迎えると、千里は深く息を吐きだし、見上げるようにして微笑みかけてくれた。
思いのたけを伝えきったかのような、すがすがしい表情だった。
すべての力を使い切った千里は、僕の胸に身を預け、そっと倒れた。
まるで一枚の木の葉が、はかなく風にさらわれていくように――。
★
――それから十日後の、水曜日の午後。僕はひとりで校舎の屋上にいた。
あの日以来、千里は眠ったままだった。
千里が最後に僕の胸の中で囁いた言葉を思いだす。歌っていたときとはまるで別人のようなか細い声だった。
「和也くん、ごめんね。あたし、疲れちゃった……」
「千里、しっかりしてくれ!」
懸命に呼びかけるけれど、千里の意識はしだいに遠のいてゆく。千里は最後の力を振り絞り、僕の手を握りながらこうもらした。
「ううん、もうじゅうぶんだよ……でも、これからも……友達とは仲良く、だよ。そうすればまた、あたしに会えるかもね――」
それから千里は安心したようにゆったりと眠り込んでしまった。
僕はその日を境に閉じこもるのをやめた。登校を再開し、学校の帰りがけに病院に立ち寄り、千里を見舞っていた。
あどけない寝顔はただ、眠っているようにしか見えなくて、けれど話しかけても目を覚ますことはなかった。
フェンスにもたれかかり屹立した山々を眺めていると、さわさわと風が吹いてきた。すこしだけ春のやわらかさを宿していることに気づく。
まるで千里の笑顔のような、あたたかみのある風だった。
僕はそよ風の中に、千里の声を感じ取る。
――和也くん、いままでありがとね。
ああ、そうなのかと、なんとなく気づいた。
見慣れたはずの風景が、急に揺らいで見えた。
空を見上げてまぶたを閉じると、瞳の上に溜まった涙がはらりとこぼれ落ちる。
――千里、きみに会えて僕は幸せだったよ。
その日は千里の旅立ちにふさわしい、きれいなセレストブルーの空だった――。
曲は男性パートへと移り、僕が歌う番となった。千里への言葉にできない想いを歌に乗せてゆく。
――che sei con me con me(きみが僕と一緒にいること)
千里は閉じたまぶたの顔で僕を見上げてちいさく微笑んだ。あふれた幸せが心からこぼれ落ちたかのような表情だった。
僕は今になってようやっと気づいた。僕たちはお互いの足りないものを求め合うように生きていたんだ。
――tu mia luna tu sei qui con me(きみは僕の月、僕とともにある)
千里が空虚だった僕の、生きる目的になってくれた。僕が千里に、たくさんの違った世界を見せてあげた。
僕たちは、まるで引力を宿しているかのように、互いを必要とし、必要とされて、同じ空間で同じ時間を過ごしてきた。
デュエットのパートに入ると、僕らは歌の中で出会い、互いの声を紡ぎ合わせてハーモニーを昇華させる。千里と僕の、最初で最後の共演だ。
ふたりでしっかりと手を繋ぎ、無限のリングを空に掲げる。
――con te io li rivivr?(あなたとともにまた生きて)
声が重なり、風になる。
空に溶けて永遠になる。
――con te partir?(あなたとともに旅立とう)
僕たちは、きっといつまでも繋がっている。
そうだ、千里と僕の友情は、永遠に続くんだ――。
歌が終焉を迎えると、千里は深く息を吐きだし、見上げるようにして微笑みかけてくれた。
思いのたけを伝えきったかのような、すがすがしい表情だった。
すべての力を使い切った千里は、僕の胸に身を預け、そっと倒れた。
まるで一枚の木の葉が、はかなく風にさらわれていくように――。
★
――それから十日後の、水曜日の午後。僕はひとりで校舎の屋上にいた。
あの日以来、千里は眠ったままだった。
千里が最後に僕の胸の中で囁いた言葉を思いだす。歌っていたときとはまるで別人のようなか細い声だった。
「和也くん、ごめんね。あたし、疲れちゃった……」
「千里、しっかりしてくれ!」
懸命に呼びかけるけれど、千里の意識はしだいに遠のいてゆく。千里は最後の力を振り絞り、僕の手を握りながらこうもらした。
「ううん、もうじゅうぶんだよ……でも、これからも……友達とは仲良く、だよ。そうすればまた、あたしに会えるかもね――」
それから千里は安心したようにゆったりと眠り込んでしまった。
僕はその日を境に閉じこもるのをやめた。登校を再開し、学校の帰りがけに病院に立ち寄り、千里を見舞っていた。
あどけない寝顔はただ、眠っているようにしか見えなくて、けれど話しかけても目を覚ますことはなかった。
フェンスにもたれかかり屹立した山々を眺めていると、さわさわと風が吹いてきた。すこしだけ春のやわらかさを宿していることに気づく。
まるで千里の笑顔のような、あたたかみのある風だった。
僕はそよ風の中に、千里の声を感じ取る。
――和也くん、いままでありがとね。
ああ、そうなのかと、なんとなく気づいた。
見慣れたはずの風景が、急に揺らいで見えた。
空を見上げてまぶたを閉じると、瞳の上に溜まった涙がはらりとこぼれ落ちる。
――千里、きみに会えて僕は幸せだったよ。
その日は千里の旅立ちにふさわしい、きれいなセレストブルーの空だった――。