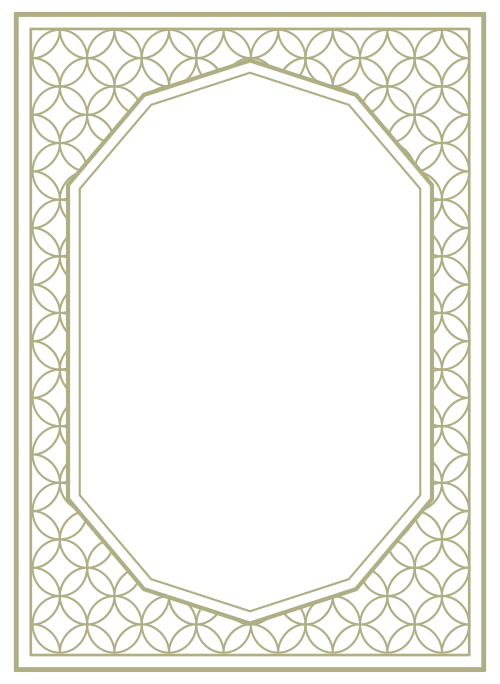★
冬の夜は足が早い。いつの間にか空は群青に支配されていた。西の地平線の際に浮かぶ細長い下弦の月が、まるで沈没船のように見えた。
僕らは路頭に迷ったように、公園のベンチに座り込んでいる。
葉山と僕の間に挟まれた高円寺さんは、肩を震わせてぽろぽろと涙をこぼしていた。
「うっ、うっ……千里ちゃん、可哀想だよぉ……」
葉山は高円寺さんの背中をさすりながら小声で尋ねる。
「千里たん、病気だったのか……」
「知らなかったけど……もしかしたら、って思っていたんだ……」
高円寺さんは心痛を滲ませた声をもらす。やっぱり、それとなく気づいていたのか。僕は正直に打ち明けることにした。
「千里のお腹にはおおきな傷があったんだ。たぶん、内臓の病気を起こしていたんだ」
ふたりは目を丸くして僕を見た。高円寺さんは街灯の薄明かりでもわかるくらい、目を腫らせている。
「そうだったんだ……最近、なんだか顔色が悪い気がしていたの。すこしだるそうだったし……」
「くっ、それなのにあんなに明るく振る舞っていたなんて……」
それからふたりとも口を閉ざす。皆、思っていることは同じだろう。
僕ら三人の仲は千里が繋いでくれたものだ。そのかすがいが外れた僕らは、心が迷子になったように、ただ寂しくて不安で、うろたえることしかできなかった。
千里の存在が、どれだけ皆の心を穏和にしてくれていたのかを実感する。
「さっきまで、あんなに楽しかったのにね……」
僕がそう言うとふたりとも黙ったままうなずく。感情の落差が自然と口を閉ざさせた。見上げると、宇宙まで見渡せる深淵の空が目に映る。
どうして、冬の空はこんなに澄んでいるのだろう。千里には見えない星空が、今日は無情なほど眩しく感じる。
ふと、星がひとつ、こぼれ落ちた。
「あ……」
僕はすぐさま胸の内の願いを口にする。でも、言い終わらないうちに星は空からすっと消えて、同時に視界が歪んだ。頬にはらりと冷たい雫が伝う。
運命に対して、僕はまるで無力だった。神様は願いのひとつすら、聞く耳を持ってくれなかったのだ。
僕らは身も心も冷えきっていたけれど、それでもなかなか帰路につくことができないままでいた。
深夜になって、おばさんから僕のスマホに連絡があった。危険な状態は乗り切ったけれど、しばらくは会えないということだった。
事情を話すからと言われたので、僕らは後日、千里のいない家を三人で訪れることになった。
数日ぶりに会うおばさんは、まるで別人のように意気消沈していた。ただでさえ千里のことで悲しいはずなのに、僕たちへの呵責がそれを後押ししているように思える。
「ごめんね、みんなに黙っていて……」
テーブルを挟んで向かい合うおばさんは震える声でそう言った。けれど、僕も黙ってはいられない。
「薄々気づいていました。たぶん、僕が再会してから高校に入学するまでの間に、なにかあったんですよね」
おばさんの反応は驚いたようでもあり、首肯しているようでもあった。
「ほんとうにごめんなさい。いつかはみんなに悲しい思いをさせてしまうかもしれないってわかっていながら、千里の希望を叶えてあげたいと思っていたの……」
僕らは皆、黙ったまま首を横に振り、おばさんの呵責を否定する。おばさんはやっぱりみんな優しいのね、と言って事情を話し始めた。
中学生の僕と再会したすぐ後に、千里はお腹の中に「肉腫」という悪性の病気を発症したらしい。そういった厄介な病気が、遺伝子の異常を持つ「網膜芽細胞腫」の患者には高頻度で発生するという。
手術をしたけれど、残存の可能性が否定できなかったらしい。完全に切除できなければ治癒はできない、つまり、その病気で命を落とす、ということらしかった。
その後、飲み薬の治療を続けていたが、しばしば検査が必要なようで頻繁に通院をしていた。でも、担当の先生は週のうち一日だけ、別の病院に勤務していて、その日は通院スケジュールが入らなかったらしい。それが水曜日、とのことだった。
「だから、せめて水曜日だけは病気のことを忘れて、友達と楽しく過ごせる日にさせてあげたかったの」
そうだったのか。千里が会うのを水曜日に限定した理由が腑に落ちた。それに高校入学時、僕との再会に迷いのようなものがあったのは、病気がちゃんと治ってからにしたい、という理由だったのだろう。
けれど、胃からの出血は腫瘍の再発が原因だった。――それはもう、治せない病状だということを意味していた。
葉山も高円寺さんもうつむいたままで、理性が崩れないように繋ぎ止めているようだった。
僕たちはもう、いままでみたいに無邪気に笑うことはできないと思う。それに、これからどういうふうに千里に接したらいいのか、まるで想像ができないでいる。
「止血できてだいぶ落ち着いたから、もうすぐお見舞いの面会もできると思う。でも、病気の再発のことは言わないでほしいの」
そうだよな、と納得した。おばさんが僕らを呼んだ一番の理由は、千里に会うなら病気のことを絶対に喋らないようにと念を押すためだったのだろう。
高円寺さんと葉山は困惑しながらも了承した。僕もおばさんの気持ちは理解できる。けれど、千里はほんとうにそれでいいのだろうか。
僕はおばさんに自分の率直な思いを告げる。
「だけど、ちゃんと伝えたほうがいいかもしれません。だって千里は自分の病状に気づいているはずですから」
「えっ……?」
僕の言葉におばさんは瞠目した。きっと、千里には治る病気だと伝えていたのだろう。
冬の夜は足が早い。いつの間にか空は群青に支配されていた。西の地平線の際に浮かぶ細長い下弦の月が、まるで沈没船のように見えた。
僕らは路頭に迷ったように、公園のベンチに座り込んでいる。
葉山と僕の間に挟まれた高円寺さんは、肩を震わせてぽろぽろと涙をこぼしていた。
「うっ、うっ……千里ちゃん、可哀想だよぉ……」
葉山は高円寺さんの背中をさすりながら小声で尋ねる。
「千里たん、病気だったのか……」
「知らなかったけど……もしかしたら、って思っていたんだ……」
高円寺さんは心痛を滲ませた声をもらす。やっぱり、それとなく気づいていたのか。僕は正直に打ち明けることにした。
「千里のお腹にはおおきな傷があったんだ。たぶん、内臓の病気を起こしていたんだ」
ふたりは目を丸くして僕を見た。高円寺さんは街灯の薄明かりでもわかるくらい、目を腫らせている。
「そうだったんだ……最近、なんだか顔色が悪い気がしていたの。すこしだるそうだったし……」
「くっ、それなのにあんなに明るく振る舞っていたなんて……」
それからふたりとも口を閉ざす。皆、思っていることは同じだろう。
僕ら三人の仲は千里が繋いでくれたものだ。そのかすがいが外れた僕らは、心が迷子になったように、ただ寂しくて不安で、うろたえることしかできなかった。
千里の存在が、どれだけ皆の心を穏和にしてくれていたのかを実感する。
「さっきまで、あんなに楽しかったのにね……」
僕がそう言うとふたりとも黙ったままうなずく。感情の落差が自然と口を閉ざさせた。見上げると、宇宙まで見渡せる深淵の空が目に映る。
どうして、冬の空はこんなに澄んでいるのだろう。千里には見えない星空が、今日は無情なほど眩しく感じる。
ふと、星がひとつ、こぼれ落ちた。
「あ……」
僕はすぐさま胸の内の願いを口にする。でも、言い終わらないうちに星は空からすっと消えて、同時に視界が歪んだ。頬にはらりと冷たい雫が伝う。
運命に対して、僕はまるで無力だった。神様は願いのひとつすら、聞く耳を持ってくれなかったのだ。
僕らは身も心も冷えきっていたけれど、それでもなかなか帰路につくことができないままでいた。
深夜になって、おばさんから僕のスマホに連絡があった。危険な状態は乗り切ったけれど、しばらくは会えないということだった。
事情を話すからと言われたので、僕らは後日、千里のいない家を三人で訪れることになった。
数日ぶりに会うおばさんは、まるで別人のように意気消沈していた。ただでさえ千里のことで悲しいはずなのに、僕たちへの呵責がそれを後押ししているように思える。
「ごめんね、みんなに黙っていて……」
テーブルを挟んで向かい合うおばさんは震える声でそう言った。けれど、僕も黙ってはいられない。
「薄々気づいていました。たぶん、僕が再会してから高校に入学するまでの間に、なにかあったんですよね」
おばさんの反応は驚いたようでもあり、首肯しているようでもあった。
「ほんとうにごめんなさい。いつかはみんなに悲しい思いをさせてしまうかもしれないってわかっていながら、千里の希望を叶えてあげたいと思っていたの……」
僕らは皆、黙ったまま首を横に振り、おばさんの呵責を否定する。おばさんはやっぱりみんな優しいのね、と言って事情を話し始めた。
中学生の僕と再会したすぐ後に、千里はお腹の中に「肉腫」という悪性の病気を発症したらしい。そういった厄介な病気が、遺伝子の異常を持つ「網膜芽細胞腫」の患者には高頻度で発生するという。
手術をしたけれど、残存の可能性が否定できなかったらしい。完全に切除できなければ治癒はできない、つまり、その病気で命を落とす、ということらしかった。
その後、飲み薬の治療を続けていたが、しばしば検査が必要なようで頻繁に通院をしていた。でも、担当の先生は週のうち一日だけ、別の病院に勤務していて、その日は通院スケジュールが入らなかったらしい。それが水曜日、とのことだった。
「だから、せめて水曜日だけは病気のことを忘れて、友達と楽しく過ごせる日にさせてあげたかったの」
そうだったのか。千里が会うのを水曜日に限定した理由が腑に落ちた。それに高校入学時、僕との再会に迷いのようなものがあったのは、病気がちゃんと治ってからにしたい、という理由だったのだろう。
けれど、胃からの出血は腫瘍の再発が原因だった。――それはもう、治せない病状だということを意味していた。
葉山も高円寺さんもうつむいたままで、理性が崩れないように繋ぎ止めているようだった。
僕たちはもう、いままでみたいに無邪気に笑うことはできないと思う。それに、これからどういうふうに千里に接したらいいのか、まるで想像ができないでいる。
「止血できてだいぶ落ち着いたから、もうすぐお見舞いの面会もできると思う。でも、病気の再発のことは言わないでほしいの」
そうだよな、と納得した。おばさんが僕らを呼んだ一番の理由は、千里に会うなら病気のことを絶対に喋らないようにと念を押すためだったのだろう。
高円寺さんと葉山は困惑しながらも了承した。僕もおばさんの気持ちは理解できる。けれど、千里はほんとうにそれでいいのだろうか。
僕はおばさんに自分の率直な思いを告げる。
「だけど、ちゃんと伝えたほうがいいかもしれません。だって千里は自分の病状に気づいているはずですから」
「えっ……?」
僕の言葉におばさんは瞠目した。きっと、千里には治る病気だと伝えていたのだろう。