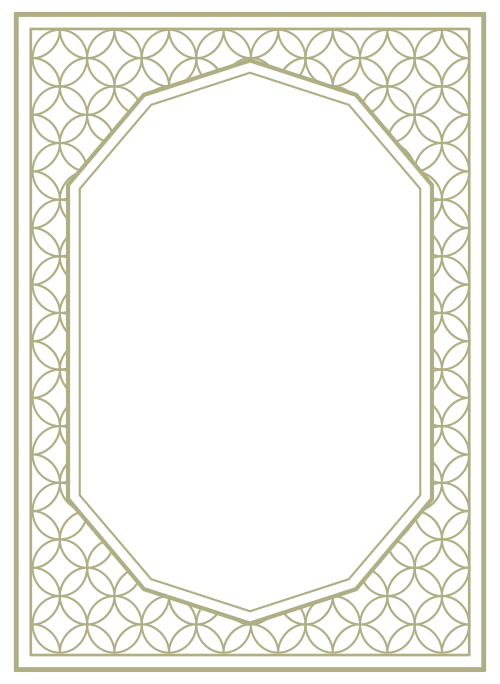「天気の実況中継を録音してどうする! あっ、俺、葉山陽一。来年の抱負は絶対、試合デビューしまっす!」
「願掛けじゃないでしょ、あっ、録音されている? 高円寺有紗です。えっと……とにかく、友達頑張ります!」
「なんだ有紗、その友達頑張るって。まさか百人作るつもりかよ。さてはおまえ、浮気症だな!」
「違っ……! ずっと友達でいようってことよ!」
「だはは、顔真っ赤!」
「葉山、高円寺さんはこう見えても一応、乙女なんだからからかうなよ」
「京本くんこそそれ、失言だってば!」
皆で思い思いのことを録音したところで、最初から聴きなおす。
私と京本くんは思った以上にしどろもどろで、聴いて自分の声に恥ずかしくなったり吹きだしたりした。葉山くんも千里ちゃんも、遠慮なしにげらげらと笑っている。
けれど、録音された声は皆、楽しそうに聴こえる。
私たちは、ようやっとほんとうの友達になれたんだって思えた。
「さて、そろそろ結果発表にいきますか」
葉山くんは千里ちゃんに勝敗の裁定を促す。
「うーん、ちょっと待ってね」
千里ちゃんは決めあぐねているようで、ふたきれの食べかけのパウンドケーキを前に動きを止めていた。
「ちょっ……ちょっと……もう一度味見させてくれる?」
そう言ってうつむき、私のパウンドケーキのほうにそろりと手を伸ばす。もしかすると京本くんに勝てるのではないかと、期待のまなざしで千里ちゃんを見つめる。
千里ちゃんの手がかすかに震えていた。表情をうかがうと、ひたいには汗がにじんでいる。
なにか様子がおかしいと直感した。千里ちゃんはパウンドケーキを持ち上げて口に運ぶ。不思議とスローモーションのように見えた。
男子ふたりは期待のまなざしを崩していない。
一口含めて咀嚼する。飲み込もうとしたとき、口で手を押さえて動きを止めた。
ごほっとおおきく変な咳をした。やけに湿り気を含んだ音の咳だった。
「あらら、違うところに入っちゃったね。あわてなくていいのに」
京本くんが千里ちゃんの背中をさすってあげる。千里ちゃんはしばらく、身をかがめていた。
ようやっと落ち着きを取り戻したようで、「ごめん……」と苦しさの残る小声をこぼす。
のっそり顔を上げる。その表情に私はぎょっとした。
千里ちゃんはひたいに大粒の汗を浮かべ、顔色は蝋のように蒼白になっていたのだ。
京本くんは驚いたように目を見開いていた。視線は千里ちゃんの口を押えた手のひらに向けられている。京本くんの言葉は怯えたように震えていた。
「千里……なにか赤いもの、飲んだのか? それ……」
「えっ……それってなに……?」
「手……手のひらだよ……」
私はその質問の意味が理解できなかった。けれど、千里ちゃんが口に当てていた手を開くと。
そこには、見間違うはずもない――べっとりと、赤黒い血液が付着していた。同じ色に染まった、溶けかけたパウンドケーキの破片も見えた。
千里ちゃんはか細い声でつぶやく。
「あれ、なんかあたし……」
声が、力なく薄らいで途切れる。
そうして、千里ちゃんは京本くんの胸の中に、ふわりと崩れ落ちていった。
そう、まるで綿毛が舞うように、やわらかく、そしてはかなく――。
私たちは、たぶん、このときまでが一番、幸せだったのだと思う。
お互いを信じていれば、みんなに明るい未来が訪れるのだと、盲信していたのかもしれない。
だけど、息詰まるほど苦しくて、絶対に抗えない運命があるのだということを、私は、みんなは、思い知ることになるなんて。
そのときまでは、ほんのひとかけらも想像していなかった。
いや、気づきながらも、目を背けていただけだったんだ――。
「願掛けじゃないでしょ、あっ、録音されている? 高円寺有紗です。えっと……とにかく、友達頑張ります!」
「なんだ有紗、その友達頑張るって。まさか百人作るつもりかよ。さてはおまえ、浮気症だな!」
「違っ……! ずっと友達でいようってことよ!」
「だはは、顔真っ赤!」
「葉山、高円寺さんはこう見えても一応、乙女なんだからからかうなよ」
「京本くんこそそれ、失言だってば!」
皆で思い思いのことを録音したところで、最初から聴きなおす。
私と京本くんは思った以上にしどろもどろで、聴いて自分の声に恥ずかしくなったり吹きだしたりした。葉山くんも千里ちゃんも、遠慮なしにげらげらと笑っている。
けれど、録音された声は皆、楽しそうに聴こえる。
私たちは、ようやっとほんとうの友達になれたんだって思えた。
「さて、そろそろ結果発表にいきますか」
葉山くんは千里ちゃんに勝敗の裁定を促す。
「うーん、ちょっと待ってね」
千里ちゃんは決めあぐねているようで、ふたきれの食べかけのパウンドケーキを前に動きを止めていた。
「ちょっ……ちょっと……もう一度味見させてくれる?」
そう言ってうつむき、私のパウンドケーキのほうにそろりと手を伸ばす。もしかすると京本くんに勝てるのではないかと、期待のまなざしで千里ちゃんを見つめる。
千里ちゃんの手がかすかに震えていた。表情をうかがうと、ひたいには汗がにじんでいる。
なにか様子がおかしいと直感した。千里ちゃんはパウンドケーキを持ち上げて口に運ぶ。不思議とスローモーションのように見えた。
男子ふたりは期待のまなざしを崩していない。
一口含めて咀嚼する。飲み込もうとしたとき、口で手を押さえて動きを止めた。
ごほっとおおきく変な咳をした。やけに湿り気を含んだ音の咳だった。
「あらら、違うところに入っちゃったね。あわてなくていいのに」
京本くんが千里ちゃんの背中をさすってあげる。千里ちゃんはしばらく、身をかがめていた。
ようやっと落ち着きを取り戻したようで、「ごめん……」と苦しさの残る小声をこぼす。
のっそり顔を上げる。その表情に私はぎょっとした。
千里ちゃんはひたいに大粒の汗を浮かべ、顔色は蝋のように蒼白になっていたのだ。
京本くんは驚いたように目を見開いていた。視線は千里ちゃんの口を押えた手のひらに向けられている。京本くんの言葉は怯えたように震えていた。
「千里……なにか赤いもの、飲んだのか? それ……」
「えっ……それってなに……?」
「手……手のひらだよ……」
私はその質問の意味が理解できなかった。けれど、千里ちゃんが口に当てていた手を開くと。
そこには、見間違うはずもない――べっとりと、赤黒い血液が付着していた。同じ色に染まった、溶けかけたパウンドケーキの破片も見えた。
千里ちゃんはか細い声でつぶやく。
「あれ、なんかあたし……」
声が、力なく薄らいで途切れる。
そうして、千里ちゃんは京本くんの胸の中に、ふわりと崩れ落ちていった。
そう、まるで綿毛が舞うように、やわらかく、そしてはかなく――。
私たちは、たぶん、このときまでが一番、幸せだったのだと思う。
お互いを信じていれば、みんなに明るい未来が訪れるのだと、盲信していたのかもしれない。
だけど、息詰まるほど苦しくて、絶対に抗えない運命があるのだということを、私は、みんなは、思い知ることになるなんて。
そのときまでは、ほんのひとかけらも想像していなかった。
いや、気づきながらも、目を背けていただけだったんだ――。