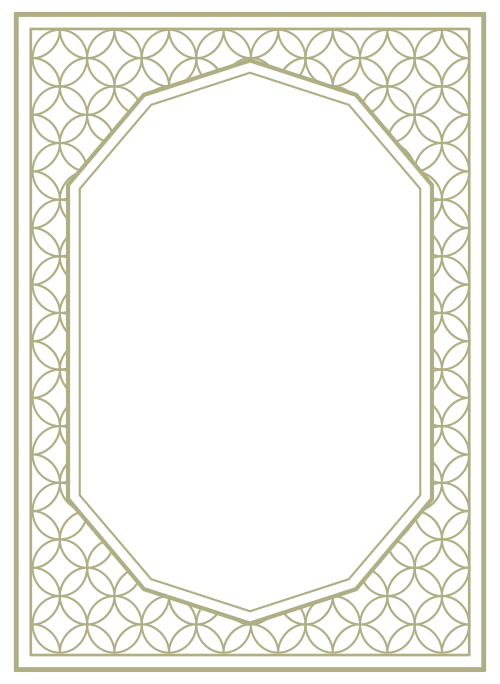あの日の約束通り、葉山くんと私は隔週で千里ちゃんの家を訪れていた。もちろん、そのときは京本くんも一緒に。
『マインド・コネクト・ゲーム』の結果に従って、皆でサイクリングをしたり、おしゃれな喫茶店でデザートを食べたり、神社にお参りに行ったりと、さまざまな楽しみを満喫していた。
千里ちゃんのお母さんは、そんな私たちを温かく見守っていてくれた。
そうして冬が訪れた。
「千里たん、聞いてくれよ! 俺、ついに部活でレギュラーになれたんだぜ」
「陽一くん、すごぉい!」
「へっ、いよいよ伝説が幕を開けるんだぜ!」
葉山くんは千里ちゃんに向かって意気揚々と語っている。京本くんと私は、彼の伝説の幕開け話(今はまだ、取らぬ狸の皮算用なのに!)をさんざん聞かされた犠牲者だ。
サッカー部は今年の試合スケジュールをすべて終え、新たなチーム編成がなされたらしい。葉山くんは一年生ながら試合のメンバーに滑り込んだらしく、そのことを伝えたくて先週からうずうずしていた。
「ねぇ、ポジションっていろいろあるんでしょ。どこになったの?」
「ああ、今はなんと、べンチだ!」
「ベッ、ベンチってどんなことしているの!」
「それはな、誰かが倒れたときに登場する救世主ってとこだ。だいたい、主人公は一歩遅れて登場するものだからな」
「わぁ、なんだかかっこいい!」
千里ちゃんはサッカーのルールがわかっていないらしく、葉山くんのポジティブな雰囲気にあっけなく騙されている。
でも、葉山くんは内心、ベンチ入りだけで気が済んでいるはずはない。今後は本気でスタメンを奪いにいくつもりなのだろう。
――私も春のコンクールメンバーに選ばれたいな。それが千里ちゃんに対する恩返しになるんだから。
千里ちゃんは京本くんに尋ねる。
「和也くんって、水曜日以外はアルバイトしているんだよね。たしか本屋さんって聞いたけれど、どんなところなの?」
「ああ、うちの駅から近くの商店街にあるちいさな古本屋で、『エルシド』っていう名前なんだ」
「へえ、駅の商店街かぁ。なんとなく覚えているような、いないような……」
千里ちゃんは記憶の糸を手繰り寄せるように天井を仰いだ。もともとは近所だったはずだけど、あまり鮮明に覚えていないらしい。
「ところで千里たん、今日はどこか出かけるか?」
「うーん、インドアがいいなぁ」
寒いのが苦手なのか、最近の千里ちゃんは出不精になってきた。これからは家でできるゲームが楽しみの中心になるのかもしれない。
「じゃあ、有紗と千里たんの練習デーでいいか。いやぁ、千里たんの歌、楽しみだなぁ」
「私は嬉しいけれど、京本くんはそれでいいかな?」
「僕は別に構わないよ。でも、せっかくだから次回はなにをするか決めておかない? インドアの楽しみには準備が必要だからね」
「あっ、それがいいね」
葉山くんも同意したので、三枚ずつカードを配り、皆が思い思いのことを書き入れた。それを千里ちゃんの目の前に並べる。千里ちゃんはわくわくしながら指先でカードを探りあてる。
「とうっ!」
勢いよく一枚目のカードを捲り上げる。
『京本と有紗が』
「おおっ、誰だ、この組み合わせを書いたやつ!」
「おいおい葉山、おまえが書いたに決まっているだろ」
「むぅ、次回、あたしはただの傍観者なのかぁ。じゃあ二枚目いくよー、えいっ!」
『ケーキを』
京本くんと葉山くんはふたり、同時に私の顔を見た。女子は甘いものが好き、だからケーキと結びつくのは私。それが男子の共通認識なのだろう。まあ、書いたのは私なんだけど。
千里ちゃんはこの「ケーキ」の運命が書かれた三枚目のカードに指を伸ばす。
「じゃあ、三枚目。おりゃあ!」
千里ちゃんが私たちに向けたカードにはこう書かれている。
『創作勝負をする』
「なんでっ!」
この難題は京本くんの字だった。彼はアドリブでの作詞作曲を想定してこう書き入れたのだろう。
これが『マインド・コネクト・ゲーム』の真髄だろうか。カードは私にケーキを作れという、無謀な要求をしてきた。
「おおっ! 互いにケーキを作って、どっちが美味しいか千里たんにジャッジしてもらうってことだな」
「ちょ、ちょっと待って。私、お菓子作りなんてあんまり……」
「え、そうなの? 僕はぜんぜんいいけど」
あわてふためく私をよそに、京本くんはさらりと答える。
「げっ、マジかよ。おまえ、パティシエ男子だったのかよ」
「んー、ときどきだけどね」
私はお菓子作りの経験なんてほとんどない。京本くんの裏の特技を知って動揺する。だけど、ここで引いたら女子としての面目丸潰れだ。
しかも、悔しいけれど、千里ちゃんとの気持ちの繋がりは、私よりも京本くんのほうがはるかに強固だ。
それに、つい先日の中間テストで、私は京本くんに僅差で敗北していた。(ちなみに葉山くんは私たちの敵ではない)
だから、いろんな意味で彼に後塵を拝している私にとって、この勝負は闘争心を燃え上がらせるものだった。
――よぉーし! 京本くんよりも千里ちゃんを唸らせるケーキを作ってやるぞ!
「いいよ、やったろうじゃん!」
私は覚悟を決めて返事をし、京本くんをにらみつけた。彼は涼しい顔で口を三日月にしてみせる。まったく、憎たらしいことこのうえない笑顔だ。
千里ちゃんは「やったぁ、ふたりのスイーツが味わえるなんて、最高の企画!」と手を叩いて大喜びだったけれど。
★
「パンパカパーン、お待たせしました! 京本和也対、高円寺有紗のスイーツ対決を開催します!」
「いやっほー、あたし、この日を楽しみにしていたよー」
『マインド・コネクト・ゲーム』の結果に従って、皆でサイクリングをしたり、おしゃれな喫茶店でデザートを食べたり、神社にお参りに行ったりと、さまざまな楽しみを満喫していた。
千里ちゃんのお母さんは、そんな私たちを温かく見守っていてくれた。
そうして冬が訪れた。
「千里たん、聞いてくれよ! 俺、ついに部活でレギュラーになれたんだぜ」
「陽一くん、すごぉい!」
「へっ、いよいよ伝説が幕を開けるんだぜ!」
葉山くんは千里ちゃんに向かって意気揚々と語っている。京本くんと私は、彼の伝説の幕開け話(今はまだ、取らぬ狸の皮算用なのに!)をさんざん聞かされた犠牲者だ。
サッカー部は今年の試合スケジュールをすべて終え、新たなチーム編成がなされたらしい。葉山くんは一年生ながら試合のメンバーに滑り込んだらしく、そのことを伝えたくて先週からうずうずしていた。
「ねぇ、ポジションっていろいろあるんでしょ。どこになったの?」
「ああ、今はなんと、べンチだ!」
「ベッ、ベンチってどんなことしているの!」
「それはな、誰かが倒れたときに登場する救世主ってとこだ。だいたい、主人公は一歩遅れて登場するものだからな」
「わぁ、なんだかかっこいい!」
千里ちゃんはサッカーのルールがわかっていないらしく、葉山くんのポジティブな雰囲気にあっけなく騙されている。
でも、葉山くんは内心、ベンチ入りだけで気が済んでいるはずはない。今後は本気でスタメンを奪いにいくつもりなのだろう。
――私も春のコンクールメンバーに選ばれたいな。それが千里ちゃんに対する恩返しになるんだから。
千里ちゃんは京本くんに尋ねる。
「和也くんって、水曜日以外はアルバイトしているんだよね。たしか本屋さんって聞いたけれど、どんなところなの?」
「ああ、うちの駅から近くの商店街にあるちいさな古本屋で、『エルシド』っていう名前なんだ」
「へえ、駅の商店街かぁ。なんとなく覚えているような、いないような……」
千里ちゃんは記憶の糸を手繰り寄せるように天井を仰いだ。もともとは近所だったはずだけど、あまり鮮明に覚えていないらしい。
「ところで千里たん、今日はどこか出かけるか?」
「うーん、インドアがいいなぁ」
寒いのが苦手なのか、最近の千里ちゃんは出不精になってきた。これからは家でできるゲームが楽しみの中心になるのかもしれない。
「じゃあ、有紗と千里たんの練習デーでいいか。いやぁ、千里たんの歌、楽しみだなぁ」
「私は嬉しいけれど、京本くんはそれでいいかな?」
「僕は別に構わないよ。でも、せっかくだから次回はなにをするか決めておかない? インドアの楽しみには準備が必要だからね」
「あっ、それがいいね」
葉山くんも同意したので、三枚ずつカードを配り、皆が思い思いのことを書き入れた。それを千里ちゃんの目の前に並べる。千里ちゃんはわくわくしながら指先でカードを探りあてる。
「とうっ!」
勢いよく一枚目のカードを捲り上げる。
『京本と有紗が』
「おおっ、誰だ、この組み合わせを書いたやつ!」
「おいおい葉山、おまえが書いたに決まっているだろ」
「むぅ、次回、あたしはただの傍観者なのかぁ。じゃあ二枚目いくよー、えいっ!」
『ケーキを』
京本くんと葉山くんはふたり、同時に私の顔を見た。女子は甘いものが好き、だからケーキと結びつくのは私。それが男子の共通認識なのだろう。まあ、書いたのは私なんだけど。
千里ちゃんはこの「ケーキ」の運命が書かれた三枚目のカードに指を伸ばす。
「じゃあ、三枚目。おりゃあ!」
千里ちゃんが私たちに向けたカードにはこう書かれている。
『創作勝負をする』
「なんでっ!」
この難題は京本くんの字だった。彼はアドリブでの作詞作曲を想定してこう書き入れたのだろう。
これが『マインド・コネクト・ゲーム』の真髄だろうか。カードは私にケーキを作れという、無謀な要求をしてきた。
「おおっ! 互いにケーキを作って、どっちが美味しいか千里たんにジャッジしてもらうってことだな」
「ちょ、ちょっと待って。私、お菓子作りなんてあんまり……」
「え、そうなの? 僕はぜんぜんいいけど」
あわてふためく私をよそに、京本くんはさらりと答える。
「げっ、マジかよ。おまえ、パティシエ男子だったのかよ」
「んー、ときどきだけどね」
私はお菓子作りの経験なんてほとんどない。京本くんの裏の特技を知って動揺する。だけど、ここで引いたら女子としての面目丸潰れだ。
しかも、悔しいけれど、千里ちゃんとの気持ちの繋がりは、私よりも京本くんのほうがはるかに強固だ。
それに、つい先日の中間テストで、私は京本くんに僅差で敗北していた。(ちなみに葉山くんは私たちの敵ではない)
だから、いろんな意味で彼に後塵を拝している私にとって、この勝負は闘争心を燃え上がらせるものだった。
――よぉーし! 京本くんよりも千里ちゃんを唸らせるケーキを作ってやるぞ!
「いいよ、やったろうじゃん!」
私は覚悟を決めて返事をし、京本くんをにらみつけた。彼は涼しい顔で口を三日月にしてみせる。まったく、憎たらしいことこのうえない笑顔だ。
千里ちゃんは「やったぁ、ふたりのスイーツが味わえるなんて、最高の企画!」と手を叩いて大喜びだったけれど。
★
「パンパカパーン、お待たせしました! 京本和也対、高円寺有紗のスイーツ対決を開催します!」
「いやっほー、あたし、この日を楽しみにしていたよー」