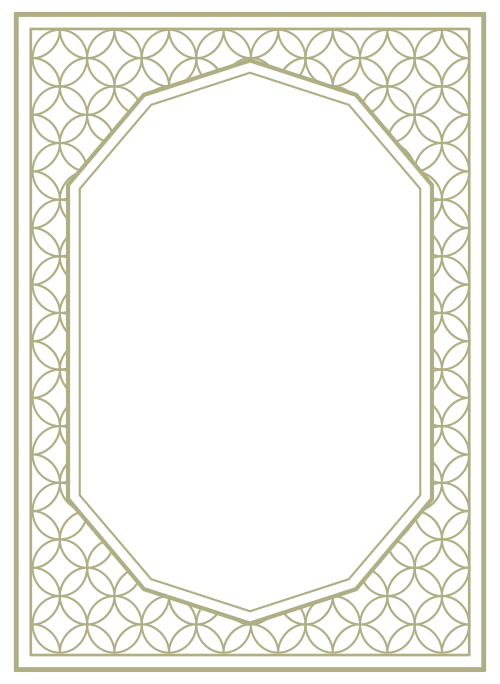★
その日の学校帰り、私はこっそりと京本くんの後を追う。
授業の終わりを告げるチャイムが鳴ると、京本くんはそそくさと荷物をまとめて足早に教室を後にした。人目を避けるように見えたのは、ほんとうに避けているのかもしれないし、「蜜月」という二文字が私の脳裏で悶々としているから、そう感じるのかもしれない。
京本くんは、電車で二十分ほどの、すこし離れた街に住んでいる。葉山くんの話によると、部活には所属していなくて、毎日アルバイトに勤しんでいる。地元の本屋さんの手伝いをしているらしい。
けれど学校の帰り道、京本くんが向かったのは駅とは違う方角だった。やっぱり不自然だと直感する。
京本くんは通学路の国道を脇にそれて坂道を登ってゆく。その先には丘陵の上に開発された見晴らしの良いホームタウンがある。閑静で落ち着いた雰囲気は抜群に住み心地が良いのだと、ポストに入っていた住宅販売の広告で見たことがある。
蜜月――ほんとうにそうなのだろうか?
いくばくかの罪悪感がつきまとうけれど、それ以上に好奇心が私の背中を後押ししていた。
――あんなにおとなしそうな人が会いに行く女性って、どんな人なんだろう?
ブロック塀の陰に身を隠し、見失わないように彼の姿を追う。京本くんは細い路地を抜け、ちいさな一戸建ての家の前で足を止めた。
その家に向かって白いワンボックスカーが近づいてきた。停車すると、ゆっくりとバックをして車庫に収まる。京本くんは車の運転を見守りながら、運転席に向かって一度、深々と頭を下げた。
運転席から降りてきたのは、見た目が四十代くらいの女性だった。買い物に出かけるようなカジュアルな服装で、京本くんを見て笑顔を浮かべる。声質が明瞭で、「いらっしゃい、いつもありがとう」と言っているのが遠くからでも聞こえた。私は気づかれないように壁際から様子をうかがう。
――誰だろう、親戚の人かな。
やわらかな物腰のその女性は、車の後部座席の扉を開け、中に手を差し入れた。もうひとり、誰かが乗っているみたい。
手を取って降り立ったのは、私と同年代の女の子だった。
トイプードルのようなふわくしゅのくせっ毛、やわらかな輪郭の丸顔、にきびひとつない、陽射しに映えるきれいな素肌。同級生に比べて雰囲気があどけなく感じられる。
私の高校からさほど遠くない自宅だというのに、その女の子は見たことのない臙脂色のブレザーをまとっている。
私はその女の子の挙動に違和感を覚えた。探るように手のひらを家の外壁に当てていて、足の運びもやけに慎重だ。しかも、その子の両眼はかたくなに閉じられている。
運転手の女性が車から白い棒のようなものを取りだして女の子に渡す。女の子はそれを握って地面を突いた。
女の子が握っていたのは、「白杖」だと気づいた。
――まさか、目が見えない子なの?
でも、それ以上に驚いたことは、京本くんが運転手の女性から女の子の手を受け取り、そっと握りしめたことだった。女の子はまぶたを閉じたまま京本くんの顔を見上げ、花が咲いたような笑顔を浮かべる。ふたりの息が合っていることに、私の胸がひどくざわついた。
女の子は無邪気に京本くんに話しかける。
「和也くん、来てくれたんだね。ありがとう」
「当然だって。今日は水曜日だからな」
――えっ?
今、信じられなかったけれど、私は確かに京本くんの声を聞いた。水曜日は絶対に喋らないはずの京本くんは、彼女に対してだけは言葉を発していた。その声は格別に優しい音調に感じられた。
女の子は目を閉じたまま、嬉しそうに首を縦に振っている。京本くんも口元を緩めているように見えるけれど、やっぱりどこか辛そうだ。その不自然さは朝、屋上で見かけるときよりも、はるかに色を濃くしている。
葉山くんは彼がリア充をしているように見えるって言っていたけれど、私からすれば彼は息苦しくなるような痛みを伴っているように感じる。いったいどうしてなんだろう?
もしかすると、あの女の子が京本くんの苦しみの原因になっているんじゃないだろうか。あの女の子が彼の水曜日を縛っているからじゃないだろうか。彼が音のない水曜日を過ごす理由が彼女にあることは間違いないのだから。
次々と水曜日の疑問が湧いてきたけれど、私はそれ以上どうすることもできなくて。
結局、京本くんが「蜜月の相手」と家の中へ消えていくの、息をひそめて見届けることしかできなかった。
その日の学校帰り、私はこっそりと京本くんの後を追う。
授業の終わりを告げるチャイムが鳴ると、京本くんはそそくさと荷物をまとめて足早に教室を後にした。人目を避けるように見えたのは、ほんとうに避けているのかもしれないし、「蜜月」という二文字が私の脳裏で悶々としているから、そう感じるのかもしれない。
京本くんは、電車で二十分ほどの、すこし離れた街に住んでいる。葉山くんの話によると、部活には所属していなくて、毎日アルバイトに勤しんでいる。地元の本屋さんの手伝いをしているらしい。
けれど学校の帰り道、京本くんが向かったのは駅とは違う方角だった。やっぱり不自然だと直感する。
京本くんは通学路の国道を脇にそれて坂道を登ってゆく。その先には丘陵の上に開発された見晴らしの良いホームタウンがある。閑静で落ち着いた雰囲気は抜群に住み心地が良いのだと、ポストに入っていた住宅販売の広告で見たことがある。
蜜月――ほんとうにそうなのだろうか?
いくばくかの罪悪感がつきまとうけれど、それ以上に好奇心が私の背中を後押ししていた。
――あんなにおとなしそうな人が会いに行く女性って、どんな人なんだろう?
ブロック塀の陰に身を隠し、見失わないように彼の姿を追う。京本くんは細い路地を抜け、ちいさな一戸建ての家の前で足を止めた。
その家に向かって白いワンボックスカーが近づいてきた。停車すると、ゆっくりとバックをして車庫に収まる。京本くんは車の運転を見守りながら、運転席に向かって一度、深々と頭を下げた。
運転席から降りてきたのは、見た目が四十代くらいの女性だった。買い物に出かけるようなカジュアルな服装で、京本くんを見て笑顔を浮かべる。声質が明瞭で、「いらっしゃい、いつもありがとう」と言っているのが遠くからでも聞こえた。私は気づかれないように壁際から様子をうかがう。
――誰だろう、親戚の人かな。
やわらかな物腰のその女性は、車の後部座席の扉を開け、中に手を差し入れた。もうひとり、誰かが乗っているみたい。
手を取って降り立ったのは、私と同年代の女の子だった。
トイプードルのようなふわくしゅのくせっ毛、やわらかな輪郭の丸顔、にきびひとつない、陽射しに映えるきれいな素肌。同級生に比べて雰囲気があどけなく感じられる。
私の高校からさほど遠くない自宅だというのに、その女の子は見たことのない臙脂色のブレザーをまとっている。
私はその女の子の挙動に違和感を覚えた。探るように手のひらを家の外壁に当てていて、足の運びもやけに慎重だ。しかも、その子の両眼はかたくなに閉じられている。
運転手の女性が車から白い棒のようなものを取りだして女の子に渡す。女の子はそれを握って地面を突いた。
女の子が握っていたのは、「白杖」だと気づいた。
――まさか、目が見えない子なの?
でも、それ以上に驚いたことは、京本くんが運転手の女性から女の子の手を受け取り、そっと握りしめたことだった。女の子はまぶたを閉じたまま京本くんの顔を見上げ、花が咲いたような笑顔を浮かべる。ふたりの息が合っていることに、私の胸がひどくざわついた。
女の子は無邪気に京本くんに話しかける。
「和也くん、来てくれたんだね。ありがとう」
「当然だって。今日は水曜日だからな」
――えっ?
今、信じられなかったけれど、私は確かに京本くんの声を聞いた。水曜日は絶対に喋らないはずの京本くんは、彼女に対してだけは言葉を発していた。その声は格別に優しい音調に感じられた。
女の子は目を閉じたまま、嬉しそうに首を縦に振っている。京本くんも口元を緩めているように見えるけれど、やっぱりどこか辛そうだ。その不自然さは朝、屋上で見かけるときよりも、はるかに色を濃くしている。
葉山くんは彼がリア充をしているように見えるって言っていたけれど、私からすれば彼は息苦しくなるような痛みを伴っているように感じる。いったいどうしてなんだろう?
もしかすると、あの女の子が京本くんの苦しみの原因になっているんじゃないだろうか。あの女の子が彼の水曜日を縛っているからじゃないだろうか。彼が音のない水曜日を過ごす理由が彼女にあることは間違いないのだから。
次々と水曜日の疑問が湧いてきたけれど、私はそれ以上どうすることもできなくて。
結局、京本くんが「蜜月の相手」と家の中へ消えていくの、息をひそめて見届けることしかできなかった。