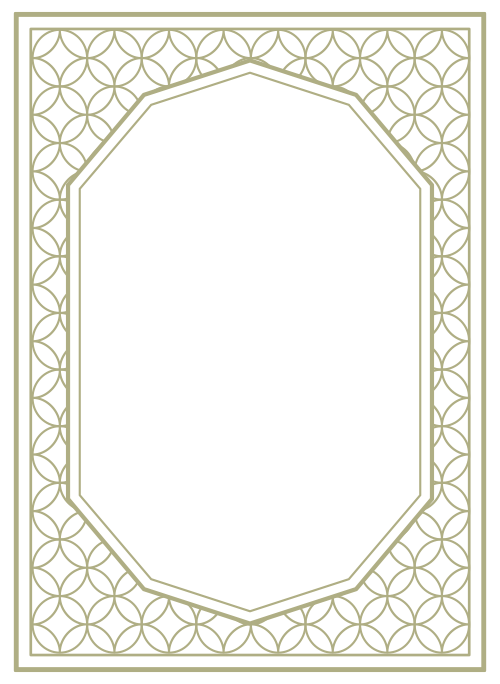遠くに望む山麓がすこしずつ秋色の衣をまとい始めた頃。屋上で購買のお弁当をたいらげた葉山くんは私に尋ねてきた。
「有紗、そう言えばアンサンブル部の県大会どうだったんだ」
「んー、グループはふたつあったけど、五位と七位だったから、今年は全国大会に出られなかったんだ。まあ、私はメンバーになれなかったけどね」
最近は屋上でおしゃべりしながら昼食をとるのが日課になっている。葉山くんと、それから――京本くんと。
「でも高円寺さん、だいぶ上手くなったよね。音がいきいきしていて、前とはぜんぜん違っているよ」
「千里ちゃんのおかげだよ。自分の長所も欠点も、わかりやすく教えてくれるんだもん」
「じゃあ有紗、もしかすると春期コンクールはメンバー狙えるんじゃね?」
「確かに、今の上達ぶりならいけるかもしれないよ」
「うーん、みんな経験者ばっかりだからねぇ……。でも、京本くんに褒められると、素直に嬉しいよ。葉山くんに褒められると、なぜか警戒心が沸き起こるけど」
「なんだと有紗、そんなこと言うなら良家仕立てのだし巻き卵食わせろ!」
葉山くんの箸が私の弁当箱に向かってするすると伸びてきた。
「高円寺さん、きたよ。今日こそは逃げ切れ!」
「最後の楽しみ、奪われてなるものかぁ!」
弁当箱を両手でしっかりと握り、ひょいひょいっと動かして箸をかわす。
「くっ、逃げられたか。だし巻き玉子との語らいを夢見ていたのに」
「まあ、こっちを生贄に捧げるから鎮まってくれ」
京本くんは自分の唐揚げをひとつ、箸の持ち手側で挟んで葉山くんの弁当のパックにぽとりと落とす。京本くんのお弁当はいつもてんこ盛りだ。
「おっ、サンキューな」
「じゃあ、高円寺さんにはこっちね」
京本くんは爪楊枝が刺さったイチゴとキウイのフルーツセットをひとつつまんで私にくれた。
「あっ、ありがとう」
「母さんの作るランチは量が多すぎるんだ。いくらバイトで帰りが遅いからって、こんなにはいらないよ」
「それは親心なんじゃない。でも、食べきれないならお言葉に甘えていただきまーす」
フルーツセットを受け取って口に放り込む。ああ、爽やかな果汁が口の中に広がる。
堪能していると、京本くんが急に真剣な顔になって尋ねてきた。
「高円寺さん、ちょっと聞きたいんだけど」
「むふぁ?」
「千里の病気って、なんなのかなぁ。ネットで調べたんだけど、目が見えなくなる病気ってたくさんあって。それに千里やおばさんに直接訊くわけにもいかなくてさ」
「千里ちゃんの、病気ねぇ……」
私はお兄ちゃんから病名を聞いたとき、ほんとうにそうなのか自分なりに調べていた。本から得た知識をもとに病名が正しいか確認する。
「ねえ、ひょっとすると瞳の奥が白っぽく見えたりする病気?」
京本くんは目を丸くした。その表情に私は確信を持つ。
「じつは……僕が記憶している千里の、最後の姿がそうだった」
やっぱり間違いない。お兄ちゃんの推測は的を射ていたんだ。さすがは秀才。
「それ、『網膜芽細胞腫』っていう病気なんだと思う」
「へえ、よく知っているね」
「お兄ちゃんに聞いたんだ。たしか、生まれつきの遺伝子異常が原因で、両眼にほぼ同時に腫瘍ができる病気って言っていたよ」
「そうなのか……」
葉山くんも真剣な顔で察してくる。
「とすると、千里たんは生まれつき病気になる運命だったってことなのか」
「うん、たぶん」
京本くんはしばらく考え込んでいたけれど、唐突に顔を上げ、意外なことを私に尋ねた。
「ねえ、その病気って、問題が起きるのは眼だけなの?」
「えっ――?」
そう訊かれて、お兄ちゃんの言葉を思いだした。
『いろんな病気を併発しやすいっていう特徴があるらしい』
背中が冷水を注がれたようにぞっとする。その「いろんな病気」が具体的になにを意味するのかわからないけれど、京本くんの尋ね方はなんらかの心当たりがあるようだった。
でも、私の憶測でみんなの不安を煽るようなことはしたくない。気を取り直して笑顔を繕う。
「あんなに元気なんだから、なんにもないんじゃない?」
「そっか、そうだよね」
京本くんはまるで自分に言い聞かせるようにそう言う。葉山くんはさほど気にしていないようだった。
「それにしても千里たん、可愛いよなぁ。あんなに素直な子、見たことねえ」
「僕が思うに、外から悪い情報が入ってこないからじゃないかな」
「俺もそう思っている。自分ができることに一生懸命だし前向きだし。でも、これからどんな人生になるんだろうな、正直想像がつかねえよ」
葉山くんは京本くんの顔を直視した。まるで京本くんの思惑を探っているようでもある。
けれど京本くんはこともなげに返事をする。
「ああ、僕がいるからなんとかなるんじゃない?」
京本くんはいつだってそうだった。自分の人生をぜんぶ、千里ちゃんに投げだしたって構わないという雰囲気がある。将来を誓い合った関係というわけでもないのに。
――なんでそこまで尽くそうと思えるんだろう?
私には彼のその覚悟が、どうしても理解できなかった。
★
水曜日の朝、京本くんは相変わらず無口なままで読書を続けている。皆で千里ちゃんの家を訪れる日でもそれは変わらない。ただときどき、本を読むのをやめて私のフルートに耳を傾けていた。そんなとき、彼は唯一の私の聴衆で、私は彼の奏者だった。
晩秋になると、屋上から望む山麓は鮮やかに彩られる。けれど、そんな季節が過ぎる頃には、朝の冷え込みが身に沁みるようになっていた。そろそろ、いままでのように朝練を続けるわけにもいかなそう。
「有紗、そう言えばアンサンブル部の県大会どうだったんだ」
「んー、グループはふたつあったけど、五位と七位だったから、今年は全国大会に出られなかったんだ。まあ、私はメンバーになれなかったけどね」
最近は屋上でおしゃべりしながら昼食をとるのが日課になっている。葉山くんと、それから――京本くんと。
「でも高円寺さん、だいぶ上手くなったよね。音がいきいきしていて、前とはぜんぜん違っているよ」
「千里ちゃんのおかげだよ。自分の長所も欠点も、わかりやすく教えてくれるんだもん」
「じゃあ有紗、もしかすると春期コンクールはメンバー狙えるんじゃね?」
「確かに、今の上達ぶりならいけるかもしれないよ」
「うーん、みんな経験者ばっかりだからねぇ……。でも、京本くんに褒められると、素直に嬉しいよ。葉山くんに褒められると、なぜか警戒心が沸き起こるけど」
「なんだと有紗、そんなこと言うなら良家仕立てのだし巻き卵食わせろ!」
葉山くんの箸が私の弁当箱に向かってするすると伸びてきた。
「高円寺さん、きたよ。今日こそは逃げ切れ!」
「最後の楽しみ、奪われてなるものかぁ!」
弁当箱を両手でしっかりと握り、ひょいひょいっと動かして箸をかわす。
「くっ、逃げられたか。だし巻き玉子との語らいを夢見ていたのに」
「まあ、こっちを生贄に捧げるから鎮まってくれ」
京本くんは自分の唐揚げをひとつ、箸の持ち手側で挟んで葉山くんの弁当のパックにぽとりと落とす。京本くんのお弁当はいつもてんこ盛りだ。
「おっ、サンキューな」
「じゃあ、高円寺さんにはこっちね」
京本くんは爪楊枝が刺さったイチゴとキウイのフルーツセットをひとつつまんで私にくれた。
「あっ、ありがとう」
「母さんの作るランチは量が多すぎるんだ。いくらバイトで帰りが遅いからって、こんなにはいらないよ」
「それは親心なんじゃない。でも、食べきれないならお言葉に甘えていただきまーす」
フルーツセットを受け取って口に放り込む。ああ、爽やかな果汁が口の中に広がる。
堪能していると、京本くんが急に真剣な顔になって尋ねてきた。
「高円寺さん、ちょっと聞きたいんだけど」
「むふぁ?」
「千里の病気って、なんなのかなぁ。ネットで調べたんだけど、目が見えなくなる病気ってたくさんあって。それに千里やおばさんに直接訊くわけにもいかなくてさ」
「千里ちゃんの、病気ねぇ……」
私はお兄ちゃんから病名を聞いたとき、ほんとうにそうなのか自分なりに調べていた。本から得た知識をもとに病名が正しいか確認する。
「ねえ、ひょっとすると瞳の奥が白っぽく見えたりする病気?」
京本くんは目を丸くした。その表情に私は確信を持つ。
「じつは……僕が記憶している千里の、最後の姿がそうだった」
やっぱり間違いない。お兄ちゃんの推測は的を射ていたんだ。さすがは秀才。
「それ、『網膜芽細胞腫』っていう病気なんだと思う」
「へえ、よく知っているね」
「お兄ちゃんに聞いたんだ。たしか、生まれつきの遺伝子異常が原因で、両眼にほぼ同時に腫瘍ができる病気って言っていたよ」
「そうなのか……」
葉山くんも真剣な顔で察してくる。
「とすると、千里たんは生まれつき病気になる運命だったってことなのか」
「うん、たぶん」
京本くんはしばらく考え込んでいたけれど、唐突に顔を上げ、意外なことを私に尋ねた。
「ねえ、その病気って、問題が起きるのは眼だけなの?」
「えっ――?」
そう訊かれて、お兄ちゃんの言葉を思いだした。
『いろんな病気を併発しやすいっていう特徴があるらしい』
背中が冷水を注がれたようにぞっとする。その「いろんな病気」が具体的になにを意味するのかわからないけれど、京本くんの尋ね方はなんらかの心当たりがあるようだった。
でも、私の憶測でみんなの不安を煽るようなことはしたくない。気を取り直して笑顔を繕う。
「あんなに元気なんだから、なんにもないんじゃない?」
「そっか、そうだよね」
京本くんはまるで自分に言い聞かせるようにそう言う。葉山くんはさほど気にしていないようだった。
「それにしても千里たん、可愛いよなぁ。あんなに素直な子、見たことねえ」
「僕が思うに、外から悪い情報が入ってこないからじゃないかな」
「俺もそう思っている。自分ができることに一生懸命だし前向きだし。でも、これからどんな人生になるんだろうな、正直想像がつかねえよ」
葉山くんは京本くんの顔を直視した。まるで京本くんの思惑を探っているようでもある。
けれど京本くんはこともなげに返事をする。
「ああ、僕がいるからなんとかなるんじゃない?」
京本くんはいつだってそうだった。自分の人生をぜんぶ、千里ちゃんに投げだしたって構わないという雰囲気がある。将来を誓い合った関係というわけでもないのに。
――なんでそこまで尽くそうと思えるんだろう?
私には彼のその覚悟が、どうしても理解できなかった。
★
水曜日の朝、京本くんは相変わらず無口なままで読書を続けている。皆で千里ちゃんの家を訪れる日でもそれは変わらない。ただときどき、本を読むのをやめて私のフルートに耳を傾けていた。そんなとき、彼は唯一の私の聴衆で、私は彼の奏者だった。
晩秋になると、屋上から望む山麓は鮮やかに彩られる。けれど、そんな季節が過ぎる頃には、朝の冷え込みが身に沁みるようになっていた。そろそろ、いままでのように朝練を続けるわけにもいかなそう。