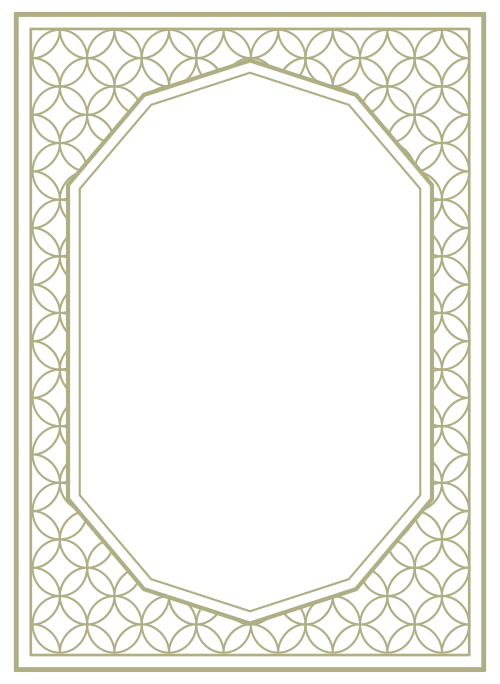京本くんにとっては、その時間はたぶんすごく大切なもので、だから私たちが邪魔しちゃいけないはずなの」
京本くんをちらと見ると、私の言動に驚いたようで身を起こしていた。膝をついて京本くんと向かい合う。
「ほんとうは私も千里ちゃんにフルートを聴いてもらいたいし、千里ちゃんの歌を聴きたいし、一緒に遊んだりしたいんだ。
でもね、相手の大切なものも尊重してあげなくちゃいけないと思う。私はそれができていなかったから、京本くんを怒らせちゃったんじゃないかな」
伝えきったところで皆、黙り込む。芝生が風に撫でられる乾いた音だけがあたりに広がっていた。どう思われたのかと不安になって胸が早鐘を打つ。
最初に言葉を発したのは、意外にも京本くん自身だった。
「高円寺さん。――あのさ、その……」
京本くんは顔を赤らめ、ためらいを見せる。薄く閉じたまぶたの下で瞳が揺らいでいた。彼のそんな表情は初めて見た。
「――ありがとう。僕のことを、ちゃんと考えてくれて」
彼の言葉に私は驚いて息をのんだ。こんなに温和に答えてくれるなんて想像していなかったから。
素直になってくれた京本くんに私も本心で向き合う。
「あっ、うん。私こそほんとうにごめんね。勝手に千里ちゃんの家におじゃまして、大切な時間を奪っちゃって」
そうだよ、なにも難しく考えることなんてなかったんだ。みんな、大切に思っていることがあるのに、それを隠して上手く振る舞おうとするから、どこかおかしくなるんだ。
「そうしたら……千里と会うの、高円寺さんは隔週でもいいかな? そのときは僕も参加するよ」
「うん、私は――それでいいよ。今日みたいにまた、みんなで出かけようね」
「ああ」
京本くんがうなずくと同時に、千里ちゃんの顔がぱああと明るくなる。ああ、やっぱり、千里ちゃんはみんなに仲良くなってほしいと思っていたんだ。
そんな私たちの様子を見て、葉山くんは遠慮なしに吹きだした。
「ぶはっ、隔週って、おまえら週替わりサービスランチかよ!」
「「うるさいっ!」」
からかわれて私の顔も火照る。でも、京本くんに私の気持ちが伝わったことが嬉しくて心の奥がくすぐったい。
西の空からやわらかな紅が伸びてきて、風が鋭くなってきた。
千里ちゃんが自分の両腕を手のひらで押さえてブルルと震えた。
「寒くなってきちまったな、そろそろ帰ろうか」
「ああっ、今日が終わっちゃうの、ざんねーん!」
けれど、私は胸の奥が毛布に包まれたみたいにほかほかとしている。
「私は……なんかあったかい……かな」
「僕も寒くはないよ。一緒に帰ろうか」
「うん」
京本くんともう一度、顔を見合わせる。ふふ、と私が笑うと彼も照れくさそうにはにかんだ。
紅に彩られた帰り道、自転車を手で押しながら私は思っていた。
水曜日に彼が喋らない理由を探る必要なんて、もうないのかもしれない。
だって、きっといつか、彼が自分から話してくれるんだろうなと、そんな予感がしたのだから。
京本くんをちらと見ると、私の言動に驚いたようで身を起こしていた。膝をついて京本くんと向かい合う。
「ほんとうは私も千里ちゃんにフルートを聴いてもらいたいし、千里ちゃんの歌を聴きたいし、一緒に遊んだりしたいんだ。
でもね、相手の大切なものも尊重してあげなくちゃいけないと思う。私はそれができていなかったから、京本くんを怒らせちゃったんじゃないかな」
伝えきったところで皆、黙り込む。芝生が風に撫でられる乾いた音だけがあたりに広がっていた。どう思われたのかと不安になって胸が早鐘を打つ。
最初に言葉を発したのは、意外にも京本くん自身だった。
「高円寺さん。――あのさ、その……」
京本くんは顔を赤らめ、ためらいを見せる。薄く閉じたまぶたの下で瞳が揺らいでいた。彼のそんな表情は初めて見た。
「――ありがとう。僕のことを、ちゃんと考えてくれて」
彼の言葉に私は驚いて息をのんだ。こんなに温和に答えてくれるなんて想像していなかったから。
素直になってくれた京本くんに私も本心で向き合う。
「あっ、うん。私こそほんとうにごめんね。勝手に千里ちゃんの家におじゃまして、大切な時間を奪っちゃって」
そうだよ、なにも難しく考えることなんてなかったんだ。みんな、大切に思っていることがあるのに、それを隠して上手く振る舞おうとするから、どこかおかしくなるんだ。
「そうしたら……千里と会うの、高円寺さんは隔週でもいいかな? そのときは僕も参加するよ」
「うん、私は――それでいいよ。今日みたいにまた、みんなで出かけようね」
「ああ」
京本くんがうなずくと同時に、千里ちゃんの顔がぱああと明るくなる。ああ、やっぱり、千里ちゃんはみんなに仲良くなってほしいと思っていたんだ。
そんな私たちの様子を見て、葉山くんは遠慮なしに吹きだした。
「ぶはっ、隔週って、おまえら週替わりサービスランチかよ!」
「「うるさいっ!」」
からかわれて私の顔も火照る。でも、京本くんに私の気持ちが伝わったことが嬉しくて心の奥がくすぐったい。
西の空からやわらかな紅が伸びてきて、風が鋭くなってきた。
千里ちゃんが自分の両腕を手のひらで押さえてブルルと震えた。
「寒くなってきちまったな、そろそろ帰ろうか」
「ああっ、今日が終わっちゃうの、ざんねーん!」
けれど、私は胸の奥が毛布に包まれたみたいにほかほかとしている。
「私は……なんかあったかい……かな」
「僕も寒くはないよ。一緒に帰ろうか」
「うん」
京本くんともう一度、顔を見合わせる。ふふ、と私が笑うと彼も照れくさそうにはにかんだ。
紅に彩られた帰り道、自転車を手で押しながら私は思っていた。
水曜日に彼が喋らない理由を探る必要なんて、もうないのかもしれない。
だって、きっといつか、彼が自分から話してくれるんだろうなと、そんな予感がしたのだから。