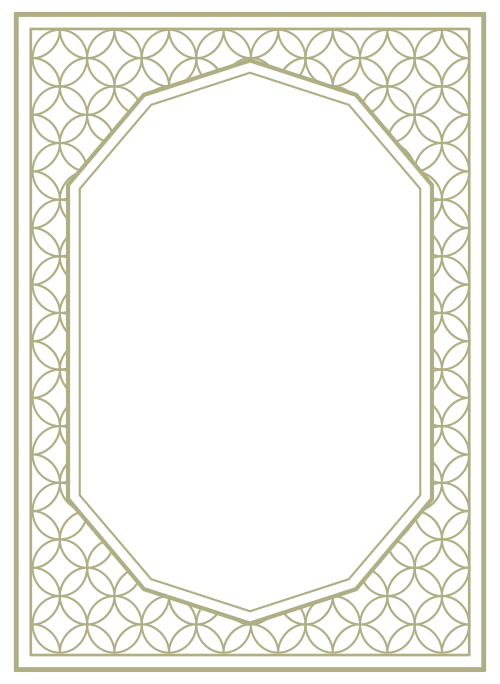私は今、千里さんという盲目の子と対峙している。それも、京本くんが毎週訪れる、彼女の部屋で。ああ、これが修羅場っていうやつなのか。初めて経験した。
正座で向かい合い、互いに頭を下げる。喉はカラカラに乾ききっていて、背中は冷たい汗でじっとりしている。彼女は閉じたまぶたの向こうから、私の気配をうかがっているに違いない。
京本くんと千里さんの関係はいびつだけど立ち入る隙がないほど強固に思えた。重厚な城壁に突っ込むようなものだから、無謀としかいいようがない。緊張のあまり握りしめた手が勝手に震えだす。
だけど千里さんは、彼の日常を知らないはず。それだけが私の強みであり武器だった。意を決して切りだす。
「千里さん、あなたは水曜日の京本くんが、学校でどんなふうか知っているんですか?」
「え……?」
その詰問に、千里さんの表情が動揺の色を浮かべる。やっぱりそうだ、彼女は水曜日、それも放課後限定の仲でしかない。残りの日常の京本くんは、彼女の手中にはない。
京本くんは焦ったみたいで、すかさず割り込んできた。
「高円寺さん、それは千里とは関係な――」
「和也くんは黙っていて! あたし、高円寺さんと話をしているの。和也くんはしばらく、出て行ってくれないかな」
千里さんが京本くんの加勢を拒んだのは意外なことだった。京本くんの驚いた表情は、彼にとっても心外だったことを表している。
ということは、千里さん自身、京本くんに聞かれたくないことがあるのかもしれない。
結局、彼はしぶしぶ身を引き部屋を後にする。扉が閉まると同時に私はその意図をうかがう。
「ふたりきりになるなんて、どういうつもりなんですか。視えないのに怖くないんですか」
視界が閉ざされた中、ひとりで駆け引きをするつもりなのだろうか? 千里さんは突然、柔和な態度になる。
「ていねい語は話しづらいからやめようよ。同級生なんだし。いい?」
「え……?」
意図がつかめず、これは演技じゃないのかと察した。おのずと警戒心が沸き起こる。どう答えようか迷っていると、千里さんは扉に顔を向けて声をあげた。
「聞き耳立てちゃだめだよー」
扉の向こうに京本くんの気配を感じたのだろう。廊下がきしんだから、彼は中の様子をうかがっていたみたいだった。千里さんは相当、察しが良い女の子みたい。とにかく油断は禁物だ。すでに背中がびっしょりと濡れて冷たい。
「いいわよ。私も普通に話すから」
「よかった。それでね」
それから千里さんは決めてあったように話を続ける。
「和也くんのことで尋ねたいことがあるの。どうしても本人に聞けないことだから」
「尋ねたいこと?」
「和也くん、学校ではどんな日常を送っているのか知りたくて。部活とかやっていないみたいだし、ちゃんと友達はいるのかなって」
やっぱり彼のことを知りたいんだ。私はどんな反応をするのか知りたくて、迷わず京本くんのことを伝えることにした。
「部活はしていないけど、アルバイトをやっているみたい。友達は多くなさそう、っていうか、いないかも。それに、水曜日はひとことも喋らないの」
「えっ、水曜日は喋らない……?」
考えもしなかったようで、千里さんは困惑した表情になる。その隙を突いてたたみかける。
「うん。誰かが話しかけても、先生に質問されてもね。しかも水曜日にかぎって、すごく苦しそうな表情を見せるの。どうしてだかわかる?」
暗にあなたのせい、という意味を込めたつもりだけれど、千里さんはどう返事をしてよいのかわからない様子。まるで心当たりがないのか、それとも彼女に自覚がないだけなのか。間髪入れず続ける。
「私は、あなたに会うことがその原因じゃないかって思っている」
「え……あたしに?」
千里さんは明らかに動揺していた。いったいふたりはどんな関係なのか、知りたい気持ちと知ることへの恐怖が私の胸の中でせめぎ合っている。けれど、勇気を振り絞ってさらに追いつめる。
「あなた、京本くんとふたり、密室でなにをしているの?」
「それは……え、と……」
雰囲気がしどろもどろで、ますます怪しい。この分なら核心に迫れるかもしれない。
「言えないようなことなの?」
「ううん。ただ、本を読んでくれて、おやつを食べて帰るだけだけど……」
「へっ? 本を読むって、読書っていうこと?」
意外すぎてつい、すっとんきょうな声になってしまった。
「うん、朗読してくれるんだ。和也くんが勧める本、どれも面白いよ」
「うそ、信じられない。ほんとうにそれだけ?」
「それだけだよ。あたし、盲目だからどこにも出かけられないし。病気で手術するまではちゃんと見えていたんだけどね」
痺れるほど緊張した私とは対照的に、千里さんはあっけらかんとした雰囲気で話を進める。
「でも、あたしは不思議でならないの。和也くんがどうしてあたしにここまで親切にしてくれるのか」
そう言う千里さんの表情はすこぶる素直で、嘘をついているようには思えなかった。
「それじゃあ、あなたが無理強いしているわけじゃないっていうこと?」
「和也くんの気持ちはわからないけど……あたしは気楽で楽しいよ。和也くんもきっとそうだと思う。うん」
その言い方には、当初抱いていた魔女のようなイメージとは程遠い、子供のように素直なあどけなさがある。
そのときになって、千里さんが私に会うことを承諾したのは、私を叩きのめすためではないのだと思った。
正座で向かい合い、互いに頭を下げる。喉はカラカラに乾ききっていて、背中は冷たい汗でじっとりしている。彼女は閉じたまぶたの向こうから、私の気配をうかがっているに違いない。
京本くんと千里さんの関係はいびつだけど立ち入る隙がないほど強固に思えた。重厚な城壁に突っ込むようなものだから、無謀としかいいようがない。緊張のあまり握りしめた手が勝手に震えだす。
だけど千里さんは、彼の日常を知らないはず。それだけが私の強みであり武器だった。意を決して切りだす。
「千里さん、あなたは水曜日の京本くんが、学校でどんなふうか知っているんですか?」
「え……?」
その詰問に、千里さんの表情が動揺の色を浮かべる。やっぱりそうだ、彼女は水曜日、それも放課後限定の仲でしかない。残りの日常の京本くんは、彼女の手中にはない。
京本くんは焦ったみたいで、すかさず割り込んできた。
「高円寺さん、それは千里とは関係な――」
「和也くんは黙っていて! あたし、高円寺さんと話をしているの。和也くんはしばらく、出て行ってくれないかな」
千里さんが京本くんの加勢を拒んだのは意外なことだった。京本くんの驚いた表情は、彼にとっても心外だったことを表している。
ということは、千里さん自身、京本くんに聞かれたくないことがあるのかもしれない。
結局、彼はしぶしぶ身を引き部屋を後にする。扉が閉まると同時に私はその意図をうかがう。
「ふたりきりになるなんて、どういうつもりなんですか。視えないのに怖くないんですか」
視界が閉ざされた中、ひとりで駆け引きをするつもりなのだろうか? 千里さんは突然、柔和な態度になる。
「ていねい語は話しづらいからやめようよ。同級生なんだし。いい?」
「え……?」
意図がつかめず、これは演技じゃないのかと察した。おのずと警戒心が沸き起こる。どう答えようか迷っていると、千里さんは扉に顔を向けて声をあげた。
「聞き耳立てちゃだめだよー」
扉の向こうに京本くんの気配を感じたのだろう。廊下がきしんだから、彼は中の様子をうかがっていたみたいだった。千里さんは相当、察しが良い女の子みたい。とにかく油断は禁物だ。すでに背中がびっしょりと濡れて冷たい。
「いいわよ。私も普通に話すから」
「よかった。それでね」
それから千里さんは決めてあったように話を続ける。
「和也くんのことで尋ねたいことがあるの。どうしても本人に聞けないことだから」
「尋ねたいこと?」
「和也くん、学校ではどんな日常を送っているのか知りたくて。部活とかやっていないみたいだし、ちゃんと友達はいるのかなって」
やっぱり彼のことを知りたいんだ。私はどんな反応をするのか知りたくて、迷わず京本くんのことを伝えることにした。
「部活はしていないけど、アルバイトをやっているみたい。友達は多くなさそう、っていうか、いないかも。それに、水曜日はひとことも喋らないの」
「えっ、水曜日は喋らない……?」
考えもしなかったようで、千里さんは困惑した表情になる。その隙を突いてたたみかける。
「うん。誰かが話しかけても、先生に質問されてもね。しかも水曜日にかぎって、すごく苦しそうな表情を見せるの。どうしてだかわかる?」
暗にあなたのせい、という意味を込めたつもりだけれど、千里さんはどう返事をしてよいのかわからない様子。まるで心当たりがないのか、それとも彼女に自覚がないだけなのか。間髪入れず続ける。
「私は、あなたに会うことがその原因じゃないかって思っている」
「え……あたしに?」
千里さんは明らかに動揺していた。いったいふたりはどんな関係なのか、知りたい気持ちと知ることへの恐怖が私の胸の中でせめぎ合っている。けれど、勇気を振り絞ってさらに追いつめる。
「あなた、京本くんとふたり、密室でなにをしているの?」
「それは……え、と……」
雰囲気がしどろもどろで、ますます怪しい。この分なら核心に迫れるかもしれない。
「言えないようなことなの?」
「ううん。ただ、本を読んでくれて、おやつを食べて帰るだけだけど……」
「へっ? 本を読むって、読書っていうこと?」
意外すぎてつい、すっとんきょうな声になってしまった。
「うん、朗読してくれるんだ。和也くんが勧める本、どれも面白いよ」
「うそ、信じられない。ほんとうにそれだけ?」
「それだけだよ。あたし、盲目だからどこにも出かけられないし。病気で手術するまではちゃんと見えていたんだけどね」
痺れるほど緊張した私とは対照的に、千里さんはあっけらかんとした雰囲気で話を進める。
「でも、あたしは不思議でならないの。和也くんがどうしてあたしにここまで親切にしてくれるのか」
そう言う千里さんの表情はすこぶる素直で、嘘をついているようには思えなかった。
「それじゃあ、あなたが無理強いしているわけじゃないっていうこと?」
「和也くんの気持ちはわからないけど……あたしは気楽で楽しいよ。和也くんもきっとそうだと思う。うん」
その言い方には、当初抱いていた魔女のようなイメージとは程遠い、子供のように素直なあどけなさがある。
そのときになって、千里さんが私に会うことを承諾したのは、私を叩きのめすためではないのだと思った。