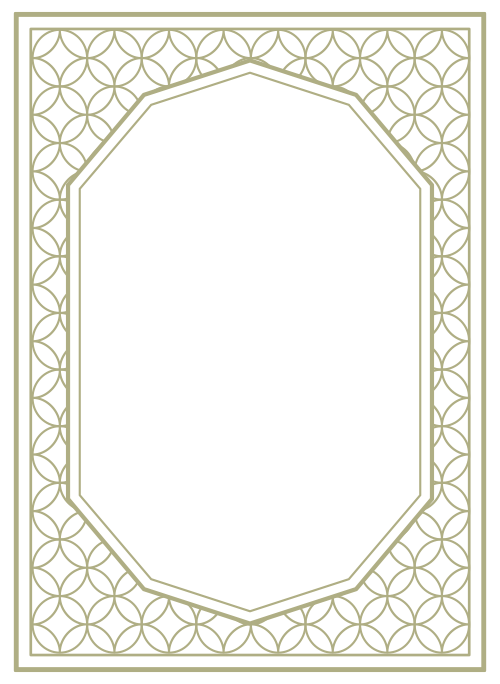「有紗の笑顔はとびきり可愛いね」
「お父さんとお母さんの宝物だよ」
私はきっと、誰の目からも幸せに包まれているようにしか見えないと思う。お父さんが大学病院の内科医で家は裕福なほう。みっつ年上のお兄ちゃんは、この城西高校の卒業生。アンサンブル部の部員で昨年、フルート奏者としてコンクールで全国大会金賞に輝いた経歴がある。しかも成績は超優秀で今年、医学部に進学している。
アイデンティティの塊みたいなお兄ちゃんはいつも私の憧れだった。だから私もこの高校、それもアンサンブル部に入部し、同じフルートを練習している。浅はかな私はなにも考えず、憧憬だけでそうしてしまった。
『高円寺涼太先輩の妹の、高円寺有紗』
高校に入学し、アンサンブル部に入部した当初、私はそんなレッテルだけで注目を浴びた。好寄と期待の視線で見られたけれど、演奏の音色を耳にした先輩たちはすぐに落胆の表情へと変わった。
考えてみれば、全国大会に出場した部活に人気がないはずはない。実力者が集まっていて、同級生の一年生ですら、中学時代に実績のある人ばかりだった。
私は早々に居場所を失うことになった。音楽室の壁にかけられた全国大会金賞の賞状を見るたびに胸が痛い。
憧れはあっても、勉強も音楽も、お兄ちゃんの才能にはとうてい及ばない。頑張っても、お兄ちゃんみたいにうまくいくはずがない。
そんなこと、とっくに気づいていた。
けれど、実績のある「高円寺涼太」の妹が挫折するところなんて見せられるはずがない。だから部活をやめるわけにもいかない。
家族だって、部活で全国大会を目指せとか、大学は医学部を目指せとか、そんな高望みはしてこない。
私はいったい、なにができるのだろう。どうしたら羽ばたけるのだろう。自分らしさって、どこにあるのだろう。五線譜の幅の中にはりついた音符のように、ただ、決められた場所で与えられた音の長さを示すことしかできないでいる。
だから、どんなに自分がみじめでも笑顔を浮かべ続けるしかなかった。
なにひとつ誇れることのない自分を、このどうしようもない葛藤を、誰にも知られずひた隠すための、牢獄の笑顔を。
それでもなんとか巻き返そうと、自主朝練だけは欠かさなかった。朝、誰もいない屋上でひとり、黙々とフルートを奏でる。
だけど、水曜日にかぎって屋上には先客がいた。ほとんど接点のない、クラスメートの男の子。
挨拶をしても微笑み返すだけで喋ることはない。ずっと本を読んでいて、ときどき思い返しては苦痛に耐えるような顔をする。まるで支えきれないほどの重いなにかを背負っているかのように。
ああ、この人はきっと、胸の奥に誰も知らない苦悩を抱えているんだ。彼の痛々しい表情が脳裏に焼きつき、心が音叉のように共鳴する。
京本和也くん。きみも逃れられない牢獄の中にいるのかな? じつは私もなんだよ。すごく苦しくて、息もできないくらい。でも、もしもそんなきみが楽になれるなら、私にも未来が見えるのかな?
いつだって、心の中できみに話しかけていた。まるで誰もいない孤独の世界で、初めて仲間に出会えたような、そんな不思議な感覚。
だから、きみのことをもっと知りたい。苦しさの根源を打ち明けてほしい。誰にも言えなかったことを、一緒に話しあえる相手がほしい。きみにそんな人になってほしい。
私の渇望は、日に日に胸の中で体積を増大させてゆく。水曜日に自主朝練を続けていたのは、そんな頼りない願いに支えられていたから。
ある日ついに、京本くんが水曜日に喋らない理由のヒントを手に入れた。貴重な情報は二学期になって後ろの席になった葉山陽一くんからだった。
「深窓の令嬢と蜜月しているらしい」
その衝撃の噂を耳にして、京本くんがどこか遠い世界に連れて行かれてしまうような感覚に陥る。焦燥感や、喪失感にも似た不穏な感情に呑まれそうになる。
私はいてもたってもいられなくなり、彼の喋らない理由の真相を確かめるため、水曜日の放課後に彼の後を追った。
京本くんが盲目の女の子に会っていることを知った。同時に水曜日、誰とも話すことがなく、あんなに苦しそうな顔をしているのは、彼女と関係があるのだと確信した。
だから私は京本くんを屋上に呼びだし、思っていることを正直に話そうとした。だけど京本くんは心を閉ざし、かたくなに拒絶していた。私は、きみとたくさん、話がしたかったのに。
『僕はきみが思っているようなことで苦しんだりなんかしてない! 千里と一緒にいようって決めたのは僕自身だ!』
ねえ、そんなことを言われて引き下がれると思う?
彼を得体の知れない束縛から解放してあげなくちゃ、って気持ちが湧き起こる。屋上から去ろうとする彼に向かって、衝動的に口走っていた。
『その子に直接、会わせてくれないかな。私がその子の本心を聞きだしてあげるから』
その女の子が身勝手に京本くんの未来を縛ろうとするなら、私が普通の日常に連れ戻してあげたい。
そんな無謀な賭けに出たのは、京本くんとは辛苦をわかり合える仲になれるかも、って期待していたから。
「お父さんとお母さんの宝物だよ」
私はきっと、誰の目からも幸せに包まれているようにしか見えないと思う。お父さんが大学病院の内科医で家は裕福なほう。みっつ年上のお兄ちゃんは、この城西高校の卒業生。アンサンブル部の部員で昨年、フルート奏者としてコンクールで全国大会金賞に輝いた経歴がある。しかも成績は超優秀で今年、医学部に進学している。
アイデンティティの塊みたいなお兄ちゃんはいつも私の憧れだった。だから私もこの高校、それもアンサンブル部に入部し、同じフルートを練習している。浅はかな私はなにも考えず、憧憬だけでそうしてしまった。
『高円寺涼太先輩の妹の、高円寺有紗』
高校に入学し、アンサンブル部に入部した当初、私はそんなレッテルだけで注目を浴びた。好寄と期待の視線で見られたけれど、演奏の音色を耳にした先輩たちはすぐに落胆の表情へと変わった。
考えてみれば、全国大会に出場した部活に人気がないはずはない。実力者が集まっていて、同級生の一年生ですら、中学時代に実績のある人ばかりだった。
私は早々に居場所を失うことになった。音楽室の壁にかけられた全国大会金賞の賞状を見るたびに胸が痛い。
憧れはあっても、勉強も音楽も、お兄ちゃんの才能にはとうてい及ばない。頑張っても、お兄ちゃんみたいにうまくいくはずがない。
そんなこと、とっくに気づいていた。
けれど、実績のある「高円寺涼太」の妹が挫折するところなんて見せられるはずがない。だから部活をやめるわけにもいかない。
家族だって、部活で全国大会を目指せとか、大学は医学部を目指せとか、そんな高望みはしてこない。
私はいったい、なにができるのだろう。どうしたら羽ばたけるのだろう。自分らしさって、どこにあるのだろう。五線譜の幅の中にはりついた音符のように、ただ、決められた場所で与えられた音の長さを示すことしかできないでいる。
だから、どんなに自分がみじめでも笑顔を浮かべ続けるしかなかった。
なにひとつ誇れることのない自分を、このどうしようもない葛藤を、誰にも知られずひた隠すための、牢獄の笑顔を。
それでもなんとか巻き返そうと、自主朝練だけは欠かさなかった。朝、誰もいない屋上でひとり、黙々とフルートを奏でる。
だけど、水曜日にかぎって屋上には先客がいた。ほとんど接点のない、クラスメートの男の子。
挨拶をしても微笑み返すだけで喋ることはない。ずっと本を読んでいて、ときどき思い返しては苦痛に耐えるような顔をする。まるで支えきれないほどの重いなにかを背負っているかのように。
ああ、この人はきっと、胸の奥に誰も知らない苦悩を抱えているんだ。彼の痛々しい表情が脳裏に焼きつき、心が音叉のように共鳴する。
京本和也くん。きみも逃れられない牢獄の中にいるのかな? じつは私もなんだよ。すごく苦しくて、息もできないくらい。でも、もしもそんなきみが楽になれるなら、私にも未来が見えるのかな?
いつだって、心の中できみに話しかけていた。まるで誰もいない孤独の世界で、初めて仲間に出会えたような、そんな不思議な感覚。
だから、きみのことをもっと知りたい。苦しさの根源を打ち明けてほしい。誰にも言えなかったことを、一緒に話しあえる相手がほしい。きみにそんな人になってほしい。
私の渇望は、日に日に胸の中で体積を増大させてゆく。水曜日に自主朝練を続けていたのは、そんな頼りない願いに支えられていたから。
ある日ついに、京本くんが水曜日に喋らない理由のヒントを手に入れた。貴重な情報は二学期になって後ろの席になった葉山陽一くんからだった。
「深窓の令嬢と蜜月しているらしい」
その衝撃の噂を耳にして、京本くんがどこか遠い世界に連れて行かれてしまうような感覚に陥る。焦燥感や、喪失感にも似た不穏な感情に呑まれそうになる。
私はいてもたってもいられなくなり、彼の喋らない理由の真相を確かめるため、水曜日の放課後に彼の後を追った。
京本くんが盲目の女の子に会っていることを知った。同時に水曜日、誰とも話すことがなく、あんなに苦しそうな顔をしているのは、彼女と関係があるのだと確信した。
だから私は京本くんを屋上に呼びだし、思っていることを正直に話そうとした。だけど京本くんは心を閉ざし、かたくなに拒絶していた。私は、きみとたくさん、話がしたかったのに。
『僕はきみが思っているようなことで苦しんだりなんかしてない! 千里と一緒にいようって決めたのは僕自身だ!』
ねえ、そんなことを言われて引き下がれると思う?
彼を得体の知れない束縛から解放してあげなくちゃ、って気持ちが湧き起こる。屋上から去ろうとする彼に向かって、衝動的に口走っていた。
『その子に直接、会わせてくれないかな。私がその子の本心を聞きだしてあげるから』
その女の子が身勝手に京本くんの未来を縛ろうとするなら、私が普通の日常に連れ戻してあげたい。
そんな無謀な賭けに出たのは、京本くんとは辛苦をわかり合える仲になれるかも、って期待していたから。