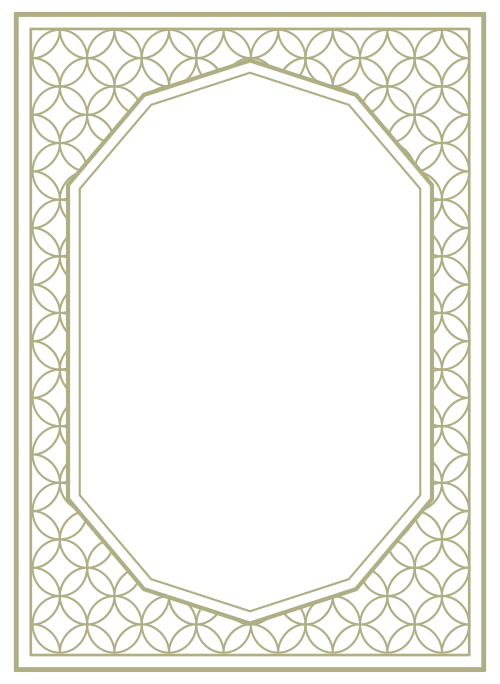★
翌水曜日は掃除当番の週だったので、千里の家へ行くのがいつもよりすこし遅れた。連絡はしておいたから多少遅れても不安に思うことはないはずだ。秋晴れの空の下、家に続く坂道を駆け足で登ってゆく。
千里の家に着くと、なんとなく雰囲気が違っていた。見慣れない自転車がふたつ、ブロック塀に寄りかかるようにして置かれている。誰かが勝手に停めているのだろうか。それに、どこからか楽しそうな笑い声が聞こえてくる。
庭の掃除をしていたおばさんは僕の顔を見るやいなや、「いらっしゃい、もう来ているわよ。さあどうぞ」と笑顔を向ける。
どういうことだ? 僕にはおばさんの言う意味がさっぱりわからなかった。
家に上がらせてもらい、一歩一歩、千里の部屋へと近づいていくと、起きたり収まったりの忙しい笑い声が聞こえてきた。ひどく嫌な予感がしたけれど、その予感はしだいに現実味を帯びてくる。
千里の部屋の扉をノックすると、「入っていいよー」といつにもまして明るい声が返ってきた。部屋の中には複数の人の気配があった。ほかに誰かがいることは疑いようもない。
僕と一緒に千里の家を訪れることができる人がいるとしたら――心当たりはひとりだけだ。
覚悟を決め、千里の部屋の扉を開いた。僕の目に飛び込んできたのは、見慣れた同級生である高円寺有紗と、さらには――葉山陽一の姿まであったのだ。
信じられるはずがない光景だ。いったい、なにが起きたんだ?
千里は、僕とふたりの時間を大切にしていたんじゃないのか?
この部屋は、誰にも邪魔されない聖域だったんじゃないのか?
三人はそろいもそろって屈託のない笑顔を僕に向ける。僕は思わず葉山を指さし、喘ぎ声のような声をもらした。
「なっ……なんでおまえまでここにいるんだよぉ……」
葉山は片方の口角を派手に吊り上げてみせる。狙いすましたように僕を指さし返して叫んだ。
「京本おまえ、水曜日だってのに喋っているじゃーん!」
葉山のしてやったりの顔が、僕には地獄に誘う死神のように見えた。
翌水曜日は掃除当番の週だったので、千里の家へ行くのがいつもよりすこし遅れた。連絡はしておいたから多少遅れても不安に思うことはないはずだ。秋晴れの空の下、家に続く坂道を駆け足で登ってゆく。
千里の家に着くと、なんとなく雰囲気が違っていた。見慣れない自転車がふたつ、ブロック塀に寄りかかるようにして置かれている。誰かが勝手に停めているのだろうか。それに、どこからか楽しそうな笑い声が聞こえてくる。
庭の掃除をしていたおばさんは僕の顔を見るやいなや、「いらっしゃい、もう来ているわよ。さあどうぞ」と笑顔を向ける。
どういうことだ? 僕にはおばさんの言う意味がさっぱりわからなかった。
家に上がらせてもらい、一歩一歩、千里の部屋へと近づいていくと、起きたり収まったりの忙しい笑い声が聞こえてきた。ひどく嫌な予感がしたけれど、その予感はしだいに現実味を帯びてくる。
千里の部屋の扉をノックすると、「入っていいよー」といつにもまして明るい声が返ってきた。部屋の中には複数の人の気配があった。ほかに誰かがいることは疑いようもない。
僕と一緒に千里の家を訪れることができる人がいるとしたら――心当たりはひとりだけだ。
覚悟を決め、千里の部屋の扉を開いた。僕の目に飛び込んできたのは、見慣れた同級生である高円寺有紗と、さらには――葉山陽一の姿まであったのだ。
信じられるはずがない光景だ。いったい、なにが起きたんだ?
千里は、僕とふたりの時間を大切にしていたんじゃないのか?
この部屋は、誰にも邪魔されない聖域だったんじゃないのか?
三人はそろいもそろって屈託のない笑顔を僕に向ける。僕は思わず葉山を指さし、喘ぎ声のような声をもらした。
「なっ……なんでおまえまでここにいるんだよぉ……」
葉山は片方の口角を派手に吊り上げてみせる。狙いすましたように僕を指さし返して叫んだ。
「京本おまえ、水曜日だってのに喋っているじゃーん!」
葉山のしてやったりの顔が、僕には地獄に誘う死神のように見えた。