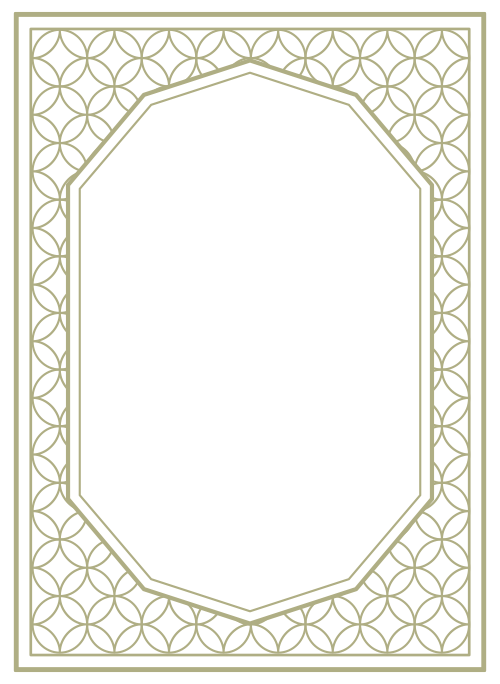「じゃあ聞くけど有紗、それが恋じゃないなら、いったいなんだって言うんだよ」
私の背後の席に鎮座するクラスメート、葉山陽一くんは腕を組んでふんぞり返り、そう断言する。
「そんなんじゃないよ、だって入学して半年近く経つのに、ほとんど口も聞いたことないんだから」
「ぶはっ! 恋に落ちるのに言葉なんかいらねえんだよ。俺に相談を持ちかける時点でフラグ立ちまくりじゃん」
「ちょっとやめてよ、どうして葉山くんは思考のベクトルがそっちを向くのかなぁ」
あわてて両手を振って否定しつつ周囲を見回す。さいわい、教室の喧騒が葉山くんの邪推をかき消してくれたので、誰にも聞かれることはなかったみたい。年頃のクラスメートは恋ってキーワードに過敏なんだから、うかつに恋バナ的発言をされるのは誤解のもとになる。
「京本くんは水曜日だけ人が変わる、『ちょっと気になるクラスメート』なだけだよ」
「気になる、ねぇ……」
葉山くんは両腕を頭の後ろに回し、上履きを脱いで両足を机の上に放りだす。
「じゃあ俺の立ち位置は?」
にかっと白い歯を見せて意気揚々と尋ねてきた。恥ずかしげもなくそう訊くことのできる彼はある意味、尊敬に値する。その鋼のメンタル、私にもおすそ分けしてほしい。
ちなみに今のひとことも、別段、恋人に立候補しているわけではなく、私のことをからかっているだけ。そうでなければ、堂々と足の裏を私の目の前に並べるはずがない。
「見た目二枚目、話すと三枚目? ひとことで言えばイケメン風味、かな」
「ひでっ!」
「あとね私、葉山くんの足の裏を眺めるために生まれてきたわけじゃないんだけど。それから、この靴下はもうだめみたいね」
机の上に並んだ足の裏をシャーペンの先で突っつくと、当の本人は逃げるように足を引っ込め足裏を確認した。かかとのあたりは生地が擦り減り、地肌がすけて見えていた。
「そか、ついに殉死かよ、俺のアディダス。さんざん苦労かけたからなぁ」
「サッカー部ならしょうがないよね、上達の犠牲だと思おうよ。目標のエースどころか、スタメンもまだ遠いんでしょ」
「まあな、先輩方はやっぱうめぇよ。ポジション争い厳しいぜ」
葉山くんはショートレイヤーの髪を無造作に掻いてみせる。多少手厳しいことを言っても後腐れがないから、『気さくな話し相手』としては最高だ。こういうのを男友達っていうのかな。
「でもさ、葉山くんは一学期、京本くんの隣の席だったし、よく話しかけていたじゃない? だから京本くんの喋らない事情を知っているんじゃないかと思って」
葉山くんなら、何食わぬ顔で尋問していてもおかしくはない。
「ああ、確かにあいつ、水曜日だけは人が変わったように無口になるよな」
葉山くんはうって変わって真剣な顔で答えた。普段からこんな表情でいれば、お望み通りそれなりにモテるはずなのに、って思えなくもない。
「理由を知りたいんだったら、有紗が本人に直接聞いてみりゃいいじゃん」
そう言われたけれど、さすがにそれはご遠慮願いたい。話しかけられないというよりは、触れてはいけないことのような気がするから。
「訊きたいけど、そうそう訊けないよ」
「ああ? 俺には言いたいこと言うくせに、ほかのやつの前ではカマトトぶるのかよ」
「だって、水曜日の京本くんは、どこか苦しそうなんだもん……」
教室の向こう側、窓際の席に座っている京本くんに視線を向ける。朝の屋上に引き続き、一心不乱に本を読み込んでいる。
「そうか? 俺にはリア充してるように見えるけどな。ほら、あれって目的を持っているやつの顔じゃん。ああいう表情をするやつはなにかに夢中になっているはずだぜ」
葉山くんは親指を立て、くいっと手首を返して京本くんのほうに向けた。
確かに、夢中になっている表情と言えばそう捉えられなくもない。けれど、私には言葉では形容しがたい危うさがあるように感じられる。
私が彼のことを気になってしかたないのは、そんな漠然とした懸念を感じさせられるからだ。まるで表面張力のおかげで水面に浮いていられる一円玉のような、とても不安定な感覚。下手に触れると、いとも簡単に沈んでしまいそう。
葉山くんは、私が考え込む表情を見て助け舟を出そうと思ったのか、いくぶん耳元に口を寄せてきた。誰にも聞こえないように気を遣うっていうことは、重要なことを伝えるつもりに違いない。私は喧噪に邪魔されないよう、耳元に神経を集中する。
私の背後の席に鎮座するクラスメート、葉山陽一くんは腕を組んでふんぞり返り、そう断言する。
「そんなんじゃないよ、だって入学して半年近く経つのに、ほとんど口も聞いたことないんだから」
「ぶはっ! 恋に落ちるのに言葉なんかいらねえんだよ。俺に相談を持ちかける時点でフラグ立ちまくりじゃん」
「ちょっとやめてよ、どうして葉山くんは思考のベクトルがそっちを向くのかなぁ」
あわてて両手を振って否定しつつ周囲を見回す。さいわい、教室の喧騒が葉山くんの邪推をかき消してくれたので、誰にも聞かれることはなかったみたい。年頃のクラスメートは恋ってキーワードに過敏なんだから、うかつに恋バナ的発言をされるのは誤解のもとになる。
「京本くんは水曜日だけ人が変わる、『ちょっと気になるクラスメート』なだけだよ」
「気になる、ねぇ……」
葉山くんは両腕を頭の後ろに回し、上履きを脱いで両足を机の上に放りだす。
「じゃあ俺の立ち位置は?」
にかっと白い歯を見せて意気揚々と尋ねてきた。恥ずかしげもなくそう訊くことのできる彼はある意味、尊敬に値する。その鋼のメンタル、私にもおすそ分けしてほしい。
ちなみに今のひとことも、別段、恋人に立候補しているわけではなく、私のことをからかっているだけ。そうでなければ、堂々と足の裏を私の目の前に並べるはずがない。
「見た目二枚目、話すと三枚目? ひとことで言えばイケメン風味、かな」
「ひでっ!」
「あとね私、葉山くんの足の裏を眺めるために生まれてきたわけじゃないんだけど。それから、この靴下はもうだめみたいね」
机の上に並んだ足の裏をシャーペンの先で突っつくと、当の本人は逃げるように足を引っ込め足裏を確認した。かかとのあたりは生地が擦り減り、地肌がすけて見えていた。
「そか、ついに殉死かよ、俺のアディダス。さんざん苦労かけたからなぁ」
「サッカー部ならしょうがないよね、上達の犠牲だと思おうよ。目標のエースどころか、スタメンもまだ遠いんでしょ」
「まあな、先輩方はやっぱうめぇよ。ポジション争い厳しいぜ」
葉山くんはショートレイヤーの髪を無造作に掻いてみせる。多少手厳しいことを言っても後腐れがないから、『気さくな話し相手』としては最高だ。こういうのを男友達っていうのかな。
「でもさ、葉山くんは一学期、京本くんの隣の席だったし、よく話しかけていたじゃない? だから京本くんの喋らない事情を知っているんじゃないかと思って」
葉山くんなら、何食わぬ顔で尋問していてもおかしくはない。
「ああ、確かにあいつ、水曜日だけは人が変わったように無口になるよな」
葉山くんはうって変わって真剣な顔で答えた。普段からこんな表情でいれば、お望み通りそれなりにモテるはずなのに、って思えなくもない。
「理由を知りたいんだったら、有紗が本人に直接聞いてみりゃいいじゃん」
そう言われたけれど、さすがにそれはご遠慮願いたい。話しかけられないというよりは、触れてはいけないことのような気がするから。
「訊きたいけど、そうそう訊けないよ」
「ああ? 俺には言いたいこと言うくせに、ほかのやつの前ではカマトトぶるのかよ」
「だって、水曜日の京本くんは、どこか苦しそうなんだもん……」
教室の向こう側、窓際の席に座っている京本くんに視線を向ける。朝の屋上に引き続き、一心不乱に本を読み込んでいる。
「そうか? 俺にはリア充してるように見えるけどな。ほら、あれって目的を持っているやつの顔じゃん。ああいう表情をするやつはなにかに夢中になっているはずだぜ」
葉山くんは親指を立て、くいっと手首を返して京本くんのほうに向けた。
確かに、夢中になっている表情と言えばそう捉えられなくもない。けれど、私には言葉では形容しがたい危うさがあるように感じられる。
私が彼のことを気になってしかたないのは、そんな漠然とした懸念を感じさせられるからだ。まるで表面張力のおかげで水面に浮いていられる一円玉のような、とても不安定な感覚。下手に触れると、いとも簡単に沈んでしまいそう。
葉山くんは、私が考え込む表情を見て助け舟を出そうと思ったのか、いくぶん耳元に口を寄せてきた。誰にも聞こえないように気を遣うっていうことは、重要なことを伝えるつもりに違いない。私は喧噪に邪魔されないよう、耳元に神経を集中する。