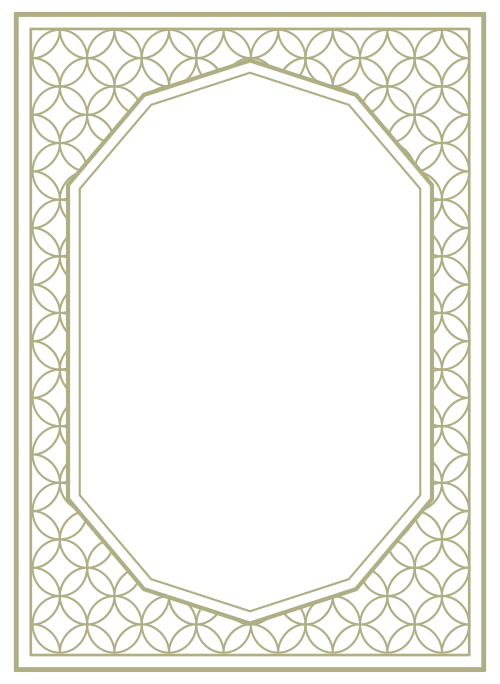千里の家に着いた。息が整ったところで、最後に一度、おおきく深呼吸をする。もうとっくに心の準備はできている。迷わず呼び鈴を鳴らすと、思いのほかすぐに扉が開いた。千里本人が思いっきり開け放ち、しかも勢い余ってよろけて出てきた。
転びそうになったので両手で支えると、僕に気づいて驚いたようだった。まぶたを閉じたままの顔を上げ、真剣な表情で話しかけてくる。
「和也くん、また会いに来てくれたんだ」
「ああ、約束したじゃん。これから毎週来ることにしたから」
「和也くんって、浮世離れしているくらいのお人好しだったんだね」
感極まった小声でそう言う千里は、以前のような浮かれた雰囲気ではなかった。半年も経ってないのに、あのとき感じたあどけなさが薄れていて、やけに大人っぽく感じた。女子は男子よりも心の成長が早いというから、僕がそう感じているだけなのだろうか。
千里に続いておばさんも玄関から出てきた。僕を見て口元を緩めたので、すかさず僕から挨拶をする。
「こんにちは、おばさん。また、おじゃましてしまってすみません」
「いらっしゃい、和也くん。それにおめでとう、千里から聞いたわよ。城西高校に入学したんですってね。さすがね~」
おばさんの上手な笑顔を見て、千里は母親似なのだと思う。ふたりの丸みのある温和な笑顔は僕の波立つ気分を落ち着かせてくれる。
「ありがとうございます。あの……せっかく近くの高校になったので、おばさんの都合が悪くなければ、水曜日の学校帰りにおじゃましてもよろしいですか?」
おばさんは一瞬、迷いを浮かべたように見えた。けれど、すぐに明るい表情になって快い返事をくれる。
「もちろん大歓迎よ。千里、和也くんに会えるのが待ち遠しかったみたい。今日だってずっと玄関で待っていたのよ」
「お母さん、余計なこと言わなくていいから!」
千里は頬を紅潮させ、おばさんに向かって声を張り上げた。どうやら千里に拒絶されていたわけではないらしく、まずは安堵した。
「ほんとうによかったわね。偶然とはいえ、水曜日が楽しみになったわね」
「うっ、うん……」
千里はあいまいに返事をする。僕が千里のために城西高等学校を選んだという事実を、おばさんには話していないようだ。
じゃあ家に上がってね、と促されてふたたび千里の家に足を踏み入れる。
千里の部屋は、荷物を置く場所や家具の配置が以前見たときとまったく同じだった。千里の脳裏には部屋の見取り図が焼きついているのだろう。
「和也くん、どうぞ座って」
千里はそう言いながら、手探りで探し当てた座椅子を僕に差しだす。
「いや、いいよ。千里が座ってくれるかな。だって今日は休日だし、この前より長い時間おじゃましていたいから。いいかな?」
「えっ、なにかあるの?」
千里が探るように聞いたところで、僕はあたためてきたひとことを告げる。
「本の物語を朗読するから」
僕がそう言うと、千里は肩を跳ねて驚きをあらわにした。
「千里、ほんとうは僕にそうしてほしかったんでしょ?」
「嬉しいけど……でも、その言い方だと、この前来てくれたとき、あたしのお願い、わかっていて断ったんだよね?」
「ん、まぁ……だって、あんなに露骨に催促するんだから誰だってわかるよ」
「やっぱり! じゃあ、なんで今になって本を読んでくれる気になったの?」
千里の洞察力はなかなか鋭くて内心たじろいだ。でも、千里にはこの心臓を締め上げるような呵責を気づかれたくない。
とっさにまっとうな理由を探してごまかす。
「せっかく気楽な友達になってくれたんだから、すこしは楽しみを分け与えてあげたいじゃん。それに受験が終わって時間ができたし、やりたい部活もないからさ」
「そっか。じゃあ、素直にお言葉に甘えて水曜日は家で待っているね。……でも、それ以外の曜日は、あたしのことは気にせず高校生活を謳歌してほしいな。けっして抜き打ちで遊びにきたりしないこと、それ約束ね」
「あっ、うん。わかったよ」
千里は、水曜日以外はとにかく都合が悪いらしい。尋ねても言い訳じみたことを返し、しまいには「女の子の予定を詮索するなんて紳士じゃないぞ!」と叱責されて僕は引き下がることになった。
機嫌を損ねかけた千里は背中を向けて布団の上に体育座りをした。すこし間があってから、ぼそっと尋ねる。
「ねえ、どんな本があるの」
「いろいろだよ」
僕なりに多種多様なジャンルをそろえたつもりだ。
「いろいろって言うなら――誰も行けない場所を旅するような物語が聴きたい!」
「そっか。じゃあ、これなんかはどうかな」
文庫本を一冊取りだす。
転びそうになったので両手で支えると、僕に気づいて驚いたようだった。まぶたを閉じたままの顔を上げ、真剣な表情で話しかけてくる。
「和也くん、また会いに来てくれたんだ」
「ああ、約束したじゃん。これから毎週来ることにしたから」
「和也くんって、浮世離れしているくらいのお人好しだったんだね」
感極まった小声でそう言う千里は、以前のような浮かれた雰囲気ではなかった。半年も経ってないのに、あのとき感じたあどけなさが薄れていて、やけに大人っぽく感じた。女子は男子よりも心の成長が早いというから、僕がそう感じているだけなのだろうか。
千里に続いておばさんも玄関から出てきた。僕を見て口元を緩めたので、すかさず僕から挨拶をする。
「こんにちは、おばさん。また、おじゃましてしまってすみません」
「いらっしゃい、和也くん。それにおめでとう、千里から聞いたわよ。城西高校に入学したんですってね。さすがね~」
おばさんの上手な笑顔を見て、千里は母親似なのだと思う。ふたりの丸みのある温和な笑顔は僕の波立つ気分を落ち着かせてくれる。
「ありがとうございます。あの……せっかく近くの高校になったので、おばさんの都合が悪くなければ、水曜日の学校帰りにおじゃましてもよろしいですか?」
おばさんは一瞬、迷いを浮かべたように見えた。けれど、すぐに明るい表情になって快い返事をくれる。
「もちろん大歓迎よ。千里、和也くんに会えるのが待ち遠しかったみたい。今日だってずっと玄関で待っていたのよ」
「お母さん、余計なこと言わなくていいから!」
千里は頬を紅潮させ、おばさんに向かって声を張り上げた。どうやら千里に拒絶されていたわけではないらしく、まずは安堵した。
「ほんとうによかったわね。偶然とはいえ、水曜日が楽しみになったわね」
「うっ、うん……」
千里はあいまいに返事をする。僕が千里のために城西高等学校を選んだという事実を、おばさんには話していないようだ。
じゃあ家に上がってね、と促されてふたたび千里の家に足を踏み入れる。
千里の部屋は、荷物を置く場所や家具の配置が以前見たときとまったく同じだった。千里の脳裏には部屋の見取り図が焼きついているのだろう。
「和也くん、どうぞ座って」
千里はそう言いながら、手探りで探し当てた座椅子を僕に差しだす。
「いや、いいよ。千里が座ってくれるかな。だって今日は休日だし、この前より長い時間おじゃましていたいから。いいかな?」
「えっ、なにかあるの?」
千里が探るように聞いたところで、僕はあたためてきたひとことを告げる。
「本の物語を朗読するから」
僕がそう言うと、千里は肩を跳ねて驚きをあらわにした。
「千里、ほんとうは僕にそうしてほしかったんでしょ?」
「嬉しいけど……でも、その言い方だと、この前来てくれたとき、あたしのお願い、わかっていて断ったんだよね?」
「ん、まぁ……だって、あんなに露骨に催促するんだから誰だってわかるよ」
「やっぱり! じゃあ、なんで今になって本を読んでくれる気になったの?」
千里の洞察力はなかなか鋭くて内心たじろいだ。でも、千里にはこの心臓を締め上げるような呵責を気づかれたくない。
とっさにまっとうな理由を探してごまかす。
「せっかく気楽な友達になってくれたんだから、すこしは楽しみを分け与えてあげたいじゃん。それに受験が終わって時間ができたし、やりたい部活もないからさ」
「そっか。じゃあ、素直にお言葉に甘えて水曜日は家で待っているね。……でも、それ以外の曜日は、あたしのことは気にせず高校生活を謳歌してほしいな。けっして抜き打ちで遊びにきたりしないこと、それ約束ね」
「あっ、うん。わかったよ」
千里は、水曜日以外はとにかく都合が悪いらしい。尋ねても言い訳じみたことを返し、しまいには「女の子の予定を詮索するなんて紳士じゃないぞ!」と叱責されて僕は引き下がることになった。
機嫌を損ねかけた千里は背中を向けて布団の上に体育座りをした。すこし間があってから、ぼそっと尋ねる。
「ねえ、どんな本があるの」
「いろいろだよ」
僕なりに多種多様なジャンルをそろえたつもりだ。
「いろいろって言うなら――誰も行けない場所を旅するような物語が聴きたい!」
「そっか。じゃあ、これなんかはどうかな」
文庫本を一冊取りだす。