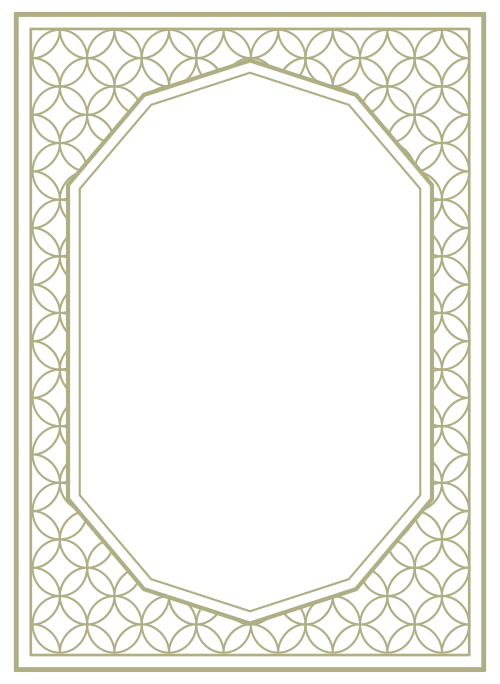★
帰りの電車で座席に腰をおろし、背もたれに身を預ける。向かい側の窓から差し込むオレンジの光が眩しくてまぶたを閉ざす。
電車に揺られていると、知らない街を訪れたことでの疲労と、ほんのりとした座席の暖かさが僕をまどろみの世界へ誘ってゆく。
ふと気づくと僕の意識は、夢と現実の狭間のような空間をふわふわと漂っていた。
昔の自分を思いだしているようで、おぼろげな記憶の中をさまよっている。千里に会ったことがきっかけとなったのか、当時の記憶の輪郭がしだいに明瞭になってゆく。
それはまだ僕が小学校低学年の頃だった。千里が登場する過去の中では、最も表層にあたる記憶だ。
庭の生垣に身を隠し、密集した葉の隙間から庭の様子をうかがう。背後の窓を挟んだリビングからは、世間話で盛り上がる女性陣の笑い声が聞こえてくる。ひとりは幼稚園で同じクラスだった女の子のお母さん。もちろん、その女の子も一緒に来訪している。
隣に視線を向けると、僕と並んで庭を見つめる女の子の横顔があった。じっとしゃがんだまま息をひそめている。
そうだ、僕の記憶の片隅にある千里の姿だ。
庭の中央の石畳には、割り箸で立てたザルがあった。その下にはパンの切れ端が置かれていて、割り箸には凧糸が結びつけられている。凧糸はこちらに伸びて、僕の手元に繋がっていた。
スズメをつかまえるための自作の罠だ。千里は僕のほうを向いて問いかけてくる。
「ねぇ、こんなのでつかまえられるの?」
千里は電線の上で様子をうかがうスズメたちを指さす。目的の獲物に向けられた両眼は艶のある飴色で、このときの千里はまだ、光に満ちた世界に住んでいた。
「だってこの前ほんとうにつかまえたもん」
僕は自信満々に答えた。野鳥をつかまえたという自尊心と、かっこいいところを見せたいという虚栄心があったのだと思う。
「ほんとうに? すごいねー。今日はごはん、食べに来るかな?」
好奇心旺盛な千里は期待のまなざしを僕に向ける。
間近で顔を見合わせたとき、僕は千里の眼の違和感に気づいた。両側の瞳が日差しを受けてパール色に輝いていたのだ。
「あれ? 千里の目、光っているよ」
それは絵本で見た、妖精の瞳にも似ていた。物語の上では、人間に正しい未来を教えるための、特別な力を持った瞳。けれど、千里は瞳の色が変化しているという自覚がないようで、不思議そうにまぶたをぱちくりしている。
「真珠が入っているみたい。なんか可愛いしきれい……」
「えっ、恥ずかしいよぉ」
そう言いながら照れくさそうに伏せる千里の顔を無理やり起こし、まじまじと瞳の中をのぞき込む。目の中で光が跳ねて、まるで魔法を宿しているかのようだった。当時の僕にはそう見えたのだ。
「きっとこれ、神様がくれたんだよ。千里の宝物だね。いいなぁ、僕もこんな目がほしいなぁ」
千里は褒められたと思ったのか、照れて顔を紅潮させている。
「ええっ、どうなっているのかな。ちょっと見てくるね」
その後、千里は家に駆け込み、鏡に映る自分の目をのぞき込んでにんまりしていた。
鏡の中の誇らしげな千里が、僕の記憶にある千里の最後の姿だった。
我に返ったのは、電車が停車したのとほぼ同時だった。電車の窓に広がる景色は薄闇色の世界に置き換わっている。扉が開いて足元に冷ややかな空気が流れ込んできた。陽が沈んで急激に気温が下がったようだ。
寝過ごしてしまったらしく、電車は自宅のある駅のふたつ先に到着したところだった。発車メロディが流れたので、僕はカバンをつかみ、あわてて電車から飛びだした。
頭が冷気にあてられ、朦朧としていた思考がしだいにクリアになってゆく。ホーム上で足を止め、見た夢を思い返す。
――千里、幼い頃はちゃんと目が見えていたんだよなぁ。
今日という一日を振り返る。思い切って行動したことは、歌っていた女の子が千里だったという意外な驚きを僕にもたらした。
けれど千里の日常は僕の知る中学生のそれではなかった。千里が違う世界の住人のような気さえしていた。不自由の中で探す千里の未来は、僕の未来と交錯することはないのだろうと思えた。
ふと、千里の家のリビングで聞いたおばさんの言葉を思いだす。
――目がおかしかったことを隠していたみたいなの。
――ちゃんと見えるから大丈夫って言って、病院に行くのを嫌がっちゃってねぇ。
同時に、僕は疑問を抱きながらも、深く考えず素通りしてしまったことを自覚する。
それは、どうして千里の病気の発見が遅れたのか。どうして千里は病院に行くことを拒んだのか、ということだった。
突然、幼いころのおぼろげな記憶が今日の記憶と繋がりを持った。血の気が引き、全身に鳥肌が立つ。どっと嫌な汗が吹きだしてきた。
――まさか。
心臓の拍動が、捉えきれない速度で疾走し、喉の奥から飛びだしそうになる。
「うっ……」
五臓六腑を寄生虫に掻きむしられるようなおぞましい感覚に襲われる。その場にうずくまって身動きができなくなった。
「うえっぷ……ッ!」
突如、胃袋が締め上げられたように痙攣し、内容物が一気に込み上げてきた。
「おっ……おえええっ……!」
ご馳走になったロールケーキが無惨な液状になってホームの上にぶちまけられた。ひどいめまいを自覚して、僕はその上に倒れ込む。
深い闇の中に引きずり込まれるような、得体の知れない恐怖がのしかかる。
なぜなら、僕の記憶は、千里の目の治療が遅れた理由を明確に物語っていたからだ。
千里は僕が言ったことを真に受け、色の変わった瞳を神様の贈り物だと思い込んだに違いない。
それが致命的な病気だということは、幼い千里にわかるはずもない。もちろん、僕だってそうだ。
けれど。
たとえどんな理由があろうとも。
この僕が千里の光を奪ってしまったのだ!
――千里……僕は……僕は……ッ!
自分の頭をアスファルトのホームに打ち付ける。脳が、ずんと重く鈍い痛みを覚えた。うずくまって胸をかきむしりながら、何度も吐き戻す。それでも、いくらあがいても、この呵責は和らぐことはない。
――すまない……僕のせいで、きみは光を……ッ!
僕はこの瞬間、どんなに謝っても償うことのできない罪を自覚し、身を潰されるほどの重い十字架を背負うことになったのだ――。
帰りの電車で座席に腰をおろし、背もたれに身を預ける。向かい側の窓から差し込むオレンジの光が眩しくてまぶたを閉ざす。
電車に揺られていると、知らない街を訪れたことでの疲労と、ほんのりとした座席の暖かさが僕をまどろみの世界へ誘ってゆく。
ふと気づくと僕の意識は、夢と現実の狭間のような空間をふわふわと漂っていた。
昔の自分を思いだしているようで、おぼろげな記憶の中をさまよっている。千里に会ったことがきっかけとなったのか、当時の記憶の輪郭がしだいに明瞭になってゆく。
それはまだ僕が小学校低学年の頃だった。千里が登場する過去の中では、最も表層にあたる記憶だ。
庭の生垣に身を隠し、密集した葉の隙間から庭の様子をうかがう。背後の窓を挟んだリビングからは、世間話で盛り上がる女性陣の笑い声が聞こえてくる。ひとりは幼稚園で同じクラスだった女の子のお母さん。もちろん、その女の子も一緒に来訪している。
隣に視線を向けると、僕と並んで庭を見つめる女の子の横顔があった。じっとしゃがんだまま息をひそめている。
そうだ、僕の記憶の片隅にある千里の姿だ。
庭の中央の石畳には、割り箸で立てたザルがあった。その下にはパンの切れ端が置かれていて、割り箸には凧糸が結びつけられている。凧糸はこちらに伸びて、僕の手元に繋がっていた。
スズメをつかまえるための自作の罠だ。千里は僕のほうを向いて問いかけてくる。
「ねぇ、こんなのでつかまえられるの?」
千里は電線の上で様子をうかがうスズメたちを指さす。目的の獲物に向けられた両眼は艶のある飴色で、このときの千里はまだ、光に満ちた世界に住んでいた。
「だってこの前ほんとうにつかまえたもん」
僕は自信満々に答えた。野鳥をつかまえたという自尊心と、かっこいいところを見せたいという虚栄心があったのだと思う。
「ほんとうに? すごいねー。今日はごはん、食べに来るかな?」
好奇心旺盛な千里は期待のまなざしを僕に向ける。
間近で顔を見合わせたとき、僕は千里の眼の違和感に気づいた。両側の瞳が日差しを受けてパール色に輝いていたのだ。
「あれ? 千里の目、光っているよ」
それは絵本で見た、妖精の瞳にも似ていた。物語の上では、人間に正しい未来を教えるための、特別な力を持った瞳。けれど、千里は瞳の色が変化しているという自覚がないようで、不思議そうにまぶたをぱちくりしている。
「真珠が入っているみたい。なんか可愛いしきれい……」
「えっ、恥ずかしいよぉ」
そう言いながら照れくさそうに伏せる千里の顔を無理やり起こし、まじまじと瞳の中をのぞき込む。目の中で光が跳ねて、まるで魔法を宿しているかのようだった。当時の僕にはそう見えたのだ。
「きっとこれ、神様がくれたんだよ。千里の宝物だね。いいなぁ、僕もこんな目がほしいなぁ」
千里は褒められたと思ったのか、照れて顔を紅潮させている。
「ええっ、どうなっているのかな。ちょっと見てくるね」
その後、千里は家に駆け込み、鏡に映る自分の目をのぞき込んでにんまりしていた。
鏡の中の誇らしげな千里が、僕の記憶にある千里の最後の姿だった。
我に返ったのは、電車が停車したのとほぼ同時だった。電車の窓に広がる景色は薄闇色の世界に置き換わっている。扉が開いて足元に冷ややかな空気が流れ込んできた。陽が沈んで急激に気温が下がったようだ。
寝過ごしてしまったらしく、電車は自宅のある駅のふたつ先に到着したところだった。発車メロディが流れたので、僕はカバンをつかみ、あわてて電車から飛びだした。
頭が冷気にあてられ、朦朧としていた思考がしだいにクリアになってゆく。ホーム上で足を止め、見た夢を思い返す。
――千里、幼い頃はちゃんと目が見えていたんだよなぁ。
今日という一日を振り返る。思い切って行動したことは、歌っていた女の子が千里だったという意外な驚きを僕にもたらした。
けれど千里の日常は僕の知る中学生のそれではなかった。千里が違う世界の住人のような気さえしていた。不自由の中で探す千里の未来は、僕の未来と交錯することはないのだろうと思えた。
ふと、千里の家のリビングで聞いたおばさんの言葉を思いだす。
――目がおかしかったことを隠していたみたいなの。
――ちゃんと見えるから大丈夫って言って、病院に行くのを嫌がっちゃってねぇ。
同時に、僕は疑問を抱きながらも、深く考えず素通りしてしまったことを自覚する。
それは、どうして千里の病気の発見が遅れたのか。どうして千里は病院に行くことを拒んだのか、ということだった。
突然、幼いころのおぼろげな記憶が今日の記憶と繋がりを持った。血の気が引き、全身に鳥肌が立つ。どっと嫌な汗が吹きだしてきた。
――まさか。
心臓の拍動が、捉えきれない速度で疾走し、喉の奥から飛びだしそうになる。
「うっ……」
五臓六腑を寄生虫に掻きむしられるようなおぞましい感覚に襲われる。その場にうずくまって身動きができなくなった。
「うえっぷ……ッ!」
突如、胃袋が締め上げられたように痙攣し、内容物が一気に込み上げてきた。
「おっ……おえええっ……!」
ご馳走になったロールケーキが無惨な液状になってホームの上にぶちまけられた。ひどいめまいを自覚して、僕はその上に倒れ込む。
深い闇の中に引きずり込まれるような、得体の知れない恐怖がのしかかる。
なぜなら、僕の記憶は、千里の目の治療が遅れた理由を明確に物語っていたからだ。
千里は僕が言ったことを真に受け、色の変わった瞳を神様の贈り物だと思い込んだに違いない。
それが致命的な病気だということは、幼い千里にわかるはずもない。もちろん、僕だってそうだ。
けれど。
たとえどんな理由があろうとも。
この僕が千里の光を奪ってしまったのだ!
――千里……僕は……僕は……ッ!
自分の頭をアスファルトのホームに打ち付ける。脳が、ずんと重く鈍い痛みを覚えた。うずくまって胸をかきむしりながら、何度も吐き戻す。それでも、いくらあがいても、この呵責は和らぐことはない。
――すまない……僕のせいで、きみは光を……ッ!
僕はこの瞬間、どんなに謝っても償うことのできない罪を自覚し、身を潰されるほどの重い十字架を背負うことになったのだ――。