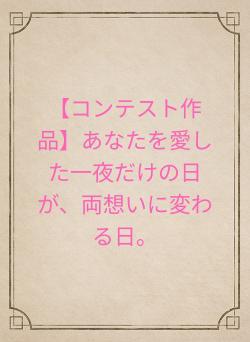その日私は家に帰ってから、ずっと萌恵の言葉が頭に残っていた。
【んー、友達だったらなおさらないね】
最近桜木と一緒にいすぎて、よくわからなくなってる。私は桜木と一緒にいるのが当たり前になってるんだな、きっと。
でも桜木が私を助けてくれたあの日、泣いている私をギュッと抱きしめてくれたあの温もりに、私は心地良さと温かさを感じていた。
「……そっか」
あの心地良さと温かさは、桜木だから感じるものなのかもしれないんだ。
だって他の男子には感じたことはない。 頭をポンポンと撫でられた時も、私はそんなこと感じたことなかった。
「でも……好きだって言われてないし」
桜木と一緒にいる時間が多すぎて、単純に麻痺してるだけのような気がする。
✱ ✱ ✱
「おはよう、萌恵」
「真琴、おはよう」
次の日から私は、変に桜木を意識するようになってしまい、桜木と目を合わせることがなぜか出来なくなった。
「あ、おはよう桜木くん」
「お、おはよう」
「……おっ、おは、よう」
「おはよう、真琴」
桜木と目が合いビックリした私は、逃げるように自分の席に着いた。
「……はあ」
桜木と目を合うだけで、驚くなんて……。こんなんじゃ情けない。
でもどうしたらいいのか、わからない。
「真琴、大丈夫?」
萌恵にそう聞かれるけど「大丈夫」と唱えるように呟いた。
「そうそう。今日の体育、バドミントンだって」
「え、バドミントン? いいじゃん」
そんな会話をしていると、「おい、真琴」と桜木が近寄ってくる。