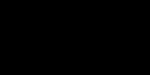─────
──────────
───────────────---
------──────────────────────────────
**
──ハァ。
耳を舌で撫ぜられるような気色悪さに頭を振った。
いくら年月が経とうとも慣れない。気持ち悪い。気色悪い。生理的な嫌悪。痴漢に遭っているような。知っている言葉を並べたててみる。すべてがその通りのような微妙に違うような。うまく説明ができない。これまで経験したどの感覚にも似ているようで、どれも違う。
これにつきまとわれるようになったのは、いつからだろう。
ほんの出来心だった。
学生時代、あたしを名指しして裏掲示板に悪口を書き込んでいた同級生。
友達だと思ってたのに気持ち悪い、裏切られたと騒ぎたてられちょっとした騒ぎになった。
親にはただこじれた喧嘩だと言ってある。あの時本当の事を伝えていたらきっと卒倒しただろう。
その同級生についての噂話を流していったのが最初だったように思う。事実を絶妙に混ぜ込んで盛って、ネット上の各掲示板やツイッターに流した。「少しの事実」が現実味を帯びて、彼女はその後引きこもりになったと風の噂で聞いた時は因果応報だと笑った。
あの頃から少しずつ聞こえはじめたあれは、年月を重ねるうちに存在を大きくしていった。
だけど、あたしは知っている。
慣れることはないけどどうにでもなる。
最初の数年こそ恐怖で慄いたけど、今はもういい。
空間の隅で蠢く黒い淀み。突然襲われる怪異。慣れてしまえばどうってことはない。あれは本来みんなが持っているものだ。何かの拍子に具現化したものだと思っているし、飼い慣らせばこちらのものなのに。
「あたしと同類かなって思ってたんだけど……けっこう可愛いらしいんだねえ、芳野さんは」
くすくす笑いながら歩いていると、すれ違った看護師が怪訝そうに首を傾げた。会釈をして歩みを進める。
あの危うい年上の女性は、いつかああなると思っていた。
櫻木の話を振ると、いつだって目に蔭が過ったからだ。その場からあの男が立ち去ると、まるで母親に置き去りにされた子供のような視線を向けていたのが印象的だった。
櫻木との会話から察するに、櫻木の元恋人にもあれは現れたんだろう。
要因である櫻木の身に何もないというのは不条理だとは思うけど、あんなにずる賢く逃げることに慣れた男なら無理もない。鈍感な人間ほど掴まらないものだから。
「……なんでみんな気づかないのかな」
ため息も、目玉も、黒い淀みも──全部全部、自分なんだってことにさ。
清廉潔白な人間なんていないし、みんなみんな内に何かを抱えている。ふとした瞬間に足を踏み入れたり、もしくは踏み外したり。真っ黒な自分を抱えているはずだ。
それらを認めることが出来たら──飼い慣らすことができたら、恐怖心なんて忘れてしまえるのに。
飼い慣らせるのと「慣れる」ことは別物だけどね。
「さあて。どうなるかな」
病院の長い廊下を歩きながら、あたしはスマホをタップして櫻木の名前を選んだ。