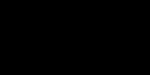「椎菜、落ち着け」
隆介の声が遠い。
「紗和さんのこと、まだそんなに好きなの」
思わず口にした名前に、隆介の顔色が変わるのがわかった。
「なんで紗和の名前を知ってる」
会って話したからだよ、と歪んだ笑みが浮かんだ。
この人は何も知らない。私が何をしてきたのかも、紗和が何をしていたのかも。
「私の名前を教えたんだってね。まあ普段ほとんど名乗らない名前だから助かったけど。紗和さん、私は『よしの』って名前だと思ってたよ。古風で素敵なお名前ですねって言われた」
くすくす笑いながら教えてあげる。隆介の顔が引き攣った。
あの喫茶店で初めて顔を合わせ、名刺を交換した時。
フリーランスになった時『芳野 椎菜』と『よしの』の二種類の名刺から後者を差し出した自分を心底褒めた。仕事の相手でもない紗和に、『よしの』を出して正解だったと。
まさか原因となった私の名前を教えてただなんて、どこまで愚鈍なんだろう。
まあ、結果的にはうまくいったからいいけど。
頭文字のSを片仮名にしたエスというアカウント名は、紗和のSだと思っていたから、まさか隆介に教えられた『椎菜』のSなんて思いもしなかったけど。
「あーでも、もしかしたら耳で聞いた『しいな』を苗字だと思ってたのかな。まぁどっちでもいいよ、私だってバレなきゃそれでよかったんだから」
勝手に身体が揺れている。
頭が痛い。だけど口は止まらなかった。
隆介は私を凝視したまま動かない。動けないのだろう。
おかしくなったと思われたのかもしれない。どっちでもいい。どうでもいい。きっとどちらでもある。
紗和のことは、一方的に知っていた。
尊敬する上司の恋人。櫻木さんと呼んでいた頃の隆介は──今も変わらないが、仕事中には決して私情を交えない。
スマートフォンも仕事用と私用で分けている。私用を手にしている姿はたった一度しか見たことがない。
そのたった一度が、遠くから紗和を見たあの日だった。
打ち合わせが終わって作家が帰り、二人きりになった喫茶店。
恋人がいるらしいことは、他の社員や打ち合わせ相手たちから耳にしたことがあった。
仕事にプライベートを持ち込まないことを徹底しているらしく、本当かと疑わしい日々を送っていた。
そんなことを疑い始めたのは他でもない、隆介を好きになっていたからだ。見せてくださいよ、なんて軽口を叩くと「私生活の話をするつもりはない」とハッキリ断られていた。取りつく島もなかった。
こんな人の恋人はさぞ我慢して我慢して、いつか爆発して隆介は捨てられるだろうと思っていた。
でも、違った。
あの日、隆介が珍しく焦ったように私用のスマートフォンに触れた。
すまん待っててくれと私に告げて、店を出て行った。
絶対についてくるような真似をするなよと釘を刺された。私の気持ちに気づいていたのもあるだろうが、他の編集者たちも同じような対応をされていたらしいから本当にプライベートを見せたくない人なのだろう。
でも、こっそり見に行った。運よく気づかれることはなかったが、恋人の顔を見ることは出来なかった。こちら側に背を向けていたからだ。細く長い髪がさらさらと揺れていたのだけが印象的で、そんな彼女に向き合う隆介の表情があまりに優しくて驚いた。
そこからこっそり調べた。止まらなかった。
それとなく色んな人から情報を集めて集めて、どうにか自動車販売の営業をしているところまで辿り着いた。
ホームページで顔を見た。綺麗な人だと思った。
隆介と渡り合えそうな大人な人だとも思った。
だから私は正反対を演じた。
冷たいように見えて一度情を交わした相手を見捨てられない、面倒見のいい隆介の隙をついた。
彼は馬鹿みたいに紗和に浮気を白状したらしいけど、浮気らしい浮気なんて本当はしていない。
付き合ってもいなかった。
だから紗和の話を聞いた時、心底驚いた。
きっとあれは紗和を想って、自分に愛想をつかせるためについた嘘だと私は思っている。
だって、無理やり酔いつぶした隆介を私が襲っただけのことだ。
普段、女性が同席する飲みで隆介が酔うなんてこと絶対にない。警戒心が強いから。
でも私はそれまでに作り上げた「放っておけない後輩像」をいいことに、彼が席を外すたびに強い酒を継ぎ足した。こっそり薬も盛った。
あの頃はどうかしていた。
ほんの出来心だったんです。
紗和を思い出す。私だって、最初はほんの出来心だった。
結果、隆介と一夜を共にすることに成功した。ただ、同時に思い知った。
相手の意識もおぼろで、感情の伴わないセックスなんてただの作業に過ぎない。虚しさしか残らない。
この日のために伸ばした髪のせいか、隆介は最中に何度か紗和の名を呼んでいた。虚しさしかなかった。それでも朝になって驚愕した隆介の顔を見た時、恥ずかしげに視線を落としながら喜びを伝えた。
馬鹿みたいに堅物で真面目な隆介は、紗和に別れを告げることになる。
私に対する振る舞いも、私が自分に冷めてほしいという全てからきている態度だと、本当はわかっていた。
今夜の事は自分の責任だけれど、付き合うことは出来ないとあの朝に宣言されたから。
それでもいいからと、名ばかりの恋人の座を欲しがったのは私だ。だからどんな扱いをされても別れるつもりはなかった。
ひどい扱いをして、私から別れを切り出すのを待っていることを知っていたから。
だからどれだけ不満が募っても、私が彼に言えることは何もない。
その頃から、あれの気配に悩まされるようになった。
ただ、遠かった。
時々揺らぐ息だけ。
だから、気のせいだと思い込んでいた。