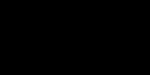横を通り過ぎた車のライトが反射し、銀色の細い糸がいくつもおりていることに気付いた。
雨だ。あまりに細く、音のない雨でわからなかった。傘は持っていないからそのまま歩く。髪がしっとりするくらいだろうと頭の隅で笑った。
あれからすぐに個室に入ると、受付の男性が言っていた通りパソコンにはメール画面が表示されていた。
画面いっぱいに文字化けして打ち込まれていた文字は何ひとつなく、シャットダウンをしようとしていたのに壁紙でもなく、メール画面だった。開いていた記憶は全くない。
またおかしなことが書かれたメール──それこそ宛先人不明のようなものが届いているのではと身構えたが、何のことはない。担当作家からの返信だった。
私は何を見たのだろう。疲れが見せた幻覚?
とぼとぼと重い足取りで今、隆介のマンションに向かっていた。
他に行くあてがなかった。自宅が怖い。ネカフェも怖い。ホテルだって同じだろう。ひとりで過ごす限り、あれからは逃げられない。
隆介には連絡しておいた。これから行くと。色々あって泊めてほしいと。
ネカフェですぐに打ち込んだが、さっき確認したら未読のままだった。いつものことだ。それでも「連絡した」という証明にはなる。何も言わずに行くよりも断然マシだろう。
何度想像しても、ドアを開けて私の姿を捉えた彼は微笑んではくれない。
でも、拒むこともしない。そういう人だ。
もしも家に居なかったら、合い鍵で入る。それでいい。取材で帰ってこなかったら結局ひとりだと一瞬過ぎったが、まさか隆介の家で何か起こることはないだろう。
不特定多数の人間がいる空間では起きた。外でも起きた。でも、全くの他人が所有する個室ではどうなるのか──今は、現れないという考えで進むしかない。
何より、隆介がそういったものを全く信じていないのだ。
信じない相手にはないものと同じだから作用しないと、どこかで聞いたことがある。
一パーセントでも可能性があるのなら、私はそれに賭ける。
雨に音がついてきた。粒が大きくなり、髪や肩から濡れていく。隆介の家までもう少し。顔を上げて、目的のマンションを見た。高層であることにプラスして、窓が多すぎてどの部屋かはわからない。それでも、明かりが灯っていることを祈った。
隆介はいなかった。
オートロックを開けてもらうため、何度目かインターフォンを押したところで諦めて留守を認めた。
番号を入力してからロビーに入り、エレベーターで十二階にある隆介の部屋へ向かう。中でスマホを開き、『留守みたいだから入らせてもらうね』と送っておいた。その前に送ったメッセージも未読であることにため息を吐くと、ちょうど目的階に到着する。
静かな共有廊下を歩いていると、ヒールの中がぐしゅりぐしゅりと音を漏らした。
やまない雨にすっかり濡れていることはわかっていた。足元を見遣って、振り返る。足跡が見事に水跡となっている。やっぱり風呂も借りなくては風邪をひくだろう。
部屋の前に辿り着くと、隆介とお揃いのキーホルダーを付けた鍵を取り出して解錠した。
ドアを開ける。当然のことながら、中は真っ暗だ。心臓がきゅっとしたものの、自分の部屋に帰ったときほどの緊張感や恐怖がない。たぶん、隆介のにおいがしたからだ。彼の匂いがしただけで、こんなにも安心するとは思わなかった。
それでも内側に腕だけ侵入し、先に電気を点ける。
室内が明かりに満たされたのを確認してから玄関に入って施錠する。
濡れたヒールを隅に並べて中にあがった。私の足のかたちがそのまま水跡となっているのを理解し、あとで拭かなければと思う。
広いLDKに入ると、隆介のにおいで満ちていた。
ここは安心できる。大丈夫。
少なくとも私の感情が恐怖で埋め尽くされることがない。あれはそういう隙をも狙っているから。
緊張が解けたのか、ふと全身の冷えを感じた。さすがに降られすぎたらしい。
これだけ濡れてしまっているとソファにも座れない。仕方なしと浴室へ向かって風呂を沸かすスイッチを押した。
着ている服を脱いで洗濯機に放り込む。下着までぐっしょりだ。すべてを脱ぐと、隆介の部屋着が置いてある作り付けの棚を引き出す。適当に借りておこう。風呂が沸くまでこの姿では風邪をひいてしまう。下着は──まぁいいだろう。風呂に入って全身を温めたあと、コンビニにでも行って買ってこればいい。
全身隆介のにおいに包まれてリビングに戻る。ひとりなのに、何も怖くない。
隆介の部屋だというだけで、こんなにも恐怖をどこかへ置いてこれるなんて思わなかった。さすがにもう少し色々と警戒する自分を想像していた。
モスグリーンの、大きなソファに腰を沈める。
革張りのこれは、私が隆介の部屋で一番気に入っているものだ。買ってまだ半年。ちょうど私と付き合い始めたころに新調したと言っていた。膝を抱えてころんと転がってみると、新しい家具のにおいがする。
まだ隆介のにおいが染みこんでいない。煙草を吸わなくなったからだろう。
私があまり煙草の匂いが得意ではないと伝えたのは、まだこうなる前だった。
今思えば、あれは隆介なりの意志表示だったのかもしれない。
この先一緒にいたいと思ってくれていたから、煙草をやめたのだ。そのはずだ。