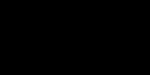「マジで来るとはね」
ストローでレモンスカッシュを飲み込んだ後、ユキナは苦笑した。
彼女との打ち合わせはいつも同じ喫茶店だ。流行りのカフェとは違う、老紳士が営む昔ながらの喫茶店。
レトロというわけではなく、本当にただ古いだけの店。隆介が担当していた頃からここなので、理由は知らない。
私は汗を拭きながらユキナの向かいに座ると、カウンター奥にいる老紳士に「アイスコーヒーを」と注文した。息を落ち着かせるため胸元に左手をやりながら、右手で鞄を漁る。
「行きますって言いましたよ」
「そうですけどぉ。本当に大丈夫なの?」
大丈夫です、と力強く返し、鞄から原稿を取り出した。
今日の打ち合わせは、方向性の確定。
新人作家の挿絵とカバー絵をユキナに担当してもらうことは決まっていた。
まずはその作家の文章のクセや雰囲気を知りたいから、前作の原稿を読ませてということだった。すでに本になっているものを読むと、カバー絵や挿絵の存在が逆に邪魔になるそうだ。
こういった内容ならば、データで送るだけで充分な挿絵作家やイラストレーターは少なくない。だが、ユキナは必ずこうして直接会っての打ち合わせを好んだ。
紙の原稿を読みたいと言う。そうしないと、自分が担当した時にイメージが全く湧かないそうだ。
私にはわからないが、彼女の仕事はいつも評判がいい。ならば希望通りに動くのが編集の仕事だ。
「その新人作家さんが来れないのは、あたしとしては微妙なんですけどね」
原稿を受け取ったユキナは、微かに眉を顰めながら呟く。口元はまだ緩んでいるから、本気で機嫌を損ねているわけではない。
ただ来れないという事実を口にしているだけ。彼女が不機嫌になったら、こんなものではない。
それでも一応、私からの謝罪はしておく。当然その新人作家も担当しているからだ。
「すみません。試験が近くて難しいと」
「あー。現役大学生だっけ?」
「ええ。勉強に悪影響があれば、すぐにでも小説はやめなさいと親御さんから言われているそうで」
ああそうだったね、とユキナはため息を吐いた。
私の頼んだアイスコーヒーがテーブルに置かれる。老紳士に会釈をして喉を潤すと、彼女はそれを確認してから話を続ける。
「親の気持ちもわからなくもないけどね。作家とかって不安定な職業だから。あたしにも未だにうるさいですもん、親の小言」
「また電話来たんですか?」
「うん。芳野さんには何回か話したよね。健康面の心配はありがたく受け取るけど、その次には今付き合ってる人はいるの、絵を描いてなんて一人で食べていけないよ、いい加減いい男見つけろ。そんで嫁に行きなさい。そんなんばっかですよ」
ユキナは饒舌だ。しかし、文字を追う目は真剣そのもので、私はいつも彼女の集中力には驚かされている。
こんな風に話しながらなのに、内容の確認に漏れを生じたことはこれまでただ一度もない。
次々と紙をめくりながら、それでね、と続ける。
「もし彼氏がいたとしてもさ、あたしの仕事が不安定だからって理由で嫁に貰ってくれって、どう考えても頭おかしいですよね。そこらへんわかってないのが問題」
そしてあっと言う間に確認は終わる。はい、と私に返してきた。
「新人作家のクセはわかった。ありがと。萌えも必要かもしれないけど、そこまで振り切らなくてもよさそうですね」
ずずーっとレモンスカッシュを吸い込む。この早さも彼女の特徴だ。
「芳野さんは親から何か言われる?」
「え」
「会社やめて、フリーの編集になったじゃないですか」
「あー……実は親には言ってなくて」
「マジ!?」
「仕事内容は変わらないし、まぁ言わなくてもいいかって……」
「その手があったか! へえ、芳野さんってキッチリ親に報告タイプだと思ってましたよ」
「いやぁ……隆介さんとのことでもうるさいので、それ以上面倒な事になるのは……」
つい正直に答えてしまった私を、ユキナはあぁそうかもね、と軽く流す。
「……ま、結婚だのなんだの、あたしの場合はそれ以前の問題ですけどね」
「問題っていう表現は違うんじゃないんですか」
ユキナの声に被せるように、つい声が出てしまった。
ユキナは少し驚いたように目を見開くと、肩を竦めてふふっと笑う。
「芳野さんは優しいから、そんな風に言ってくれるだけだよ」
「違います」
「ま、一生親には言うつもりないですけどね。これ以上親に精神的負担与えるわけにはいかないっしょ」
何てことのないようにユキナは笑う。
やるせない気持ちになってしまったのが伝わったのだろう、「やだなぁ」と明るく肩を叩かれた。
「てかさ。それより何があったの? 倒れてたって」
「えっ」
「だって普通じゃないよ。気づいたら倒れてるとか。芳野さん貧血持ちでしたっけ?」
「え、いえ、違いますけど……」
「本当に病院行かなくてよかったの?」
純粋に心配の言葉をかけてくれるユキナの声が、自分の心臓の音でかき消されそうになっていく。
目の前にいるのはユキナなのに、部屋に戻される気がした。
ここは喫茶店で、今は打ち合わせ中で、ノートパソコンは持ってこなかった。
あのため息だって、聞こえてこない。
「芳野さん? ちょっと、どうしたの。すごい汗」
息が荒くなっているのは自覚していた。
俯いてしまった私の顔を、ユキナが心配そうにのぞきこんでくる。視界の端で、老紳士がこちらの様子を窺っているのもわかった。
大丈夫です、とようやく顔を上げたところで、ヒッと喉の奥が引き攣る。
ユキナの顔が、真っ黒だった。