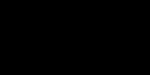ほんの出来心だったんです、と彼女は薄い唇を開いた。
意外なほどか弱い声に、私は思わず息を飲む。
ショートカットに切り揃えられたダークブラウンの髪と、切れ長の瞳。長い脚を包むパンツスーツは彼女によく似合っており、車の営業職をしているという前情報通り快活な印象を抱いていたのに。
「……まさか自分があんなことできるなんて」
続けてため息のようにこぼれ落ちた彼女の声が聞き取り辛く、私は身を乗り出した。
高い天井の中央にシャンデリアがさがり、オレンジや白の灯りが店内を華やかに照らしている。女性に人気でランチ時には必ず並ぶという喫茶店は、なるほど周囲を見回しても見事なほどに女性ばかりだ。
弾むような声が周囲から聞こえてくる中、この場に、そして自身の顔立ちに不似合いなほど表情をなくした彼女──多々野紗和は、言葉を続けた。
「きっかけは、彼氏に浮気されたことでした」
何が悪かったのかわかりません。
あえて言うなら、私は可愛げのない恋人だったということです。
当時の私は就職して五年を過ぎ、男性ばかりの営業の中で必死でした。同期の女の子は三年も経たずに次々辞めていて、残っていたのはフロア担当の後輩の女の子が二人。
営業の後輩が出来てもどんどん辞めちゃうんです。そりゃそうですよね。車社会の地域ならともかく、私が担当していたのはそこまで車が重要視されてないところだったんですよ。
そこのお年寄りたちは矍鑠としていて、電車や地下鉄を使います。体調が悪ければタクシーです。自家用車なんてお金持ちの道楽か、ただ車好きかって感じのお客様が圧倒的でした。
でもそんな中、一位二位を争うくらいには売ってました。報奨金が上乗せされるのが嬉しかったし、単純に結果が出ることが喜びだったんです。わかりやすくていいじゃないですか。
辛いこともたくさんありましたよ。売れない月はどん底でした。
彼氏に「無理するなよ」「転職したら」って言われたことも数回じゃないです。週一の休みもお客様から故障だの車が動かないだの呼び出されることが多かったので、そんな私を見ていて思うところがあったんでしょうね。
でもそのたびに、「大丈夫」って答えてました。どんなに大丈夫じゃなくても。
彼も忙しいのを知っていたから、そんなこと言われても困るだろうなと思っていたんです。だから一言も、辛いとか大変とか、言った事ありませんでした。
そこまで一気に話した紗和の細くて長い指が、紅茶の入ったカップに添えられる。
あまりに青白い顔色に「無理はしないでください」と声をかけると、紗和は静かに首を振って力なく微笑んだ。大丈夫です、と。
──クセなんですよ。
だって、違いますか? 大丈夫? と聞かれたら「大丈夫」と答えることしか出来ないんです。少なくとも私はそうです。今もそうだったでしょう? まぁ、今は本当に大丈夫なんですけど。……あのあとに起きたことに比べたら全然辛くない。
どこまで話しましたっけ?
ああそうだ、彼にとって可愛げのない恋人だったという話です。彼――櫻木にとっては、私は最後まで我儘な女だったんでしょうね。我儘を一切言わないという我儘な女。
大学時代から付き合っていたから……六年ですね。六年を過ぎた頃にフラれました。「紗和は俺がいなくても生きていけるよな」って。言わなきゃいいのに、馬鹿正直というか何というか……もう会社の部下の女性と付き合ってるって。本当に馬鹿ですよね。
浮気。二股。まぁとにかくそれをされて怒るなという方が無理です。それとこれとは話が別だって彼を責めて罵ろうと思って――出来ませんでした。そうなんだ、とだけ言って別れました。
「どうしてですか」
思わず口をついて出ていた。
紗和にはその権利がある。いくら別れという結論が出ていても、まだその瞬間までは二人の関係性は恋人だった。一方的に冷めてたとはいえ、櫻木が他の女性とお付き合いを始めていい理由にはならない。
紗和の青白い顔にほんのりと赤みがさした。見ると、運ばれてきたドルチェを味わっている。何かを食べて美味しいと思えるのなら大丈夫だ。身に覚えがある。しかし──
「それで、あの……」
私が聞きたいのはその先だ。
ほんの出来心だったと紗和は言った。今聞いた話は、そのきっかけに過ぎない。
紗和は上品にドルチェを食べてしまうと、気づかわしげに頷いた。
「そうでしたね。ごめんなさい」
首を振った私に、視線を合わさずに紗和は言う。
「あなたには時間がないのでしょう」
瞬間、後ろから視線を感じた。
ソファ席に向き合って座っているのだから、背後には誰もいない。そのはずだ。
気のせいだと言い聞かせてきたその気配から逃れるために、私と同じような経験をした人をツテを辿りまくって探しあて、こうして話を聞くことができたというのに。
ただひとつだけ違うこと。
紗和は逃れることが出来た。私はまだ、出来ていない。
「……続きを、お願いします」
おそらく私の顔色は、先程までの紗和のように青白いだろう。
意外なほどか弱い声に、私は思わず息を飲む。
ショートカットに切り揃えられたダークブラウンの髪と、切れ長の瞳。長い脚を包むパンツスーツは彼女によく似合っており、車の営業職をしているという前情報通り快活な印象を抱いていたのに。
「……まさか自分があんなことできるなんて」
続けてため息のようにこぼれ落ちた彼女の声が聞き取り辛く、私は身を乗り出した。
高い天井の中央にシャンデリアがさがり、オレンジや白の灯りが店内を華やかに照らしている。女性に人気でランチ時には必ず並ぶという喫茶店は、なるほど周囲を見回しても見事なほどに女性ばかりだ。
弾むような声が周囲から聞こえてくる中、この場に、そして自身の顔立ちに不似合いなほど表情をなくした彼女──多々野紗和は、言葉を続けた。
「きっかけは、彼氏に浮気されたことでした」
何が悪かったのかわかりません。
あえて言うなら、私は可愛げのない恋人だったということです。
当時の私は就職して五年を過ぎ、男性ばかりの営業の中で必死でした。同期の女の子は三年も経たずに次々辞めていて、残っていたのはフロア担当の後輩の女の子が二人。
営業の後輩が出来てもどんどん辞めちゃうんです。そりゃそうですよね。車社会の地域ならともかく、私が担当していたのはそこまで車が重要視されてないところだったんですよ。
そこのお年寄りたちは矍鑠としていて、電車や地下鉄を使います。体調が悪ければタクシーです。自家用車なんてお金持ちの道楽か、ただ車好きかって感じのお客様が圧倒的でした。
でもそんな中、一位二位を争うくらいには売ってました。報奨金が上乗せされるのが嬉しかったし、単純に結果が出ることが喜びだったんです。わかりやすくていいじゃないですか。
辛いこともたくさんありましたよ。売れない月はどん底でした。
彼氏に「無理するなよ」「転職したら」って言われたことも数回じゃないです。週一の休みもお客様から故障だの車が動かないだの呼び出されることが多かったので、そんな私を見ていて思うところがあったんでしょうね。
でもそのたびに、「大丈夫」って答えてました。どんなに大丈夫じゃなくても。
彼も忙しいのを知っていたから、そんなこと言われても困るだろうなと思っていたんです。だから一言も、辛いとか大変とか、言った事ありませんでした。
そこまで一気に話した紗和の細くて長い指が、紅茶の入ったカップに添えられる。
あまりに青白い顔色に「無理はしないでください」と声をかけると、紗和は静かに首を振って力なく微笑んだ。大丈夫です、と。
──クセなんですよ。
だって、違いますか? 大丈夫? と聞かれたら「大丈夫」と答えることしか出来ないんです。少なくとも私はそうです。今もそうだったでしょう? まぁ、今は本当に大丈夫なんですけど。……あのあとに起きたことに比べたら全然辛くない。
どこまで話しましたっけ?
ああそうだ、彼にとって可愛げのない恋人だったという話です。彼――櫻木にとっては、私は最後まで我儘な女だったんでしょうね。我儘を一切言わないという我儘な女。
大学時代から付き合っていたから……六年ですね。六年を過ぎた頃にフラれました。「紗和は俺がいなくても生きていけるよな」って。言わなきゃいいのに、馬鹿正直というか何というか……もう会社の部下の女性と付き合ってるって。本当に馬鹿ですよね。
浮気。二股。まぁとにかくそれをされて怒るなという方が無理です。それとこれとは話が別だって彼を責めて罵ろうと思って――出来ませんでした。そうなんだ、とだけ言って別れました。
「どうしてですか」
思わず口をついて出ていた。
紗和にはその権利がある。いくら別れという結論が出ていても、まだその瞬間までは二人の関係性は恋人だった。一方的に冷めてたとはいえ、櫻木が他の女性とお付き合いを始めていい理由にはならない。
紗和の青白い顔にほんのりと赤みがさした。見ると、運ばれてきたドルチェを味わっている。何かを食べて美味しいと思えるのなら大丈夫だ。身に覚えがある。しかし──
「それで、あの……」
私が聞きたいのはその先だ。
ほんの出来心だったと紗和は言った。今聞いた話は、そのきっかけに過ぎない。
紗和は上品にドルチェを食べてしまうと、気づかわしげに頷いた。
「そうでしたね。ごめんなさい」
首を振った私に、視線を合わさずに紗和は言う。
「あなたには時間がないのでしょう」
瞬間、後ろから視線を感じた。
ソファ席に向き合って座っているのだから、背後には誰もいない。そのはずだ。
気のせいだと言い聞かせてきたその気配から逃れるために、私と同じような経験をした人をツテを辿りまくって探しあて、こうして話を聞くことができたというのに。
ただひとつだけ違うこと。
紗和は逃れることが出来た。私はまだ、出来ていない。
「……続きを、お願いします」
おそらく私の顔色は、先程までの紗和のように青白いだろう。