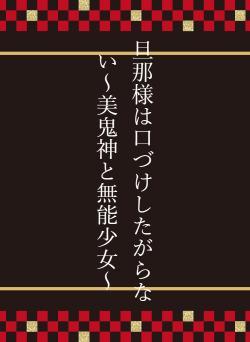そんじゃ、行ってくるわ、と誰に告げるわけでもなくボソリ呟くと、悠太は底のすり減った白いスニーカーに足を押し入れ、玄関のドアを開けた。
その瞬間、居間からオギャーッという耳をつんざくような泣き声が聞こえてきて、悠太はまるで耳を塞ぐかのように慌ててドアをバタンと閉める。
まだ午前八時半だというのに容赦なく照りつけてくる太陽と、ミーンミーンと鳴り響く蝉の声に急き立てられるように、悠太は足早に塾へと向かう。
「……ったく、朝からギャーギャー、マジで勘弁してほしいよ」
真夏の陽光を受け、水面をきらきらと輝かせている多摩川を横目に、悠太はひとりごちる。
母、美幸は三ヶ月ほど前、41歳で愛花を出産した。聞けば、かなりの難産だったという。
「……もういい歳なのに、無茶をして……」
悠太は美幸と、美幸の新しい夫・高志の顔を思い浮かべると、地面に転がっていた大きめの石を誰もいない河川敷に向かって思い切り蹴りつけた。
***
実の父親が不倫相手を身ごもらせて家を出て行ったのは、悠太が五歳のときだった。それ以来、悠太は父親の顔を見ていない。
離婚後、美幸は中規模の精密機器製造会社に経理担当として就職した。高校で簿記の資格を取っておいてよかった、と美幸は事あるごとに口にしていた。その会社で美幸が出逢ったのが、中途採用で入社してきた理系出身の営業担当、中崎高志だった。
高志は男から見てもハッとするようなイケメンで、なぜバツイチ子持ちなうえ九歳も年上の美幸を伴侶に選んだのか、悠太は今でも不思議でならない。
美幸と高志は二年ほど交際を続け、悠太が高校に入学する直前の三月に籍を入れた。悠太が入学と同時に新しい姓を名乗ることができるようにと考えてのことだったらしい。
入籍と同時に、高志は美幸と悠太の住む小さなアパートに越してきた。約十年続いてきた母との二人暮らしは突然終わりを告げ、母は父親と呼ぶには若すぎるイケメンと同じ部屋で眠るようになった。薄い壁越しになにか物音がする度に、思春期真っ只中の少年はビクッとし、熟睡できない夜が続いたのだった。
三人暮らしが始まってほどなくして、悠太は美幸から『来年妹が産まれる』と聞かされた。家族が増えることがわかり、高志と美幸は『もっと広い部屋を探さないと』と不動産屋巡りを始めた。
そうして悠太が高一の冬に、現在住んでいる多摩川沿いの茶色い壁のマンションに越してきたのだった。
高志の会社――むろん、育児休業中の美幸が勤める会社でもあるのだが――では、社会を混乱の渦に陥れた疫病が契機となり、在宅ワークが導入された。騒動が落ち着いた後も、引き続き在宅ワークが認められているという。高志は在宅ワークを上手く利用し、妻子と接する時間を積極的に設けていた。
高志は優しく温厚な人物で、悠太も決して彼のことが嫌いなわけではない。美幸が彼に惹かれた気持ちもわかる気がしていた。
だが――父親としてすんなり受け入れられるかというと、それは別問題なのだった。
一学期の終業式を翌日に控えた高校二年生――ここでは悠太の通う『中の中ランクの公立高校』に限定しておこう――の休み時間の話題といえば、『夏休み、何する?』に尽きる。日々の義務から解放される喜びのエネルギーが教室中に充満しているのを悠太は感じていた。
「中崎は夏休み、どうするの? 旅行とか行くのか」
前の席の中井が振り返り、尋ねてきた。特に親しいわけではないのだが、ワイワイやっている他の生徒たちに感化されたのかもしれない。
「――特に何も。家で寝っ転がって一日中ゲームするか漫画読むかくらいかな」
『旅行なんて、乳飲み子を抱えて行けるはずもないし』という言葉は飲み込み、悠太は相手が一番喜びそうなセリフを口から吐き出した。母親が若いイケメンの子を高齢出産したことを世間に吹聴する必要はないだろう。
案の定、中井はウンウンと頷きながらこう返してきた。
「だよなー。外に出てもクソ暑いし、やっぱクーラーをガンガンに効かせて一日中ゲームに限るよな。でも新しいソフト買おうにも金ないしなー。 まったく、なんでバイト禁止されてるんだろうな」
中井は普段よりもかなり饒舌だ。これも『明日が終業式』という解放感がなせる技なのかもしれない。
正直なところ、悠太はゲームというものにほとんど興味がない。だが、級友との当たり障りのない会話を続けるのに必要不可欠なため、小遣いを貯めてゲーム機を買い、話題になっているソフトには一応手を付けるようにしていた。
「俺らみたいな帰宅部は、マジですることないよなー。あー、彼女でもいればなぁ……。とはいっても、金ないから彼女がいてもファミレスでダベるくらいしかできないけど。――って、中崎って彼女いたっけ?」
黙って首を横に振ると、中井は「だよな」とニキビ跡で赤くなっている頬を緩めた。
『だよな』とはどういう意味かと悠太は一瞬突っ込みたくなったが、面倒なのでやめておいた。
中井の言う通り、悠太は部活に入っていない。中学生の頃は「へたに部活に入ると道具類や遠征費などで金がかかるのではないか」と考え、帰宅部を選んだ。『部活動は必須だ』と教師から注意を受けたが、家庭の事情を話すとあっさり了承してくれた。
母の再婚により金の心配をする必要のなくなった高校生活では、なにか部活に入ろうと入学前は思っていた。
だが、実際にいくつかの部活を見学してみると、中学からの基礎がない自分にはどれもハードルが高そうに思えたし、なにより団体行動というものが悠太は苦手だった。やはりここでも教師から注意を受けたが、『家に生まれたての赤ん坊がいて、両親は共働きなんです』と話すと――実際にはまだ愛花は生まれていなかったのだが――帰宅部でいることをこれまたあっさり了承してくれたのだった。
ホームルームの時間になり担任教師が入ってくると、中井は「まぁ、お互い楽しもうな」と言って前へ向き直った。
担任がなにか話しているが、悠太の耳にはなにも入っこない。
そう。悠太はこのとき初めて気付いたのだ。
夏休みだというのに、部活もバイトもなく、デートする彼女も遊びに行く仲のいい友人もいない。
(――ということは、ずっと家で過ごすことになる……)
昼夜問わずギャーギャー泣き喚く愛花。
ミルクやりとオムツ交換に追われ、寝不足で死んだように横たわっている母。
在宅ワークの隙をみては、愛花に猫なで声で話しかけ、事あるごとに美幸に触れる高志――。
家族の姿を思い出した瞬間、悠太は思わず声に出していた。
「それだけは、絶対に、イヤだ……」
翌朝、制服に着替えた悠太は、高志が「行ってきます」と言って玄関のドアを開けるのを自室で確認してから、居間に顔を出した。
「悠太、おはよう。いつもより遅いんじゃない? パン、急いで焼くから食べてから行きなさいね。――お父さん、今日は出勤日らしくて、もう出たわよ」
悠太はトースターからまだ焼き目の付いていないパンを取り出すと、バターを塗りもせずに立ったまま水で胃に流し込み、一息に言った。
「母さん、俺、塾の夏期講習受けに行きたいんだけど」
母は、きょとんとした顔をしている。
それもそうだろう。これまで悠太は塾というものに通ったことがなく、そもそも「通いたい」という意思を母に見せたことがなかったのだから。
母と二人で暮らしていた頃、母が体に鞭打って仕事と家事を両立しているということは幼心にも分かっていた。
美幸の両親は香川県で飲食店を経営しており、上京して孫の面倒を看る余裕はなかった。
ひとりで必死に自分を育ててくれている母を近くで見ていた悠太としては、進学する高校は、塾に通わなくても受かりそうな公立――定期券代を抑えられる近場であれば、なお良い――であればどこでもよかった。折よく隣駅にぴったりな学校があったため、そこを選んだだけの話だった。
「塾? あらまぁ、珍しいわねぇ……わかったわ、お父さんが帰ってきたら相談してみる。――あらあら、おしめが濡れて気持ちが悪いのかしら……」
母は紙おむつとおしり拭きシートを手早く準備すると、泣き喚く愛花の元に駆け寄り、おむつの取り外しシールに手をかけた。
悠太は目を逸らすと、それじゃ行ってくる、と呟き足早に玄関へと向かった。
(これでよし、と……。終業式が終わったら、あの塾に夏期講習の説明を聞きに行こう。で、今夜にでもあの二人に資料を見せればいい)
悠太は、高志が自分の塾通いに反対するはずがないと踏んでいた。
そして、悠太の読みは正しかった。
***
「家にいたくない」という理由で塾に通うことを決めた悠太だったが、いざ通い始めてみると、それは決して悪いものではなかった。
悠太が選んだのは、最寄り駅のすぐ近くにある少人数制の集団指導塾だった。最近は個別指導型の塾が流行っているようだが、講師との距離が近くなりすぎる気がして、悠太は自分には合わないと考えたのだった。
悠太は終業式の翌日に早速、夏期講習のレベル分けテストを受けた。結果は4クラスあるうちの下から二番目。講習の期間は七月の第四週から八月いっぱいで、お盆の期間は休みとなる。午前九時から十二時まで授業で、午後は自習室を自由に使用して構わないということだった。お昼は弁当を持参している者が多かったが、悠太はコンビニで調達し、自習室で食べることにした。
塾というものに通ったことのなかった悠太は、「スパルタだったらどうしよう」と実は少し不安に感じていたのだが、蓋を開けてみれば程よく熱心、かつ程よく適当で、ほぼノンストレスな環境だった。
それに、朝から夕方までほぼ一年間同じ空間で過ごす高校の級友たちとは違い、塾のクラスメイトとの関係性は夏期講習期間に限定されていたため、実に気楽だった。気楽だったためか悠太にしては珍しく、すぐに一緒に寄り道する仲間ができた。
その日は水曜日で、午後四時まで自習室で過ごすと、悠太たちは塾の目と鼻の先にあるハンバーガーチェーン店に立ち寄った。
「――なぁ、谷本先生ってマジでいいよな」
フライドポテトの紙ケースを持ち上げ、底に残った欠片を豪快に口にザザーッと流し込むと、高田は突然なんの脈略もなしにそう言った。
「――ップ、なんだよ、高田は谷本先生狙いか?」
コーラを飲んでいる佐々木はゲップを堪えながら、そう問い返した。
「狙っているとかそんなんじゃないけさ、谷本先生の授業は純粋にモチベ上がるわ」
「確かに。俺、英語の成績だけ上がっちゃいそー」
「だよな。それになんつーか、『清楚系』って言葉を絵に描いたような人だよな。……あれでもう少し胸があったらマジで最高だったんだけど」
「おまっ、それひどっ! それに、贅沢すぎ!」
二人は声を上げて笑うと、ズズーッと音を立ててストローを啜った。
「なぁ、谷本先生って彼氏いるのかな?」
高田は若干声を潜めてそう言うと、残りのダブルチーズバーガーをすべて口に押し込んだ。
「そりゃあ、いるだろ。あんだけの美人に彼氏がいなかったら、この世の女子大生全員、独り身だろ。――なぁ、中崎はどう思う?」
佐々木は眼鏡を外すと、テーブルの上にあった紙ナプキンでゴシゴシとレンズを拭きながら、悠太の顔も見ずに突然話を振った。
「……どう思うって聞かれても……」
悠太は上手く返すことができず、固まってしまう。
谷本早紀は夏期講習で英語を担当している学生アルバイトで、悠太たちは月、水、金の週三回、彼女の授業を受けている。 噂によると、日吉と三田にキャンパスを有する超有名私立大学の四年生らしい。早紀はいつも髪を低い位置でひとつにまとめ、白い襟付きブラウスに黒のロングスカートを合わせていた。
「うーん……」
悠太は早紀のパッチリとした優しげな瞳とほっそりとした体つきを思い出し、ますます口ごもり、俯いてしまう。何か言おうと焦れば焦るほど、頬が勝手に熱くなるのを感じていた。
高田と佐々木は顔を見合わせると、二人して悠太の顔をまじまじと覗き込んだ。
「おっ?! おまえまさか……先生に惚れてるとか?!」
ただでさえ圧迫感のある高田の顔が眼の前に迫り、悠太は思わず椅子を後ろに引いた。
「……そ、そんなんじゃないけど……」
悠太の言葉とは裏腹に、頬はますます熱を帯びていく。
「いや、やめとけやめとけ! あんな賢いお嬢様が俺らレベルを相手にしてくれるわけねぇって!」
高田は悠太の肩にポテトの油が付いたままの手を置くと、真顔でそう言った。
「『俺らレベル』って……?」と訊ねたい気もしたが、面倒だったので悠太はそのまま聞き流すことにした。
翌日の木曜日、悠太はどうしても自習室で勉強を続ける気になれず、高田と佐々木に軽く挨拶をすると、午後二時頃に塾を後にした。
電車で隣駅まで行き、駅前のゲームセンターに入る。UFOキャッチャーで六百円を使ったが、何の景品もゲットできなかった。なんだか急に気持ちが萎えてしまい、悠太は早々に店を出る。
「大事な小遣いのうちの六百円を無駄に使ってしまった」という罪悪感と、前日、高田に言われた『俺らレベル』という一言が引っかかっていた。
悠太はなんとなく目に入った書店のドアをくぐる。一歩足を踏み入れた瞬間、冷気がサーッと汗ばんだ身体を吹き抜けていった。悠太は、冷たい空気の出所を見つけると、しばしそこに佇む。
「フゥーッ……」
深呼吸すると、悠太は本棚の間をゆっくりと歩き始めた。
思えば、書店という場所にはほとんど足を踏み入れたことがなかった。
家庭の経済状況を常に気にしてきた悠太にとって、本を買うということは贅沢な行為に思われた。もちろんお年玉などまとまった金額を時々母親は渡してくれてはいたが、それを本に使おうという気持ちにはなれなかった。
(谷本先生レベルの人は、こういうところに通って本を買うんだろうなぁ……)
新刊コーナーで書籍を手にとっている早紀の姿を想像した悠太は、自分も真似してみたい気持ちに駆られた。
「新刊コーナーはどこだろう」
キョロキョロしていると、『まだまだ話題作!』というポップが目に飛び込んできた。なんとなく近付き陳列されている書籍に目をやる。
一番目立つ場所に、『嫌われる勇気』という青い装丁の本があった。タイトルに惹きつけられた悠太は一冊手に取ると、パラパラとページをめくってみる。
(なるほど、この本は哲学者と青年の対話形式になっているのか……。会話文だし読みやすそうだな)
悠太は試しに序章の部分だけ読んでみることにした。すると、3ページ目に青年のこんな台詞があった。
『――しかし、大人になるにつれ、世界はその本性を現していきます。「お前はその程度の人間なのだ」という現実を嫌というほど見せつけられ、人生に待ち受けていたはずのあらゆる可能性が"不可能性"へと反転する――』
たかだが三行ほどの文に胸の奥をぎゅっと素手で掴まれた感覚がした悠太は、ポケットからスマホを取り出すと、近くの図書館で借りられないかを調べた。すると、『待機している人の数:83名』と表示された。
悠太はスマホをしまうと、本を手にまっすぐレジへと向かった。
再び電車に乗り自宅の最寄駅で下車した悠太は、駅前のハンバーガー店で購入したばかりの本を読もうと考えた。自宅で読もうとも思ったが、泣き喚く愛花の姿を思い浮かべた瞬間、その考えは消え去った。
しかし、ハンバーガー店の入口に高田と佐々木の姿を認めた悠太は踵を返し、多摩川の方へと歩き始めた。
自販機で缶コーヒーを買い、腰を掛けられそうな日陰を探す。
(確かあの辺りは高架下になっていて、日陰があったはず……)
悠太が目星をつけていたのは、コンクリートで階段状に舗装された河川敷だった。
(やっぱり日陰がある。しかも誰もいない)
悠太は弾むような足取りできれいに舗装された階段に近付き腰掛けると、白いトートバッグから購入したばかりの本を取り出した。
――どれだけの時間、そこにそうしていただろう。
「――バカヤローッ! ふざけんなーッ!」
そう叫ぶ声が耳に届き、悠太はビクッとして顔を上げた。
辺りを見回すと、50メートルほど離れたところで若い女性が川に向かって叫び続けているのが目に入った。
「マジでコロすッ! くたばっちまえ! くそババアーッッ!」
ピンク色のトップスにジーンズ姿のその女性は、ひたすら川に向かって罵詈雑言を喚き散らしている。
(……やばい感じだな。とりあえず、ここは離れないと……)
悠太は右手をトートバックに伸ばし、本を持ったままの左手で脇に置いてあったコーヒーの空き缶を掴もうとしたが、指が滑ってしまい、缶が派手な音を立てて階段を転げ落ちていった。
(――しまった!)
恐る恐る女性のいた方角に目をやると、女性はこちらに顔を向けていた。
(……あっ……!)
悠太は女性の顔を見て、その場に凍りつく。
――その人は、谷本早紀だった……。
悠太はどうしたらよいのかわからず、すばやく空き缶を拾うと階段を上り、歩道に出た。
「――ちょっ……待って……!」
早紀の声が聞こえたが、悠太はそのまま家までの道を脇目も振らず、全速力で走ったのだった――。
――翌日、金曜日。
本来であれば、この日は早紀による英語の授業があるはずだったが、「谷本先生はお休みなので、今日は私が授業を行います」と、急遽代打で中年の女性講師が授業を行うことになった。
「かわいそうな中崎くん、今日の楽しみがなくなっちまったな」
前の席の高田は、講師がホワイトボードの方を向いた瞬間を見計らって振り返ると、ニヤッと笑ってそう呟いた。
悠太は何も言わずに視線を泳がせると、バッグからペットボトルを取り出し、乱暴にキャップを捻った。
(なんで今日、先生は休んだんだろう……。やっぱり昨日のことがあったから? 生徒の俺に目撃されたのが気になって……とか?)
気付けば悠太は早紀のことばかり考えてしまい、この日はまったく授業に集中することができなかった。
授業に身の入らなかった悠太は、せめてもの罪滅ぼしとばかりに、夕方まで自習室でなんとか勉強を続けた。夏期講習の決して安いとは言えない費用のことを思えば、悠太にとっては当然の行動だった。
午後四時になると、悠太は高田と佐々木と塾の前で別れ、前日と同じ河川敷に向かうことにした。なんとなく、そこに行けば早紀に会えるのではないかと感じたからだった。
悠太は前日と同じ場所に腰を下ろすと、トートバッグから『嫌われる勇気』を取り出した。
(会えるかどうかわからないし、ひとまず昨日の続きを読んでいよう)
読書に没頭していると、ふいに背後から「中崎くん」という女の人の声がした。
振り返ると、そこには早紀がいた。普段塾で見る姿とは異なり髪はさらりと下ろしていて、黒のロングスカートの代わりにレモンイエローのパンツを履いている。上は塾でいつも着ている白の襟付きブラウスだ。
早紀は乗っていた白のスポーツ自転車をその場に止めると、「ここに来れば会えるかもしれないと思って……。よかった……。少しだけ隣、いいかな?」と尋ねた。
悠太がぎこちなく首を縦に振るのを認めると、早紀は階段を降りてきて、悠太の隣で膝を折ってしゃがみこんだ。
「……中崎くん、昨日はお見苦しいところをお見せしちゃって、本当にごめんなさいっ!」
早紀は頭を下げると、そのまま折り畳んだ膝に顔を埋めた。頬にかかる髪で、表情はまったく見えない。
「……いえ、そんな、気にしないでください」と悠太は小声で返す。
(……あぁ、なんて気の利かない返しなんだ……!)
悠太は、凡庸な自分に腹を立てていた。
「――ありがと……。本当は『塾では気取ってるくせに、なんて下品な女なんだ』と思ったでしょ?」
早紀は下を向いたままだ。
「そんなっ! げ、下品だなんて……そんなこと、思ってません!」
早紀に似つかわしくない自虐的な言葉に悠太が声を上げると、早紀はゆっくりと顔を上げた。
白い頬は赤く染まっている。
早紀は頬にかかる髪を耳にかけると、頬杖をついて悠太を見た。
「――ありがとう。中崎くん、優しいのね」
目尻にかけて緩やかなカーブを描く大きな瞳が悠太だけを見つめている。
(……カ、カワイイ……! 顔が……顔が燃えるように熱いっ! 俺、きっと真っ赤だよ……恥ずかしい!)
そう思いながらも、悠太は早紀から目を逸らすことができずにいた。それはまるで、魔法にかかっているかのような感覚だった。
しばし見つめ合ったあと、先に目を逸らしたのは早紀の方だった。
「……ちょっとむしゃくしゃしていて、どうしても叫ばずにはいられないことがあったの。だからといって、あれはちょっと酷すぎたね」
そう言うと、悠太が手にしている青い表紙の本に目を向けた。
「――ところでその本、そんなに面白いんだ?」
「えっ?」
「だってほら、ペットボトルにすっかり陽が射してる。好んで日向に水を置く人はいないでしょ? 長いことここで、その本に集中していたのかなぁって」
悠太はオレンジ色の光が射しているペットボトルに手を伸ばす。それはすっかりぬるくなっていた。
『嫌われる勇気』を読んでいたことを知られるのがなんとなく恥ずかしくて、悠太はタイトルが早紀に見えないよう気を付けながら本をリュックにしまった。
(次からは、ブックカバーを付けてもらおう……)
悠太がそんな風に思っていると、早紀がぼそっと呟いた。
「……それとも、私のこと待っていてくれたのかな……」
再び一瞬で耳まで真っ赤になった悠太の返事を待たず、早紀は言葉を継いだ。
「ごめんね」
「……えっ?」
悠太は反射的に早紀の顔を見る。
「今日私、塾を休んだから……中崎くん、自分のせいだと思っちゃったんじゃない?」
「……いえ、そんな……」
「出勤しようと思って着替えとメイクは済ませていたんだけどね……どうしても行く気になれなくって……。隣駅のカフェでサボってたんだ。悪い先生だよね」
早紀はそう言うと、ヘヘッと悠太に微笑みかけた。悠太はただただその笑顔に見惚れていた。
悠太が見ているのが自分の服だと勘違いした早紀は、「私、普段は自転車に乗るからスカートじゃなくてパンツばかりなの」と話し出した。
「塾で黒のスカートに履き替えてるんだ。『下は黒色のロングスカート、上は白色の襟付きブラウス着用』っていう謎の決まりがあってね」
「……そうなんですね」
塾での清楚な姿の早紀に憧れていたはずの悠太だったが……
(いつもの黒いスカートよりも今日の鮮やかな色のパンツの方が先生らしくて素敵だ)
そう感じていた。だがそんな言葉が口から出てくるはずもなかった。
そのとき、川の方からやや強めの風が吹いてきた。
「ここは本当に気持ちがいいね……。風に吹かれていると、イヤなことぜーんぶ忘れられる気がしてくる」
早紀はそう言うとゆっくりと立ち上がった。
「今日は会えてよかった。私の話、聞いてくれてありがとうね」
悠太は黙って早紀を見上げる。
早紀は階段を登り、近くに止めていた自転車のハンドルを握った。
そのとき――。
「先生っ!」
悠太は自然と大きな声を出していた。
早紀は悠太に再び視線を向ける。
「来週の月曜日、先生が授業してくれますよね?」
早紀は微笑むと、「もちろん!」と大きな声で答えたのだった――。
その日の晩、高田からスマホにメッセージが届いた。
『明後日の日曜日、暇だったらボーリングにでも行かねぇか。佐々木にも声かけるつもり』
週末は塾もなく、自室にこもるか近所をぶらつくしか予定のない悠太は『OK !』と返事を返した。
日曜日。ボーリング場を後にした三人は、近くのビルの地下にある安くて有名なファミレスへと向かった。
「やっぱ高二の夏はまだまだ気楽でいいよなぁ。来年の今頃、俺ら地獄だぜ」
入店してからまだ二十分ほどしか経っていないにもかかわらず、高田は自分たちのテーブルとドリンクバーの間を既に五往復はしていた。
「だよなぁー。……ップ、マジで永遠に高二でいたいよ」
佐々木はおそらく炭酸飲料があまり得意ではないのだろう。口に運ぶ度にゲップをしている。
「中崎はさ、どのへんの大学目指してる?」
高田に話を振られた悠太は、「……どのへんの大学?」とオウム返しをした。
「お前ってさ、俺らと違って真面目じゃん。宿題もいつもちゃんとやってくるしさ」
「ちょっ、高田! 『俺ら』って、俺をお前と一緒にすんなよ!」
佐々木が眼鏡の縁を持ち上げながら、猛抗議している。
悠太は自習室でいつも突っ伏して寝ている高田の姿を思い出す。家にいると母親から勉強しろと言われるので、塾に残っているのだという。
「夕飯前に帰るとさ、『お疲れ様―!』って笑顔で迎えてくれるんだよね。それが気分良くってさ」
高田は悪びれもせずにそう話していた。
高田は東急東横線沿線の私立高校、佐々木は東急多摩川線沿線の私立高校に通っている。高校を受験する際に私立への進学は一切考えていなかった悠太は、二人の学校名を聞いてもどれくらいのランクの学校なのかピンと来なかった。後でネット検索してみたところ、二人の高校は悠太の通う公立高校よりも偏差値が低かった。
「中崎、俺らよりも頭イイ学校に通ってるのに、なんで俺らと同じクラスなんだろな」
佐々木は唐揚げを口に放り込みながら、不思議そうに首を傾げている。
(――そんなの私立の方が授業の進度が速いからに決まってんだろ)
喉まで出かけた言葉を悠太はアイスコーヒーで無理やり胃に流し込む。
「まぁ、俺らレベルじゃ、行けてもそこそこの大学だよなぁ――そこへいくと谷本先生はカワイイし大学は慶明だし、マジで人生勝ち組だよなぁー」
高田の口から突然出た『谷本先生』という名前に、悠太の心臓は大きく跳ねる。
「俺らレベルじゃ、どうひっくり返ったって慶明大なんて入れないもんなぁー」
佐々木は頭の後ろに手をやると、大げさに天を仰いだ。
「谷本先生の彼氏ってさ、やっぱ慶明大生なんかな。くっそー、相手の男が羨ましい!」
「きっと頭が良いだけじゃなくてイケメンなんだろうな。どっちみち俺らじゃ無理だべ」
だよなー、と二人は大げさにため息をつくと、唐揚げに同時に手を伸ばした。
悠太も二人につられてひとつ取って口に入れた。
厚い衣が吸い込んだ古い油が口の中に広がっていく。
悠太はアイスコーヒーで口の中を洗い流すと財布から五百円玉を取り出しテーブルの上に置いた。
「わりぃ、俺、用事あるんだったわ。これで足りるよな?」
そう言うと、足早に店を後にした。
家に帰ると、母の美幸は台所で夕食の準備をしていた。ベビーベッドにちらり目をやると、愛花は四肢を広げてぐっすり眠っている。
自室で部屋着に着替えてベッドで横になっていると、「晩御飯できたわよ」という美幸の明るい声がした。
居間のドアを開けると、高志が冷蔵庫からビールを取り出していた。どうやら風呂から上がったばかりのようだ。
「お、悠太くん、おかえり」
「――ただいま」
食卓に目をやると、山盛りの唐揚げが並んでいる。
「今夜は悠太の好きな唐揚げよ」
美幸は悠太と高志が食卓につくのを見計らって、炊きたての白米を順々に差し出す。
「悠太くんは唐揚げにレモンかける派だっけ?」
高志がレモンを手に尋ねる。
「あ、どっちでもいいっす」
目も合わせずに答える悠太に、高志は「じゃあ、全体にはかけずにここに置いておくわ」と、器の端にレモンを置いた。
「悠太、夏期講習の調子はどう?」
美幸はそう言いながら、高志の隣に腰かける。
「別に……普通だよ」
悠太は眼の前の母に一瞬目をやってそう答えると、唐揚げに手を伸ばした。
カリッ、ジュワーッと、口の中で旨味が広がっていく。
「――今日ね、母親学級で知り合った和美さんから聞いたんだけど」
美幸は高志の方に少し首を傾けると、先ほどよりもやや高い声で話し始めた。
「近所に有名な幼児教室があるらしいのよ。なんでもゼロ歳から英語を習えるらしくて、そこに通っていた和美さんの姪っ子ちゃん、五歳でもうペラッペラなんですって! 愛花も通わせてみたらどうかと思うのだけど……高志さん、どう思う?」
高志は唐揚げを咀嚼しながら「幼児教室かぁ……まぁ、これからの時代は英語が喋れるに越したことないからなぁ」と腕を組んでいる。
悠太は黙々と唐揚げを口に運び続ける。
「よかった! じゃあ和美さんに紹介してもらって、今度見学に行ってくるわ」
美幸は正面に向き直ると、ようやく唐揚げに手を伸ばした。
「うん! 今日のも美味しく出来たわ。――悠太、どう? 美味しい?」
「――あぁ」
「『あぁ』って、ほんとに愛想のない子ねぇ」
美幸はそう呟くと、母親教室で出会った人たちの話をし始めた。
うんうんと頷きながら話に耳を傾けている高志。
――と、愛花が突然、大きな声で泣き始めた。
駆け寄って抱き上げる美幸。
「腹が減ったのかな――ミルクを用意しようか」
高志は箸を置いて、哺乳瓶を取りに行く。美幸は母乳があまり出る方ではないので、粉ミルクを利用することが多い。
「――ほら、適温に冷やしておいたよ」
美幸は差し出された哺乳瓶を受け取ると、愛花の口に近付けた。まるで磁石に吸い寄せられるように、愛花の口は哺乳瓶のちくびを的確に捉える。
「こうやって見ると、やっぱり高志さんによく似てるわね」
どれどれ、と愛花を覗き込む高志の口元は綻んでいる。
「食欲もあるし、よく眠るし、元気な子でよかったわ……高齢出産だったから、不安もあったけどね」
「……そうだな」
高志は美幸と愛花を優しく見つめている。
(――あれ……なんかこれ、脂っこいな)
口に入れたばかりの唐揚げに違和感を覚えた悠太は、麦茶でそれを胃に流し込む。
「ごちそうさま」
悠太はボソリ呟くと、椅子を引いて立ち上がる。
「――あら、悠太、あんまり食べてないんじゃない?」
「さっき友達と少し食べてきたから」
「……そう」
数秒、悠太に目をやっていた美幸は、再び愛花に視線を戻す。
「よちよち、たくさん飲んでいい子でちゅねー」
美幸が愛花を抱き起こし背中を優しく叩くと、やがてガポッという空気音が小さな口から吐き出された。
よく食べ、よく眠る愛花。
イケメンの父親に似ている愛花。
ゼロ歳から幼児教室に通わせてもらい、五歳で英語がペラッペラになる将来が約束されている愛花。
ふいに、高田が口にした『俺らレベル』、『人生勝ち組』という言葉が脳裏に浮かんだ。
(――愛花はきっと『人生勝ち組』なんだろうな)
悠太が居間のドアノブに手をかけた瞬間、「あ、そうだ、悠太」と美幸に呼び止められた。
「来週の日曜、みんなで外食しない? 赤ちゃん連れでもオッケーなイタリアンのお店、和美さんに教えてもらったの。本格的なピザ窯のあるお店だそうよ」
悠太が中学生の頃、『東急東横線沿線グルメ旅』というテレビ番組を母と一緒に見たことがある。若手お笑い芸人とアイドルの女の子が話題のレストランを紹介するという番組だった。二人が訪れたのは、イタリアで修行した日本人シェフが本格的なピザ窯で焼き上げるマルゲリータが大評判だというイタリアンレストランだった。アイドルの女の子が『こんなに美味しいピザ、食べたことないですぅー』とテカテカに光った唇を突き出してコメントしていたのが、今でも悠太の記憶に残っている。
『ピザなんて、パンの上にハムやチーズをちょこちょこっと置いて焼くだけでしょ。あれで千五百円もするだなんて、ぼったくりよねぇ。同じ金額を払うのなら、お刺身定食の方がいいわ』
あの時、美幸はたしかそう言っていたはずだ――。
「日曜だし、予約を入れておいた方がいいかもしれないわね」
「そうだな、後で電話しておくよ。ランチでいいよね?」
二人は愛花をベビーベッドに寝かせながらそう話している。
「――俺、行かないよ」
悠太は振り返らずに告げた。
「――えっ?」
背中に二人の視線を感じる。
「友達と会う約束してるから」
「友達って……学校の?」
「……どこの友達だっていいだろ!」
悠太は語気を強めた。ドアノブに置かれたままの手がじわり汗ばんでいる。
「……せっかく家族四人で楽しく過ごそうと思ってたのにィ……」
美幸の甘えた物言いが、少年の中で膨らむだけ膨らんだ黒い風船に針を刺した。
「……なにが『家族四人』だよ」
悠太はドアノブから手を離し、勢いよく振り返ると美幸の顔を睨み叫んだ。
「俺がいない方が、家族三人、水入らずで楽しめていいじゃねえかっ!」
美幸は呆気にとられているのか、口を開いたまま身じろぎもしない。
悠太は再び背を向けると、ドアノブに手をかける。
胸の中のマグマが今にも噴き出そうとグツグツいっている。唐揚げを飲み物で胃に流し込んだときのように、悠太はゴクリと唾液を飲みこむ。
だが、マグマは猛スピードで喉元まで上がってきた。
「――何が幼児教室だよ……俺が……俺がどれだけ今まで我慢してきたのか、知ってるのかよっ……! 幼児教室の前にもっと考えること、あるだろうがっ……!」
悠太はわざと派手な音を立ててドアを閉めた。
自室に入るとき、愛花の泣き声が耳に届いた気がした。
――翌日、月曜日。
悠太は誰にも会わないように早朝家を出ると、隣駅にある漫画喫茶で時間を潰した。
どうしても塾に行く気にはなれなかった。
『来週の月曜日、先生が授業してくれますよね?』
早紀にそう訊ねたくせに、自分が塾をサボってしまった。
(先生、今日塾来たかな……。俺がいなくて、心配したかな……いや、するわけないか)
夕方になると悠太は電車に乗り、先日早紀と話した河川敷へと向かっていた。
(先生がわざわざここに来るとは思えない。だけど、ひょっとしたらここは塾からの帰り道なのかもしれないし……)
悠太はレモンイエローのパンツ姿でスポーツ自転車にまたがる早紀の姿を思い出し、頬を緩めた。
階段に腰掛け、トートバッグから『嫌われる勇気』を取り出すと、栞を挟んでいたページを開く。青年と哲学者の会話もいよいよ終盤に差し掛かっていた。
『いったいどうすれば、自分には価値があると思えるようになるのか?』という問いに対する哲学者の答えを目にした瞬間、悠太は頭を殴られたような気がした。
『人は「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる』
(……『共同体』ってつまり……家族や仲間ってことだよな)
悠太は本を閉じ、夕方だというのにまだまだ明るい陽の光を浴びてキラキラ輝く水面に目をやった。
(俺は家族にとって有益じゃない……。それどころか、害悪だ)
悠太は自分の怒声に呆然としていた美幸の顔を思い出す。
(あの二人は俺のことをまったく考えていない訳じゃない。現にこうして夏期講習にも通わせてくれた……。なのに俺は……)
悠太は頭をクシャクシャっと掻き上げると立ち上がり、近くにあった石を力任せに川に向かって投げた。
(……どんな顔をして家に帰ったらいいんだ……)
大きく嘆息したそのとき、「中崎くーん!」という声が背後から飛んできた。
振り向くと、そこには自転車を手で押している早紀の姿があった。
「――先生……」
「大丈夫? ひょっとしたら、ここかなと思って……。来てみてよかったわ」
早紀は階段に腰掛けると、悠太に手招きをした。今日はスカイブルー色のパンツを履いている。
「何かあった? 私でよければ、話聞くよ?」
柔らかな視線に促されるように、悠太は早紀の隣に腰を下ろすと口を開いた。
「――先生、すみませんでした。月曜日に来てくださいって言っておいて、俺がサボってしまいました」
早紀は、いいのよそんなこと、と小さく答える。
悠太はどこから話していいのかわからず、二人の間にしばし沈黙が流れた。
川面を撫でてから河川敷に吹き寄せる風が、早紀のセミロングの髪を揺らしている。
「あー、気持ちいいねー!」
早紀は両腕で膝を抱え、空を見ている。
悠太はそんな早紀にちらり目をやった。
(塾で髪をひとつにまとめている先生も清楚でカワイイけれど、こうして髪を風になびかせている先生の方が、なんか先生らしくて好きだな。――って俺、なに考えてるんだよ!)
「――中崎くん?」
ひとりで赤くなっている悠太の顔を早紀は覗き込む。
「大丈夫? 熱中症になったら大変! 水、持ってる?」
「――だ、大丈夫です! 水はほら、ここにありますし」
悠太はペットボトルのキャップを捻ると、喉を鳴らして水を飲んだ。
そして、ふぅっと息をひとつ吐くと、前の日の晩、家であったことを語り始めたのだった――。
「――そっかぁ……」
早紀は立ち上がると川面を見つめて言った。
「中崎くんのお母さん、今は新しい旦那さんとの関係を固めるのに必死なんじゃないかな」
「……えっ?」
「私にはまだ子供がいないから、想像でしか言えないのだけれど……お母さんは離婚されたことで、誰よりも大切なあなたに苦労をかけてしまったと悩んでいたんじゃないかな。新しいパートナーが見つかってお子さんができた。けれど、また夫婦関係で失敗してしまったら、あなたをいつまでたっても幸せにできない。だからまずは、旦那さんとの関係を固めようとされている。言い換えれば、あなたとの関係は旦那さんとの関係よりもずっとずーっと強固なものなのよ。壊れるはずがないってお母さんは安心しているの。あなたを信じて、あなたに甘えているのかもしれないわね」
早紀はそう言うと、振り返って悠太に微笑みかけた。
「ずっと苦労されてきたお母さんを、甘えさせてあげるっていうのはどうかな……。それってすっごくカッコよくない?」
「……お、俺……母さんに酷いことを……」
俯いた悠太の頬を涙が伝う。
「大丈夫! 言ったでしょ? お母さんはあなたのことを誰よりも信じているの。そんな一時の感情に任せて出た言葉くらいで、二人の絆が壊れるわけがないわ!」
悠太は立てた膝に顔を突っ伏して泣いた。
――どれだけの間、そうしていただろう。
顔を上げると、陽は傾き始めていた。
早紀は変わらず自分に背を向け、川面を見つめている。
悠太はトートバッグからティッシュを取り出すと、思い切り鼻をかんだ。
それに気付いた早紀は、再び口を開く。
「――人生ってさ、自分の居場所を求め続ける旅みたいだよね……」
悠太は黙って耳を傾ける。
「きっと大事なのはさ……ここを自分の居場所にするんだって覚悟を決めることなんだよね……」
そう言った声が少し震えているような気がしたが、悠太から早紀の表情は見えない。
「ここを自分の居場所にするんだっていう覚悟……」
悠太は早紀の言葉をただ繰り返す。
やがて早紀は振り返り「遅くなっちゃったね。そろそろ帰ろうか」と明るい声を出した。
だが、逆光のせいで悠太には早紀の表情は見えなかった――。
その晩、悠太が玄関のドアを開けると、キッチンから「おかえりー」という美幸の声が聞こえてきた。
悠太は一瞬廊下で立ち止まると、早紀の優しい笑顔を頭に思い描く。そして、『ここを自分の居場所にするんだっていう覚悟』と小さく呟くと、居間のドアを開けた。
「……ただいま」
「おぉ、悠太くん、今日もお疲れさま。お先に一杯やっていたよ」
高志はビールグラスを片手に微笑んでいる。
「悠太、すぐにご飯だから手を洗ってきちゃいなさい」
美幸はトマトを切りながらそう言った。
「――その前に……」
悠太はバッグを肩から下ろすと一息に言った。
「昨日は酷いことを言って、ごめんなさい……。俺、本当はあんなこと言うつもりなかったんだ……」
そう言って頭を下げると、目の奥がツーンとしてきた。やばい、泣きそう、と思ったときには既に遅かった。
「……母さんには幸せになってもらいたいと思ってるし、高志さんがいい人だってこともわかってる。なのに……心がついていかないんだ……ゴメン」
立ち尽くしたまま流れる涙を手の甲で拭っていると、手の平がそっと肩に置かれたのがわかった。それは、とても大きくて温かかった。
「悠太くん……つらい思いをさせてしまって、本当にすまない。僕の配慮が足りなかった」
そんなことないです、と悠太は首を横に振る。
「正直言うとね――」
高志は悠太の肩を抱き、居間のソファーに座るよう促す。
「僕はね、悠太くんの正直な気持ちに触れることができて、よかったと思ってる」
えっ、と顔を上げる悠太。
「だって僕らは家族なんだから。いや、この際、綺麗事はよそう。『家族になりつつある』んだからさ、なんでも腹割って話そうよ……。時間をかけて、家族になっていこう」
眼鏡の奥の高志の瞳は、少し潤んでいるように見えた。
「――はい……!」
悠太はそんな高志の瞳をしっかりと見つめ返して答える。
「――もう、悠太ったらびっくりさせるんだから……」
夫と息子の様子を台所から見守っていた美幸が、バラ柄のエプロンで手を拭きながら悠太に近付く。
「悠太、ごめんね……。悠太はいつでも母さんの味方でいてくれるからって、甘え過ぎてたね……。あなたは私の大切な大切な息子よ。死ぬまでこれは、絶対に変わらない」
美幸はそう言って、涙で濡れた悠太の手を両手でしっかりと握った。
「……ゆっくり……ゆっくりやっていこう。私も、もっと悠太のことをちゃんと見ていくから。悠太も母さんのことをこれからも見ていてほしい」
悠太は自分の手を握っている母親の手を見つめた。
シミがぽつぽつと出始めていて、少し皺の寄った小さな手――。
「……うん、わかった」
悠太と美幸は互いに鼻をグズグズ鳴らしながら、笑い合った。
***
――五年後。
「そんじゃ、行ってくるわ。――ほら愛花、帽子をかぶらないと」
悠太は小さな頭に麦わら帽子をかぶせると、玄関先の姿見に自分を映し、髪を軽く掻き上げた。
「悠太、よろしく頼むわね。――愛ちゃん、今日はママ一緒に行けないから、お兄ちゃんの言うことをよーく聞くのよ」
「うん、わかった!」
悠太は愛花の手を引きながら玄関のドアを開けた。
もう夕方だというのに、空気は相変わらずむわっと湿り気を帯びている。
「愛花、どんな先生か、楽しみだな」
「うん、楽しみー!」
二人は多摩川沿いの土手を手を繋いで歩く。
ここを歩くと英会話教室までは少し遠回りなのだが、愛花は外に出ると決まって「川、通ってこうよー」と言う。
真夏の日差しを受けてキラキラ輝く水面は、否応なしに悠太に谷本早紀のことを思い出させる。
(あれからちょうど五年かぁ……)
高二の夏、悠太が早紀の姿を見たのは、悠太が家族と和解した日――あれは八月初旬の月曜日だった――の翌々日、水曜日の授業が最後だった。
金曜日からは、以前に一度、早紀の代理を務めた中年女性講師が悠太のクラスの正式な英語担当となった。
「マジでモチベ上がんねー」
前の席だった高田はしょっちゅう悠太の方を振り向いては、そうこぼしていたのだった。
夏期講習の全日程が終わると、悠太は近くの個別指導塾に移ることにした。もちろん両親の同意あってのことだ。あの日、悠太が叫んだ『幼児教室の前にもっと考えること、あるだろうがっ……!』という言葉が響いたのか、両親は愛花の英才教育よりも目の前の息子の大学受験を優先することに決めたのだった。
集団指導から個別指導に変えたのは、高田や佐々木のような『経済的に恵まれているからとりあえず塾通いしているけれど、やる気はゼロ』タイプの人間と距離を取りたかったからだ。事あるごとに『俺らレベル』と十把一絡げにされるのも、たまらなく嫌だった。
個別指導塾は悠太に合っていたようで、成績は右肩上がりで伸び続けた。
そして高校を卒業した翌月、悠太は『GMARCH』と称される都内の有名私立大学の門をくぐったのだった。
地方の国公立を目指したらどうか、と塾の講師からは勧められたが、悠太はあえて自宅から通える大学を選んだ。
(一人暮らしをしてしまったら、帰省する度に家族に対して違和感を覚えるのは目に見えている。あの人たちと家族になる覚悟を決めよう)
悠太はそう決意したのだった――。
時は流れ、悠太は大学四年になった。
愛花は五歳になり、あたりまえだがすっかり意思疎通ができるようになった。ころころ変わる表情を見ているだけで、悠太の口角は自然と上がる。
「愛花、暑くないか? 少し水分補給しよう」
悠太は立ち止まりリュックから子供用のドリンクを取り出すと、キャップを開けて少女に手渡す。
愛花はこめかみに汗をにじませながら、ゴクゴクと喉を鳴らしている。
「さぁ、あともう少しで着くぞ」
ドリンクをリュックにしまうと、悠太は再び小さな手を取った。
大学三年の夏から始めた就職活動だったが、悠太はつい二ヶ月ほど前に無事内定をもらっていた。
母の美幸は息子が無事社会人になることに安堵したのか、ある日の夕食の席で「悠太も落ち着いたことだし、そろそろ愛ちゃんに英会話を習わせたい」と言い出した。
食事が終わると高志はダイニングテーブルにノート型パソコンを置き、早速良さそうな英会話教室を探し始めた。
「ここはどうだろう。駅前だし、悪くなさそうだ。――悠太、ちょっと見てくれる? こういうのは若い人の感覚で見てもらった方がいいかもしれない」
声をかけられた悠太は高志のパソコンを覗き込む。そこには『スマイル英会話教室』という大きな文字が踊っていた。
「ここに座って、見てくれていいよ。俺はあっちに座っとくから」
高志はそう言ってソファーを指差した。悠太は高志が座っていた椅子に腰掛けじっくりとサイトを見始める。比較検討するために、似たような教室のサイトもいくつか開いてみることにした。
「場所も近いし費用も平均的だけど、肝心なのはどんな人が教えているかだよな。えーっと、プロフィール欄はどこだ――? あ、あった!」
そう独りごちながら、カーソルを『講師プロフィール』に合わせクリックする。
(――え……?)
悠太の目に飛び込んできたのは、五年前に会ったきりの谷本早紀の笑顔だった。
(……た、谷本先生っっ?!)
髪色が明るくなっているとはいえ、そこにいる早紀は五年前に河川敷で話したときの彼女となんら変わりはないように悠太には思えた。
(どうして先生が子供の英会話教室を……? あ、でも先生、英語担当だったし不思議ではないか……)
微動だにせず画面を呆然と見つめる悠太。
「悠太、どう思った? 他にいいところがあれば、そっちでもいいのだけど」
高志の声が耳に届き、悠太はハッと我に返る。
「――こ、ここでいいんじゃないかな……」
悠太はそう言って立ち上がると冷蔵庫から麦茶を取り出した。コップに注ぎ、一気に喉に流し込むと、プハーッと大きく息を吐く。
「そうか、じゃあ早速、体験レッスンを申し込もうか」
高志の言葉に、悠太の胸はドクンと音を立てる。
(ひょっとしたら……また先生に会えるかもしれない……)
「父さん、体験教室には俺が行ってもいいかな」
気付くと悠太はそう口にしていた。
「え……もちろんいいけど、急にどうしたんだい?」
「――ほら、子供向けの英会話教室って、きっと英語の知育玩具とか絵本とか色々置いてあると思うんだよね。来年からの俺の仕事とも無関係じゃないっつーか……」
悠太が言い淀んでいると、高志はニコリと微笑み「わかった、任せるよ」と言ったのだった。
土手から住宅街に入ると、悠太はスマホを片手に『スマイル英会話教室』を探す。
(――この建物の三階か)
建物の入口で部屋番号を押すとすぐに「はい」という女性の声がした。
「五時に体験レッスンを予約している中崎ですが……」というと、「どうぞ三階の301にいらしてください」と言われた。
(今のは谷本先生……ではないな。声がちょっと違う気がする……)
教室のドアを開けると、五十代とおぼしきふくよかな女性が笑顔で迎えてくれた。
「中崎愛花さんですね。お待ちしておりました。体験レッスンは十分後に始まりますので、あちらの教室でお待ち下さい。お手洗いは廊下の突きあたり右側にございますので」
「……あの、私はどこにいたらよいのでしょうか」
「保護者の方は教室の後ろに椅子を用意してございますので、そちらに掛けていただいても結構ですし、こうして廊下の窓越しに見学していただくこともできますよ」
悠太が愛花の手を引いて教室に入ると、他にはまだ誰もいなかった。
開始時刻が近付くと、愛花と同年齢くらいの女の子が二人入ってきた。どうやら今日の体験レッスンは三名で行うらしい。
悠太は他の母親たちと同様、後ろに用意されている椅子に腰を掛けた。
五時になると、谷本早紀が姿を現した。
ホームページで見るよりも髪は明るい茶色に染められており、肌も五年前に比べると少しばかり焼けていた。細身のスタイルはまったく変わっておらず、白いTシャツとスキニーパンツがよく似合っていた。
“Hi! everybody! Welcome to Smile English conversation class! I’m so glad to see you !”
(みんな、こんにちは! 『スマイル英会話教室』へようこそ! みんなに会えて嬉しいです)
早紀は流暢な英語で子どもたちに話しかける。
だが、少女たちは一様にポカンとした顔をしている。
「みんな、こんにちは! 私は早紀先生です。今日はね、ウサギのミミーと一緒にみんなに会いにきました。一緒に“Mimi! Come here!”『ミミー、こっちにおいで!』って呼んでみようか。せーの!」
“Mimi! Come here!”
comeの意味もhereの意味も知らないはずの愛花だが、早紀とまったく同じ発音でミミーを呼んでいる。
(……愛花って、ひょっとしたら英語の才能があるのかも……?!)
そんな思いが一瞬悠太の頭をよぎる。
(……あ、これがいわゆる親ばかってやつか……親じゃないけど)
悠太は思わず鼻を鳴らしてフッと笑ってしまった。
――その瞬間。
うさぎのパペットを左手にはめた早紀と目がバチッと合ってしまった。
早紀は呆然とし、動けないでいる。
悠太は軽く頭を下げると素早く荷物を手にし、ドアから外に出てトイレへ向かった。
しばらくして教室の前に戻ってくると、ミミーになりきった早紀の流暢な英語が教室の外まで響いていた。
「すみません、ちょっと出てきてもいいですか。終了時刻までには必ず戻ってきますんで」
先ほどのふくよかな女性に声をかけるとオーケーをもらえたので、悠太は近所を少し歩いてくることにした。
(谷本先生の教室だ、愛花を任せておいても何も心配はいらない)
悠太は近くの自販機でコーヒーを買うと、ゆっくり味わいながら歩き始めた。
「先生、相変わらずカワイイなぁ……」
子どもたちに笑顔で話しかける早紀の姿を思い出し、悠太は思わず声に出して呟いていた。
「それに……元気そうで、よかった」
そのまま歩き続けて土手に出ると、悠太は両腕を広げた。
多摩川を吹き抜けてくる夕刻の風を全身で受けとめる。
(五年も会っていなかったのに、全然そんな気はしなかったな)
悠太は何度か深呼吸をすると、『スマイル英会話教室』へ戻った。
「――もう! ほんっとーに驚いたんだから!」
授業が終わり、愛花と一緒に教室から出てきた早紀は悠太を軽く睨んでそう言った。
「すみません、なんか前もって言うのもなんか違うかなと思って」
「まぁ、その気持もわかるけど……体験レッスンの名簿を見たとき、保護者欄にはお父様のお名前が書いてあったから気付かなかったのよね。――愛花ちゃん、飲み込みが早いね。お兄ちゃん譲りかな」
早紀はそう言うと、視線を愛花に合わせるように腰を折り、少女の頭を優しく撫でた。
「……俺は全然飲み込み早くないっすよ……」
「え、そんなことないよ! 五年前、私思ってたよ? 中崎くんは頭の回転が速い子だって」
早紀はそう言って立ち上がると、悠太の目を正面から捉えた。
「……そ、そうかな……」
生まれて初めてかけられた言葉に、悠太は視線を逸らすとひたすら頭を掻いた。
「それにしても、中崎くん、背伸びたね。五年前は私よりちょっと高いくらいだったのに」
早紀は自分の頭にかざした手を悠太の頭に付けようと、つま先立ちになっている。
「あ、俺、高二の秋から急に伸びたんですよね」
そう言いながらふと横を見ると、体験レッスンに参加した二人の少女の母親たちが、早紀と話したそうにちらちらとこちらを見ていた。
「あ、他のお母さんたちが先生を待ってるみたいなんで、今日はここで……」
早紀は、あ、うんわかった、と言うと、愛花にバイバーイと手を振った。
悠太は唾をごくりと飲み込むと「先生」と呼び、小さな声で続けた。
「――もしよかったら、明後日の日曜、午後四時に会えませんか……あのときの河川敷で……」
早紀は一瞬目を大きく見開いたが、すぐにふっと目尻を下げ、手でオッケー印を作った。
日曜日――。
『スマイル英会話教室』は日曜日が休みだということを悠太は前もって調べていた。
午後四時にしたのは、五年前にあの河川敷で早紀が悠太に声をかけてくれた時刻だったからだ。
悠太は四時十五分ほど前に河川敷にやってきて、舗装された階段に腰掛けた。
リュックから青表紙の本――『嫌われる勇気』を取り出す。
栞が挟んであるページを開くと、『人は「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる』という一文が目に飛び込んできた。
「……懐かしいな」
悠太はフッと口元を緩ませた。
その時、「中崎くーん!」という明るい声が耳に届いた。振り向くと、レモンイエロー色のパンツ姿の早紀が自転車を止めているところだった。
「ごめんね、待った?」
「いえ、俺も今来たところです」
「――の割に、本読んでるね」
早紀はアハハッと白い歯を見せて笑った。
「あれ……それって、あの時も読んでなかったっけ?」
早紀が悠太の隣に腰を下ろそうとしたのを見計らって、悠太は「これ、使ってください」とハンカチを差し出した。
ありがとう、と言って早紀はハンカチを受け取ると、尻の下に敷いた。
「中崎くんがこんな風に気を遣ってくれるだなんて……時の流れを感じるわ」
早紀は悠太の顔を覗き込むようにして言った。
「――先生も」
「ん?」
「先生も、あの時と同じ色のズボン、履いてますね」
「……あ、気付いた? 気付かないかなーと思ったけど、さすが中崎くんだね」
早紀はエヘヘと笑うと、右手で髪を掻き上げた。
川から吹く風に乗り、甘くて爽やかな香りが悠太の鼻腔をくすぐる。
「――どうして……どうして五年前、突然塾に来なくなっちゃったんですか」
ずっと訊きたかったことを悠太は思い切って口にした。
「実は私、あの塾出身でね……」
早紀は膝を抱えていた両手を後ろに回して地面に付けると、顎を上げて空を見上げた。
「塾長にはすごくお世話になってね、塾長のおかげで希望の大学に入れたも同然なの」
悠太は四十代半ばとおぼしき塾長の、年齢の割に均整の取れた体型と切れ長の理知的な目を思い出す。
「私が教育に興味を持ったのも――あ、私ね、文学部教育学科を出ているの」
悠太は早紀の大学名は知っていたが学科は知らなかったため、そうなんですね、と相槌を打つ。
「教育学科に進もうと決めたのも、あの塾でお世話になった先生たちの影響が大きいと思う。本当は大学に入ってすぐにあの塾でアルバイトがしたかったのだけれど、英語講師の空きがなくってね。それで仕方なく他の塾で教えてた。英語以外なら、あの塾にも空きがあったんだけど、私、他の教科を教える自信がなくって……。四年生になって就活も終わった頃にやっとあの塾に英語講師の空きが出てね。それがあの時の夏期講習だったんだ」
(他の塾でずっと教えてたんだ……どうりで教え方が上手なはずだ)
悠太は密かにそう納得すると、黙って早紀の話に耳を傾ける。
「だけど……塾長の奥さんが、塾長と私の仲を疑ってね」
えっ、と悠太は早紀の顔を覗き込む。
「もちろん塾長と私はそんな仲じゃなかったよ。けど奥さんは疑ってた」
「……奥さんって、俺、会ったことあるかな」
「あるはずだよ。私が辞めた後に中崎くんのクラスを担当することになったはずだから」
えぇっ! と悠太は大きな声を上げた。
(あのおばさんが塾長の奥さんだったなんて……!)
眉間と口元に皺が深く刻まれた化粧っ気のない顔を悠太は思い出す。
「ひょっとして、あのおばさ――いや、塾長の奥さん、二人の仲を疑って、先生に嫌がらせをしていたとか……?」
早紀はちらっと悠太に視線を投げると、こくり頷いた。
「――そんな……だって奥さんの完全なる勘違いだったんでしょ?」
「うん。でもね、ああいうタイプの人は一度思い込むともうダメね。私を塾から追い出そうと必死だった。自分は授業を受け持っているわけでもないのに、しょっちゅうやって来ては隣の教室で私の授業を壁越しに聞いているの。で、授業後に『あなた、説明がヘタクソすぎるけど、本当に英検一級なの?』だの『あの言い方、生徒に色目使ってるんじゃないの?』だの……本当に辛かったわ」
悠太は『スマイル英会話教室』のホームページの講師プロフィールに『英検一級』と記載されていたのを思い出す。
(――先生は本当に優秀なんだな……いや、今重要なのはそこじゃない)
悠太はふと気になったことを口にした。
「――塾長には相談しなかったんですか」
「……したわ。だけど、塾長が奥さんを注意したことが、余計に事を荒らげてしまった。私を辞めさせて自分が代わりに講師をする。でなければ、離婚って言い出したそうなの」
「そんな……! そんなことって……」
「塾長には当時まだ小学生のお子さんが二人いてね。お子さんたちのためにも離婚はなんとしても避けたい……っていうことで、私が辞めるしかなかったの。まぁ、バイトだったしね」
「先生は……先生は何一つ悪くないのに、そんなの酷すぎますよっ!」
悠太はそう吐き捨てると、ペットボトルのキャップを捻り、水を喉に勢いよく流し込んだ。
早紀はフッと微笑むと、ありがとう、と呟いた。
「そんなふうに怒ってもらえると、なんか気分がスッとする。――授業を途中で投げ出すことになって中崎くんたちには申し訳ないと思ったのだけどね。私もまだ学生だったし、そうするしかなかったんだ……」
ふと悠太はあることを思い出し、リュックに手を突っ込む。
「――先生、これ一緒に食べません?」
「あ、ポテチ! いいね、私ポテチ大好き!」
『大好き』という響きに悠太の心臓は勝手に反応し、ドキドキ音を立て始める。
それを隠すかのように、わざと音を立てて袋を大きく開く。
「おいしー! 川辺でポテチ……なんか青春って感じ」
早紀はパリパリと音を立てながら頬を緩ませている。
「――五年前、ここで話したときにね……」
しばらくすると、早紀は再び口を開いた。
「私、中崎くんに居場所がどうのって偉そうなことを言っちゃった気がしていて……あんな事を言ったのに、自分がすぐに居場所を放棄しちゃったから、ずっと申し訳ないことしたなって思ってたんだ……」
口についたポテトチップスの油を手の甲で拭うと、悠太は幾度となく脳内で再生してきた早紀の言葉を思い出す。
――『きっと大事なのはさ……ここを自分の居場所にするんだって覚悟を決めることなんだよね……』
悠太は、いえ、と口に出すと言葉を継いだ。
「俺はあのときの先生の言葉にマジで救われました。あの言葉が背中を押してくれたから……あの家族が俺の居場所なんだって、覚悟を決めることができたんです」
早紀は、そう、と言ってふわり微笑んだ。
「愛花ちゃんと中崎くん、めっちゃ仲良しだもんね。愛花ちゃん、お兄ちゃんのことが好きで好きでたまらないって感じだったし」
「……そうっすか、ね」
悠太は頭を掻きながら、愛花の父親そっくりのくっきりとした二重の瞳と母親そっくりのふわふわのくせ毛を思い出す。
「中崎くんは、あれからどうしていたの? 今は、大学生? それとも――」
「今は大学四年です。青教大の経済学部です」
「……わぁ! 中崎くん、すごい! 青教大に進んだのね?」
青教大よりも早紀の出身大学の方が大学のランクは上だ。だが、早紀が嫌味でそう言っているのではなく、心からそう思ってくれているのが悠太には手に取るようにわかっていた。
「中崎くんは飲み込みが早かったもんね……。それで、卒業後の進路はもう決まっているの?」
「はい、一応内定はもらってます。知育玩具や絵本の制作、それから輸入販売をしている会社です」
「わぁ、内定おめでとう! ――知育玩具や絵本……どうしてその業界にしたの? やっぱり愛花ちゃんの存在があってっていうことかな?」
「そうですね。うちは両親共働きなんで、俺も愛花の面倒をみることがよくあって……遊びながら脳が育つおもちゃないかなぁって、よく店に見に行ったりネットで探したりしてたんです。そしたら、最近の幼児向け玩具って本当にすごいんですよね。そこから興味を持ったんです」
なるほどねー、と早紀は瞳をキラキラさせて悠太の話に耳を傾けている。
「その会社は英語の絵本を海外から輸入したりもしてるのかな?」
「はい、海外のメーカーと提携しているみたいです」
「そうなんだ……私も教室に絵本を置きたいなと思ってたんだよね」
「あ、それなら渋谷にうちの会社の店舗がありますよ」
『うちの会社』って、まだ就職したわけじゃないけど……と悠太は笑いながら付け足す。
「――今度、一緒に行ってみますか?」
深く考えずにそう言った瞬間、悠太はハッとした。
(今のって……デートに誘ってるみたいだったかな……)
慌てて何かを付け足そうと口をパクパクさせていると、早紀は、うん、ぜひ! と顔を輝かせた。
「なんか嬉しいな……。私ね、大学を出た後、教育系の出版社に就職したの。希望の業種に進めて張り切ってた。今度こそ、ここを自分の居場所にするんだって」
傾き始めた陽の光で橙色に変わりつつある多摩川を見ながら、早紀は続ける。
「だけどね、あの塾と同じようなことが起きたの……。女性の上司に嫌われて、とことんいじめられてね……。ストレスで片耳が聞こえづらくなってしまって、結局二年で退職したの」
悠太は黙って早紀の横顔を見つめている。
「自分の居場所なんて、どこにもないんじゃないかって、散々悩んだわ。世の中を恨めしくも思った。でもね、半年ほど家に引きこもっていたときに、ふと気が付いたの。私はいつも誰かから『ここに居ていいよ』って認めてもらうことしか考えてなかったって。私の人生の主役は私じゃなくて、いつだって『他人』だったのよ」
早紀の声がやや震えていることに気付いた悠太は、リュックからポケットティッシュを取り出すと早紀にそっと手渡す。愛花と出かけることがよくあるため、こういった物は常時持ち歩いているのだ。
「――ありがとう。優しいのね……。それでアメリカに留学したの。働いていたときに貯めていたお金を使ってね。向こうの人たちは、みんな本当に明るくてね。そして自己主張もしっかりするの。そんな環境にいたからかな、私も自分が本当にやりたいことをやっていこうって腹をくくることができたんだ」
「それが、英会話教室だったんですね」
早紀は頷くと、言葉を継いだ。
「自分の教室を開くとなると、どこか部屋を借りなきゃいけないし、責任も大きくなる。最初は不安だったわ。でも、誰かが用意した場所に『私はそこにふさわしい人間です』と申し出て、『そこに居てもよい』という許可をもらう生き方は、きっと私には向いていない。これまでの経験で痛感したわ。だから自分で自分の居場所を作り出すしかないって思ったの」
(――先生は五年前と変わらずカワイイ。だけどカワイイだけじゃない。あの頃よりも凛としていて……キレイだ……)
悠太は夕陽を受けた早紀の横顔にただただ見惚れていた。
「――先生は、本当にカッコイイです」
やっとの思いでそう言うと、早紀はありがとう、と髪を耳にかけながら小さく答えた。
「年下の男の子に『カッコイイ』なんて言われちゃうと、『もっといい女にならなきゃ!』ってモチベ上がるね」
えへへと笑いながらそう言うと、早紀はズボンのポケットからスマホを取り出し、画面をタップした。
「――連絡先、交換しよ」
悠太は、えっ?! と早紀の顔を凝視する。
「だってほら、渋谷の絵本のお店、一緒に行くんでしょ?」
そう言った直後、早紀は伏し目がちになりボソボソと付け加えた。
「――それともあれかな、彼女が……嫌がるとか……?」
「……! か、彼女なんて、いません!」
悠太は顔が熱くなるのを感じていたが、気取られまいとリュックに手を突っ込み、スマホを探しているふりをした。
「でも、いたこともあるでしょ?」
早紀の方をちらり窺うと、ただでさえ大きな瞳をくりくりさせて自分を見つめている。
「……い、いたこともあります。でも、半年前に振られました。他に好きな人ができたとかって」
悠太はそこでずっと気になっていたことを思い切って口にした。
「せ、先生こそ、彼氏とか……いるんじゃないですか」
悠太は早紀の顔を見ることができず、スマホをぎゅっと握った自分の両手を凝視している。
「ん……いたらさすがに中崎くんと二人では出かけられないかな」
甘い響きを伴う――少なくとも悠太にはそう感じられた――返事を耳にした瞬間、悠太は勢いよく顔を上げた。
早紀の頬は心なしか赤くなっているように見える。もしくは夕陽のせいか。
二人はスマホのアプリに相手の連絡先を登録し、メッセージをきちんと受け取れるか試しに送信し合うことにした。
ほどなくして、悠太のスマホ画面に『早紀です。よろしくお願いします』というメッセージが届いた。
『谷本』でもなく『谷本早紀』でもなく『早紀です』という文面に、悠太の心臓はぎゅっとなる。
悠太はすぐに『悠太です。こちらこそよろしくです』と返信する。
二人はどちらからともなく、えへへと笑い合った。
「――悠太くん、お腹空いてない? 駅前のファミレスでも行って、ご飯食べながら渋谷へ行く日決めない?」
『悠太くん』と呼ばれたことに一瞬舞い上がりそうになったが、「あ、いいっすね。――晩飯いらないって、母さんに連絡いれなきゃ」とスマホに目を落とした。
悠太は『今日、遅くなるから晩飯いらないよ。もう作っちゃってたら明日の朝食べるね』と美幸にメッセージを送りながら、早紀に「あの店のチーズハンバーグ、美味いですよね」と話しかける。
「やっぱりそう思う?」と微笑む早紀。
二人は立ち上がり、階段を登った。悠太は自転車を押す早紀の隣を歩く。
(自分で自分の居場所を生み出すのは本当にカッコイイことだ。誰にでもできることじゃない。だけど、いつか俺が……このとびきり可愛らしくてカッコイイ女性の居場所になれたらいいな……)
橙色に染まった多摩川を見つめながら、悠太はそっと願った。
その瞬間、居間からオギャーッという耳をつんざくような泣き声が聞こえてきて、悠太はまるで耳を塞ぐかのように慌ててドアをバタンと閉める。
まだ午前八時半だというのに容赦なく照りつけてくる太陽と、ミーンミーンと鳴り響く蝉の声に急き立てられるように、悠太は足早に塾へと向かう。
「……ったく、朝からギャーギャー、マジで勘弁してほしいよ」
真夏の陽光を受け、水面をきらきらと輝かせている多摩川を横目に、悠太はひとりごちる。
母、美幸は三ヶ月ほど前、41歳で愛花を出産した。聞けば、かなりの難産だったという。
「……もういい歳なのに、無茶をして……」
悠太は美幸と、美幸の新しい夫・高志の顔を思い浮かべると、地面に転がっていた大きめの石を誰もいない河川敷に向かって思い切り蹴りつけた。
***
実の父親が不倫相手を身ごもらせて家を出て行ったのは、悠太が五歳のときだった。それ以来、悠太は父親の顔を見ていない。
離婚後、美幸は中規模の精密機器製造会社に経理担当として就職した。高校で簿記の資格を取っておいてよかった、と美幸は事あるごとに口にしていた。その会社で美幸が出逢ったのが、中途採用で入社してきた理系出身の営業担当、中崎高志だった。
高志は男から見てもハッとするようなイケメンで、なぜバツイチ子持ちなうえ九歳も年上の美幸を伴侶に選んだのか、悠太は今でも不思議でならない。
美幸と高志は二年ほど交際を続け、悠太が高校に入学する直前の三月に籍を入れた。悠太が入学と同時に新しい姓を名乗ることができるようにと考えてのことだったらしい。
入籍と同時に、高志は美幸と悠太の住む小さなアパートに越してきた。約十年続いてきた母との二人暮らしは突然終わりを告げ、母は父親と呼ぶには若すぎるイケメンと同じ部屋で眠るようになった。薄い壁越しになにか物音がする度に、思春期真っ只中の少年はビクッとし、熟睡できない夜が続いたのだった。
三人暮らしが始まってほどなくして、悠太は美幸から『来年妹が産まれる』と聞かされた。家族が増えることがわかり、高志と美幸は『もっと広い部屋を探さないと』と不動産屋巡りを始めた。
そうして悠太が高一の冬に、現在住んでいる多摩川沿いの茶色い壁のマンションに越してきたのだった。
高志の会社――むろん、育児休業中の美幸が勤める会社でもあるのだが――では、社会を混乱の渦に陥れた疫病が契機となり、在宅ワークが導入された。騒動が落ち着いた後も、引き続き在宅ワークが認められているという。高志は在宅ワークを上手く利用し、妻子と接する時間を積極的に設けていた。
高志は優しく温厚な人物で、悠太も決して彼のことが嫌いなわけではない。美幸が彼に惹かれた気持ちもわかる気がしていた。
だが――父親としてすんなり受け入れられるかというと、それは別問題なのだった。
一学期の終業式を翌日に控えた高校二年生――ここでは悠太の通う『中の中ランクの公立高校』に限定しておこう――の休み時間の話題といえば、『夏休み、何する?』に尽きる。日々の義務から解放される喜びのエネルギーが教室中に充満しているのを悠太は感じていた。
「中崎は夏休み、どうするの? 旅行とか行くのか」
前の席の中井が振り返り、尋ねてきた。特に親しいわけではないのだが、ワイワイやっている他の生徒たちに感化されたのかもしれない。
「――特に何も。家で寝っ転がって一日中ゲームするか漫画読むかくらいかな」
『旅行なんて、乳飲み子を抱えて行けるはずもないし』という言葉は飲み込み、悠太は相手が一番喜びそうなセリフを口から吐き出した。母親が若いイケメンの子を高齢出産したことを世間に吹聴する必要はないだろう。
案の定、中井はウンウンと頷きながらこう返してきた。
「だよなー。外に出てもクソ暑いし、やっぱクーラーをガンガンに効かせて一日中ゲームに限るよな。でも新しいソフト買おうにも金ないしなー。 まったく、なんでバイト禁止されてるんだろうな」
中井は普段よりもかなり饒舌だ。これも『明日が終業式』という解放感がなせる技なのかもしれない。
正直なところ、悠太はゲームというものにほとんど興味がない。だが、級友との当たり障りのない会話を続けるのに必要不可欠なため、小遣いを貯めてゲーム機を買い、話題になっているソフトには一応手を付けるようにしていた。
「俺らみたいな帰宅部は、マジですることないよなー。あー、彼女でもいればなぁ……。とはいっても、金ないから彼女がいてもファミレスでダベるくらいしかできないけど。――って、中崎って彼女いたっけ?」
黙って首を横に振ると、中井は「だよな」とニキビ跡で赤くなっている頬を緩めた。
『だよな』とはどういう意味かと悠太は一瞬突っ込みたくなったが、面倒なのでやめておいた。
中井の言う通り、悠太は部活に入っていない。中学生の頃は「へたに部活に入ると道具類や遠征費などで金がかかるのではないか」と考え、帰宅部を選んだ。『部活動は必須だ』と教師から注意を受けたが、家庭の事情を話すとあっさり了承してくれた。
母の再婚により金の心配をする必要のなくなった高校生活では、なにか部活に入ろうと入学前は思っていた。
だが、実際にいくつかの部活を見学してみると、中学からの基礎がない自分にはどれもハードルが高そうに思えたし、なにより団体行動というものが悠太は苦手だった。やはりここでも教師から注意を受けたが、『家に生まれたての赤ん坊がいて、両親は共働きなんです』と話すと――実際にはまだ愛花は生まれていなかったのだが――帰宅部でいることをこれまたあっさり了承してくれたのだった。
ホームルームの時間になり担任教師が入ってくると、中井は「まぁ、お互い楽しもうな」と言って前へ向き直った。
担任がなにか話しているが、悠太の耳にはなにも入っこない。
そう。悠太はこのとき初めて気付いたのだ。
夏休みだというのに、部活もバイトもなく、デートする彼女も遊びに行く仲のいい友人もいない。
(――ということは、ずっと家で過ごすことになる……)
昼夜問わずギャーギャー泣き喚く愛花。
ミルクやりとオムツ交換に追われ、寝不足で死んだように横たわっている母。
在宅ワークの隙をみては、愛花に猫なで声で話しかけ、事あるごとに美幸に触れる高志――。
家族の姿を思い出した瞬間、悠太は思わず声に出していた。
「それだけは、絶対に、イヤだ……」
翌朝、制服に着替えた悠太は、高志が「行ってきます」と言って玄関のドアを開けるのを自室で確認してから、居間に顔を出した。
「悠太、おはよう。いつもより遅いんじゃない? パン、急いで焼くから食べてから行きなさいね。――お父さん、今日は出勤日らしくて、もう出たわよ」
悠太はトースターからまだ焼き目の付いていないパンを取り出すと、バターを塗りもせずに立ったまま水で胃に流し込み、一息に言った。
「母さん、俺、塾の夏期講習受けに行きたいんだけど」
母は、きょとんとした顔をしている。
それもそうだろう。これまで悠太は塾というものに通ったことがなく、そもそも「通いたい」という意思を母に見せたことがなかったのだから。
母と二人で暮らしていた頃、母が体に鞭打って仕事と家事を両立しているということは幼心にも分かっていた。
美幸の両親は香川県で飲食店を経営しており、上京して孫の面倒を看る余裕はなかった。
ひとりで必死に自分を育ててくれている母を近くで見ていた悠太としては、進学する高校は、塾に通わなくても受かりそうな公立――定期券代を抑えられる近場であれば、なお良い――であればどこでもよかった。折よく隣駅にぴったりな学校があったため、そこを選んだだけの話だった。
「塾? あらまぁ、珍しいわねぇ……わかったわ、お父さんが帰ってきたら相談してみる。――あらあら、おしめが濡れて気持ちが悪いのかしら……」
母は紙おむつとおしり拭きシートを手早く準備すると、泣き喚く愛花の元に駆け寄り、おむつの取り外しシールに手をかけた。
悠太は目を逸らすと、それじゃ行ってくる、と呟き足早に玄関へと向かった。
(これでよし、と……。終業式が終わったら、あの塾に夏期講習の説明を聞きに行こう。で、今夜にでもあの二人に資料を見せればいい)
悠太は、高志が自分の塾通いに反対するはずがないと踏んでいた。
そして、悠太の読みは正しかった。
***
「家にいたくない」という理由で塾に通うことを決めた悠太だったが、いざ通い始めてみると、それは決して悪いものではなかった。
悠太が選んだのは、最寄り駅のすぐ近くにある少人数制の集団指導塾だった。最近は個別指導型の塾が流行っているようだが、講師との距離が近くなりすぎる気がして、悠太は自分には合わないと考えたのだった。
悠太は終業式の翌日に早速、夏期講習のレベル分けテストを受けた。結果は4クラスあるうちの下から二番目。講習の期間は七月の第四週から八月いっぱいで、お盆の期間は休みとなる。午前九時から十二時まで授業で、午後は自習室を自由に使用して構わないということだった。お昼は弁当を持参している者が多かったが、悠太はコンビニで調達し、自習室で食べることにした。
塾というものに通ったことのなかった悠太は、「スパルタだったらどうしよう」と実は少し不安に感じていたのだが、蓋を開けてみれば程よく熱心、かつ程よく適当で、ほぼノンストレスな環境だった。
それに、朝から夕方までほぼ一年間同じ空間で過ごす高校の級友たちとは違い、塾のクラスメイトとの関係性は夏期講習期間に限定されていたため、実に気楽だった。気楽だったためか悠太にしては珍しく、すぐに一緒に寄り道する仲間ができた。
その日は水曜日で、午後四時まで自習室で過ごすと、悠太たちは塾の目と鼻の先にあるハンバーガーチェーン店に立ち寄った。
「――なぁ、谷本先生ってマジでいいよな」
フライドポテトの紙ケースを持ち上げ、底に残った欠片を豪快に口にザザーッと流し込むと、高田は突然なんの脈略もなしにそう言った。
「――ップ、なんだよ、高田は谷本先生狙いか?」
コーラを飲んでいる佐々木はゲップを堪えながら、そう問い返した。
「狙っているとかそんなんじゃないけさ、谷本先生の授業は純粋にモチベ上がるわ」
「確かに。俺、英語の成績だけ上がっちゃいそー」
「だよな。それになんつーか、『清楚系』って言葉を絵に描いたような人だよな。……あれでもう少し胸があったらマジで最高だったんだけど」
「おまっ、それひどっ! それに、贅沢すぎ!」
二人は声を上げて笑うと、ズズーッと音を立ててストローを啜った。
「なぁ、谷本先生って彼氏いるのかな?」
高田は若干声を潜めてそう言うと、残りのダブルチーズバーガーをすべて口に押し込んだ。
「そりゃあ、いるだろ。あんだけの美人に彼氏がいなかったら、この世の女子大生全員、独り身だろ。――なぁ、中崎はどう思う?」
佐々木は眼鏡を外すと、テーブルの上にあった紙ナプキンでゴシゴシとレンズを拭きながら、悠太の顔も見ずに突然話を振った。
「……どう思うって聞かれても……」
悠太は上手く返すことができず、固まってしまう。
谷本早紀は夏期講習で英語を担当している学生アルバイトで、悠太たちは月、水、金の週三回、彼女の授業を受けている。 噂によると、日吉と三田にキャンパスを有する超有名私立大学の四年生らしい。早紀はいつも髪を低い位置でひとつにまとめ、白い襟付きブラウスに黒のロングスカートを合わせていた。
「うーん……」
悠太は早紀のパッチリとした優しげな瞳とほっそりとした体つきを思い出し、ますます口ごもり、俯いてしまう。何か言おうと焦れば焦るほど、頬が勝手に熱くなるのを感じていた。
高田と佐々木は顔を見合わせると、二人して悠太の顔をまじまじと覗き込んだ。
「おっ?! おまえまさか……先生に惚れてるとか?!」
ただでさえ圧迫感のある高田の顔が眼の前に迫り、悠太は思わず椅子を後ろに引いた。
「……そ、そんなんじゃないけど……」
悠太の言葉とは裏腹に、頬はますます熱を帯びていく。
「いや、やめとけやめとけ! あんな賢いお嬢様が俺らレベルを相手にしてくれるわけねぇって!」
高田は悠太の肩にポテトの油が付いたままの手を置くと、真顔でそう言った。
「『俺らレベル』って……?」と訊ねたい気もしたが、面倒だったので悠太はそのまま聞き流すことにした。
翌日の木曜日、悠太はどうしても自習室で勉強を続ける気になれず、高田と佐々木に軽く挨拶をすると、午後二時頃に塾を後にした。
電車で隣駅まで行き、駅前のゲームセンターに入る。UFOキャッチャーで六百円を使ったが、何の景品もゲットできなかった。なんだか急に気持ちが萎えてしまい、悠太は早々に店を出る。
「大事な小遣いのうちの六百円を無駄に使ってしまった」という罪悪感と、前日、高田に言われた『俺らレベル』という一言が引っかかっていた。
悠太はなんとなく目に入った書店のドアをくぐる。一歩足を踏み入れた瞬間、冷気がサーッと汗ばんだ身体を吹き抜けていった。悠太は、冷たい空気の出所を見つけると、しばしそこに佇む。
「フゥーッ……」
深呼吸すると、悠太は本棚の間をゆっくりと歩き始めた。
思えば、書店という場所にはほとんど足を踏み入れたことがなかった。
家庭の経済状況を常に気にしてきた悠太にとって、本を買うということは贅沢な行為に思われた。もちろんお年玉などまとまった金額を時々母親は渡してくれてはいたが、それを本に使おうという気持ちにはなれなかった。
(谷本先生レベルの人は、こういうところに通って本を買うんだろうなぁ……)
新刊コーナーで書籍を手にとっている早紀の姿を想像した悠太は、自分も真似してみたい気持ちに駆られた。
「新刊コーナーはどこだろう」
キョロキョロしていると、『まだまだ話題作!』というポップが目に飛び込んできた。なんとなく近付き陳列されている書籍に目をやる。
一番目立つ場所に、『嫌われる勇気』という青い装丁の本があった。タイトルに惹きつけられた悠太は一冊手に取ると、パラパラとページをめくってみる。
(なるほど、この本は哲学者と青年の対話形式になっているのか……。会話文だし読みやすそうだな)
悠太は試しに序章の部分だけ読んでみることにした。すると、3ページ目に青年のこんな台詞があった。
『――しかし、大人になるにつれ、世界はその本性を現していきます。「お前はその程度の人間なのだ」という現実を嫌というほど見せつけられ、人生に待ち受けていたはずのあらゆる可能性が"不可能性"へと反転する――』
たかだが三行ほどの文に胸の奥をぎゅっと素手で掴まれた感覚がした悠太は、ポケットからスマホを取り出すと、近くの図書館で借りられないかを調べた。すると、『待機している人の数:83名』と表示された。
悠太はスマホをしまうと、本を手にまっすぐレジへと向かった。
再び電車に乗り自宅の最寄駅で下車した悠太は、駅前のハンバーガー店で購入したばかりの本を読もうと考えた。自宅で読もうとも思ったが、泣き喚く愛花の姿を思い浮かべた瞬間、その考えは消え去った。
しかし、ハンバーガー店の入口に高田と佐々木の姿を認めた悠太は踵を返し、多摩川の方へと歩き始めた。
自販機で缶コーヒーを買い、腰を掛けられそうな日陰を探す。
(確かあの辺りは高架下になっていて、日陰があったはず……)
悠太が目星をつけていたのは、コンクリートで階段状に舗装された河川敷だった。
(やっぱり日陰がある。しかも誰もいない)
悠太は弾むような足取りできれいに舗装された階段に近付き腰掛けると、白いトートバッグから購入したばかりの本を取り出した。
――どれだけの時間、そこにそうしていただろう。
「――バカヤローッ! ふざけんなーッ!」
そう叫ぶ声が耳に届き、悠太はビクッとして顔を上げた。
辺りを見回すと、50メートルほど離れたところで若い女性が川に向かって叫び続けているのが目に入った。
「マジでコロすッ! くたばっちまえ! くそババアーッッ!」
ピンク色のトップスにジーンズ姿のその女性は、ひたすら川に向かって罵詈雑言を喚き散らしている。
(……やばい感じだな。とりあえず、ここは離れないと……)
悠太は右手をトートバックに伸ばし、本を持ったままの左手で脇に置いてあったコーヒーの空き缶を掴もうとしたが、指が滑ってしまい、缶が派手な音を立てて階段を転げ落ちていった。
(――しまった!)
恐る恐る女性のいた方角に目をやると、女性はこちらに顔を向けていた。
(……あっ……!)
悠太は女性の顔を見て、その場に凍りつく。
――その人は、谷本早紀だった……。
悠太はどうしたらよいのかわからず、すばやく空き缶を拾うと階段を上り、歩道に出た。
「――ちょっ……待って……!」
早紀の声が聞こえたが、悠太はそのまま家までの道を脇目も振らず、全速力で走ったのだった――。
――翌日、金曜日。
本来であれば、この日は早紀による英語の授業があるはずだったが、「谷本先生はお休みなので、今日は私が授業を行います」と、急遽代打で中年の女性講師が授業を行うことになった。
「かわいそうな中崎くん、今日の楽しみがなくなっちまったな」
前の席の高田は、講師がホワイトボードの方を向いた瞬間を見計らって振り返ると、ニヤッと笑ってそう呟いた。
悠太は何も言わずに視線を泳がせると、バッグからペットボトルを取り出し、乱暴にキャップを捻った。
(なんで今日、先生は休んだんだろう……。やっぱり昨日のことがあったから? 生徒の俺に目撃されたのが気になって……とか?)
気付けば悠太は早紀のことばかり考えてしまい、この日はまったく授業に集中することができなかった。
授業に身の入らなかった悠太は、せめてもの罪滅ぼしとばかりに、夕方まで自習室でなんとか勉強を続けた。夏期講習の決して安いとは言えない費用のことを思えば、悠太にとっては当然の行動だった。
午後四時になると、悠太は高田と佐々木と塾の前で別れ、前日と同じ河川敷に向かうことにした。なんとなく、そこに行けば早紀に会えるのではないかと感じたからだった。
悠太は前日と同じ場所に腰を下ろすと、トートバッグから『嫌われる勇気』を取り出した。
(会えるかどうかわからないし、ひとまず昨日の続きを読んでいよう)
読書に没頭していると、ふいに背後から「中崎くん」という女の人の声がした。
振り返ると、そこには早紀がいた。普段塾で見る姿とは異なり髪はさらりと下ろしていて、黒のロングスカートの代わりにレモンイエローのパンツを履いている。上は塾でいつも着ている白の襟付きブラウスだ。
早紀は乗っていた白のスポーツ自転車をその場に止めると、「ここに来れば会えるかもしれないと思って……。よかった……。少しだけ隣、いいかな?」と尋ねた。
悠太がぎこちなく首を縦に振るのを認めると、早紀は階段を降りてきて、悠太の隣で膝を折ってしゃがみこんだ。
「……中崎くん、昨日はお見苦しいところをお見せしちゃって、本当にごめんなさいっ!」
早紀は頭を下げると、そのまま折り畳んだ膝に顔を埋めた。頬にかかる髪で、表情はまったく見えない。
「……いえ、そんな、気にしないでください」と悠太は小声で返す。
(……あぁ、なんて気の利かない返しなんだ……!)
悠太は、凡庸な自分に腹を立てていた。
「――ありがと……。本当は『塾では気取ってるくせに、なんて下品な女なんだ』と思ったでしょ?」
早紀は下を向いたままだ。
「そんなっ! げ、下品だなんて……そんなこと、思ってません!」
早紀に似つかわしくない自虐的な言葉に悠太が声を上げると、早紀はゆっくりと顔を上げた。
白い頬は赤く染まっている。
早紀は頬にかかる髪を耳にかけると、頬杖をついて悠太を見た。
「――ありがとう。中崎くん、優しいのね」
目尻にかけて緩やかなカーブを描く大きな瞳が悠太だけを見つめている。
(……カ、カワイイ……! 顔が……顔が燃えるように熱いっ! 俺、きっと真っ赤だよ……恥ずかしい!)
そう思いながらも、悠太は早紀から目を逸らすことができずにいた。それはまるで、魔法にかかっているかのような感覚だった。
しばし見つめ合ったあと、先に目を逸らしたのは早紀の方だった。
「……ちょっとむしゃくしゃしていて、どうしても叫ばずにはいられないことがあったの。だからといって、あれはちょっと酷すぎたね」
そう言うと、悠太が手にしている青い表紙の本に目を向けた。
「――ところでその本、そんなに面白いんだ?」
「えっ?」
「だってほら、ペットボトルにすっかり陽が射してる。好んで日向に水を置く人はいないでしょ? 長いことここで、その本に集中していたのかなぁって」
悠太はオレンジ色の光が射しているペットボトルに手を伸ばす。それはすっかりぬるくなっていた。
『嫌われる勇気』を読んでいたことを知られるのがなんとなく恥ずかしくて、悠太はタイトルが早紀に見えないよう気を付けながら本をリュックにしまった。
(次からは、ブックカバーを付けてもらおう……)
悠太がそんな風に思っていると、早紀がぼそっと呟いた。
「……それとも、私のこと待っていてくれたのかな……」
再び一瞬で耳まで真っ赤になった悠太の返事を待たず、早紀は言葉を継いだ。
「ごめんね」
「……えっ?」
悠太は反射的に早紀の顔を見る。
「今日私、塾を休んだから……中崎くん、自分のせいだと思っちゃったんじゃない?」
「……いえ、そんな……」
「出勤しようと思って着替えとメイクは済ませていたんだけどね……どうしても行く気になれなくって……。隣駅のカフェでサボってたんだ。悪い先生だよね」
早紀はそう言うと、ヘヘッと悠太に微笑みかけた。悠太はただただその笑顔に見惚れていた。
悠太が見ているのが自分の服だと勘違いした早紀は、「私、普段は自転車に乗るからスカートじゃなくてパンツばかりなの」と話し出した。
「塾で黒のスカートに履き替えてるんだ。『下は黒色のロングスカート、上は白色の襟付きブラウス着用』っていう謎の決まりがあってね」
「……そうなんですね」
塾での清楚な姿の早紀に憧れていたはずの悠太だったが……
(いつもの黒いスカートよりも今日の鮮やかな色のパンツの方が先生らしくて素敵だ)
そう感じていた。だがそんな言葉が口から出てくるはずもなかった。
そのとき、川の方からやや強めの風が吹いてきた。
「ここは本当に気持ちがいいね……。風に吹かれていると、イヤなことぜーんぶ忘れられる気がしてくる」
早紀はそう言うとゆっくりと立ち上がった。
「今日は会えてよかった。私の話、聞いてくれてありがとうね」
悠太は黙って早紀を見上げる。
早紀は階段を登り、近くに止めていた自転車のハンドルを握った。
そのとき――。
「先生っ!」
悠太は自然と大きな声を出していた。
早紀は悠太に再び視線を向ける。
「来週の月曜日、先生が授業してくれますよね?」
早紀は微笑むと、「もちろん!」と大きな声で答えたのだった――。
その日の晩、高田からスマホにメッセージが届いた。
『明後日の日曜日、暇だったらボーリングにでも行かねぇか。佐々木にも声かけるつもり』
週末は塾もなく、自室にこもるか近所をぶらつくしか予定のない悠太は『OK !』と返事を返した。
日曜日。ボーリング場を後にした三人は、近くのビルの地下にある安くて有名なファミレスへと向かった。
「やっぱ高二の夏はまだまだ気楽でいいよなぁ。来年の今頃、俺ら地獄だぜ」
入店してからまだ二十分ほどしか経っていないにもかかわらず、高田は自分たちのテーブルとドリンクバーの間を既に五往復はしていた。
「だよなぁー。……ップ、マジで永遠に高二でいたいよ」
佐々木はおそらく炭酸飲料があまり得意ではないのだろう。口に運ぶ度にゲップをしている。
「中崎はさ、どのへんの大学目指してる?」
高田に話を振られた悠太は、「……どのへんの大学?」とオウム返しをした。
「お前ってさ、俺らと違って真面目じゃん。宿題もいつもちゃんとやってくるしさ」
「ちょっ、高田! 『俺ら』って、俺をお前と一緒にすんなよ!」
佐々木が眼鏡の縁を持ち上げながら、猛抗議している。
悠太は自習室でいつも突っ伏して寝ている高田の姿を思い出す。家にいると母親から勉強しろと言われるので、塾に残っているのだという。
「夕飯前に帰るとさ、『お疲れ様―!』って笑顔で迎えてくれるんだよね。それが気分良くってさ」
高田は悪びれもせずにそう話していた。
高田は東急東横線沿線の私立高校、佐々木は東急多摩川線沿線の私立高校に通っている。高校を受験する際に私立への進学は一切考えていなかった悠太は、二人の学校名を聞いてもどれくらいのランクの学校なのかピンと来なかった。後でネット検索してみたところ、二人の高校は悠太の通う公立高校よりも偏差値が低かった。
「中崎、俺らよりも頭イイ学校に通ってるのに、なんで俺らと同じクラスなんだろな」
佐々木は唐揚げを口に放り込みながら、不思議そうに首を傾げている。
(――そんなの私立の方が授業の進度が速いからに決まってんだろ)
喉まで出かけた言葉を悠太はアイスコーヒーで無理やり胃に流し込む。
「まぁ、俺らレベルじゃ、行けてもそこそこの大学だよなぁ――そこへいくと谷本先生はカワイイし大学は慶明だし、マジで人生勝ち組だよなぁー」
高田の口から突然出た『谷本先生』という名前に、悠太の心臓は大きく跳ねる。
「俺らレベルじゃ、どうひっくり返ったって慶明大なんて入れないもんなぁー」
佐々木は頭の後ろに手をやると、大げさに天を仰いだ。
「谷本先生の彼氏ってさ、やっぱ慶明大生なんかな。くっそー、相手の男が羨ましい!」
「きっと頭が良いだけじゃなくてイケメンなんだろうな。どっちみち俺らじゃ無理だべ」
だよなー、と二人は大げさにため息をつくと、唐揚げに同時に手を伸ばした。
悠太も二人につられてひとつ取って口に入れた。
厚い衣が吸い込んだ古い油が口の中に広がっていく。
悠太はアイスコーヒーで口の中を洗い流すと財布から五百円玉を取り出しテーブルの上に置いた。
「わりぃ、俺、用事あるんだったわ。これで足りるよな?」
そう言うと、足早に店を後にした。
家に帰ると、母の美幸は台所で夕食の準備をしていた。ベビーベッドにちらり目をやると、愛花は四肢を広げてぐっすり眠っている。
自室で部屋着に着替えてベッドで横になっていると、「晩御飯できたわよ」という美幸の明るい声がした。
居間のドアを開けると、高志が冷蔵庫からビールを取り出していた。どうやら風呂から上がったばかりのようだ。
「お、悠太くん、おかえり」
「――ただいま」
食卓に目をやると、山盛りの唐揚げが並んでいる。
「今夜は悠太の好きな唐揚げよ」
美幸は悠太と高志が食卓につくのを見計らって、炊きたての白米を順々に差し出す。
「悠太くんは唐揚げにレモンかける派だっけ?」
高志がレモンを手に尋ねる。
「あ、どっちでもいいっす」
目も合わせずに答える悠太に、高志は「じゃあ、全体にはかけずにここに置いておくわ」と、器の端にレモンを置いた。
「悠太、夏期講習の調子はどう?」
美幸はそう言いながら、高志の隣に腰かける。
「別に……普通だよ」
悠太は眼の前の母に一瞬目をやってそう答えると、唐揚げに手を伸ばした。
カリッ、ジュワーッと、口の中で旨味が広がっていく。
「――今日ね、母親学級で知り合った和美さんから聞いたんだけど」
美幸は高志の方に少し首を傾けると、先ほどよりもやや高い声で話し始めた。
「近所に有名な幼児教室があるらしいのよ。なんでもゼロ歳から英語を習えるらしくて、そこに通っていた和美さんの姪っ子ちゃん、五歳でもうペラッペラなんですって! 愛花も通わせてみたらどうかと思うのだけど……高志さん、どう思う?」
高志は唐揚げを咀嚼しながら「幼児教室かぁ……まぁ、これからの時代は英語が喋れるに越したことないからなぁ」と腕を組んでいる。
悠太は黙々と唐揚げを口に運び続ける。
「よかった! じゃあ和美さんに紹介してもらって、今度見学に行ってくるわ」
美幸は正面に向き直ると、ようやく唐揚げに手を伸ばした。
「うん! 今日のも美味しく出来たわ。――悠太、どう? 美味しい?」
「――あぁ」
「『あぁ』って、ほんとに愛想のない子ねぇ」
美幸はそう呟くと、母親教室で出会った人たちの話をし始めた。
うんうんと頷きながら話に耳を傾けている高志。
――と、愛花が突然、大きな声で泣き始めた。
駆け寄って抱き上げる美幸。
「腹が減ったのかな――ミルクを用意しようか」
高志は箸を置いて、哺乳瓶を取りに行く。美幸は母乳があまり出る方ではないので、粉ミルクを利用することが多い。
「――ほら、適温に冷やしておいたよ」
美幸は差し出された哺乳瓶を受け取ると、愛花の口に近付けた。まるで磁石に吸い寄せられるように、愛花の口は哺乳瓶のちくびを的確に捉える。
「こうやって見ると、やっぱり高志さんによく似てるわね」
どれどれ、と愛花を覗き込む高志の口元は綻んでいる。
「食欲もあるし、よく眠るし、元気な子でよかったわ……高齢出産だったから、不安もあったけどね」
「……そうだな」
高志は美幸と愛花を優しく見つめている。
(――あれ……なんかこれ、脂っこいな)
口に入れたばかりの唐揚げに違和感を覚えた悠太は、麦茶でそれを胃に流し込む。
「ごちそうさま」
悠太はボソリ呟くと、椅子を引いて立ち上がる。
「――あら、悠太、あんまり食べてないんじゃない?」
「さっき友達と少し食べてきたから」
「……そう」
数秒、悠太に目をやっていた美幸は、再び愛花に視線を戻す。
「よちよち、たくさん飲んでいい子でちゅねー」
美幸が愛花を抱き起こし背中を優しく叩くと、やがてガポッという空気音が小さな口から吐き出された。
よく食べ、よく眠る愛花。
イケメンの父親に似ている愛花。
ゼロ歳から幼児教室に通わせてもらい、五歳で英語がペラッペラになる将来が約束されている愛花。
ふいに、高田が口にした『俺らレベル』、『人生勝ち組』という言葉が脳裏に浮かんだ。
(――愛花はきっと『人生勝ち組』なんだろうな)
悠太が居間のドアノブに手をかけた瞬間、「あ、そうだ、悠太」と美幸に呼び止められた。
「来週の日曜、みんなで外食しない? 赤ちゃん連れでもオッケーなイタリアンのお店、和美さんに教えてもらったの。本格的なピザ窯のあるお店だそうよ」
悠太が中学生の頃、『東急東横線沿線グルメ旅』というテレビ番組を母と一緒に見たことがある。若手お笑い芸人とアイドルの女の子が話題のレストランを紹介するという番組だった。二人が訪れたのは、イタリアで修行した日本人シェフが本格的なピザ窯で焼き上げるマルゲリータが大評判だというイタリアンレストランだった。アイドルの女の子が『こんなに美味しいピザ、食べたことないですぅー』とテカテカに光った唇を突き出してコメントしていたのが、今でも悠太の記憶に残っている。
『ピザなんて、パンの上にハムやチーズをちょこちょこっと置いて焼くだけでしょ。あれで千五百円もするだなんて、ぼったくりよねぇ。同じ金額を払うのなら、お刺身定食の方がいいわ』
あの時、美幸はたしかそう言っていたはずだ――。
「日曜だし、予約を入れておいた方がいいかもしれないわね」
「そうだな、後で電話しておくよ。ランチでいいよね?」
二人は愛花をベビーベッドに寝かせながらそう話している。
「――俺、行かないよ」
悠太は振り返らずに告げた。
「――えっ?」
背中に二人の視線を感じる。
「友達と会う約束してるから」
「友達って……学校の?」
「……どこの友達だっていいだろ!」
悠太は語気を強めた。ドアノブに置かれたままの手がじわり汗ばんでいる。
「……せっかく家族四人で楽しく過ごそうと思ってたのにィ……」
美幸の甘えた物言いが、少年の中で膨らむだけ膨らんだ黒い風船に針を刺した。
「……なにが『家族四人』だよ」
悠太はドアノブから手を離し、勢いよく振り返ると美幸の顔を睨み叫んだ。
「俺がいない方が、家族三人、水入らずで楽しめていいじゃねえかっ!」
美幸は呆気にとられているのか、口を開いたまま身じろぎもしない。
悠太は再び背を向けると、ドアノブに手をかける。
胸の中のマグマが今にも噴き出そうとグツグツいっている。唐揚げを飲み物で胃に流し込んだときのように、悠太はゴクリと唾液を飲みこむ。
だが、マグマは猛スピードで喉元まで上がってきた。
「――何が幼児教室だよ……俺が……俺がどれだけ今まで我慢してきたのか、知ってるのかよっ……! 幼児教室の前にもっと考えること、あるだろうがっ……!」
悠太はわざと派手な音を立ててドアを閉めた。
自室に入るとき、愛花の泣き声が耳に届いた気がした。
――翌日、月曜日。
悠太は誰にも会わないように早朝家を出ると、隣駅にある漫画喫茶で時間を潰した。
どうしても塾に行く気にはなれなかった。
『来週の月曜日、先生が授業してくれますよね?』
早紀にそう訊ねたくせに、自分が塾をサボってしまった。
(先生、今日塾来たかな……。俺がいなくて、心配したかな……いや、するわけないか)
夕方になると悠太は電車に乗り、先日早紀と話した河川敷へと向かっていた。
(先生がわざわざここに来るとは思えない。だけど、ひょっとしたらここは塾からの帰り道なのかもしれないし……)
悠太はレモンイエローのパンツ姿でスポーツ自転車にまたがる早紀の姿を思い出し、頬を緩めた。
階段に腰掛け、トートバッグから『嫌われる勇気』を取り出すと、栞を挟んでいたページを開く。青年と哲学者の会話もいよいよ終盤に差し掛かっていた。
『いったいどうすれば、自分には価値があると思えるようになるのか?』という問いに対する哲学者の答えを目にした瞬間、悠太は頭を殴られたような気がした。
『人は「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる』
(……『共同体』ってつまり……家族や仲間ってことだよな)
悠太は本を閉じ、夕方だというのにまだまだ明るい陽の光を浴びてキラキラ輝く水面に目をやった。
(俺は家族にとって有益じゃない……。それどころか、害悪だ)
悠太は自分の怒声に呆然としていた美幸の顔を思い出す。
(あの二人は俺のことをまったく考えていない訳じゃない。現にこうして夏期講習にも通わせてくれた……。なのに俺は……)
悠太は頭をクシャクシャっと掻き上げると立ち上がり、近くにあった石を力任せに川に向かって投げた。
(……どんな顔をして家に帰ったらいいんだ……)
大きく嘆息したそのとき、「中崎くーん!」という声が背後から飛んできた。
振り向くと、そこには自転車を手で押している早紀の姿があった。
「――先生……」
「大丈夫? ひょっとしたら、ここかなと思って……。来てみてよかったわ」
早紀は階段に腰掛けると、悠太に手招きをした。今日はスカイブルー色のパンツを履いている。
「何かあった? 私でよければ、話聞くよ?」
柔らかな視線に促されるように、悠太は早紀の隣に腰を下ろすと口を開いた。
「――先生、すみませんでした。月曜日に来てくださいって言っておいて、俺がサボってしまいました」
早紀は、いいのよそんなこと、と小さく答える。
悠太はどこから話していいのかわからず、二人の間にしばし沈黙が流れた。
川面を撫でてから河川敷に吹き寄せる風が、早紀のセミロングの髪を揺らしている。
「あー、気持ちいいねー!」
早紀は両腕で膝を抱え、空を見ている。
悠太はそんな早紀にちらり目をやった。
(塾で髪をひとつにまとめている先生も清楚でカワイイけれど、こうして髪を風になびかせている先生の方が、なんか先生らしくて好きだな。――って俺、なに考えてるんだよ!)
「――中崎くん?」
ひとりで赤くなっている悠太の顔を早紀は覗き込む。
「大丈夫? 熱中症になったら大変! 水、持ってる?」
「――だ、大丈夫です! 水はほら、ここにありますし」
悠太はペットボトルのキャップを捻ると、喉を鳴らして水を飲んだ。
そして、ふぅっと息をひとつ吐くと、前の日の晩、家であったことを語り始めたのだった――。
「――そっかぁ……」
早紀は立ち上がると川面を見つめて言った。
「中崎くんのお母さん、今は新しい旦那さんとの関係を固めるのに必死なんじゃないかな」
「……えっ?」
「私にはまだ子供がいないから、想像でしか言えないのだけれど……お母さんは離婚されたことで、誰よりも大切なあなたに苦労をかけてしまったと悩んでいたんじゃないかな。新しいパートナーが見つかってお子さんができた。けれど、また夫婦関係で失敗してしまったら、あなたをいつまでたっても幸せにできない。だからまずは、旦那さんとの関係を固めようとされている。言い換えれば、あなたとの関係は旦那さんとの関係よりもずっとずーっと強固なものなのよ。壊れるはずがないってお母さんは安心しているの。あなたを信じて、あなたに甘えているのかもしれないわね」
早紀はそう言うと、振り返って悠太に微笑みかけた。
「ずっと苦労されてきたお母さんを、甘えさせてあげるっていうのはどうかな……。それってすっごくカッコよくない?」
「……お、俺……母さんに酷いことを……」
俯いた悠太の頬を涙が伝う。
「大丈夫! 言ったでしょ? お母さんはあなたのことを誰よりも信じているの。そんな一時の感情に任せて出た言葉くらいで、二人の絆が壊れるわけがないわ!」
悠太は立てた膝に顔を突っ伏して泣いた。
――どれだけの間、そうしていただろう。
顔を上げると、陽は傾き始めていた。
早紀は変わらず自分に背を向け、川面を見つめている。
悠太はトートバッグからティッシュを取り出すと、思い切り鼻をかんだ。
それに気付いた早紀は、再び口を開く。
「――人生ってさ、自分の居場所を求め続ける旅みたいだよね……」
悠太は黙って耳を傾ける。
「きっと大事なのはさ……ここを自分の居場所にするんだって覚悟を決めることなんだよね……」
そう言った声が少し震えているような気がしたが、悠太から早紀の表情は見えない。
「ここを自分の居場所にするんだっていう覚悟……」
悠太は早紀の言葉をただ繰り返す。
やがて早紀は振り返り「遅くなっちゃったね。そろそろ帰ろうか」と明るい声を出した。
だが、逆光のせいで悠太には早紀の表情は見えなかった――。
その晩、悠太が玄関のドアを開けると、キッチンから「おかえりー」という美幸の声が聞こえてきた。
悠太は一瞬廊下で立ち止まると、早紀の優しい笑顔を頭に思い描く。そして、『ここを自分の居場所にするんだっていう覚悟』と小さく呟くと、居間のドアを開けた。
「……ただいま」
「おぉ、悠太くん、今日もお疲れさま。お先に一杯やっていたよ」
高志はビールグラスを片手に微笑んでいる。
「悠太、すぐにご飯だから手を洗ってきちゃいなさい」
美幸はトマトを切りながらそう言った。
「――その前に……」
悠太はバッグを肩から下ろすと一息に言った。
「昨日は酷いことを言って、ごめんなさい……。俺、本当はあんなこと言うつもりなかったんだ……」
そう言って頭を下げると、目の奥がツーンとしてきた。やばい、泣きそう、と思ったときには既に遅かった。
「……母さんには幸せになってもらいたいと思ってるし、高志さんがいい人だってこともわかってる。なのに……心がついていかないんだ……ゴメン」
立ち尽くしたまま流れる涙を手の甲で拭っていると、手の平がそっと肩に置かれたのがわかった。それは、とても大きくて温かかった。
「悠太くん……つらい思いをさせてしまって、本当にすまない。僕の配慮が足りなかった」
そんなことないです、と悠太は首を横に振る。
「正直言うとね――」
高志は悠太の肩を抱き、居間のソファーに座るよう促す。
「僕はね、悠太くんの正直な気持ちに触れることができて、よかったと思ってる」
えっ、と顔を上げる悠太。
「だって僕らは家族なんだから。いや、この際、綺麗事はよそう。『家族になりつつある』んだからさ、なんでも腹割って話そうよ……。時間をかけて、家族になっていこう」
眼鏡の奥の高志の瞳は、少し潤んでいるように見えた。
「――はい……!」
悠太はそんな高志の瞳をしっかりと見つめ返して答える。
「――もう、悠太ったらびっくりさせるんだから……」
夫と息子の様子を台所から見守っていた美幸が、バラ柄のエプロンで手を拭きながら悠太に近付く。
「悠太、ごめんね……。悠太はいつでも母さんの味方でいてくれるからって、甘え過ぎてたね……。あなたは私の大切な大切な息子よ。死ぬまでこれは、絶対に変わらない」
美幸はそう言って、涙で濡れた悠太の手を両手でしっかりと握った。
「……ゆっくり……ゆっくりやっていこう。私も、もっと悠太のことをちゃんと見ていくから。悠太も母さんのことをこれからも見ていてほしい」
悠太は自分の手を握っている母親の手を見つめた。
シミがぽつぽつと出始めていて、少し皺の寄った小さな手――。
「……うん、わかった」
悠太と美幸は互いに鼻をグズグズ鳴らしながら、笑い合った。
***
――五年後。
「そんじゃ、行ってくるわ。――ほら愛花、帽子をかぶらないと」
悠太は小さな頭に麦わら帽子をかぶせると、玄関先の姿見に自分を映し、髪を軽く掻き上げた。
「悠太、よろしく頼むわね。――愛ちゃん、今日はママ一緒に行けないから、お兄ちゃんの言うことをよーく聞くのよ」
「うん、わかった!」
悠太は愛花の手を引きながら玄関のドアを開けた。
もう夕方だというのに、空気は相変わらずむわっと湿り気を帯びている。
「愛花、どんな先生か、楽しみだな」
「うん、楽しみー!」
二人は多摩川沿いの土手を手を繋いで歩く。
ここを歩くと英会話教室までは少し遠回りなのだが、愛花は外に出ると決まって「川、通ってこうよー」と言う。
真夏の日差しを受けてキラキラ輝く水面は、否応なしに悠太に谷本早紀のことを思い出させる。
(あれからちょうど五年かぁ……)
高二の夏、悠太が早紀の姿を見たのは、悠太が家族と和解した日――あれは八月初旬の月曜日だった――の翌々日、水曜日の授業が最後だった。
金曜日からは、以前に一度、早紀の代理を務めた中年女性講師が悠太のクラスの正式な英語担当となった。
「マジでモチベ上がんねー」
前の席だった高田はしょっちゅう悠太の方を振り向いては、そうこぼしていたのだった。
夏期講習の全日程が終わると、悠太は近くの個別指導塾に移ることにした。もちろん両親の同意あってのことだ。あの日、悠太が叫んだ『幼児教室の前にもっと考えること、あるだろうがっ……!』という言葉が響いたのか、両親は愛花の英才教育よりも目の前の息子の大学受験を優先することに決めたのだった。
集団指導から個別指導に変えたのは、高田や佐々木のような『経済的に恵まれているからとりあえず塾通いしているけれど、やる気はゼロ』タイプの人間と距離を取りたかったからだ。事あるごとに『俺らレベル』と十把一絡げにされるのも、たまらなく嫌だった。
個別指導塾は悠太に合っていたようで、成績は右肩上がりで伸び続けた。
そして高校を卒業した翌月、悠太は『GMARCH』と称される都内の有名私立大学の門をくぐったのだった。
地方の国公立を目指したらどうか、と塾の講師からは勧められたが、悠太はあえて自宅から通える大学を選んだ。
(一人暮らしをしてしまったら、帰省する度に家族に対して違和感を覚えるのは目に見えている。あの人たちと家族になる覚悟を決めよう)
悠太はそう決意したのだった――。
時は流れ、悠太は大学四年になった。
愛花は五歳になり、あたりまえだがすっかり意思疎通ができるようになった。ころころ変わる表情を見ているだけで、悠太の口角は自然と上がる。
「愛花、暑くないか? 少し水分補給しよう」
悠太は立ち止まりリュックから子供用のドリンクを取り出すと、キャップを開けて少女に手渡す。
愛花はこめかみに汗をにじませながら、ゴクゴクと喉を鳴らしている。
「さぁ、あともう少しで着くぞ」
ドリンクをリュックにしまうと、悠太は再び小さな手を取った。
大学三年の夏から始めた就職活動だったが、悠太はつい二ヶ月ほど前に無事内定をもらっていた。
母の美幸は息子が無事社会人になることに安堵したのか、ある日の夕食の席で「悠太も落ち着いたことだし、そろそろ愛ちゃんに英会話を習わせたい」と言い出した。
食事が終わると高志はダイニングテーブルにノート型パソコンを置き、早速良さそうな英会話教室を探し始めた。
「ここはどうだろう。駅前だし、悪くなさそうだ。――悠太、ちょっと見てくれる? こういうのは若い人の感覚で見てもらった方がいいかもしれない」
声をかけられた悠太は高志のパソコンを覗き込む。そこには『スマイル英会話教室』という大きな文字が踊っていた。
「ここに座って、見てくれていいよ。俺はあっちに座っとくから」
高志はそう言ってソファーを指差した。悠太は高志が座っていた椅子に腰掛けじっくりとサイトを見始める。比較検討するために、似たような教室のサイトもいくつか開いてみることにした。
「場所も近いし費用も平均的だけど、肝心なのはどんな人が教えているかだよな。えーっと、プロフィール欄はどこだ――? あ、あった!」
そう独りごちながら、カーソルを『講師プロフィール』に合わせクリックする。
(――え……?)
悠太の目に飛び込んできたのは、五年前に会ったきりの谷本早紀の笑顔だった。
(……た、谷本先生っっ?!)
髪色が明るくなっているとはいえ、そこにいる早紀は五年前に河川敷で話したときの彼女となんら変わりはないように悠太には思えた。
(どうして先生が子供の英会話教室を……? あ、でも先生、英語担当だったし不思議ではないか……)
微動だにせず画面を呆然と見つめる悠太。
「悠太、どう思った? 他にいいところがあれば、そっちでもいいのだけど」
高志の声が耳に届き、悠太はハッと我に返る。
「――こ、ここでいいんじゃないかな……」
悠太はそう言って立ち上がると冷蔵庫から麦茶を取り出した。コップに注ぎ、一気に喉に流し込むと、プハーッと大きく息を吐く。
「そうか、じゃあ早速、体験レッスンを申し込もうか」
高志の言葉に、悠太の胸はドクンと音を立てる。
(ひょっとしたら……また先生に会えるかもしれない……)
「父さん、体験教室には俺が行ってもいいかな」
気付くと悠太はそう口にしていた。
「え……もちろんいいけど、急にどうしたんだい?」
「――ほら、子供向けの英会話教室って、きっと英語の知育玩具とか絵本とか色々置いてあると思うんだよね。来年からの俺の仕事とも無関係じゃないっつーか……」
悠太が言い淀んでいると、高志はニコリと微笑み「わかった、任せるよ」と言ったのだった。
土手から住宅街に入ると、悠太はスマホを片手に『スマイル英会話教室』を探す。
(――この建物の三階か)
建物の入口で部屋番号を押すとすぐに「はい」という女性の声がした。
「五時に体験レッスンを予約している中崎ですが……」というと、「どうぞ三階の301にいらしてください」と言われた。
(今のは谷本先生……ではないな。声がちょっと違う気がする……)
教室のドアを開けると、五十代とおぼしきふくよかな女性が笑顔で迎えてくれた。
「中崎愛花さんですね。お待ちしておりました。体験レッスンは十分後に始まりますので、あちらの教室でお待ち下さい。お手洗いは廊下の突きあたり右側にございますので」
「……あの、私はどこにいたらよいのでしょうか」
「保護者の方は教室の後ろに椅子を用意してございますので、そちらに掛けていただいても結構ですし、こうして廊下の窓越しに見学していただくこともできますよ」
悠太が愛花の手を引いて教室に入ると、他にはまだ誰もいなかった。
開始時刻が近付くと、愛花と同年齢くらいの女の子が二人入ってきた。どうやら今日の体験レッスンは三名で行うらしい。
悠太は他の母親たちと同様、後ろに用意されている椅子に腰を掛けた。
五時になると、谷本早紀が姿を現した。
ホームページで見るよりも髪は明るい茶色に染められており、肌も五年前に比べると少しばかり焼けていた。細身のスタイルはまったく変わっておらず、白いTシャツとスキニーパンツがよく似合っていた。
“Hi! everybody! Welcome to Smile English conversation class! I’m so glad to see you !”
(みんな、こんにちは! 『スマイル英会話教室』へようこそ! みんなに会えて嬉しいです)
早紀は流暢な英語で子どもたちに話しかける。
だが、少女たちは一様にポカンとした顔をしている。
「みんな、こんにちは! 私は早紀先生です。今日はね、ウサギのミミーと一緒にみんなに会いにきました。一緒に“Mimi! Come here!”『ミミー、こっちにおいで!』って呼んでみようか。せーの!」
“Mimi! Come here!”
comeの意味もhereの意味も知らないはずの愛花だが、早紀とまったく同じ発音でミミーを呼んでいる。
(……愛花って、ひょっとしたら英語の才能があるのかも……?!)
そんな思いが一瞬悠太の頭をよぎる。
(……あ、これがいわゆる親ばかってやつか……親じゃないけど)
悠太は思わず鼻を鳴らしてフッと笑ってしまった。
――その瞬間。
うさぎのパペットを左手にはめた早紀と目がバチッと合ってしまった。
早紀は呆然とし、動けないでいる。
悠太は軽く頭を下げると素早く荷物を手にし、ドアから外に出てトイレへ向かった。
しばらくして教室の前に戻ってくると、ミミーになりきった早紀の流暢な英語が教室の外まで響いていた。
「すみません、ちょっと出てきてもいいですか。終了時刻までには必ず戻ってきますんで」
先ほどのふくよかな女性に声をかけるとオーケーをもらえたので、悠太は近所を少し歩いてくることにした。
(谷本先生の教室だ、愛花を任せておいても何も心配はいらない)
悠太は近くの自販機でコーヒーを買うと、ゆっくり味わいながら歩き始めた。
「先生、相変わらずカワイイなぁ……」
子どもたちに笑顔で話しかける早紀の姿を思い出し、悠太は思わず声に出して呟いていた。
「それに……元気そうで、よかった」
そのまま歩き続けて土手に出ると、悠太は両腕を広げた。
多摩川を吹き抜けてくる夕刻の風を全身で受けとめる。
(五年も会っていなかったのに、全然そんな気はしなかったな)
悠太は何度か深呼吸をすると、『スマイル英会話教室』へ戻った。
「――もう! ほんっとーに驚いたんだから!」
授業が終わり、愛花と一緒に教室から出てきた早紀は悠太を軽く睨んでそう言った。
「すみません、なんか前もって言うのもなんか違うかなと思って」
「まぁ、その気持もわかるけど……体験レッスンの名簿を見たとき、保護者欄にはお父様のお名前が書いてあったから気付かなかったのよね。――愛花ちゃん、飲み込みが早いね。お兄ちゃん譲りかな」
早紀はそう言うと、視線を愛花に合わせるように腰を折り、少女の頭を優しく撫でた。
「……俺は全然飲み込み早くないっすよ……」
「え、そんなことないよ! 五年前、私思ってたよ? 中崎くんは頭の回転が速い子だって」
早紀はそう言って立ち上がると、悠太の目を正面から捉えた。
「……そ、そうかな……」
生まれて初めてかけられた言葉に、悠太は視線を逸らすとひたすら頭を掻いた。
「それにしても、中崎くん、背伸びたね。五年前は私よりちょっと高いくらいだったのに」
早紀は自分の頭にかざした手を悠太の頭に付けようと、つま先立ちになっている。
「あ、俺、高二の秋から急に伸びたんですよね」
そう言いながらふと横を見ると、体験レッスンに参加した二人の少女の母親たちが、早紀と話したそうにちらちらとこちらを見ていた。
「あ、他のお母さんたちが先生を待ってるみたいなんで、今日はここで……」
早紀は、あ、うんわかった、と言うと、愛花にバイバーイと手を振った。
悠太は唾をごくりと飲み込むと「先生」と呼び、小さな声で続けた。
「――もしよかったら、明後日の日曜、午後四時に会えませんか……あのときの河川敷で……」
早紀は一瞬目を大きく見開いたが、すぐにふっと目尻を下げ、手でオッケー印を作った。
日曜日――。
『スマイル英会話教室』は日曜日が休みだということを悠太は前もって調べていた。
午後四時にしたのは、五年前にあの河川敷で早紀が悠太に声をかけてくれた時刻だったからだ。
悠太は四時十五分ほど前に河川敷にやってきて、舗装された階段に腰掛けた。
リュックから青表紙の本――『嫌われる勇気』を取り出す。
栞が挟んであるページを開くと、『人は「わたしは共同体にとって有益なのだ」と思えたときにこそ、自らの価値を実感できる』という一文が目に飛び込んできた。
「……懐かしいな」
悠太はフッと口元を緩ませた。
その時、「中崎くーん!」という明るい声が耳に届いた。振り向くと、レモンイエロー色のパンツ姿の早紀が自転車を止めているところだった。
「ごめんね、待った?」
「いえ、俺も今来たところです」
「――の割に、本読んでるね」
早紀はアハハッと白い歯を見せて笑った。
「あれ……それって、あの時も読んでなかったっけ?」
早紀が悠太の隣に腰を下ろそうとしたのを見計らって、悠太は「これ、使ってください」とハンカチを差し出した。
ありがとう、と言って早紀はハンカチを受け取ると、尻の下に敷いた。
「中崎くんがこんな風に気を遣ってくれるだなんて……時の流れを感じるわ」
早紀は悠太の顔を覗き込むようにして言った。
「――先生も」
「ん?」
「先生も、あの時と同じ色のズボン、履いてますね」
「……あ、気付いた? 気付かないかなーと思ったけど、さすが中崎くんだね」
早紀はエヘヘと笑うと、右手で髪を掻き上げた。
川から吹く風に乗り、甘くて爽やかな香りが悠太の鼻腔をくすぐる。
「――どうして……どうして五年前、突然塾に来なくなっちゃったんですか」
ずっと訊きたかったことを悠太は思い切って口にした。
「実は私、あの塾出身でね……」
早紀は膝を抱えていた両手を後ろに回して地面に付けると、顎を上げて空を見上げた。
「塾長にはすごくお世話になってね、塾長のおかげで希望の大学に入れたも同然なの」
悠太は四十代半ばとおぼしき塾長の、年齢の割に均整の取れた体型と切れ長の理知的な目を思い出す。
「私が教育に興味を持ったのも――あ、私ね、文学部教育学科を出ているの」
悠太は早紀の大学名は知っていたが学科は知らなかったため、そうなんですね、と相槌を打つ。
「教育学科に進もうと決めたのも、あの塾でお世話になった先生たちの影響が大きいと思う。本当は大学に入ってすぐにあの塾でアルバイトがしたかったのだけれど、英語講師の空きがなくってね。それで仕方なく他の塾で教えてた。英語以外なら、あの塾にも空きがあったんだけど、私、他の教科を教える自信がなくって……。四年生になって就活も終わった頃にやっとあの塾に英語講師の空きが出てね。それがあの時の夏期講習だったんだ」
(他の塾でずっと教えてたんだ……どうりで教え方が上手なはずだ)
悠太は密かにそう納得すると、黙って早紀の話に耳を傾ける。
「だけど……塾長の奥さんが、塾長と私の仲を疑ってね」
えっ、と悠太は早紀の顔を覗き込む。
「もちろん塾長と私はそんな仲じゃなかったよ。けど奥さんは疑ってた」
「……奥さんって、俺、会ったことあるかな」
「あるはずだよ。私が辞めた後に中崎くんのクラスを担当することになったはずだから」
えぇっ! と悠太は大きな声を上げた。
(あのおばさんが塾長の奥さんだったなんて……!)
眉間と口元に皺が深く刻まれた化粧っ気のない顔を悠太は思い出す。
「ひょっとして、あのおばさ――いや、塾長の奥さん、二人の仲を疑って、先生に嫌がらせをしていたとか……?」
早紀はちらっと悠太に視線を投げると、こくり頷いた。
「――そんな……だって奥さんの完全なる勘違いだったんでしょ?」
「うん。でもね、ああいうタイプの人は一度思い込むともうダメね。私を塾から追い出そうと必死だった。自分は授業を受け持っているわけでもないのに、しょっちゅうやって来ては隣の教室で私の授業を壁越しに聞いているの。で、授業後に『あなた、説明がヘタクソすぎるけど、本当に英検一級なの?』だの『あの言い方、生徒に色目使ってるんじゃないの?』だの……本当に辛かったわ」
悠太は『スマイル英会話教室』のホームページの講師プロフィールに『英検一級』と記載されていたのを思い出す。
(――先生は本当に優秀なんだな……いや、今重要なのはそこじゃない)
悠太はふと気になったことを口にした。
「――塾長には相談しなかったんですか」
「……したわ。だけど、塾長が奥さんを注意したことが、余計に事を荒らげてしまった。私を辞めさせて自分が代わりに講師をする。でなければ、離婚って言い出したそうなの」
「そんな……! そんなことって……」
「塾長には当時まだ小学生のお子さんが二人いてね。お子さんたちのためにも離婚はなんとしても避けたい……っていうことで、私が辞めるしかなかったの。まぁ、バイトだったしね」
「先生は……先生は何一つ悪くないのに、そんなの酷すぎますよっ!」
悠太はそう吐き捨てると、ペットボトルのキャップを捻り、水を喉に勢いよく流し込んだ。
早紀はフッと微笑むと、ありがとう、と呟いた。
「そんなふうに怒ってもらえると、なんか気分がスッとする。――授業を途中で投げ出すことになって中崎くんたちには申し訳ないと思ったのだけどね。私もまだ学生だったし、そうするしかなかったんだ……」
ふと悠太はあることを思い出し、リュックに手を突っ込む。
「――先生、これ一緒に食べません?」
「あ、ポテチ! いいね、私ポテチ大好き!」
『大好き』という響きに悠太の心臓は勝手に反応し、ドキドキ音を立て始める。
それを隠すかのように、わざと音を立てて袋を大きく開く。
「おいしー! 川辺でポテチ……なんか青春って感じ」
早紀はパリパリと音を立てながら頬を緩ませている。
「――五年前、ここで話したときにね……」
しばらくすると、早紀は再び口を開いた。
「私、中崎くんに居場所がどうのって偉そうなことを言っちゃった気がしていて……あんな事を言ったのに、自分がすぐに居場所を放棄しちゃったから、ずっと申し訳ないことしたなって思ってたんだ……」
口についたポテトチップスの油を手の甲で拭うと、悠太は幾度となく脳内で再生してきた早紀の言葉を思い出す。
――『きっと大事なのはさ……ここを自分の居場所にするんだって覚悟を決めることなんだよね……』
悠太は、いえ、と口に出すと言葉を継いだ。
「俺はあのときの先生の言葉にマジで救われました。あの言葉が背中を押してくれたから……あの家族が俺の居場所なんだって、覚悟を決めることができたんです」
早紀は、そう、と言ってふわり微笑んだ。
「愛花ちゃんと中崎くん、めっちゃ仲良しだもんね。愛花ちゃん、お兄ちゃんのことが好きで好きでたまらないって感じだったし」
「……そうっすか、ね」
悠太は頭を掻きながら、愛花の父親そっくりのくっきりとした二重の瞳と母親そっくりのふわふわのくせ毛を思い出す。
「中崎くんは、あれからどうしていたの? 今は、大学生? それとも――」
「今は大学四年です。青教大の経済学部です」
「……わぁ! 中崎くん、すごい! 青教大に進んだのね?」
青教大よりも早紀の出身大学の方が大学のランクは上だ。だが、早紀が嫌味でそう言っているのではなく、心からそう思ってくれているのが悠太には手に取るようにわかっていた。
「中崎くんは飲み込みが早かったもんね……。それで、卒業後の進路はもう決まっているの?」
「はい、一応内定はもらってます。知育玩具や絵本の制作、それから輸入販売をしている会社です」
「わぁ、内定おめでとう! ――知育玩具や絵本……どうしてその業界にしたの? やっぱり愛花ちゃんの存在があってっていうことかな?」
「そうですね。うちは両親共働きなんで、俺も愛花の面倒をみることがよくあって……遊びながら脳が育つおもちゃないかなぁって、よく店に見に行ったりネットで探したりしてたんです。そしたら、最近の幼児向け玩具って本当にすごいんですよね。そこから興味を持ったんです」
なるほどねー、と早紀は瞳をキラキラさせて悠太の話に耳を傾けている。
「その会社は英語の絵本を海外から輸入したりもしてるのかな?」
「はい、海外のメーカーと提携しているみたいです」
「そうなんだ……私も教室に絵本を置きたいなと思ってたんだよね」
「あ、それなら渋谷にうちの会社の店舗がありますよ」
『うちの会社』って、まだ就職したわけじゃないけど……と悠太は笑いながら付け足す。
「――今度、一緒に行ってみますか?」
深く考えずにそう言った瞬間、悠太はハッとした。
(今のって……デートに誘ってるみたいだったかな……)
慌てて何かを付け足そうと口をパクパクさせていると、早紀は、うん、ぜひ! と顔を輝かせた。
「なんか嬉しいな……。私ね、大学を出た後、教育系の出版社に就職したの。希望の業種に進めて張り切ってた。今度こそ、ここを自分の居場所にするんだって」
傾き始めた陽の光で橙色に変わりつつある多摩川を見ながら、早紀は続ける。
「だけどね、あの塾と同じようなことが起きたの……。女性の上司に嫌われて、とことんいじめられてね……。ストレスで片耳が聞こえづらくなってしまって、結局二年で退職したの」
悠太は黙って早紀の横顔を見つめている。
「自分の居場所なんて、どこにもないんじゃないかって、散々悩んだわ。世の中を恨めしくも思った。でもね、半年ほど家に引きこもっていたときに、ふと気が付いたの。私はいつも誰かから『ここに居ていいよ』って認めてもらうことしか考えてなかったって。私の人生の主役は私じゃなくて、いつだって『他人』だったのよ」
早紀の声がやや震えていることに気付いた悠太は、リュックからポケットティッシュを取り出すと早紀にそっと手渡す。愛花と出かけることがよくあるため、こういった物は常時持ち歩いているのだ。
「――ありがとう。優しいのね……。それでアメリカに留学したの。働いていたときに貯めていたお金を使ってね。向こうの人たちは、みんな本当に明るくてね。そして自己主張もしっかりするの。そんな環境にいたからかな、私も自分が本当にやりたいことをやっていこうって腹をくくることができたんだ」
「それが、英会話教室だったんですね」
早紀は頷くと、言葉を継いだ。
「自分の教室を開くとなると、どこか部屋を借りなきゃいけないし、責任も大きくなる。最初は不安だったわ。でも、誰かが用意した場所に『私はそこにふさわしい人間です』と申し出て、『そこに居てもよい』という許可をもらう生き方は、きっと私には向いていない。これまでの経験で痛感したわ。だから自分で自分の居場所を作り出すしかないって思ったの」
(――先生は五年前と変わらずカワイイ。だけどカワイイだけじゃない。あの頃よりも凛としていて……キレイだ……)
悠太は夕陽を受けた早紀の横顔にただただ見惚れていた。
「――先生は、本当にカッコイイです」
やっとの思いでそう言うと、早紀はありがとう、と髪を耳にかけながら小さく答えた。
「年下の男の子に『カッコイイ』なんて言われちゃうと、『もっといい女にならなきゃ!』ってモチベ上がるね」
えへへと笑いながらそう言うと、早紀はズボンのポケットからスマホを取り出し、画面をタップした。
「――連絡先、交換しよ」
悠太は、えっ?! と早紀の顔を凝視する。
「だってほら、渋谷の絵本のお店、一緒に行くんでしょ?」
そう言った直後、早紀は伏し目がちになりボソボソと付け加えた。
「――それともあれかな、彼女が……嫌がるとか……?」
「……! か、彼女なんて、いません!」
悠太は顔が熱くなるのを感じていたが、気取られまいとリュックに手を突っ込み、スマホを探しているふりをした。
「でも、いたこともあるでしょ?」
早紀の方をちらり窺うと、ただでさえ大きな瞳をくりくりさせて自分を見つめている。
「……い、いたこともあります。でも、半年前に振られました。他に好きな人ができたとかって」
悠太はそこでずっと気になっていたことを思い切って口にした。
「せ、先生こそ、彼氏とか……いるんじゃないですか」
悠太は早紀の顔を見ることができず、スマホをぎゅっと握った自分の両手を凝視している。
「ん……いたらさすがに中崎くんと二人では出かけられないかな」
甘い響きを伴う――少なくとも悠太にはそう感じられた――返事を耳にした瞬間、悠太は勢いよく顔を上げた。
早紀の頬は心なしか赤くなっているように見える。もしくは夕陽のせいか。
二人はスマホのアプリに相手の連絡先を登録し、メッセージをきちんと受け取れるか試しに送信し合うことにした。
ほどなくして、悠太のスマホ画面に『早紀です。よろしくお願いします』というメッセージが届いた。
『谷本』でもなく『谷本早紀』でもなく『早紀です』という文面に、悠太の心臓はぎゅっとなる。
悠太はすぐに『悠太です。こちらこそよろしくです』と返信する。
二人はどちらからともなく、えへへと笑い合った。
「――悠太くん、お腹空いてない? 駅前のファミレスでも行って、ご飯食べながら渋谷へ行く日決めない?」
『悠太くん』と呼ばれたことに一瞬舞い上がりそうになったが、「あ、いいっすね。――晩飯いらないって、母さんに連絡いれなきゃ」とスマホに目を落とした。
悠太は『今日、遅くなるから晩飯いらないよ。もう作っちゃってたら明日の朝食べるね』と美幸にメッセージを送りながら、早紀に「あの店のチーズハンバーグ、美味いですよね」と話しかける。
「やっぱりそう思う?」と微笑む早紀。
二人は立ち上がり、階段を登った。悠太は自転車を押す早紀の隣を歩く。
(自分で自分の居場所を生み出すのは本当にカッコイイことだ。誰にでもできることじゃない。だけど、いつか俺が……このとびきり可愛らしくてカッコイイ女性の居場所になれたらいいな……)
橙色に染まった多摩川を見つめながら、悠太はそっと願った。