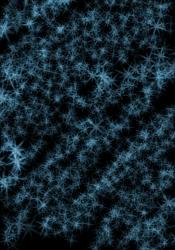次の日。
日曜日だったが、早くに目が覚めた。
隣では布団をひいて涼くんが寝ていた。
まったくわたしの部屋にいつ侵入してきたのか。
ぼんやりとした頭でなんとなく
自分の部屋でテレビをつける。
『本日梅雨入りが発表されました』
「梅雨入り、か」
たまたま見ていたニュースを見つめる。
梅雨入りの今日、家族はまだ誰も起きていない中で、わたしは自分の部屋を出て顔を洗って歯を磨いてリビングのソファーに座った。
先程のテレビを消して、ぼんやりしていると涼くんが起きてきた。
「翠」
「……なんで泊まってるわけ?」
「おばさんがいいっていったから」
お母さん、そんなあっさり決めないでくれとため息をついていると、涼くんはわたしの隣に座る。
「翠、考えてくれた?」
「何を?」
眉を潜めると、涼ちゃんはそっとわたしの顔を覗く。
「五年前に言ったでしょ、俺は翠のことが好きだって」
「え……」
「だから答えを聞くために、アメリカから戻ってきた」
「……待って、あれ、本気だったの?」
「当たり前だろ」
真剣に話すが、よく考えてみて涼くんに聞かずにいられなかった。
「なんでわたしのこと好きなの?」
「わかんねーよ」
「はあ?」
「でも俺は顔もよくて頭もよくて学歴もある、翠とは小さい頃から一緒にいて翠のだいたいのことは理解してあげられる。翠は俺と付き合うのになにか問題ある?」
確かに彼の言うことは正しいのかもしれない。
でも。
「めっちゃ自信家だね」
「全部翠のためだよ」
「……ごめんなさい、本気なら涼くんの気持ちには答えられない」
「なんで」
「なんでって……」
「俺のこと嫌い?」
「まあめちゃくちゃ嫌いってわけじゃないけど」
「ならいいじゃん」
「よくないよ」
「なんで」
「なんでって」
「翠」
「なに」
「……他に好きな人いるだろ?」
「え?」
少し固まってしまう。
好きな人?
そんな人はいない。
ただ、気になる人はいるかもしれない。
あのバス停の、男の子。
でもあれは……好きなんだろうか?
「いないよ」
「だったら俺と付き合ってくれるはずだ」
「だからどこからの自信……?」
「幼なじみとしての自信だよ」
「はあ?」
「翠の好きな人って誰?」
その時、さーと雨が降る。
その時、わたしの頭の中に何かがにじみ出るような感覚を覚えた。
「あ……れ?」
何かはわからないけど、寝起きのまま三角座りをして、その感覚に集中する。
「な、に」
一つ一つ、何かが鮮明になっていく。
一つ一つ、何かを思い出してくる。
それは、少しずつ……そう、少しずつ。
わたしはばっと顔をあげた。
思い出せたのは、
涼くんに『好きな人って誰?』と聞かれたからじゃない。
今日、梅雨入りしたからだ。
さーと雨の音がする。
全部全部、思い出した。
「……青、くん」
「え?」
「青くん」
「あおくん……?」
「……ごめん涼くん、わたし行かなきゃ」
私はソファーから立ち上がる。
「は、おい翠!」
「ごめん」
「こんな朝早くにどこ行くんだよ、おい、翠!?」
家を飛び出して、傘をさして、雨の中を走り出す。
最寄り駅の紫陽花の咲くバス停まで。
走りながら思い出した記憶を整理した。
梅雨明けのバス停のベンチで泣いている男の子の名前は青くん。
他人が聞いたら信じられない話だが彼は紫陽花の妖精で、毎年梅雨入りから梅雨明けの間だけ何故か人間になれる。
二年前の梅雨の日、青くんは綺麗な顔すぎたからなのか、太った見知らぬ親父から痴漢にあっていた。その痴漢を目撃したわたしは痴漢するその親父が心底許せなくてその親父を傘でぶん殴ったことは今なら鮮明に思い出せる。
(その時のわたしは痴漢とはいえ相手を怪我しないように多少は手加減した、多分)
青くんと仲良くなって、わたしが恋に落ちるのに時間はかからなかった。
青くんは綺麗な人で、優しくて、誰よりもわたしの存在を肯定してくれる。
わたしの初めての恋だ。
どういう理由かはわからないが、
紫陽花の青くんは梅雨明けでも
種になり、また花を咲かせながら
わたしとの思い出を毎年上書きすることができ、わたしのことを忘れることはない。
わたしは梅雨明けの瞬間に彼との記憶が消え、
紫陽花をみかけても、次の梅雨入りまで青くんの記憶は封印され、つまりは忘れてしまう。
青くんは梅雨明けの昼間でには紫陽花に戻る。
梅雨入りしたこの瞬間に思うのだ。
聞けずにいるけど、
毎年、彼を泣かせてしまっているのはきっと……わたしだ。
バス停が見えてくる。
彼はベンチにいた。
わたしに気がついて、そっと立ち上がった。
「ただいま、青くん」
青くんはなにも言わないまま微笑む。
わたしは傘を投げ捨てて彼の胸に飛び込む。
「お帰り、翠ちゃん」
青くんはただ優しくわたしを抱き締めた。
日曜日だったが、早くに目が覚めた。
隣では布団をひいて涼くんが寝ていた。
まったくわたしの部屋にいつ侵入してきたのか。
ぼんやりとした頭でなんとなく
自分の部屋でテレビをつける。
『本日梅雨入りが発表されました』
「梅雨入り、か」
たまたま見ていたニュースを見つめる。
梅雨入りの今日、家族はまだ誰も起きていない中で、わたしは自分の部屋を出て顔を洗って歯を磨いてリビングのソファーに座った。
先程のテレビを消して、ぼんやりしていると涼くんが起きてきた。
「翠」
「……なんで泊まってるわけ?」
「おばさんがいいっていったから」
お母さん、そんなあっさり決めないでくれとため息をついていると、涼くんはわたしの隣に座る。
「翠、考えてくれた?」
「何を?」
眉を潜めると、涼ちゃんはそっとわたしの顔を覗く。
「五年前に言ったでしょ、俺は翠のことが好きだって」
「え……」
「だから答えを聞くために、アメリカから戻ってきた」
「……待って、あれ、本気だったの?」
「当たり前だろ」
真剣に話すが、よく考えてみて涼くんに聞かずにいられなかった。
「なんでわたしのこと好きなの?」
「わかんねーよ」
「はあ?」
「でも俺は顔もよくて頭もよくて学歴もある、翠とは小さい頃から一緒にいて翠のだいたいのことは理解してあげられる。翠は俺と付き合うのになにか問題ある?」
確かに彼の言うことは正しいのかもしれない。
でも。
「めっちゃ自信家だね」
「全部翠のためだよ」
「……ごめんなさい、本気なら涼くんの気持ちには答えられない」
「なんで」
「なんでって……」
「俺のこと嫌い?」
「まあめちゃくちゃ嫌いってわけじゃないけど」
「ならいいじゃん」
「よくないよ」
「なんで」
「なんでって」
「翠」
「なに」
「……他に好きな人いるだろ?」
「え?」
少し固まってしまう。
好きな人?
そんな人はいない。
ただ、気になる人はいるかもしれない。
あのバス停の、男の子。
でもあれは……好きなんだろうか?
「いないよ」
「だったら俺と付き合ってくれるはずだ」
「だからどこからの自信……?」
「幼なじみとしての自信だよ」
「はあ?」
「翠の好きな人って誰?」
その時、さーと雨が降る。
その時、わたしの頭の中に何かがにじみ出るような感覚を覚えた。
「あ……れ?」
何かはわからないけど、寝起きのまま三角座りをして、その感覚に集中する。
「な、に」
一つ一つ、何かが鮮明になっていく。
一つ一つ、何かを思い出してくる。
それは、少しずつ……そう、少しずつ。
わたしはばっと顔をあげた。
思い出せたのは、
涼くんに『好きな人って誰?』と聞かれたからじゃない。
今日、梅雨入りしたからだ。
さーと雨の音がする。
全部全部、思い出した。
「……青、くん」
「え?」
「青くん」
「あおくん……?」
「……ごめん涼くん、わたし行かなきゃ」
私はソファーから立ち上がる。
「は、おい翠!」
「ごめん」
「こんな朝早くにどこ行くんだよ、おい、翠!?」
家を飛び出して、傘をさして、雨の中を走り出す。
最寄り駅の紫陽花の咲くバス停まで。
走りながら思い出した記憶を整理した。
梅雨明けのバス停のベンチで泣いている男の子の名前は青くん。
他人が聞いたら信じられない話だが彼は紫陽花の妖精で、毎年梅雨入りから梅雨明けの間だけ何故か人間になれる。
二年前の梅雨の日、青くんは綺麗な顔すぎたからなのか、太った見知らぬ親父から痴漢にあっていた。その痴漢を目撃したわたしは痴漢するその親父が心底許せなくてその親父を傘でぶん殴ったことは今なら鮮明に思い出せる。
(その時のわたしは痴漢とはいえ相手を怪我しないように多少は手加減した、多分)
青くんと仲良くなって、わたしが恋に落ちるのに時間はかからなかった。
青くんは綺麗な人で、優しくて、誰よりもわたしの存在を肯定してくれる。
わたしの初めての恋だ。
どういう理由かはわからないが、
紫陽花の青くんは梅雨明けでも
種になり、また花を咲かせながら
わたしとの思い出を毎年上書きすることができ、わたしのことを忘れることはない。
わたしは梅雨明けの瞬間に彼との記憶が消え、
紫陽花をみかけても、次の梅雨入りまで青くんの記憶は封印され、つまりは忘れてしまう。
青くんは梅雨明けの昼間でには紫陽花に戻る。
梅雨入りしたこの瞬間に思うのだ。
聞けずにいるけど、
毎年、彼を泣かせてしまっているのはきっと……わたしだ。
バス停が見えてくる。
彼はベンチにいた。
わたしに気がついて、そっと立ち上がった。
「ただいま、青くん」
青くんはなにも言わないまま微笑む。
わたしは傘を投げ捨てて彼の胸に飛び込む。
「お帰り、翠ちゃん」
青くんはただ優しくわたしを抱き締めた。