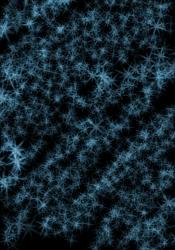「おねえちゃん、お帰りー」
最寄りのバス停から坂道を上がって、小さな公園を通りすぎ、徒歩15分。
家の玄関の扉をあけると、奏太が小走りで駆け寄ってきた。
「お帰りー」
「ただいま、奏太」
「お土産はー?」
「……ないよ、あるわけない」
「なんで? 学校行ってきたんでしょ?」
「学校にお土産売り場ないの」
「……ちぇっ」
奏太は口を尖らせて行ってしまった。
「もう、学校をなんだと思ってるのよ」
わたしも口を尖らせて靴を脱ぐ。
はあとため息をついてからリビングに行くと、畳んだ洗濯物を抱えたお母さんと目が合う。
「あ、おかえり、涼くん来てるけど?」
「は?」
「お母さん二階にお父さんの洗濯物置いてくる」
「え?」
お母さんは二階へ行った。
「翠っ」
ソファーに座っていた幼なじみの涼くんは振り向き、片手を軽くあげにこりとした。
会うのは……小6の時、つまり五年前以来か。
突然両親の仕事の都合でアメリカに飛び立ち、なにも言わずに帰ってきたらしい。
「随分久しぶりだね。わたしのいないところで勝手に家入らないでよね」
「おばさんの許可もらったから」
「でも……」
「ゲームするぞー」
なんで家の住人じゃない涼くんが決めるんだろう。
五年以来でも自己中心的でマイペースでなんにも変わらず相変わらずな性格である。
また涼くんに振り回される未来予想図ができると、わたしははあとまたため息をつく。
お父さんはまだ仕事から帰ってきていない。
「トイレ行ってくる」
涼くんはわたしの内心に少しも気づいていないままトイレに行った。
奏太はテレビの前で正座して画面を見るのに神経を走らせていた。
何を見ているのかなと近づくと、テレビでは天気予報が始まった。
『今日の近畿は曇り空。遅れている梅雨入りの発表は明日にもありそうです』
わたしは奏太を背中から抱え込み、後ろに下げソファーに座らせた。
「あ。何するんだよー」
「近くで見すぎ、目悪くなるでしょ?」
「ちぇっ」
奏太は口を尖らせたが、すぐににこりとして画面を指差す。
「ねえ、おねえちゃん」
「なに」
「明日梅雨入りなんだね」
「そうみたいだね。というか奏太は難しい言葉知ってるね?」
「梅雨入り、か」
奏太はぱっと顔を明るくしてわたしに微笑む。
「ようやく、明日会えるね」
わたしは首をかしげた。
「会える? 誰に?」
「青くんだよ」
「青くん……?」
思い返してみるが、何も思い出せないわたしに奏太はきょとんとした。
「忘れたの?」
「え、と……誰だっけ?」
記憶を辿る。奏太の声のボリュームが少し上がる。
「紫陽花の青くんだよ?」
「……え? なに紫陽花って」
「紫陽花は紫陽花だよ。目の下にほくろがある、青くんのことだよ? ほら思い出せた?」
奏太は自分の目の下を指でちょんちょんと触ってわたしにアピールした。
「紫陽花? ほくろ?」
「去年も一昨年も会ってるじゃん、梅雨の日に」
「梅雨の日……?」
「今年は僕も喋れるようになったし、今年は青くんとおねえちゃんの二人きりの中に僕を入れてね。二人でデートしないでね?」
「……はあ?」
眉を寄せるしかない。
でも奏太はわたしににこりとしている。
わたしは考える。
一体誰の話なんだろう? と。
「なんの話してるの」
涼くんが戻ってきて、見知らぬ誰かの話といいかけたところで、お母さんも二階から戻ってきて口を開く。
「奏太、涼くん、今日ハンバーグ作るよ」
「え、やったー手伝うー」
ソファーを勢いよく降りた奏太は行ってしまった。
「俺もー」
涼くんも行ってしまった。
なんだか涼くんのはしゃぎかたは奏太と同じだ。
二歳の奏太はアメリカから帰国したばかりの涼くんと今日が初めて会ったはずなのにすっかりなついていた。
はあとため息をついたあとで
……そういえば、と思う。
バス停。
紫陽花の咲いたベンチ。
梅雨明けに一日しか会えない彼には、
目の下にほくろがある。