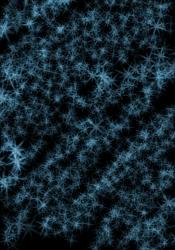二回目の彼に会ってから季節は巡り
六月の上旬の曇り空の日。
梅雨入り前。
梅雨が明けたら三度目がやってくる。
今年こそ……話しかけよう。
梅雨入りして梅雨が明けて、あのバス停のベンチに座って彼がまた泣いてたら、訳を聞こう。
変に思われるかもしれない。
けど、気になるから。
彼のことがやたら気になるんだ。
わたしは自分の席で窓の外を見ながら静かに決意した。
「翠《すい》、帰ろう?」
クラスメートの飛倉紗那《ひくらさな》はいつの間にかわたしの目の前に立っていた。
「わ……」
「なに驚いてるの?」
紗那ちゃんの長いストレート髪は緩やかな風にゆれていた。女子の中でも背は高めだし、大きな目は若干つり上がっているから一見怖そうに見えるけど、とてもフレンドリーな性格をしている。
「ちょっと考えてごとしてたから、いきなり紗那ちゃんがいてびっくりして」
「考えごと? なに考えたの?」
ふふふと笑い、紗那は首を捻る。
「いいの、帰ろう」
わたしがたち上がると急いで鞄を持つと、紗那ちゃんは苦笑した。
二人で一階に降りると、雨が上がっていた。
わたしと紗那は持ってきた傘を忘れずに持ち、一緒に歩き出す。
「翠パーマかけたんだね」
「梅雨明けにむけて少し早めにお洒落しようかと」
「かわいい。でも梅雨明けにお洒落って、なにそれ」
「あ、なんでもない」
「ふーん」
思わず余計なことを口走ってしまい、慌てて口を閉じる。
だって実際のところ自分にもよく分からない感情だから。
どうして梅雨入り前にお洒落をしたくなるのか分からないから。
門をくぐり抜けるあたりで紗那ちゃんが口を開く。
「今日のテストどうだった?」
「え、まあまあ……かな」
「わたしも。テストもそこそこにできて早く帰れるって最高だよね」
「うん」
わたしが頷くと、紗那ちゃんの目線が少し落ちたのが分かった。
「……ねえねえ翠、前々から思ってたこと話していい?」
「ん? なに??」
「翠の傘の持ち方、変じゃない? 持つのが上下反対だよね?」
紗那ちゃんは傘を持つわたしの手を指差した。
わたしはゆっくりと視線を落として自分の手を見ると思わず「あー……」と思わず濁した声を漏らし、言葉を重ねる。
「不審者対策で」
「不審者、対策?」
ごくりと唾を飲み込んだ紗那ちゃんを見て、深刻になりすぎないように笑顔を作りながら質問の返答する。
「この辺痴漢多いらしいんだよね」
「え……痴漢、会ったことあるの?」
「んー……ない。噂だけ」
「なんだ、よかった」
「でも傘を持っている日はね反対向きに持ってるんだ。この持ち方ならいざというとき相手を殴れるかなって」
わたしがにこりとすると、紗那ちゃんは目を丸め口に手をあてた。そしてむっとした。
「ちょっと翠、立ち向かわないでよ。反撃にあったらどうすんの? まず逃げなさい!」
「やだなぁ、紗那ちゃん。もちろん逃げるが前提だよ。ただ、いざというときのためにこの持ち方なだけで」
「……翠は剣道強いもんね? 中学の時から剣道部だったし、都大会で優勝したし、お父さん剣道の道場持ってるし、いざというときは撃退しそうだけど」
「でしょ?」
「でもむやみやたらに立ち向かわないでね。翠は女子なんだよ、女子。剣道部でもか弱い女子なの」
「か弱いかなぁ……?」
「とりあえずその持ち方やめな。傘は竹刀じゃないんだから。武道をやっている身の人がそんなことやっちゃだめ」
「それもそうだね。でも癖なので直るまで少々お待ちください」
「はい、待ちます」
「素直ー」
「ほら、持ち変えて」
「うん」
傘の持ち方を変えてふふとわたしが笑うと、紗那もにこりとした。
「そういえばさ、弟くん元気ー?」
「奏太? うん」
「二才になったんだっけ?」
「そうそう。ずっと人見知りだったから無音だったけど、最近、喋ることを覚えて楽しくなったらしくてほいほい人の側に行ってはすっごく言葉を覚えて帰ってきてめちゃくちゃうるさい。二歳とは思えない喋りなの」
「そうなんだー、かわいい」
「かわいくないよー? 喋らない一年前のが可愛かったよ」
「バイトない日に会わせてね」
「まあ、いいよ?」
道は十字路にさしかかる。
クレープ屋さんでバイトする紗那ちゃんはバイト前に一度家に帰るため、わたしに手を振る。
「翠ばいばーい。また明日」
「うん、また明日」
紗那ちゃんに手を振り返し、わたしはバス停に向かって歩き出す。
紫陽花の咲くバス停でバスを待ち、五分後に到着時間ぴったりのバスに乗り、窓の景色をぼんやりと眺めて、空いているバスに揺られていた。
ぼんやりしているだけで、家からの最寄り駅であるバス停に到着した。
バスを降りると、紫陽花の咲くバス停のベンチを見る。
あの泣いている彼に、一年に一度、合計で二回しか会ったことはない。
でもバスに乗るときも降りるときも何故か探してしまう。
毎年梅雨明けに一日だけ会える彼は、梅雨の始まりそうな現在じゃ、どこにもいない。