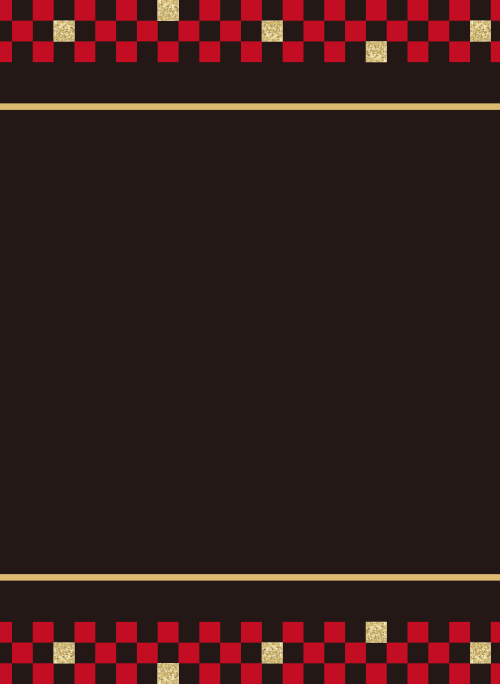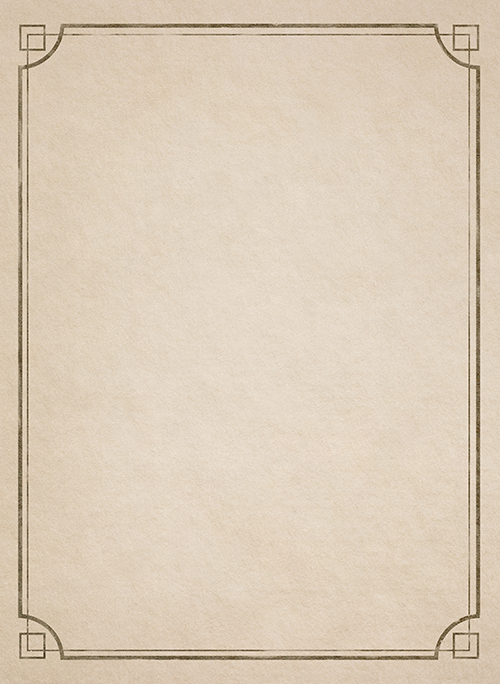駿輔はこの1年、ビルトアップ走に重点を置いてきた。ビルドアップ走はペース走同様にスピード持久力やペース感覚を養うのに効果的。そしてペースを徐々に上げる走り方をすることで、レース後半にバテないスタミナを効果的に鍛えることが出来る。当たり負けしない体幹と筋力も備えてきた。
すべては流風への恨みを晴らすために取り組んできた。それをポッと出の1年生に邪魔されるわけにはいかない。
秋の地方予選大会では駿輔がエースとして1区を走った。全国大会と同様の距離と区間を7人で走り切ったわけだが、本番も同じメンバーの同じオーダーとは限らない。もちろん光だって予選大会と同じままで満足できるわけもない。
みんなの練習終了後、密かに示し合わせた二人がタイムトライアルで雌雄を決める。
「本番1区と同じ10キロ走でいいスか?」
「本番前だ、800か1000でいいだろ」
「最低1500、3000でしょ。パイセン、レース後半すぐバテるんだから」
「チッ……俺はまだ10キロだって平気で走れる」
「自分だって、後100キロくらい余裕ですけど」
「ほざけっ! 誰もいないから思いっきり泣いても大丈夫だぞ、特別にみんなには内緒にしておいてやる」
「パイセンこそ、負けるところ見られたくないからこんな練習後の時間帯にしたんでしょ」
「じゃ、5000、丁度18時の鐘が鳴る、それを合図にスタートだ」
「タイムなんて関係ないじゃないっスか単なる競走だ」
光が呟く。目の前にある時計の針は今にも一直線になろうとしている。そんなタイミングだった。
「おい、足元に500円落ちてるぞ?!」
「え?!」
反射的に光は、足元のキラキラを探してしまう、そこに100円玉が一枚落ちていた。500円ではないが思わず手を伸ばして拾ってしまう、その刹那、
「スタートだ」
駿輔が走り出す。
「っちっくしょ~めっ……、ったく……」
自分を呪うように追いかけてスタートする。それは以前、一緒に走る空木を『今ウンコ踏んだぞ』と揶揄っていたことと類は同じだ。
自分の間抜けさに思わず笑みが零れる。
すべては流風への恨みを晴らすために取り組んできた。それをポッと出の1年生に邪魔されるわけにはいかない。
秋の地方予選大会では駿輔がエースとして1区を走った。全国大会と同様の距離と区間を7人で走り切ったわけだが、本番も同じメンバーの同じオーダーとは限らない。もちろん光だって予選大会と同じままで満足できるわけもない。
みんなの練習終了後、密かに示し合わせた二人がタイムトライアルで雌雄を決める。
「本番1区と同じ10キロ走でいいスか?」
「本番前だ、800か1000でいいだろ」
「最低1500、3000でしょ。パイセン、レース後半すぐバテるんだから」
「チッ……俺はまだ10キロだって平気で走れる」
「自分だって、後100キロくらい余裕ですけど」
「ほざけっ! 誰もいないから思いっきり泣いても大丈夫だぞ、特別にみんなには内緒にしておいてやる」
「パイセンこそ、負けるところ見られたくないからこんな練習後の時間帯にしたんでしょ」
「じゃ、5000、丁度18時の鐘が鳴る、それを合図にスタートだ」
「タイムなんて関係ないじゃないっスか単なる競走だ」
光が呟く。目の前にある時計の針は今にも一直線になろうとしている。そんなタイミングだった。
「おい、足元に500円落ちてるぞ?!」
「え?!」
反射的に光は、足元のキラキラを探してしまう、そこに100円玉が一枚落ちていた。500円ではないが思わず手を伸ばして拾ってしまう、その刹那、
「スタートだ」
駿輔が走り出す。
「っちっくしょ~めっ……、ったく……」
自分を呪うように追いかけてスタートする。それは以前、一緒に走る空木を『今ウンコ踏んだぞ』と揶揄っていたことと類は同じだ。
自分の間抜けさに思わず笑みが零れる。