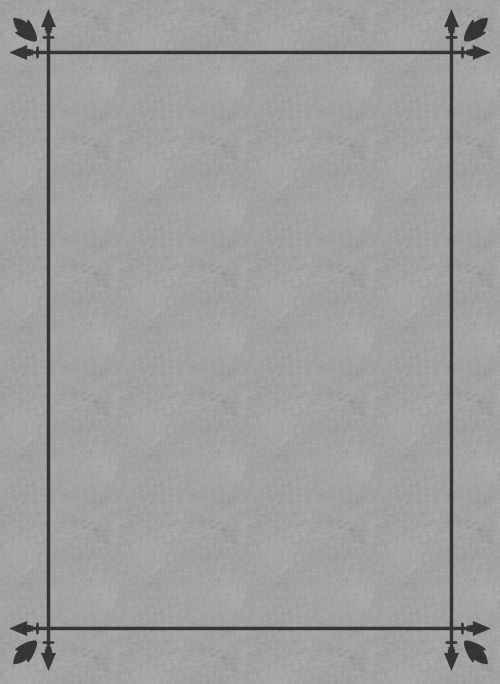「……誰かいますかぁ~」
ノックをしてから部屋に立ち入る。
少し時間を置くことで、暗闇に慣れた視界を頼りに歩みを進めた。
薄らとしか先は見えないが、どうやら部屋自体はあまり広くなさそうだった。
多分、十メートル四方くらいだろうか。
奥の方に別の部屋へと続くであろう扉も見えるが、この部屋に置かれたソファ、クローゼット、テーブルや椅子などを見るに、日常的に使っているような痕跡がある。
廊下や他の居室などに比べるとかなり綺麗だ。
ただ、部屋の中央には何とも異質なピンク色の棺が堂々と置いてあった。
よくよく見てみると、他の家具類や衣服なんかもピンク色が多い気がする。
リリス・ブラッドなる者の趣味、好みだろう。
女性なのかな?
「……というか、誰もいない?」
勝手に入ったらまずかったかなと思いつつも、興味が勝ってしまい足が止まらない。
そもそも一枚目の扉がそのまま部屋への入り口だとは思わなかった。
「留守なのかな。ずっと部屋を開けているようには見えないけど……」
魔王軍四天王といえど、その日常的な暮らしは人間とさほど変わりはないように思える。
だが、さすがに部屋の主がいないのに奥の扉にまで手をかけるのは善意に憚られたので、今日はこの辺りにしておく。
「お邪魔しました~」
俺は誰もいないであろう部屋に別れを告げて踵を返した。
刹那。
棺の蓋が大きな音を立てて隙間を作ると、その隙間から勢いよく細くてしなやかな手が伸びてきた。
「え……っ!?」
手は俺の右手首をがっしりと掴み、強い力で棺の中へと引き摺り込む。
俺はなすすべなく体勢を崩すと、勢いそのままに棺の中にダイレクトに吸い込まれてしまう。
「ちょ、ちょっと!」
俺は反射的に恐怖を覚えて暴れようとしたが、それは叶わなかった。
気がつけば、あまり大きくない棺の中で何者かに押し倒されており、全く身動きが取れなくなっていた。
「——あなたは、だれ?」
「え?」
暗闇の中で何も見えないが、か細く小さな声が聞こえてきた。女性の声だ。
「人間……じゃなくて、魔族? いや、違う?」
「……勝手に部屋に入ってすみません。俺は魔人のソロモンと言います。貴女はリリス・ブラッド……さん?」
「そう」
俺からの問いかけにリリスさんは端的に答えた。
「……」
「……」
「……あの」
十数秒ほどの無言を挟んだ末に俺は声をかける。
「なに?」
「どうして俺の首元に顔を当ててるんですかね……?」
俺の首元にはリリスさんの熱い吐息がかかっていた。彼女は熱っぽく呼吸が乱れていて、少しばかり様子がおかしい。
「いい匂いがするの」
「匂い?」
匂いとは何か……逆に、俺の方がリリスさんの甘い体臭を間近で感じている気がする。それに、多分二つ結びになっている髪が頬に当たってくすぐったい。
「うん。ずっと寝てたから、血と魔力がほしい」
「へ?」
俺が驚いたのも束の間のこと。リリスさんは突然意味不明なことを言ったかと思いきや、すぐさま大きく口を開けた。
それから間髪入れずに、鋭利な歯で俺の首元を突き刺してきた。
否、かぶりついてきた。
ちゅーちゅーと可愛らしい音を立てながら、首元から溢れ出る俺の血液を吸っているようだ。
でも、不思議と痛みはなかった。
「……んー、美味しい」
「失礼ですが、種族を聞いてもいいですか?」
俺は未だ首元に歯を突き立てるリリスさんに尋ねた。
「ぷはぁっ……ボクは、ヴァンパイアだよ?」
リリスさんは恍惚な笑みを浮かべていた。
俺の瞳を捉えて離さない。
頬はうっとり赤く染まり、湿っぽい唇と血の滴る歯が艶かしく見えた。
だが、俺はヴァンパイアという種族そのものに何よりも興味があったので、心を入れ替えてそちらの思考にシフトする。
「ヴァンパイアですか」
ヴァンパイアと言えば吸血行動が有名だ。
通常の食事のほかに他者の血液を必要とする習性があるのだ。
というのも、莫大な魔力量を獲得しながらも、細い体躯に見合わぬパワーを発揮できる代わりに、ありえないくらい燃費が悪いらしい。
おかげで、普通に過ごしているだけでじわじわと体力と魔力が減ってしまうらしく、他者の血液に含まれている魔力に頼らざるを得ないと文献で見たことがある。
「……あなたの血、今まで吸った中で一番美味しい」
リリスさんは艶かしく舌なめずりをすると、蕩けた顔つきでじっと見つめてきた。
「……それはよかったです」
「ねぇ、ボクの下僕にならない?」
「いや、それはちょっと……」
「ぶー、けち。初めての下僕だよ?」
俺が普通に断ると、リリスさんは不貞腐れたように頬を膨らませた。
眼前で見たら顔はかなり整っているし声だって可愛いらしいので、断るのはいささか気が引けた。
でも、ヴァンパイアの下僕になったら血の制約を交わすので、自由意志を一切持てなくなってしまう。
今は魔王から働かないかと誘いを受けている最中なので、リリスさんの誘惑には乗れないのだ。
「すみませんね。ところで、部屋に勝手に入ってきた俺が言うのもなんですけど、そろそろ解放してくれたりします? その……色々と近いから困るんですけど……」
俺は仰向けのままモゾモゾと動こうとしたが、閉所の中でリリスさんの全体重が乗っかっているからか身動きが取れない。
決してその体重が重いというわけではなく、密室空間で上から馬乗りにされているような状態なので満足に身動きが取れない。
おまけに、ずっと甘い香りがしてクラクラする。
やばい。早く出ないと気がおかしくなる。
「……」
「あれ? どいてくれないんですか?」
棺から抜け出す流れになると思っていたのだが、なぜかリリスさんは俺に全体重を預けたままピクリとも動かなかった。
「なんで?」
「え?」
「どいてほしいの?」
「はい」
「わかった」
リリスさんは俺を解放して棺を出ると、暗闇の中で佇みながらこちらを見下ろす。
「リリスさんはずっとこの部屋に?」
俺は上体を起こしてから尋ねる。
「うん。ボク、やりたいことがないから暇な時はずっと寝てるの」
「へー、俺も寝るのは好きなので一緒ですね」
村にいた時は一日に十時間以上寝てしまうこともあった。寝過ぎだとは思いつつも、やはり睡魔には抗えず、気持ちの良いベッドの上ですやすや眠っているのは最高だった。
「……ソロモンだっけ?」
「ソロモンです」
「そう。ソロモン、ソロモン……ソロモン、ね」
「はい……何か?」
「名前、覚えた」
「……えーっと、じゃあ、俺はこの辺で……」
言葉に詰まった俺はそそくさと棺の中から抜け出した。
しかし、リリスさんは俺との距離を詰めて体を密着させた状態でこちらを見上げてくる。
癖なのか何なのかわからないが距離が近い。
俺とリリスさんの間には手のひら一枚程度の隙間しかない。
一体何を言われるのか……。
「またね」
リリスさんは身構えた俺の予想とは打って変わって、にこりと微笑みながら軽いハグをしてきた。
ただの別れの挨拶だった。
暗闇でよく見えないけど、全身に当たる体の感触が少しばかり生々しい気がする。
あんまりこういうこと言うのは失礼だけど、体つきは幼いと思う。
「ええ、また」
俺は平静を取り繕って言葉を返すと、小さく手を振るリリスさんを一瞥してから部屋を後にした。
「……服、着てなかったな、多分」
俺は扉を背に先ほどまで全身で味わった感触を思い出した。
じっくり目を凝らしてみたわけではないから真実はわからないが……まあ、そういうことだ。
とにかく、魔王軍四天王の一人であるヴァンパイアのリリス・ブラッドさんにはこうして会うことができた。それどころか何故か普通に話せたし、今後魔王城で働くことを考えながら素晴らしい進展と言える。
「もう夕方みたいだし、急いで上に向かうか」
回廊の窓から外を見ると、既に空は赤く染まり始めていた。
別に時間制限があるわけでもないが、夜は夜で部屋で過ごしたいと思っているので早急に上を目指すことにする。
できれば、他の魔王軍四天王はあまり癖のない普通の魔族であることを願う。
ノックをしてから部屋に立ち入る。
少し時間を置くことで、暗闇に慣れた視界を頼りに歩みを進めた。
薄らとしか先は見えないが、どうやら部屋自体はあまり広くなさそうだった。
多分、十メートル四方くらいだろうか。
奥の方に別の部屋へと続くであろう扉も見えるが、この部屋に置かれたソファ、クローゼット、テーブルや椅子などを見るに、日常的に使っているような痕跡がある。
廊下や他の居室などに比べるとかなり綺麗だ。
ただ、部屋の中央には何とも異質なピンク色の棺が堂々と置いてあった。
よくよく見てみると、他の家具類や衣服なんかもピンク色が多い気がする。
リリス・ブラッドなる者の趣味、好みだろう。
女性なのかな?
「……というか、誰もいない?」
勝手に入ったらまずかったかなと思いつつも、興味が勝ってしまい足が止まらない。
そもそも一枚目の扉がそのまま部屋への入り口だとは思わなかった。
「留守なのかな。ずっと部屋を開けているようには見えないけど……」
魔王軍四天王といえど、その日常的な暮らしは人間とさほど変わりはないように思える。
だが、さすがに部屋の主がいないのに奥の扉にまで手をかけるのは善意に憚られたので、今日はこの辺りにしておく。
「お邪魔しました~」
俺は誰もいないであろう部屋に別れを告げて踵を返した。
刹那。
棺の蓋が大きな音を立てて隙間を作ると、その隙間から勢いよく細くてしなやかな手が伸びてきた。
「え……っ!?」
手は俺の右手首をがっしりと掴み、強い力で棺の中へと引き摺り込む。
俺はなすすべなく体勢を崩すと、勢いそのままに棺の中にダイレクトに吸い込まれてしまう。
「ちょ、ちょっと!」
俺は反射的に恐怖を覚えて暴れようとしたが、それは叶わなかった。
気がつけば、あまり大きくない棺の中で何者かに押し倒されており、全く身動きが取れなくなっていた。
「——あなたは、だれ?」
「え?」
暗闇の中で何も見えないが、か細く小さな声が聞こえてきた。女性の声だ。
「人間……じゃなくて、魔族? いや、違う?」
「……勝手に部屋に入ってすみません。俺は魔人のソロモンと言います。貴女はリリス・ブラッド……さん?」
「そう」
俺からの問いかけにリリスさんは端的に答えた。
「……」
「……」
「……あの」
十数秒ほどの無言を挟んだ末に俺は声をかける。
「なに?」
「どうして俺の首元に顔を当ててるんですかね……?」
俺の首元にはリリスさんの熱い吐息がかかっていた。彼女は熱っぽく呼吸が乱れていて、少しばかり様子がおかしい。
「いい匂いがするの」
「匂い?」
匂いとは何か……逆に、俺の方がリリスさんの甘い体臭を間近で感じている気がする。それに、多分二つ結びになっている髪が頬に当たってくすぐったい。
「うん。ずっと寝てたから、血と魔力がほしい」
「へ?」
俺が驚いたのも束の間のこと。リリスさんは突然意味不明なことを言ったかと思いきや、すぐさま大きく口を開けた。
それから間髪入れずに、鋭利な歯で俺の首元を突き刺してきた。
否、かぶりついてきた。
ちゅーちゅーと可愛らしい音を立てながら、首元から溢れ出る俺の血液を吸っているようだ。
でも、不思議と痛みはなかった。
「……んー、美味しい」
「失礼ですが、種族を聞いてもいいですか?」
俺は未だ首元に歯を突き立てるリリスさんに尋ねた。
「ぷはぁっ……ボクは、ヴァンパイアだよ?」
リリスさんは恍惚な笑みを浮かべていた。
俺の瞳を捉えて離さない。
頬はうっとり赤く染まり、湿っぽい唇と血の滴る歯が艶かしく見えた。
だが、俺はヴァンパイアという種族そのものに何よりも興味があったので、心を入れ替えてそちらの思考にシフトする。
「ヴァンパイアですか」
ヴァンパイアと言えば吸血行動が有名だ。
通常の食事のほかに他者の血液を必要とする習性があるのだ。
というのも、莫大な魔力量を獲得しながらも、細い体躯に見合わぬパワーを発揮できる代わりに、ありえないくらい燃費が悪いらしい。
おかげで、普通に過ごしているだけでじわじわと体力と魔力が減ってしまうらしく、他者の血液に含まれている魔力に頼らざるを得ないと文献で見たことがある。
「……あなたの血、今まで吸った中で一番美味しい」
リリスさんは艶かしく舌なめずりをすると、蕩けた顔つきでじっと見つめてきた。
「……それはよかったです」
「ねぇ、ボクの下僕にならない?」
「いや、それはちょっと……」
「ぶー、けち。初めての下僕だよ?」
俺が普通に断ると、リリスさんは不貞腐れたように頬を膨らませた。
眼前で見たら顔はかなり整っているし声だって可愛いらしいので、断るのはいささか気が引けた。
でも、ヴァンパイアの下僕になったら血の制約を交わすので、自由意志を一切持てなくなってしまう。
今は魔王から働かないかと誘いを受けている最中なので、リリスさんの誘惑には乗れないのだ。
「すみませんね。ところで、部屋に勝手に入ってきた俺が言うのもなんですけど、そろそろ解放してくれたりします? その……色々と近いから困るんですけど……」
俺は仰向けのままモゾモゾと動こうとしたが、閉所の中でリリスさんの全体重が乗っかっているからか身動きが取れない。
決してその体重が重いというわけではなく、密室空間で上から馬乗りにされているような状態なので満足に身動きが取れない。
おまけに、ずっと甘い香りがしてクラクラする。
やばい。早く出ないと気がおかしくなる。
「……」
「あれ? どいてくれないんですか?」
棺から抜け出す流れになると思っていたのだが、なぜかリリスさんは俺に全体重を預けたままピクリとも動かなかった。
「なんで?」
「え?」
「どいてほしいの?」
「はい」
「わかった」
リリスさんは俺を解放して棺を出ると、暗闇の中で佇みながらこちらを見下ろす。
「リリスさんはずっとこの部屋に?」
俺は上体を起こしてから尋ねる。
「うん。ボク、やりたいことがないから暇な時はずっと寝てるの」
「へー、俺も寝るのは好きなので一緒ですね」
村にいた時は一日に十時間以上寝てしまうこともあった。寝過ぎだとは思いつつも、やはり睡魔には抗えず、気持ちの良いベッドの上ですやすや眠っているのは最高だった。
「……ソロモンだっけ?」
「ソロモンです」
「そう。ソロモン、ソロモン……ソロモン、ね」
「はい……何か?」
「名前、覚えた」
「……えーっと、じゃあ、俺はこの辺で……」
言葉に詰まった俺はそそくさと棺の中から抜け出した。
しかし、リリスさんは俺との距離を詰めて体を密着させた状態でこちらを見上げてくる。
癖なのか何なのかわからないが距離が近い。
俺とリリスさんの間には手のひら一枚程度の隙間しかない。
一体何を言われるのか……。
「またね」
リリスさんは身構えた俺の予想とは打って変わって、にこりと微笑みながら軽いハグをしてきた。
ただの別れの挨拶だった。
暗闇でよく見えないけど、全身に当たる体の感触が少しばかり生々しい気がする。
あんまりこういうこと言うのは失礼だけど、体つきは幼いと思う。
「ええ、また」
俺は平静を取り繕って言葉を返すと、小さく手を振るリリスさんを一瞥してから部屋を後にした。
「……服、着てなかったな、多分」
俺は扉を背に先ほどまで全身で味わった感触を思い出した。
じっくり目を凝らしてみたわけではないから真実はわからないが……まあ、そういうことだ。
とにかく、魔王軍四天王の一人であるヴァンパイアのリリス・ブラッドさんにはこうして会うことができた。それどころか何故か普通に話せたし、今後魔王城で働くことを考えながら素晴らしい進展と言える。
「もう夕方みたいだし、急いで上に向かうか」
回廊の窓から外を見ると、既に空は赤く染まり始めていた。
別に時間制限があるわけでもないが、夜は夜で部屋で過ごしたいと思っているので早急に上を目指すことにする。
できれば、他の魔王軍四天王はあまり癖のない普通の魔族であることを願う。