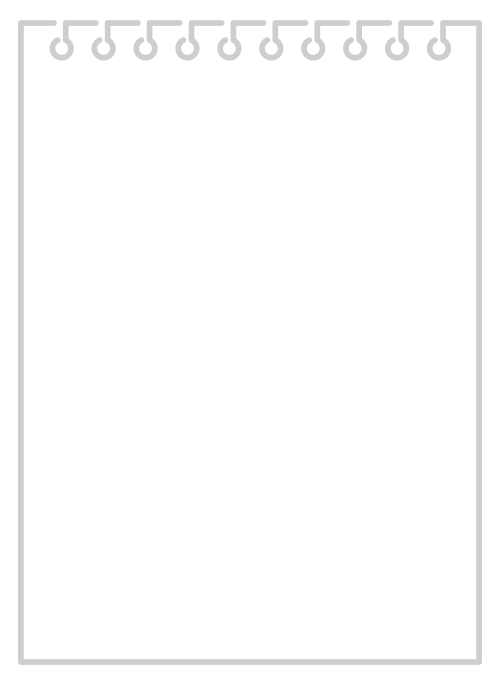「……瑞瀬くん…」
「…」
「海、行こ」
「…え」
「海へ行くのに、理由はいらないんだよ、今度は自転車がないから、2人で歩こう?」
「うん…」
「よし!決まりね!行こう!」
そう言って僕の手を引く。あの日のように。2人で走ったり歩いたりを繰り返して夕日の差す浜辺に着いた。途中で靴下を急いで脱いで浅瀬に走っていく。あの日みたい。でも一つ違うのは、僕もついて行った所。誘われる前に、自分から靴下を脱いで彼女に手を引かれて、一緒に海へ入った。
「めずらしいね、自分から来るなんて!」
「うん」
「…瑞瀬くん、ごめんね。
君と私は、ずっと、一緒になれない。
私ね、幽霊なの―。
この前新幹線で、瑞瀬くん話してくれたよね。中学生の頃入院してた時に、会った女の人と病院の屋上で話したって。その時言ってくれたこと、今でも覚えてるよ。
学校も行けない、普通じゃない私に、君は大丈夫だよって、この先もちゃんと生きれるよって、言ってくれた。
あのね、その人、私だよ。
余命宣告もされてて、もう死んじゃう私だったけど、その時から大丈夫って思えた。
死んじゃったけど、人生楽しかったって思えた。
―瑞瀬君に、会えたから。
ありがとう、おかげで何故かは私もわからないけど、この夏だけはまた会いに来れた。
ずっと会いたかったよ。
たくさん思い出を作れて良かった。
ずっと入院っていう人生だったから、初めて雪も見れた。
本当に、楽しかった。
君が、好きだったよ。
今も、大好きだよ。
でも夏が終われば消えちゃうんだ。
ごめんね。
帰りのバスで、窓に手をついた時、手の周りが透けてる気がしてびっくりしちゃったよ。
でも、私がいた証拠があるから。
瑞瀬くん。私と一緒に夏を生きてくれて、ありがとう―。
またね―。」
そう言いながら薄れていく風夏の影を、ただ見つめることしかできない。あんなに眩しかった夏も、いつの間にか終わりを迎えていた。でもいつか、風夏が言っていたことを思い出す。
『死んじゃった人って、聴覚が最後の最後まで残るんだよ』
「ありがとう。ありがとうありがとう。ありがとう―。」
声のかぎり、叫ぶ。誰もいない海に。
風夏が最後、僕にかけようとした海水が彼女のいない海に雨のように落ちた。
あれから彼女の姿を見ることはなく、夏休みは終わり、9月になった。彼女が消えてしまった日からは夏の前の日常のように1人で向き合う時間が増えた。自然にスマホを触ることも減り、最後に河川敷で話しながら見た時以来、彼女との写真を見返すことがなくなってしまった。
「そろそろ、しっかりしないと」
自分を奮い立たせて制服に腕を通す。今日は始業式だ。また、普通の日が始まる。
ゆっくり歩きながら久しぶりにスマホを見返す。
涙が溢れた―。
彼女がいなかった。何の写真にも、いなかった。
『でも、私がいた証拠があるよ。』
あの日家から帰ってきてからベッドの枕元にずっと置いてある目覚まし時計。
彼女は確かに、いた。
僕は確かに、今でも彼女に想いを馳せている―。
「…」
「海、行こ」
「…え」
「海へ行くのに、理由はいらないんだよ、今度は自転車がないから、2人で歩こう?」
「うん…」
「よし!決まりね!行こう!」
そう言って僕の手を引く。あの日のように。2人で走ったり歩いたりを繰り返して夕日の差す浜辺に着いた。途中で靴下を急いで脱いで浅瀬に走っていく。あの日みたい。でも一つ違うのは、僕もついて行った所。誘われる前に、自分から靴下を脱いで彼女に手を引かれて、一緒に海へ入った。
「めずらしいね、自分から来るなんて!」
「うん」
「…瑞瀬くん、ごめんね。
君と私は、ずっと、一緒になれない。
私ね、幽霊なの―。
この前新幹線で、瑞瀬くん話してくれたよね。中学生の頃入院してた時に、会った女の人と病院の屋上で話したって。その時言ってくれたこと、今でも覚えてるよ。
学校も行けない、普通じゃない私に、君は大丈夫だよって、この先もちゃんと生きれるよって、言ってくれた。
あのね、その人、私だよ。
余命宣告もされてて、もう死んじゃう私だったけど、その時から大丈夫って思えた。
死んじゃったけど、人生楽しかったって思えた。
―瑞瀬君に、会えたから。
ありがとう、おかげで何故かは私もわからないけど、この夏だけはまた会いに来れた。
ずっと会いたかったよ。
たくさん思い出を作れて良かった。
ずっと入院っていう人生だったから、初めて雪も見れた。
本当に、楽しかった。
君が、好きだったよ。
今も、大好きだよ。
でも夏が終われば消えちゃうんだ。
ごめんね。
帰りのバスで、窓に手をついた時、手の周りが透けてる気がしてびっくりしちゃったよ。
でも、私がいた証拠があるから。
瑞瀬くん。私と一緒に夏を生きてくれて、ありがとう―。
またね―。」
そう言いながら薄れていく風夏の影を、ただ見つめることしかできない。あんなに眩しかった夏も、いつの間にか終わりを迎えていた。でもいつか、風夏が言っていたことを思い出す。
『死んじゃった人って、聴覚が最後の最後まで残るんだよ』
「ありがとう。ありがとうありがとう。ありがとう―。」
声のかぎり、叫ぶ。誰もいない海に。
風夏が最後、僕にかけようとした海水が彼女のいない海に雨のように落ちた。
あれから彼女の姿を見ることはなく、夏休みは終わり、9月になった。彼女が消えてしまった日からは夏の前の日常のように1人で向き合う時間が増えた。自然にスマホを触ることも減り、最後に河川敷で話しながら見た時以来、彼女との写真を見返すことがなくなってしまった。
「そろそろ、しっかりしないと」
自分を奮い立たせて制服に腕を通す。今日は始業式だ。また、普通の日が始まる。
ゆっくり歩きながら久しぶりにスマホを見返す。
涙が溢れた―。
彼女がいなかった。何の写真にも、いなかった。
『でも、私がいた証拠があるよ。』
あの日家から帰ってきてからベッドの枕元にずっと置いてある目覚まし時計。
彼女は確かに、いた。
僕は確かに、今でも彼女に想いを馳せている―。