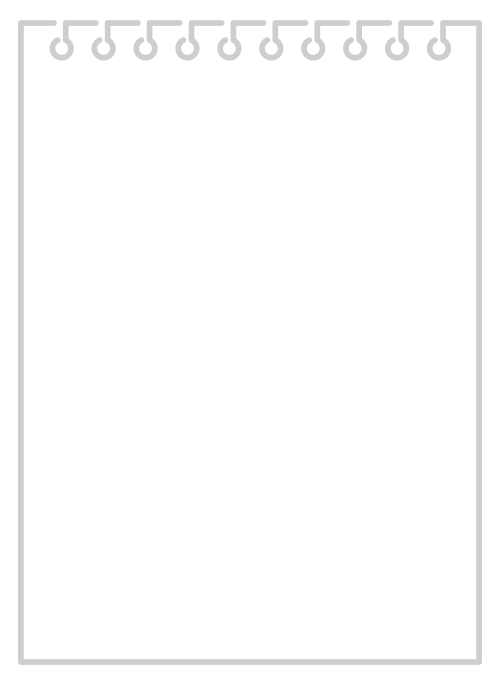「ほんとにすごいね」
夏休みでも平日だからか、教会の中は人が少なかった。窓越しに見える氷のオブジェや雪の結晶がモチーフにされたガラス張りの部屋。どれもが夏とは思えない、涼し気な様子。長い螺旋階段の真ん中には噴水のようなオブジェ。全てが美しい、その言葉では足りないくらいの綺麗で見入ってしまう魅力を持っている。
建物の真ん中の結婚式が行われる部分へ足を運ぶ。
「うわぁ……!」
「すごい」
「ね!」
高い天井に描かれた空の模様。幻想的。神秘的。そうなんだけど、その言葉では表しきれない。誰か、ぴったりな言葉を教えてほしい。そう願うほどのものだった。
それから何時間も同じところへ行ったりきたりしながら閉館の時間近くまで見てまわる。そろそろ閉館だからと外へ出ると空はもう暗く、夜になっていた。
「楽しかった…綺麗だった…雪って、こんな感じなんだなぁ……」
今日という時間を噛みしめるように言う彼女は表情を明るくして言った。
「お腹すいたね!ホテルとったんだよ、あ、ホテル代は私が出すから気にしないでね」
「そんな、悪いよ」
「大丈夫大丈夫、ついてきてくれてありがとう」
「…でも」
「大丈夫!バス来るよ!」
午後に降りたバス停からホテルに直通するバスが出ているというのでそこへ向かう。5分ほど夜風にあたって涼んでいるとすぐにバスが来た。
「本当に、一緒に来てくれてありがとう」
そう言いながら彼女はバスに乗り込んだ。僕も続く。今度は自分で荷物を持っていた。バスで移動している時も静かな時間が流れていく。教会をあとにしたのが悲しいようで、経験が嬉しいようで、複雑な表情を浮かべる彼女に僕は何も言えなかった。
「着いたね、ここだよ」
「え…!?」
「どうした?降りるよ?」
想像していたホテルと違って、驚いた。本当に高級そうというかなんというか。一流芸能人が止まるようなホテルだった。
「本当にここ?」
「そうだよ、スイートルームとかじゃないやつだけど許してねー」
軽くそう受け答えしながら彼女はチェックインをしに行ってしまった。今までに来たことがない大きなロビーを田舎者のように見渡す。本当に田舎者だということを少し忘れていた。ぼんやりと館内の装飾を見ていたら彼女が2つの鍵を持ってきた。
「夜は寝る直前まで私の部屋でゲームかなんかしようね」
「別にいいけど」
「決まりね!お部屋行こっか!」
館内の構造の想像もできない僕はただただ彼女についていく。エレベーターで7階まで上って、何回曲がったか分からないほど曲がって着いた隣り合った2つの部屋が僕達の部屋だった。
鍵を開けてからドアノブに力を込めた瞬間に、驚いた。広い。綺麗。大きい。初めて泊まる大きなホテルに頬が緩んだ。
「なにニヤニヤしてーんの」
ニヤニヤしながらそういう彼女の声で我に返り、「荷物置いたらゲームしに行くから」とだけ言ってドアを閉めた。荷物を置く動作なんて1分あれば終わるけど、ちょっとルームツアーという名のものがしてみたくて5分後くらいに彼女の部屋をノックした。
「遅かったね。部屋が大きくて気になっちゃった?」
またもニヤニヤしながらそう言う彼女の言葉で顔を赤らめる。
「別に…?」
「顔赤いよ、私がありったけの勇気を振り絞って告白した時くらい」
「別に…?」
「ま、良いや。ゲームでもする?ビデオゲーム持ってきたんだぁ」
だからあんなに荷物が重かったのか。何度も持たされたあのバッグの重さの理由がやっと解明された。
有名なゲームをいくつかしながら冗談を言い合って笑う。そんなことを夜中まで続け、彼女が眠いと言い出したので自室に戻ることにした。戻る直前、彼女はなるべく早く寝たいという思いが伝わる速さで言った。
「明日、10時のバスに乗って帰るから9時半、ドアの前集合ね!瑞瀬くんは朝苦手って感じだから8時には起きてね!」
よく重い瞼でそれを噛まずに言ったと思う。その後は僕が出ていく前にベッドに突っ伏して寝ていた。
朝、けたたましく響く電子音で7時半に目が覚めた。こんなに大きな音でアラームはつけていなかったから不思議に思い音に近づいて驚いた。そこには絶対に僕のではない目覚まし時計が入っていた。思い出した。一度だけ、荷物上に上げてあげるよ、って新幹線で彼女に荷物を預けたことがあった。あの時だな。そこからはあと30分しか寝れないし、10分ごとに鳴る目覚まし時計の止め方がわからなかったから仕方なく部屋を出る準備をすることにした。彼女のと思われる目覚まし時計の所為、いやおかげというべきか、30分前にはチェックアウトの準備ができていた。暇だから小説でも読もうかとバッグから本を出そうとした時。
「みーずーせーくん!起きたー?起きたよねさすがにー!」
「あのさ、時計…」
勢いよくドアを開けると「そんなに勢いよく開けると危ないじゃん」と頬をふくらます彼女がいた。
「僕のバッグに目覚まし時計入れたでしょ」
「えばれた!」
「逆にどこをどうしたらばれないと思えるの?」
「まぁまぁ、感謝してください!おかげで時間に余裕が持てるでしょ」
「僕遅刻したことないけど…」
「良いから良いから!さ、帰ろ!」
そう言いながら僕の背中を押しながら来た時みたいに様々な角を曲がってエレベーターに乗る。鍵を返してチェックアウトを済ませ、またバスに乗り込む。ホテルの窓側に座った彼女が「楽しかったなぁ」と声を漏らす。
「また来れば良いじゃん。教会も」
「……そうだね。」
少し寂しげな表情をしながらゆっくり進むバスの所為で見えなくなっていくホテルを名残惜しそうに見つめる。窓に手を置いて見ようとした時、何かに気がついてすぐに窓から手を離した。駅に直通するバスだから来る時よりもはやく駅に着くことができた。朝ご飯は各々で食べたからお昼の分だけ買っておく。彼女のお昼は行く時より少ない。
「食欲ないの?」
「ううん大丈夫」
終始寂しそうな彼女だったから行く時よりは少ない会話を交わしながら新幹線に乗った。
「今度は真面目に荷物上げてあげるよ」
ホテルを出てから久しぶりに見た彼女の笑顔に少し安心する。
「できれば目覚まし時計引き取ってくれると嬉しいけど」
「あげる。私の…しょうこだね」
「証拠ってなに?」
何も言わず微笑む彼女は時計を出さずに僕の荷物を上に上げた。少しだけご飯を食べて、僕は眠くなってしまった。
「寝ていいよ」
「眠くないの?」
「私は起きてたいから大丈夫」
「そっか」
「うん…」
彼女はじっと窓の外を見つめている。少しうたた寝をして起きた後も、何一つ変わらず景色を見つめていた。ずっと、今見ている景色を目に焼き付けるように。
「瑞瀬くんもうすぐ着くよ!本当に一緒に来てくれてありがとう」
彼女は何かを振り払うように明るい声でそう言った。
「ううん、楽しかった」
「そっか、それなら私も嬉しい!」
在来線に乗り換える駅へ到着したことを知らせるアナウンスが鳴り、2人で荷物を持ってホームへ降りる。もうそれが普通になっていたから彼女の荷物も持とうとした。
「いいよいいよ!私自分のちゃんと持てる!」
「最初はずっと僕が持ってたけどね」
「ごめんごめん、持ちます持ちます!」
「うん。行こうか」
「そうだね!もう迷わないから着いてきて!」
「在来線のホームに行くのは得意だもんね」
「やっと特技が活かせるよ!」
張り切って大股で在来線のホームへ向かう彼女の後ろを少し小走りで追いかける。ちょうどホームに電車が来ていたから2人で乗り込んだ。
「最後の電車だね」
「ここからが長いけどね」
「まぁね、短いよりいいよ」
少しずつ田畑が増え、最寄り駅が近づいていく。
「終わっちゃうな、」
「また来よう」
「うん……。」
まだ終わってほしくない、という僕らの思いに逆らう時の流れは残酷だ。こんなにも楽しかったと思えた旅行は初めてだったから、終わってほしくないという思いは僕の中にも確実にあった。2人で少しずつ人が減っていく車内を眺めながら思い出話をする。2人で優雅なお昼ご飯を食べたねとか、遠い教会に行ったねとか。少しでも忘れるのが遅くなることを願いながら。それでもやっぱり何にでも終わりという瞬間が来るから、最寄駅へと到着してしまった。
「着いちゃった」
外はいつもの田舎町が広がっている。日は沈み始め、綺麗な夕日が海の水面で光り輝いている。最後の切符を改札で入れ、少し切ない気持ちになった。彼女はなぜか駅名が書かれている木製の看板を写真に収めた。
「この看板ならいつでも見られるよ」
「確かにそうかもね」
その後彼女はでも、と続ける。
「撮っておきたいの。……瑞瀬くん。本当に、ありがとう。楽しかったよ。ありがとう。」
「うん…君はありがとうってよく言ってくれるよね」
「いつ言えなくなるかわかんないからね。言える時に全部言おうと思ってるの」
少し茶色の髪を耳にかけて微笑む。
それを見て、思った。伝えられるうちに、伝える。僕は君に惹かれたこと。君の隣にこれからもいたいこと。
僕の想いを全部、君に伝えよう―。
夏休みでも平日だからか、教会の中は人が少なかった。窓越しに見える氷のオブジェや雪の結晶がモチーフにされたガラス張りの部屋。どれもが夏とは思えない、涼し気な様子。長い螺旋階段の真ん中には噴水のようなオブジェ。全てが美しい、その言葉では足りないくらいの綺麗で見入ってしまう魅力を持っている。
建物の真ん中の結婚式が行われる部分へ足を運ぶ。
「うわぁ……!」
「すごい」
「ね!」
高い天井に描かれた空の模様。幻想的。神秘的。そうなんだけど、その言葉では表しきれない。誰か、ぴったりな言葉を教えてほしい。そう願うほどのものだった。
それから何時間も同じところへ行ったりきたりしながら閉館の時間近くまで見てまわる。そろそろ閉館だからと外へ出ると空はもう暗く、夜になっていた。
「楽しかった…綺麗だった…雪って、こんな感じなんだなぁ……」
今日という時間を噛みしめるように言う彼女は表情を明るくして言った。
「お腹すいたね!ホテルとったんだよ、あ、ホテル代は私が出すから気にしないでね」
「そんな、悪いよ」
「大丈夫大丈夫、ついてきてくれてありがとう」
「…でも」
「大丈夫!バス来るよ!」
午後に降りたバス停からホテルに直通するバスが出ているというのでそこへ向かう。5分ほど夜風にあたって涼んでいるとすぐにバスが来た。
「本当に、一緒に来てくれてありがとう」
そう言いながら彼女はバスに乗り込んだ。僕も続く。今度は自分で荷物を持っていた。バスで移動している時も静かな時間が流れていく。教会をあとにしたのが悲しいようで、経験が嬉しいようで、複雑な表情を浮かべる彼女に僕は何も言えなかった。
「着いたね、ここだよ」
「え…!?」
「どうした?降りるよ?」
想像していたホテルと違って、驚いた。本当に高級そうというかなんというか。一流芸能人が止まるようなホテルだった。
「本当にここ?」
「そうだよ、スイートルームとかじゃないやつだけど許してねー」
軽くそう受け答えしながら彼女はチェックインをしに行ってしまった。今までに来たことがない大きなロビーを田舎者のように見渡す。本当に田舎者だということを少し忘れていた。ぼんやりと館内の装飾を見ていたら彼女が2つの鍵を持ってきた。
「夜は寝る直前まで私の部屋でゲームかなんかしようね」
「別にいいけど」
「決まりね!お部屋行こっか!」
館内の構造の想像もできない僕はただただ彼女についていく。エレベーターで7階まで上って、何回曲がったか分からないほど曲がって着いた隣り合った2つの部屋が僕達の部屋だった。
鍵を開けてからドアノブに力を込めた瞬間に、驚いた。広い。綺麗。大きい。初めて泊まる大きなホテルに頬が緩んだ。
「なにニヤニヤしてーんの」
ニヤニヤしながらそういう彼女の声で我に返り、「荷物置いたらゲームしに行くから」とだけ言ってドアを閉めた。荷物を置く動作なんて1分あれば終わるけど、ちょっとルームツアーという名のものがしてみたくて5分後くらいに彼女の部屋をノックした。
「遅かったね。部屋が大きくて気になっちゃった?」
またもニヤニヤしながらそう言う彼女の言葉で顔を赤らめる。
「別に…?」
「顔赤いよ、私がありったけの勇気を振り絞って告白した時くらい」
「別に…?」
「ま、良いや。ゲームでもする?ビデオゲーム持ってきたんだぁ」
だからあんなに荷物が重かったのか。何度も持たされたあのバッグの重さの理由がやっと解明された。
有名なゲームをいくつかしながら冗談を言い合って笑う。そんなことを夜中まで続け、彼女が眠いと言い出したので自室に戻ることにした。戻る直前、彼女はなるべく早く寝たいという思いが伝わる速さで言った。
「明日、10時のバスに乗って帰るから9時半、ドアの前集合ね!瑞瀬くんは朝苦手って感じだから8時には起きてね!」
よく重い瞼でそれを噛まずに言ったと思う。その後は僕が出ていく前にベッドに突っ伏して寝ていた。
朝、けたたましく響く電子音で7時半に目が覚めた。こんなに大きな音でアラームはつけていなかったから不思議に思い音に近づいて驚いた。そこには絶対に僕のではない目覚まし時計が入っていた。思い出した。一度だけ、荷物上に上げてあげるよ、って新幹線で彼女に荷物を預けたことがあった。あの時だな。そこからはあと30分しか寝れないし、10分ごとに鳴る目覚まし時計の止め方がわからなかったから仕方なく部屋を出る準備をすることにした。彼女のと思われる目覚まし時計の所為、いやおかげというべきか、30分前にはチェックアウトの準備ができていた。暇だから小説でも読もうかとバッグから本を出そうとした時。
「みーずーせーくん!起きたー?起きたよねさすがにー!」
「あのさ、時計…」
勢いよくドアを開けると「そんなに勢いよく開けると危ないじゃん」と頬をふくらます彼女がいた。
「僕のバッグに目覚まし時計入れたでしょ」
「えばれた!」
「逆にどこをどうしたらばれないと思えるの?」
「まぁまぁ、感謝してください!おかげで時間に余裕が持てるでしょ」
「僕遅刻したことないけど…」
「良いから良いから!さ、帰ろ!」
そう言いながら僕の背中を押しながら来た時みたいに様々な角を曲がってエレベーターに乗る。鍵を返してチェックアウトを済ませ、またバスに乗り込む。ホテルの窓側に座った彼女が「楽しかったなぁ」と声を漏らす。
「また来れば良いじゃん。教会も」
「……そうだね。」
少し寂しげな表情をしながらゆっくり進むバスの所為で見えなくなっていくホテルを名残惜しそうに見つめる。窓に手を置いて見ようとした時、何かに気がついてすぐに窓から手を離した。駅に直通するバスだから来る時よりもはやく駅に着くことができた。朝ご飯は各々で食べたからお昼の分だけ買っておく。彼女のお昼は行く時より少ない。
「食欲ないの?」
「ううん大丈夫」
終始寂しそうな彼女だったから行く時よりは少ない会話を交わしながら新幹線に乗った。
「今度は真面目に荷物上げてあげるよ」
ホテルを出てから久しぶりに見た彼女の笑顔に少し安心する。
「できれば目覚まし時計引き取ってくれると嬉しいけど」
「あげる。私の…しょうこだね」
「証拠ってなに?」
何も言わず微笑む彼女は時計を出さずに僕の荷物を上に上げた。少しだけご飯を食べて、僕は眠くなってしまった。
「寝ていいよ」
「眠くないの?」
「私は起きてたいから大丈夫」
「そっか」
「うん…」
彼女はじっと窓の外を見つめている。少しうたた寝をして起きた後も、何一つ変わらず景色を見つめていた。ずっと、今見ている景色を目に焼き付けるように。
「瑞瀬くんもうすぐ着くよ!本当に一緒に来てくれてありがとう」
彼女は何かを振り払うように明るい声でそう言った。
「ううん、楽しかった」
「そっか、それなら私も嬉しい!」
在来線に乗り換える駅へ到着したことを知らせるアナウンスが鳴り、2人で荷物を持ってホームへ降りる。もうそれが普通になっていたから彼女の荷物も持とうとした。
「いいよいいよ!私自分のちゃんと持てる!」
「最初はずっと僕が持ってたけどね」
「ごめんごめん、持ちます持ちます!」
「うん。行こうか」
「そうだね!もう迷わないから着いてきて!」
「在来線のホームに行くのは得意だもんね」
「やっと特技が活かせるよ!」
張り切って大股で在来線のホームへ向かう彼女の後ろを少し小走りで追いかける。ちょうどホームに電車が来ていたから2人で乗り込んだ。
「最後の電車だね」
「ここからが長いけどね」
「まぁね、短いよりいいよ」
少しずつ田畑が増え、最寄り駅が近づいていく。
「終わっちゃうな、」
「また来よう」
「うん……。」
まだ終わってほしくない、という僕らの思いに逆らう時の流れは残酷だ。こんなにも楽しかったと思えた旅行は初めてだったから、終わってほしくないという思いは僕の中にも確実にあった。2人で少しずつ人が減っていく車内を眺めながら思い出話をする。2人で優雅なお昼ご飯を食べたねとか、遠い教会に行ったねとか。少しでも忘れるのが遅くなることを願いながら。それでもやっぱり何にでも終わりという瞬間が来るから、最寄駅へと到着してしまった。
「着いちゃった」
外はいつもの田舎町が広がっている。日は沈み始め、綺麗な夕日が海の水面で光り輝いている。最後の切符を改札で入れ、少し切ない気持ちになった。彼女はなぜか駅名が書かれている木製の看板を写真に収めた。
「この看板ならいつでも見られるよ」
「確かにそうかもね」
その後彼女はでも、と続ける。
「撮っておきたいの。……瑞瀬くん。本当に、ありがとう。楽しかったよ。ありがとう。」
「うん…君はありがとうってよく言ってくれるよね」
「いつ言えなくなるかわかんないからね。言える時に全部言おうと思ってるの」
少し茶色の髪を耳にかけて微笑む。
それを見て、思った。伝えられるうちに、伝える。僕は君に惹かれたこと。君の隣にこれからもいたいこと。
僕の想いを全部、君に伝えよう―。