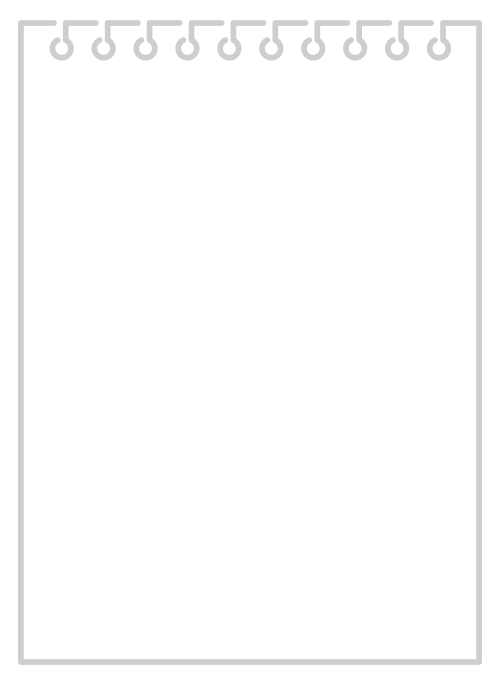「やっと着いたーーー!」
「ここからまた新幹線でしょ」
「切ないこと言わない。」
「…はい」
「どこから新幹線乗れるんだろ」
「さすがにこんな大きい駅初めてだからわかんない」
「スマホで調べちゃおっか」
少しスマホを操作してから「わかった!」と声を上げわかったことを伝えられた。
「こっち!ついてきて!」
そう言って手を引かれ連れられると着いたのはどうみても在来線のホームだった。
「…あれ?」
「これ、在来線だよね」
「…どうみても…」
何もしてない僕なのに、この状況が面白くて笑ってしまった。
「ちょっと、笑わないでよー!」
そう言いながら彼女までつられて笑う。これが、日常になる。その事実が嬉しく感じる。
「もっかい調べる!」
「調べてあげるよ」
「上から目線やめてください」
「…こっちだね」
しょうがない、という様子で後ろをついてくる彼女。その様子も少し可笑しく思えてきて歩きながら一人で笑ってしまった。
「何笑ってんのー」
「別に…」
と言いながらも笑う僕を見て彼女が眉を寄せる。
「ばかにしないでよ?」
馬鹿みたいに笑いあう今が初めて感じた心からの幸せかもしれない。ありがとう…直接言う勇気は臆病な僕にはないから、その5文字を頭に浮かべる。浮かべないよりはましだよね、そう言い聞かせながら。
ちゃんと伝えればよかった。そんな後悔しないこと、心の何処かで密かに願っていた。
「ほら、着いたよ」
「私だって本気出せば着けたし。だいたい、なんか堅苦しい雰囲気かなって思って、和らげてあげようっていうか、なんていうか。笑わせてあげようと思って分かってたけど在来線の方行って笑わせたっていうか…とにかく!私は分かって…」
「切符買った?」
「人の話は最後まで聞くって習わなかった?」
「買ってなかったらあそこの窓口いかないと」
「ねぇ!」
「…」
「知ってる?死んじゃった人って、聴覚が最後の最後まで残るんだよ」
「…」
「だから人の話をちゃんと聞くのってすごい大切」
「…」
「ずっと黙ってんじゃん!もういいよ!切符買いに行こ!」
窓口に並んでいる間にも少しずつ列は伸びていく。
「都会って人多いねー」
「僕も思ってた」
「意思疎通したね!」
「別にそういうわけではないと思うけど」
「冷たいな」
「もうすぐ順番来るよ」
「冷たいな!」
2人分の席を取り、あと少しで新幹線に乗れるからとお昼ご飯を買ってホームで待つことになった。
僕はおにぎりと漬物のセット。彼女はサンドイッチとパスタサラダと唐揚げとカップに入ったスープ。
「よく新幹線で漬物食べれるね。周りが漬物って感じの匂いになっちゃうじゃん」
「炭水化物こんなに大量に摂る人初めてみたよ」
「私は周りの人に迷惑かけてないからだいじょーぶ。」
「…。」
「言い返せないね、どんまい」
「いつからかわからないけどすごい上から目線になったよね」
「褒め言葉ありがとう」
車内の清掃が終わり、1番に乗り込む彼女。荷物は僕が代わりに持っていることを忘れているらしい。
「新幹線、初めて乗る」
「修学旅行とかは?」
「んー、たぶん風邪ひいてたんだと思う。だいたい風邪ひいてるからなぁー瑞瀬くんは病気しないの?」
「一回入院したことあるかな」
「元気そうなのに!なんで?」
「中学生の頃、事故で怪我しちゃって」
「んーそうなんだ、退屈でしょ?入院とかって」
「そうでもないよ。病院の屋上とかだと患者さんと話したりするし」
「誰かと仲良くなった?」
「んー、病院にあんまり男子がいなかったから仲良かったのは同じ年くらいの女の人とかと話したかな」
「そうなんだ…」
そう言いながらまだ発車もしてない車内でサンドイッチの袋を開ける。食べるのかと思ったらカップサラダの蓋も開けてその上に置いて。唐揚げも開けてその蓋に箸を置いて。とどめはスープを開けてスプーンでかき混ぜる。ランチセットの準備を発車までの時間で丁寧にこなした。すこし圧倒されながらも漬物を開けると「フランスとかイギリスって感じの雰囲気を漬物臭が邪魔してきた」と怒られた。だから入っていたビニールの中で爪楊枝にさしてギリギリまでビニールに入れたまま口に運ぶ。そして入れた瞬間に爪楊枝をビニールに入れてすぐさま結ぶ。そんな高度な技術を使う羽目になった。
発車に次の駅につく頃には2人共フードファイターなみに食事を第一に考えている感じが醸し出されていた。少し恥ずかしくなって今更だけど漬物をしまっておにぎりを食べることにした。でもツナマヨを買ってしまったから食べ終わったらしょっぱいものが食べたくなってしまって仕方なくまた漬物を開けた。
こんな調子で2人優雅なランチタイムを嗜んでいるとあっという間に最寄り駅に着いてしまった。午後の3時くらい。ちょうど日差しが差す時間で目的地は眩しい日差しと多くの人で体感温度はすごく高い。
「このあとどうするの?」
何もプランを聞いていなくて彼女に任せっきりの僕はただひたすらにハンカチで汗を拭き取ることしかしていない。
「よし!じゃあ帰るか!」
「すごい電車乗って、新幹線も乗ってここまで来て、僕汗を拭くことしかしてないよ」
「しょーだん!冗談冗談!どんな顔するかなって思ってさ。面白かったよ」
「ありがとうって言うべきなの?」
クスクス笑う彼女の手にはこの地のガイドブック。
「ここ行こ!」
彼女が指差す場所は氷や雪に囲まれた教会のような場所だった。
「雪…見たいの!行こ!」
連れられてバスに乗る。ここからそこまで遠くはないらしい。10分ちょっとバスに揺られると目的の教会についた。
「着いたね!楽しみ!」
楽しみ、嬉しい、そんな言葉を連呼しながら走っていく彼女をゆっくり追いかける。荷物は僕が代わりに持っていることを忘れているか、忘れているふりをしているらしい。それでも走っていく彼女の笑顔がすごく眩しく見える。ずっと隣りにいたい、そう思った。
―僕は彼女に、恋をした。
「ここからまた新幹線でしょ」
「切ないこと言わない。」
「…はい」
「どこから新幹線乗れるんだろ」
「さすがにこんな大きい駅初めてだからわかんない」
「スマホで調べちゃおっか」
少しスマホを操作してから「わかった!」と声を上げわかったことを伝えられた。
「こっち!ついてきて!」
そう言って手を引かれ連れられると着いたのはどうみても在来線のホームだった。
「…あれ?」
「これ、在来線だよね」
「…どうみても…」
何もしてない僕なのに、この状況が面白くて笑ってしまった。
「ちょっと、笑わないでよー!」
そう言いながら彼女までつられて笑う。これが、日常になる。その事実が嬉しく感じる。
「もっかい調べる!」
「調べてあげるよ」
「上から目線やめてください」
「…こっちだね」
しょうがない、という様子で後ろをついてくる彼女。その様子も少し可笑しく思えてきて歩きながら一人で笑ってしまった。
「何笑ってんのー」
「別に…」
と言いながらも笑う僕を見て彼女が眉を寄せる。
「ばかにしないでよ?」
馬鹿みたいに笑いあう今が初めて感じた心からの幸せかもしれない。ありがとう…直接言う勇気は臆病な僕にはないから、その5文字を頭に浮かべる。浮かべないよりはましだよね、そう言い聞かせながら。
ちゃんと伝えればよかった。そんな後悔しないこと、心の何処かで密かに願っていた。
「ほら、着いたよ」
「私だって本気出せば着けたし。だいたい、なんか堅苦しい雰囲気かなって思って、和らげてあげようっていうか、なんていうか。笑わせてあげようと思って分かってたけど在来線の方行って笑わせたっていうか…とにかく!私は分かって…」
「切符買った?」
「人の話は最後まで聞くって習わなかった?」
「買ってなかったらあそこの窓口いかないと」
「ねぇ!」
「…」
「知ってる?死んじゃった人って、聴覚が最後の最後まで残るんだよ」
「…」
「だから人の話をちゃんと聞くのってすごい大切」
「…」
「ずっと黙ってんじゃん!もういいよ!切符買いに行こ!」
窓口に並んでいる間にも少しずつ列は伸びていく。
「都会って人多いねー」
「僕も思ってた」
「意思疎通したね!」
「別にそういうわけではないと思うけど」
「冷たいな」
「もうすぐ順番来るよ」
「冷たいな!」
2人分の席を取り、あと少しで新幹線に乗れるからとお昼ご飯を買ってホームで待つことになった。
僕はおにぎりと漬物のセット。彼女はサンドイッチとパスタサラダと唐揚げとカップに入ったスープ。
「よく新幹線で漬物食べれるね。周りが漬物って感じの匂いになっちゃうじゃん」
「炭水化物こんなに大量に摂る人初めてみたよ」
「私は周りの人に迷惑かけてないからだいじょーぶ。」
「…。」
「言い返せないね、どんまい」
「いつからかわからないけどすごい上から目線になったよね」
「褒め言葉ありがとう」
車内の清掃が終わり、1番に乗り込む彼女。荷物は僕が代わりに持っていることを忘れているらしい。
「新幹線、初めて乗る」
「修学旅行とかは?」
「んー、たぶん風邪ひいてたんだと思う。だいたい風邪ひいてるからなぁー瑞瀬くんは病気しないの?」
「一回入院したことあるかな」
「元気そうなのに!なんで?」
「中学生の頃、事故で怪我しちゃって」
「んーそうなんだ、退屈でしょ?入院とかって」
「そうでもないよ。病院の屋上とかだと患者さんと話したりするし」
「誰かと仲良くなった?」
「んー、病院にあんまり男子がいなかったから仲良かったのは同じ年くらいの女の人とかと話したかな」
「そうなんだ…」
そう言いながらまだ発車もしてない車内でサンドイッチの袋を開ける。食べるのかと思ったらカップサラダの蓋も開けてその上に置いて。唐揚げも開けてその蓋に箸を置いて。とどめはスープを開けてスプーンでかき混ぜる。ランチセットの準備を発車までの時間で丁寧にこなした。すこし圧倒されながらも漬物を開けると「フランスとかイギリスって感じの雰囲気を漬物臭が邪魔してきた」と怒られた。だから入っていたビニールの中で爪楊枝にさしてギリギリまでビニールに入れたまま口に運ぶ。そして入れた瞬間に爪楊枝をビニールに入れてすぐさま結ぶ。そんな高度な技術を使う羽目になった。
発車に次の駅につく頃には2人共フードファイターなみに食事を第一に考えている感じが醸し出されていた。少し恥ずかしくなって今更だけど漬物をしまっておにぎりを食べることにした。でもツナマヨを買ってしまったから食べ終わったらしょっぱいものが食べたくなってしまって仕方なくまた漬物を開けた。
こんな調子で2人優雅なランチタイムを嗜んでいるとあっという間に最寄り駅に着いてしまった。午後の3時くらい。ちょうど日差しが差す時間で目的地は眩しい日差しと多くの人で体感温度はすごく高い。
「このあとどうするの?」
何もプランを聞いていなくて彼女に任せっきりの僕はただひたすらにハンカチで汗を拭き取ることしかしていない。
「よし!じゃあ帰るか!」
「すごい電車乗って、新幹線も乗ってここまで来て、僕汗を拭くことしかしてないよ」
「しょーだん!冗談冗談!どんな顔するかなって思ってさ。面白かったよ」
「ありがとうって言うべきなの?」
クスクス笑う彼女の手にはこの地のガイドブック。
「ここ行こ!」
彼女が指差す場所は氷や雪に囲まれた教会のような場所だった。
「雪…見たいの!行こ!」
連れられてバスに乗る。ここからそこまで遠くはないらしい。10分ちょっとバスに揺られると目的の教会についた。
「着いたね!楽しみ!」
楽しみ、嬉しい、そんな言葉を連呼しながら走っていく彼女をゆっくり追いかける。荷物は僕が代わりに持っていることを忘れているか、忘れているふりをしているらしい。それでも走っていく彼女の笑顔がすごく眩しく見える。ずっと隣りにいたい、そう思った。
―僕は彼女に、恋をした。