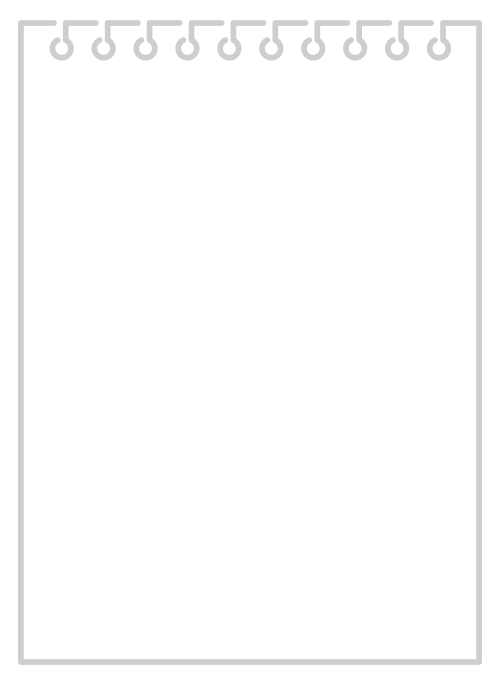「この前の海、久しぶりで楽しかったな」
「うん」
君に会いたかったと言われたあの日から、僕にとっては非日常が続いている。
今日は彼女に連れられて、少し遠出をすることになった。家族以外の誰かとどこかへ一緒に出かけること自体が珍しい。
「もうちょっとで駅着きますね!楽しみだー!」
「あのさ、敬語じゃなくて良いよ」
クラスメイトからも敬語を使われるくらい誰かと話すときは敬語を好む僕だけど、彼女から敬語で話されるとなんとなく距離を感じてしまう。その理由は僕にも分からない。恋人という関係、僕にとっての彼女になっているからか!?僕が断らなかったことが今を導いているのに、一人で考えて一人で顔を赤くする。
「じゃあ、そうするね」
「うん」
まだ顔が熱い。熱があるんじゃないかと思うくらい。
「着いたー!」
田舎町のこの町にとっては一つの貴重な駅。のはずなのに、相変わらず人はまだらだ。
「えっと、新幹線に乗り換えられる駅に行きたいから…」
「じゃあこの切符だね」
少し錆びた路線図の一つの駅を指差し、切符発行のボタンを示す。
「おー!詳しいね」
「産まれてからずっとここにいるからね」
「そっか!じゃあその切符買おう」
2人で同じ切符を手にし、ホームへ向かう。
ずっと昔からあるホーム。こんなに電車に乗るのが楽しみになったことはあるだろうか。少しずつ非日常が日常になっていく気がする。そんなことをぼんやりと考えているうちに、電車が来たらしい。彼女が電車に足を踏み入れ手招きしている。
「瑞瀬くん?行こ!」
「うん」
こんなに軽い足取りで電車に乗るのは初めて。彼女は僕にたくさんの初めてをくれる。
「結構遠いね」
10分ほど電車に揺られていると隣に座る彼女が退屈そうにそう言った。
「しょうがないよ、田舎の中の田舎って感じだし」
「確かにね」
「君はさ、ずっとこの町にいた?見たことないし、名前とか聞いたことがないっていうか…」
「…いたよ。」
もう聞かないで。そう聞こえたような気がする。ずっと明るい口調の彼女からは想像できないような、ちょっと寂しげな、そんな声。その後の沈黙がやけに静かに感じて彼女が消えてしまったのかと思った。我に返って隣を見ると白いワンピースを身にまとったいつもの彼女がいて安堵する。
「ねぇ」
珍しく真正面を見たまま口を開く彼女の姿に少し驚く。
「びっくりした!?私、いないと思ったでしょ?」
「…?」
「ちょっとびっくりするかなって思って黙ってみましたー。私にとってはすごい難しかったんだよ、いつもずっと喋ってるからかなぁ」
いつもの表情に戻って笑顔を見せる彼女を見て前よりも深い安心に包まれる。
「うん、びっくりした」
「でしょ!退屈だったからちょっとドッキリ仕掛けてみました」
初めて話したときみたいに舌を出して笑う彼女。
夏が終わって、秋が来ても、このままこの笑顔の隣にいたい。そんな願いを願ってしまう。
―僕は君に、恋したのかもしれない。
「うん」
君に会いたかったと言われたあの日から、僕にとっては非日常が続いている。
今日は彼女に連れられて、少し遠出をすることになった。家族以外の誰かとどこかへ一緒に出かけること自体が珍しい。
「もうちょっとで駅着きますね!楽しみだー!」
「あのさ、敬語じゃなくて良いよ」
クラスメイトからも敬語を使われるくらい誰かと話すときは敬語を好む僕だけど、彼女から敬語で話されるとなんとなく距離を感じてしまう。その理由は僕にも分からない。恋人という関係、僕にとっての彼女になっているからか!?僕が断らなかったことが今を導いているのに、一人で考えて一人で顔を赤くする。
「じゃあ、そうするね」
「うん」
まだ顔が熱い。熱があるんじゃないかと思うくらい。
「着いたー!」
田舎町のこの町にとっては一つの貴重な駅。のはずなのに、相変わらず人はまだらだ。
「えっと、新幹線に乗り換えられる駅に行きたいから…」
「じゃあこの切符だね」
少し錆びた路線図の一つの駅を指差し、切符発行のボタンを示す。
「おー!詳しいね」
「産まれてからずっとここにいるからね」
「そっか!じゃあその切符買おう」
2人で同じ切符を手にし、ホームへ向かう。
ずっと昔からあるホーム。こんなに電車に乗るのが楽しみになったことはあるだろうか。少しずつ非日常が日常になっていく気がする。そんなことをぼんやりと考えているうちに、電車が来たらしい。彼女が電車に足を踏み入れ手招きしている。
「瑞瀬くん?行こ!」
「うん」
こんなに軽い足取りで電車に乗るのは初めて。彼女は僕にたくさんの初めてをくれる。
「結構遠いね」
10分ほど電車に揺られていると隣に座る彼女が退屈そうにそう言った。
「しょうがないよ、田舎の中の田舎って感じだし」
「確かにね」
「君はさ、ずっとこの町にいた?見たことないし、名前とか聞いたことがないっていうか…」
「…いたよ。」
もう聞かないで。そう聞こえたような気がする。ずっと明るい口調の彼女からは想像できないような、ちょっと寂しげな、そんな声。その後の沈黙がやけに静かに感じて彼女が消えてしまったのかと思った。我に返って隣を見ると白いワンピースを身にまとったいつもの彼女がいて安堵する。
「ねぇ」
珍しく真正面を見たまま口を開く彼女の姿に少し驚く。
「びっくりした!?私、いないと思ったでしょ?」
「…?」
「ちょっとびっくりするかなって思って黙ってみましたー。私にとってはすごい難しかったんだよ、いつもずっと喋ってるからかなぁ」
いつもの表情に戻って笑顔を見せる彼女を見て前よりも深い安心に包まれる。
「うん、びっくりした」
「でしょ!退屈だったからちょっとドッキリ仕掛けてみました」
初めて話したときみたいに舌を出して笑う彼女。
夏が終わって、秋が来ても、このままこの笑顔の隣にいたい。そんな願いを願ってしまう。
―僕は君に、恋したのかもしれない。