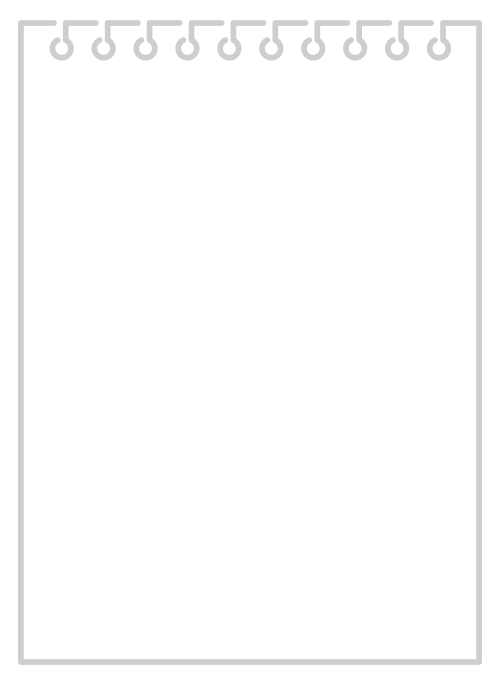「ずっと会いたかったよ」
本当になんでもない、ある夏休みの1日。
僕、松江 瑞瀬はほとんど人の通らない田舎町の河川敷で図書館の帰りに日影で本を読んでいた時、初対面の全く知らない少女にそう言われた。白いシャツに、黄色いスカート、少し茶色がかった髪を肩まで伸ばした少女。
でも、自分にむけて言ったわけではない可能性がある。彼女は僕の近くにいる誰かにそう言っているだけで、決して僕に向けて言っているわけではないかもしれない。そう思って黙々と本を読み続ける。視界に入る彼女の横顔はなんとなく透明感のある、綺麗な雰囲気だった。
「…なんで無視しちゃうの?」
少女が頬杖をつきながら顔を覗き込んでそういうから、今度は確実に僕に言っていると分かった。
「人違いではないですか…?」
「ううん、君に、会いに来た」
「勘違いです」
「だから違うって。松江 瑞瀬くん」
「名前……」
「ね、人違いじゃないでしょ」
いたずらをした子供のように舌を出す彼女の様子から見て、本当に僕に用があるらしい。
「…僕に何の用ですか」
「私、風夏です。瑞瀬くん、私と付き合ってください!」
言葉が出なくて、頭が真っ白になって、恋愛経験がない僕にとってどういう表情を取ったら良いのかわからない。この世に存在する混乱を表す言葉を使っても表しきれない混乱。そんな感じ。
でも彼女のどことなく真剣な表情と緊張しているのか少し震えていた声から、からかっているとは思えなかった。
「本気…ですか。」
「本気です。本気で本気なんです。誰よりも君を想っている自信があります。……だめ、ですか。」
彼女の表情を見ていると駄目です、なんて言い切れない。
「駄目ってわけではないんですけど…なんていうか…何で僕っていうか……顔が良いわけでも、とてつもなく人気者ってわけでも、なんでもないんです。だから…」
「だめじゃないっていうことは良いんですか!?嬉しい。嬉しいです!よろしくお願いします!瑞瀬くん!」
だからって言ったあと、自分でなんて言おうと思ったかすら覚えていない。緊張を隠しきれない彼女の表情が一瞬で明るくなって、すごく喜んでくれて。それくらいしか覚えられないほどの速さだった。それくらいの速さだったのに顔がすごく赤くなって、読んでいた本を落としそうになっちゃって―。本当に、よくわからない。素直な感想がそれだった。
「海行きましょ!」
「なんで海!?」
「海に行くのに理由なんてなくて大丈夫ですから!」
海はこの川のもう少し先にある。彼女は僕の手をひき、立たせた。そして「これこれ」という表情で僕が乗ってきた自転車を指差した。
「二人乗りで大丈夫ですよね!」
髪の先を指でくるくると回しながらそう笑った。
知らなかった。人の笑顔でこんなにも自分が染まっていくこと。そしてそれが、何も窮屈に感じないこと。
今日出会って、今日知って、今日会いたかったって言ってもらって、そんな彼女の存在が、こんなにも短い、あっという間の時間でも少しだけ大きくなっている気がする。いつもなら友達が冗談を言っている時、冗談にのれずに冷めた返事をするだけだ。でも、でも。
自転車の鍵をポケットから出してスタンドを外す。海がある方向へハンドルを向けた。
「やった!後ろ乗って良いですか?」
「二人乗り…だから…」
「乗りますね!行きましょう!」
彼女が空に突き上げた拳がスタートの合図のようにペダルを力強く踏む。
彼女が鼻歌を歌いながら進み、5分もしないうちに浜辺へ着いた。海から少し離れた所に自転車を停める。
彼女は僕の手をひき、海へ走っていく。途中で靴下を急いで脱ぎ、浅瀬へと走っていった。
「瑞瀬くんもおいでよーーー!」
肩の下まで伸ばした少し茶色がかった髪と黄色のロングスカートを揺らしながらそう笑った。
靴下を脱ぎ、少しだけズボンの裾を折る。
「来た来た!」
いつもより少しだけ早歩きで彼女の元へと駆けた。
いつもと違う、夏が始まる―。
本当になんでもない、ある夏休みの1日。
僕、松江 瑞瀬はほとんど人の通らない田舎町の河川敷で図書館の帰りに日影で本を読んでいた時、初対面の全く知らない少女にそう言われた。白いシャツに、黄色いスカート、少し茶色がかった髪を肩まで伸ばした少女。
でも、自分にむけて言ったわけではない可能性がある。彼女は僕の近くにいる誰かにそう言っているだけで、決して僕に向けて言っているわけではないかもしれない。そう思って黙々と本を読み続ける。視界に入る彼女の横顔はなんとなく透明感のある、綺麗な雰囲気だった。
「…なんで無視しちゃうの?」
少女が頬杖をつきながら顔を覗き込んでそういうから、今度は確実に僕に言っていると分かった。
「人違いではないですか…?」
「ううん、君に、会いに来た」
「勘違いです」
「だから違うって。松江 瑞瀬くん」
「名前……」
「ね、人違いじゃないでしょ」
いたずらをした子供のように舌を出す彼女の様子から見て、本当に僕に用があるらしい。
「…僕に何の用ですか」
「私、風夏です。瑞瀬くん、私と付き合ってください!」
言葉が出なくて、頭が真っ白になって、恋愛経験がない僕にとってどういう表情を取ったら良いのかわからない。この世に存在する混乱を表す言葉を使っても表しきれない混乱。そんな感じ。
でも彼女のどことなく真剣な表情と緊張しているのか少し震えていた声から、からかっているとは思えなかった。
「本気…ですか。」
「本気です。本気で本気なんです。誰よりも君を想っている自信があります。……だめ、ですか。」
彼女の表情を見ていると駄目です、なんて言い切れない。
「駄目ってわけではないんですけど…なんていうか…何で僕っていうか……顔が良いわけでも、とてつもなく人気者ってわけでも、なんでもないんです。だから…」
「だめじゃないっていうことは良いんですか!?嬉しい。嬉しいです!よろしくお願いします!瑞瀬くん!」
だからって言ったあと、自分でなんて言おうと思ったかすら覚えていない。緊張を隠しきれない彼女の表情が一瞬で明るくなって、すごく喜んでくれて。それくらいしか覚えられないほどの速さだった。それくらいの速さだったのに顔がすごく赤くなって、読んでいた本を落としそうになっちゃって―。本当に、よくわからない。素直な感想がそれだった。
「海行きましょ!」
「なんで海!?」
「海に行くのに理由なんてなくて大丈夫ですから!」
海はこの川のもう少し先にある。彼女は僕の手をひき、立たせた。そして「これこれ」という表情で僕が乗ってきた自転車を指差した。
「二人乗りで大丈夫ですよね!」
髪の先を指でくるくると回しながらそう笑った。
知らなかった。人の笑顔でこんなにも自分が染まっていくこと。そしてそれが、何も窮屈に感じないこと。
今日出会って、今日知って、今日会いたかったって言ってもらって、そんな彼女の存在が、こんなにも短い、あっという間の時間でも少しだけ大きくなっている気がする。いつもなら友達が冗談を言っている時、冗談にのれずに冷めた返事をするだけだ。でも、でも。
自転車の鍵をポケットから出してスタンドを外す。海がある方向へハンドルを向けた。
「やった!後ろ乗って良いですか?」
「二人乗り…だから…」
「乗りますね!行きましょう!」
彼女が空に突き上げた拳がスタートの合図のようにペダルを力強く踏む。
彼女が鼻歌を歌いながら進み、5分もしないうちに浜辺へ着いた。海から少し離れた所に自転車を停める。
彼女は僕の手をひき、海へ走っていく。途中で靴下を急いで脱ぎ、浅瀬へと走っていった。
「瑞瀬くんもおいでよーーー!」
肩の下まで伸ばした少し茶色がかった髪と黄色のロングスカートを揺らしながらそう笑った。
靴下を脱ぎ、少しだけズボンの裾を折る。
「来た来た!」
いつもより少しだけ早歩きで彼女の元へと駆けた。
いつもと違う、夏が始まる―。