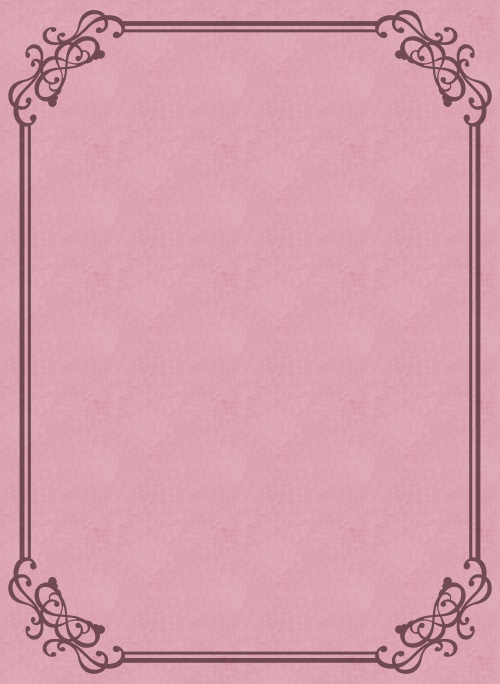高校の頃の僕は、色のない世界にいた。
それに気づいたのは、とある人との出会いがきっかけだった。
これから話すのは、僕がその人に出会う前のお話と出会ったあとのお話。
────────────
「杉原くん、これやっといて」
名前も知らないクラスメイトから渡されるホウキ。
掃除をよく任せられるが、別に掃除が好きな訳でもない、やりたくてやってる訳でもない。
やりたくも無いことをやると頭がクラクラするし、気持ち悪くなってくる。
だけど、断る勇気もない。
何回も渡してくるクラスメイトはきっと同じ人なんだろうけど、その人の名前すら知らない。
僕は人の名前を覚えるのが苦手だ。
名前も覚えれないし、顔すらまともに覚えたことも無い。
担任の先生も自分のクラスの先生と呼べば職員室から出て来てくれる。
だから特に困ったことは無い。
────────────
初めて人の名前や顔を覚えられたのは、先輩が初めてだった。
明るく、僕とは真逆で正反対。
自信のある強い、そんな素敵な先輩。
そんな先輩と出会ったのは、大学の交流会だった。
的確に指示を出していて、自分の作業もしながら周りの人達のサポートをしているそんな先輩のことを目で追っていたら、
「君、手伝ってくれる?見てないで、ほら、みんなで楽しもうよカレー作り」
「あ、はい」
交流会に参加したかった訳ではなく、学校行事に参加しないと卒業できないと言われたから仕方なく参加しただけなのに。
あー早く抜け出したい。
早く終わらないかなぁ。
そんなことばかり考えていると、積極的に声を掛ける先輩に見透かされたかのように、目が合い手を動かそうとすると先輩は僕に向かって口を開いた。
「お米研いでくれる?あ、やり方教えようか」
「分かります。自炊は一応してます」
「えらいじゃん、じゃあ色々手伝ってもらおうかな。君、名前なんだっけ、あれっ!待って聞いたっけ?」
「杉原といいます。杉原祐介(すぎはらゆうすけ)」
「杉原くんか、よし覚えた!お米研ぎ終わったらじゃがいも切るのも手伝ってくれる?」
捕まってしまった。目をつけられた。
「はい」
そう言うしか無かった。また僕は断れず、手を動かしている。
何度も何度も水を捨てては水を入れて、お米をといでは濁って、その繰り返し。
僕もこんなに濁ってるんだろうか。
さっき声をかけてきた先輩は、バタバタと色んなところを手伝っては僕みたいな人に声かけを積極的にしていた。
人当たりのいい人だとは思った。
別に興味は無いけれど、明るくなれない僕は、きっとあの人とは無縁の世界。
正反対の、暗く、静かな場所。
といでいるお米は、いくら研いでも水は濁ったままだった。
僕はきっと、お米のように、水を入れては濁っての繰り返しをしているのかもしれない。
「先輩これ、いつまでやれば…」
名前の知らない先輩も、先輩と呼べば来てくれる。
それなのに名前を覚えたのは、なぜか。
「水が濁らなくなるまでだけど、どのくらいやった?」
「今までずっとしてました」
「待ってね、確認してみる」
先輩が確認する間も、研いでみるが変わらなかった。
しばらくすると先輩は走って戻ってきて、腰を90度に曲げて手を合わせながら謝罪してきた。
「ごめん、無洗米だった。ほんっとごめん!」
「全然いいです」
出来れば関わりたくなかった。
「今度なんか奢るから!」
僕とは正反対だから、未知の世界で怖い気もした。
だけど先輩は、やっぱり積極的だった。
そんな僕にも、優しく接してくれる先輩は魅力的だった。
「今ちょっと手が空いたから飲み物奢るから行くよ、内緒だよ、早く行こ!」
「えっ、今ですか」
先輩は僕の手を掴んで引っ張って行った。
笑顔で後ろを振り返りながら、僕を連れ出す先輩は、髪が揺れて耳にかけ、他の人とは違うオーラを放っていた。
自販機の前につくと、「何がいい?」と聞かれた。
「じゃあ、天然水で」
「えっ、水じゃなくてもっと他にないの?」
水のように言われた通りの色に染まる。
水のような存在だと、自分は思っていた。
だから水が良かった。
「水じゃだめですか」
「だめってことはないけど、じゃあ私はいちごミルクかな」
そういって、あっという間に2本購入し、プラスチックを上にあげて下から取り出す。
「はい、これ杉原くんのいちごミルクね」
先輩は笑顔で渡してきた。
「え?僕が天然水ですよ」
「色がついた飲み物もたまには飲んだら? 」
先輩が僕の飲む飲み物に色をつけた。
先輩が、僕を甘党にしたのだ。
「先輩の名前、聞きましたっけ?」
初めて興味を持った。
先輩の名前を知りたくなった。
僕を甘党にした先輩。
「私の名前は、新島 香織(にいじまかおり)。覚えれそ?忘れても教えてあげないよ?こう見えて私、意地悪だから」
優しいように見えて先輩は、意地悪そうにニタニタと笑って僕を驚かせた。
「香織先輩って呼んでもいいですか、ていうか先輩、他の人とは違う感じ、オーラがあっていいですね、僕とは違って」
「杉原くんも、オーラありすぎだよ?寄せ付けない感じ逆にそういうとこ好きだけどな、私は」
「え?」
「え??なんか変なこと言った?」
先輩は、何度も僕を驚かせる。
他の人とは違う、魅力的な先輩の話は頭にスーッと入ってきて霧が晴れる。
だから、
―――――――――――――
先輩の卒業式の後。
「先輩、卒業しないでくださいッ」
先輩がいなくなる生活なんて考えられなかった。
泣いているのは紛れもない僕だった。
「杉原くん、泣かないの。また会えるから」
好きなことに気づいた。
新島香織先輩のことが。
「香織先輩のいない学校生活なんて嫌です」
惨めだ。こんな姿先輩に晒したくなかった。
でも抑えきれなかった。
「先輩、遠くの学校行っちゃうんですよね、教師として」
先輩がいつも僕の面倒を見てくれて、課題を教えてくれたりしていた。
“香織先輩、ここ分からないです”
いちごミルクがふたつ並んだ図書室の隅で、僕は勉強を教えてもらうほど先輩と仲良くなった。
“ここ読み直したら、また違った考えが持てる気がする”
“たしかに”
納得出来た。
先輩の教え方は上手かった。
”私、人に教えるの好きみたい”
知ってた。
そう言われなくても、先輩の教えてくれる時の表情を見てたら、なりたい夢も想像できてた。
「うん、そうだよ。だからまた休みの時会おうね、こっち戻ってくるから会えるよきっと」
運任せか。僕の運はもう先輩といた頃に使い果たしてしまったのかもしれない。
────────────
先輩と会えなくなって、気付けば夏がきていた。
先輩と話さなくなって、僕は元の僕に戻ってしまった感じがする。
それでも、国語教師になった先輩に憧れて本を読むようになった。
今日は大学は夏休みだ。
「今日は何しようか」
そうだ、借りていた本を返しに行こう。
新しい本も借りたいし。
そういう考えを持てるようになったのも、香織先輩の影響を受けたからだろう。
財布と携帯と借りていた本を紺色のトートバッグに詰めると、僕は外に出て家のドアに鍵を掛けた。
空を見上げると青空で、とても暑かった
セミの鳴き声を聞いて、夏を感じた
アパートの階段をおりて自転車のチェーンの鍵を外す。
外したチェーンをカゴの中に入れると肩から下げていたトートバッグを、カゴの中にストンと入れた。
自転車で図書館にやってきた僕は、自転車置き場に自転車を置いて、チェーンを掛けた。喉の乾いた僕は入口の横にある自販機で水を買う。
先輩がいなくなってから、僕はまた色のない水のように色のない世界にいるようだ。
国語教師になった先輩に憧れて、たくさんの本を読むようになった。
僕はまた先輩を追いかけている。
色のない世界作り出したのは僕だ。
それでも色のある先輩を求めて本を読む。
最近の僕は、水を飲んではあの甘い いちごミルクを 思い浮かべる。
そう考えているうちに後ろから声が聞こえた。
「あれ、何してるの? 今から図書館?」
聞き覚えのある声。
振り返ると、ずっと憧れていた先輩が、そこには立ってい た。
黄色のパンプスに、黄色のカラーパンツ、白のワイシャツ。
いかにも教師が馴染んでいるように見えて、かっこよく見えた。
先輩は卒業してしまってから中々会えずにいた。
連絡もできず、していいのかも分からず。
「私、先生になるの」
そうハッキリと言われた時は正直驚いた。
なりたい夢は想像できたけど、そんな先輩は、ずっと進路について悩んでいて、このまま先生になるか、「フリーターでもいいや」なんて言ってたから、ハッキリ先生になると言われた時は驚いた。
自分は久しぶりの再会に、驚きと緊張を隠せず少し固まってしまったが、先輩は にっこり笑って僕の前に立つ。
「久しぶりだね。元気してた?」
僕は戸惑いながらも、先輩との再会を喜んでいた。
「元気って言えば、元気です。今は夏休みなんで課題が多くて大変です」
そう言いながら僕は自販機で買った水を手に取る。
水を買うと、やっぱりいちごミルクのことが頭に浮かぶ。
先輩と話さなくなってしまって、また色が無くなっていた。
「教えたげよっか?」
そんな教師になった先輩が僕に教えようとしてくれている。
「いいん、ですか、こんなとこで仕事みたいなことしちゃって」
「今は仕事じゃなくて、杉原くんのために言ってるの。手伝ってあげるよ、ほら。行こ!」
そういって、先輩は僕の手を引っ張って、図書館へと連れていかれた。
こうしていつも僕をどこかに連れて行く。
そんな先輩が好きだった。
いざ机を前に座り込んだものの。
「そういえば僕、参考書なんて何一つ持ってきてないし、課題も置いてきましたよ」
「え、?教えられないじゃん夏休みの課題」
「何で置いてきたのかと言うと、ただ本を返して借りるのが目的だったからです」
「なんだぁ、もっーと早く言ってよ」
先輩は大きな声で言った。
するとたまたま近くを歩いてた人から、「静かにして貰えますか?」
なんて言われて、図書館を出ることにした。
図書館を出て入口の階段を降りながら先輩は言った。
「無駄足だったね」
「いや、僕は本返して借りてきたので、それが今日の目的ですから」
そう言ったあとの先輩のムッとした顔は、可愛かった。
指でつつきたくなるほど、可愛かった。
「そういや、ここら辺で綺麗な川が見られる穴場スポットあるの知ってる?」
「そんなとこあるんですか、確かにこの当たりの水綺麗って言われてますもんね」
先輩以外に興味が持てない僕は、当然その辺にあるものも知らないし、言われて始めて穴場スポットの存在を知った。
「行ってみようよ」
僕たちは綺麗な川を見るために川端まで移動することにした。
自転車の乗っていない先輩に合わせて、自分の白い自転車を手で押して歩く。
「先輩は、学校どうですか小学校の先生でしたっけ」
「そうだよ、生徒さんたち可愛いよ、私子供好きなんだなって気付いた。接してみて、初めて自分で気付いたの。教えるのは杉原くん教えてたりする時になんとなく好きなのかもって気づいたけど、子供好きなんて思わなかった」
「自分の意外性に気付くことって中々難しいことだと思います」
僕は言った。
だって、先輩が卒業するまで、ただの憧れだと思っていたから。
オーラの違う先輩を、自然と目で追っていたから。
ただそれだけだと思っていた。
自分の好意に気づくのが遅すぎた。
それでもやっぱりこうして話してると、ときめいてしまうし、喋ってるだけで可愛く感じてしまって、ちょっと落ち着かなきゃいけないのかもしれない。
川端に着いた僕たちは自転車を止めて、地べたに座り込んだ。
「杉原くんもちょっと身長大きくなったんじゃない?肩幅かな、前より大きく見える」
「そう、ですかね、特に何もしてないんですけど 」
何もしてないは嘘だ。見栄張ってこれもしてるあれもしてるなんて言いたくなかった。
かっこいい僕でありたい。
以前の僕とは変わった。
明らかに、前よりも自信のある自分に変わった。
喉の乾いた僕は、トートバッグから水を取り出して飲む。
そして隣に水を置いて小説を読み始める。
少しでも気を紛らわしたかった。
「なんの本読んでるの?」
「青春ミステリーの本です」
興味津々に先輩は僕の読んでいる本を覗き込んだ。
「ねぇ、その水貰ってもいい?喉乾いちゃった、暑いね」
そう言って腕をまくり、水を飲み始めた姿は首から汗がたれて色気を感じた。
確かに先輩の分も買えばよかったと後悔してからじゃ遅いが、自分と間接キスになってしまうと考えた頃には思考は回らなくなっていた。
ドキドキした。
先輩が僕の水を飲んでいる姿は、美しく綺麗だった。
「ありがとう水くれて」
「全然です、むしろ先輩の分、買うこと気づかなくてすみません」
「いーのいーの。貰おうと思ってたから 」
やっぱり先輩が好きだ。
どうしようもなく好きだ。
「先輩、僕先輩のことが」
「シー、今ちょっと川の音聞いてるから」
先輩は中々言わせてくれない。
「聞いてみて川の音。この景色、綺麗じゃないっ?」
空は青空で綺麗な川と一緒にフレームに収めると、先輩は僕に見せてきた。
「ほんと綺麗だよね」
そう僕に語り掛ける先輩の顔は少し赤くなっていた。
僕の気持ちに気づいてる?
今しかない、とそう感じた。
「好きです、先輩のこと。この空間にいれてることも奇跡なんじゃないかってくらい、卒業式の日に後悔しました。もっと早く気付いていればって、自分の気持ちに気付けなかった僕はだめだって」
「だめなんかじゃないよ、うれしいよ、すごく」
「先輩が好きなんです、見える景色が、先輩といると輝いて見えるんです。一緒にいたいです、だめですか」
先輩は顔を赤くしていた、先程よりも赤く。
「色のない世界にいたんだね、私が、変えたんだね。私でいいのかな」
「先輩じゃないとだめです。こればっかりは譲れません」
「そっか、私も祐介くんのこと好き、だったよ。ずっと、遅いよ、待ってたよずっと」
先輩は僕のことを待っていたという。
連れ出したのはいつも先輩だったのに、待っていたと言う。
「手繋いでもいいですか」
「初々しいなあ、かわいい。好きだけどなぁ、そういうとこ」
そういって、頬に手を添えて僕を眺める先輩は可愛かった。
「手繋ごっか。なんかドキドキするね」
僕は持っていた本を横に置いて、手を繋いだ。
「どこにも行かないでください」
「それは無理かな、学校遠いし」
僕はあからさまに下を向いて悲しんだ。
「そんな悲しい顔しないの」
そう言って手を繋いでる反対の手で僕の頬をつつく。
僕たちは見つめあって、少し目を逸らしてみるけど、目線を戻すと、目が離せなくなって、そのままキスをした。
僕の運はきっと使い果たしたんだろう。
今日という思い出を、消えないように。
しっかりと胸に刻んだ。
───────────
数年後、僕は先輩と同じく国語教師になって中学生を教えている。
やりたいことを見つけたのは、先輩のおかげである。
なんにも色がなかった世界。
白く濁ったような感覚から、スーッと晴れた感覚に変わった。
僕を変えたのは、僕を甘くしたのは、今も昔も先輩。
「香織、この生徒のこと気にかけてあげてくれないかな」
同じ学校の先生になった僕たちは、当時の僕みたいな子を、見捨てたくなくて積極的に声をかけることを決めている。
「祐介がそう言わなくても、声掛けてる、出会った当時の祐介みたいだから、かわいいんだよね似てて」
僕らは結婚して杉原香織になった先輩は、僕の中ではずっと先輩で、仕事熱心で魅力的な可愛い僕の妻だ。
白い自転車とピンクの自転車で一緒に通勤する仲間でもある、そんな香織のことがずっと目標になっている。
「香織みたいな子もいるけどな、上手く歯車が噛み合ってくれると回ってくれるんだけどな、あの時の僕みたいに」
それに気づいたのは、とある人との出会いがきっかけだった。
これから話すのは、僕がその人に出会う前のお話と出会ったあとのお話。
────────────
「杉原くん、これやっといて」
名前も知らないクラスメイトから渡されるホウキ。
掃除をよく任せられるが、別に掃除が好きな訳でもない、やりたくてやってる訳でもない。
やりたくも無いことをやると頭がクラクラするし、気持ち悪くなってくる。
だけど、断る勇気もない。
何回も渡してくるクラスメイトはきっと同じ人なんだろうけど、その人の名前すら知らない。
僕は人の名前を覚えるのが苦手だ。
名前も覚えれないし、顔すらまともに覚えたことも無い。
担任の先生も自分のクラスの先生と呼べば職員室から出て来てくれる。
だから特に困ったことは無い。
────────────
初めて人の名前や顔を覚えられたのは、先輩が初めてだった。
明るく、僕とは真逆で正反対。
自信のある強い、そんな素敵な先輩。
そんな先輩と出会ったのは、大学の交流会だった。
的確に指示を出していて、自分の作業もしながら周りの人達のサポートをしているそんな先輩のことを目で追っていたら、
「君、手伝ってくれる?見てないで、ほら、みんなで楽しもうよカレー作り」
「あ、はい」
交流会に参加したかった訳ではなく、学校行事に参加しないと卒業できないと言われたから仕方なく参加しただけなのに。
あー早く抜け出したい。
早く終わらないかなぁ。
そんなことばかり考えていると、積極的に声を掛ける先輩に見透かされたかのように、目が合い手を動かそうとすると先輩は僕に向かって口を開いた。
「お米研いでくれる?あ、やり方教えようか」
「分かります。自炊は一応してます」
「えらいじゃん、じゃあ色々手伝ってもらおうかな。君、名前なんだっけ、あれっ!待って聞いたっけ?」
「杉原といいます。杉原祐介(すぎはらゆうすけ)」
「杉原くんか、よし覚えた!お米研ぎ終わったらじゃがいも切るのも手伝ってくれる?」
捕まってしまった。目をつけられた。
「はい」
そう言うしか無かった。また僕は断れず、手を動かしている。
何度も何度も水を捨てては水を入れて、お米をといでは濁って、その繰り返し。
僕もこんなに濁ってるんだろうか。
さっき声をかけてきた先輩は、バタバタと色んなところを手伝っては僕みたいな人に声かけを積極的にしていた。
人当たりのいい人だとは思った。
別に興味は無いけれど、明るくなれない僕は、きっとあの人とは無縁の世界。
正反対の、暗く、静かな場所。
といでいるお米は、いくら研いでも水は濁ったままだった。
僕はきっと、お米のように、水を入れては濁っての繰り返しをしているのかもしれない。
「先輩これ、いつまでやれば…」
名前の知らない先輩も、先輩と呼べば来てくれる。
それなのに名前を覚えたのは、なぜか。
「水が濁らなくなるまでだけど、どのくらいやった?」
「今までずっとしてました」
「待ってね、確認してみる」
先輩が確認する間も、研いでみるが変わらなかった。
しばらくすると先輩は走って戻ってきて、腰を90度に曲げて手を合わせながら謝罪してきた。
「ごめん、無洗米だった。ほんっとごめん!」
「全然いいです」
出来れば関わりたくなかった。
「今度なんか奢るから!」
僕とは正反対だから、未知の世界で怖い気もした。
だけど先輩は、やっぱり積極的だった。
そんな僕にも、優しく接してくれる先輩は魅力的だった。
「今ちょっと手が空いたから飲み物奢るから行くよ、内緒だよ、早く行こ!」
「えっ、今ですか」
先輩は僕の手を掴んで引っ張って行った。
笑顔で後ろを振り返りながら、僕を連れ出す先輩は、髪が揺れて耳にかけ、他の人とは違うオーラを放っていた。
自販機の前につくと、「何がいい?」と聞かれた。
「じゃあ、天然水で」
「えっ、水じゃなくてもっと他にないの?」
水のように言われた通りの色に染まる。
水のような存在だと、自分は思っていた。
だから水が良かった。
「水じゃだめですか」
「だめってことはないけど、じゃあ私はいちごミルクかな」
そういって、あっという間に2本購入し、プラスチックを上にあげて下から取り出す。
「はい、これ杉原くんのいちごミルクね」
先輩は笑顔で渡してきた。
「え?僕が天然水ですよ」
「色がついた飲み物もたまには飲んだら? 」
先輩が僕の飲む飲み物に色をつけた。
先輩が、僕を甘党にしたのだ。
「先輩の名前、聞きましたっけ?」
初めて興味を持った。
先輩の名前を知りたくなった。
僕を甘党にした先輩。
「私の名前は、新島 香織(にいじまかおり)。覚えれそ?忘れても教えてあげないよ?こう見えて私、意地悪だから」
優しいように見えて先輩は、意地悪そうにニタニタと笑って僕を驚かせた。
「香織先輩って呼んでもいいですか、ていうか先輩、他の人とは違う感じ、オーラがあっていいですね、僕とは違って」
「杉原くんも、オーラありすぎだよ?寄せ付けない感じ逆にそういうとこ好きだけどな、私は」
「え?」
「え??なんか変なこと言った?」
先輩は、何度も僕を驚かせる。
他の人とは違う、魅力的な先輩の話は頭にスーッと入ってきて霧が晴れる。
だから、
―――――――――――――
先輩の卒業式の後。
「先輩、卒業しないでくださいッ」
先輩がいなくなる生活なんて考えられなかった。
泣いているのは紛れもない僕だった。
「杉原くん、泣かないの。また会えるから」
好きなことに気づいた。
新島香織先輩のことが。
「香織先輩のいない学校生活なんて嫌です」
惨めだ。こんな姿先輩に晒したくなかった。
でも抑えきれなかった。
「先輩、遠くの学校行っちゃうんですよね、教師として」
先輩がいつも僕の面倒を見てくれて、課題を教えてくれたりしていた。
“香織先輩、ここ分からないです”
いちごミルクがふたつ並んだ図書室の隅で、僕は勉強を教えてもらうほど先輩と仲良くなった。
“ここ読み直したら、また違った考えが持てる気がする”
“たしかに”
納得出来た。
先輩の教え方は上手かった。
”私、人に教えるの好きみたい”
知ってた。
そう言われなくても、先輩の教えてくれる時の表情を見てたら、なりたい夢も想像できてた。
「うん、そうだよ。だからまた休みの時会おうね、こっち戻ってくるから会えるよきっと」
運任せか。僕の運はもう先輩といた頃に使い果たしてしまったのかもしれない。
────────────
先輩と会えなくなって、気付けば夏がきていた。
先輩と話さなくなって、僕は元の僕に戻ってしまった感じがする。
それでも、国語教師になった先輩に憧れて本を読むようになった。
今日は大学は夏休みだ。
「今日は何しようか」
そうだ、借りていた本を返しに行こう。
新しい本も借りたいし。
そういう考えを持てるようになったのも、香織先輩の影響を受けたからだろう。
財布と携帯と借りていた本を紺色のトートバッグに詰めると、僕は外に出て家のドアに鍵を掛けた。
空を見上げると青空で、とても暑かった
セミの鳴き声を聞いて、夏を感じた
アパートの階段をおりて自転車のチェーンの鍵を外す。
外したチェーンをカゴの中に入れると肩から下げていたトートバッグを、カゴの中にストンと入れた。
自転車で図書館にやってきた僕は、自転車置き場に自転車を置いて、チェーンを掛けた。喉の乾いた僕は入口の横にある自販機で水を買う。
先輩がいなくなってから、僕はまた色のない水のように色のない世界にいるようだ。
国語教師になった先輩に憧れて、たくさんの本を読むようになった。
僕はまた先輩を追いかけている。
色のない世界作り出したのは僕だ。
それでも色のある先輩を求めて本を読む。
最近の僕は、水を飲んではあの甘い いちごミルクを 思い浮かべる。
そう考えているうちに後ろから声が聞こえた。
「あれ、何してるの? 今から図書館?」
聞き覚えのある声。
振り返ると、ずっと憧れていた先輩が、そこには立ってい た。
黄色のパンプスに、黄色のカラーパンツ、白のワイシャツ。
いかにも教師が馴染んでいるように見えて、かっこよく見えた。
先輩は卒業してしまってから中々会えずにいた。
連絡もできず、していいのかも分からず。
「私、先生になるの」
そうハッキリと言われた時は正直驚いた。
なりたい夢は想像できたけど、そんな先輩は、ずっと進路について悩んでいて、このまま先生になるか、「フリーターでもいいや」なんて言ってたから、ハッキリ先生になると言われた時は驚いた。
自分は久しぶりの再会に、驚きと緊張を隠せず少し固まってしまったが、先輩は にっこり笑って僕の前に立つ。
「久しぶりだね。元気してた?」
僕は戸惑いながらも、先輩との再会を喜んでいた。
「元気って言えば、元気です。今は夏休みなんで課題が多くて大変です」
そう言いながら僕は自販機で買った水を手に取る。
水を買うと、やっぱりいちごミルクのことが頭に浮かぶ。
先輩と話さなくなってしまって、また色が無くなっていた。
「教えたげよっか?」
そんな教師になった先輩が僕に教えようとしてくれている。
「いいん、ですか、こんなとこで仕事みたいなことしちゃって」
「今は仕事じゃなくて、杉原くんのために言ってるの。手伝ってあげるよ、ほら。行こ!」
そういって、先輩は僕の手を引っ張って、図書館へと連れていかれた。
こうしていつも僕をどこかに連れて行く。
そんな先輩が好きだった。
いざ机を前に座り込んだものの。
「そういえば僕、参考書なんて何一つ持ってきてないし、課題も置いてきましたよ」
「え、?教えられないじゃん夏休みの課題」
「何で置いてきたのかと言うと、ただ本を返して借りるのが目的だったからです」
「なんだぁ、もっーと早く言ってよ」
先輩は大きな声で言った。
するとたまたま近くを歩いてた人から、「静かにして貰えますか?」
なんて言われて、図書館を出ることにした。
図書館を出て入口の階段を降りながら先輩は言った。
「無駄足だったね」
「いや、僕は本返して借りてきたので、それが今日の目的ですから」
そう言ったあとの先輩のムッとした顔は、可愛かった。
指でつつきたくなるほど、可愛かった。
「そういや、ここら辺で綺麗な川が見られる穴場スポットあるの知ってる?」
「そんなとこあるんですか、確かにこの当たりの水綺麗って言われてますもんね」
先輩以外に興味が持てない僕は、当然その辺にあるものも知らないし、言われて始めて穴場スポットの存在を知った。
「行ってみようよ」
僕たちは綺麗な川を見るために川端まで移動することにした。
自転車の乗っていない先輩に合わせて、自分の白い自転車を手で押して歩く。
「先輩は、学校どうですか小学校の先生でしたっけ」
「そうだよ、生徒さんたち可愛いよ、私子供好きなんだなって気付いた。接してみて、初めて自分で気付いたの。教えるのは杉原くん教えてたりする時になんとなく好きなのかもって気づいたけど、子供好きなんて思わなかった」
「自分の意外性に気付くことって中々難しいことだと思います」
僕は言った。
だって、先輩が卒業するまで、ただの憧れだと思っていたから。
オーラの違う先輩を、自然と目で追っていたから。
ただそれだけだと思っていた。
自分の好意に気づくのが遅すぎた。
それでもやっぱりこうして話してると、ときめいてしまうし、喋ってるだけで可愛く感じてしまって、ちょっと落ち着かなきゃいけないのかもしれない。
川端に着いた僕たちは自転車を止めて、地べたに座り込んだ。
「杉原くんもちょっと身長大きくなったんじゃない?肩幅かな、前より大きく見える」
「そう、ですかね、特に何もしてないんですけど 」
何もしてないは嘘だ。見栄張ってこれもしてるあれもしてるなんて言いたくなかった。
かっこいい僕でありたい。
以前の僕とは変わった。
明らかに、前よりも自信のある自分に変わった。
喉の乾いた僕は、トートバッグから水を取り出して飲む。
そして隣に水を置いて小説を読み始める。
少しでも気を紛らわしたかった。
「なんの本読んでるの?」
「青春ミステリーの本です」
興味津々に先輩は僕の読んでいる本を覗き込んだ。
「ねぇ、その水貰ってもいい?喉乾いちゃった、暑いね」
そう言って腕をまくり、水を飲み始めた姿は首から汗がたれて色気を感じた。
確かに先輩の分も買えばよかったと後悔してからじゃ遅いが、自分と間接キスになってしまうと考えた頃には思考は回らなくなっていた。
ドキドキした。
先輩が僕の水を飲んでいる姿は、美しく綺麗だった。
「ありがとう水くれて」
「全然です、むしろ先輩の分、買うこと気づかなくてすみません」
「いーのいーの。貰おうと思ってたから 」
やっぱり先輩が好きだ。
どうしようもなく好きだ。
「先輩、僕先輩のことが」
「シー、今ちょっと川の音聞いてるから」
先輩は中々言わせてくれない。
「聞いてみて川の音。この景色、綺麗じゃないっ?」
空は青空で綺麗な川と一緒にフレームに収めると、先輩は僕に見せてきた。
「ほんと綺麗だよね」
そう僕に語り掛ける先輩の顔は少し赤くなっていた。
僕の気持ちに気づいてる?
今しかない、とそう感じた。
「好きです、先輩のこと。この空間にいれてることも奇跡なんじゃないかってくらい、卒業式の日に後悔しました。もっと早く気付いていればって、自分の気持ちに気付けなかった僕はだめだって」
「だめなんかじゃないよ、うれしいよ、すごく」
「先輩が好きなんです、見える景色が、先輩といると輝いて見えるんです。一緒にいたいです、だめですか」
先輩は顔を赤くしていた、先程よりも赤く。
「色のない世界にいたんだね、私が、変えたんだね。私でいいのかな」
「先輩じゃないとだめです。こればっかりは譲れません」
「そっか、私も祐介くんのこと好き、だったよ。ずっと、遅いよ、待ってたよずっと」
先輩は僕のことを待っていたという。
連れ出したのはいつも先輩だったのに、待っていたと言う。
「手繋いでもいいですか」
「初々しいなあ、かわいい。好きだけどなぁ、そういうとこ」
そういって、頬に手を添えて僕を眺める先輩は可愛かった。
「手繋ごっか。なんかドキドキするね」
僕は持っていた本を横に置いて、手を繋いだ。
「どこにも行かないでください」
「それは無理かな、学校遠いし」
僕はあからさまに下を向いて悲しんだ。
「そんな悲しい顔しないの」
そう言って手を繋いでる反対の手で僕の頬をつつく。
僕たちは見つめあって、少し目を逸らしてみるけど、目線を戻すと、目が離せなくなって、そのままキスをした。
僕の運はきっと使い果たしたんだろう。
今日という思い出を、消えないように。
しっかりと胸に刻んだ。
───────────
数年後、僕は先輩と同じく国語教師になって中学生を教えている。
やりたいことを見つけたのは、先輩のおかげである。
なんにも色がなかった世界。
白く濁ったような感覚から、スーッと晴れた感覚に変わった。
僕を変えたのは、僕を甘くしたのは、今も昔も先輩。
「香織、この生徒のこと気にかけてあげてくれないかな」
同じ学校の先生になった僕たちは、当時の僕みたいな子を、見捨てたくなくて積極的に声をかけることを決めている。
「祐介がそう言わなくても、声掛けてる、出会った当時の祐介みたいだから、かわいいんだよね似てて」
僕らは結婚して杉原香織になった先輩は、僕の中ではずっと先輩で、仕事熱心で魅力的な可愛い僕の妻だ。
白い自転車とピンクの自転車で一緒に通勤する仲間でもある、そんな香織のことがずっと目標になっている。
「香織みたいな子もいるけどな、上手く歯車が噛み合ってくれると回ってくれるんだけどな、あの時の僕みたいに」