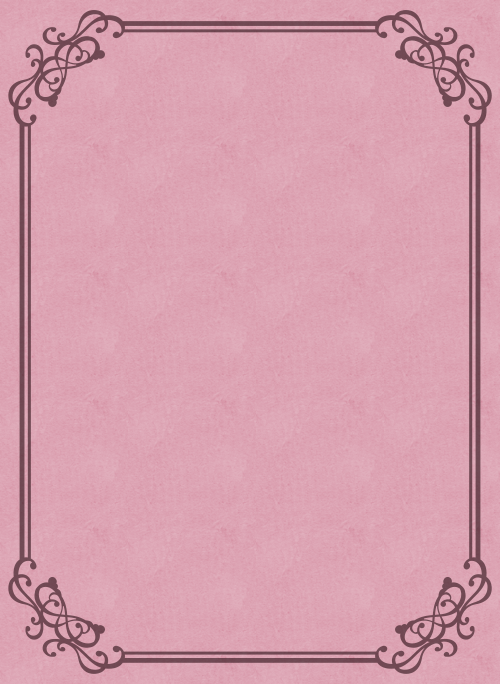イングリードVS継母姉コンビの傍らを通り過ぎてしまい、もう声が聞こえなくなってしまった。
「ああああ、こんなに人がいっぱいなのによりによって鉢合わせしちゃうなんて……」
慌てる私にアッシュが言う。
「彼女に任せておけばいい。自分のことに集中しろ」
「でも……」
「見ろ」
アッシュの視線を辿り、ドキッとした。
いつの間にか私たちは玉座の真下へ到着していた。
さっきは豆粒だった王子が、ほんの10メートルほど先に迫っている。
(う、う、嘘……いつの間に……!)
なんたることだ。
「アピールしなきゃ……どうやるの!?」
「エラ、落ち着け」
「あああ、でも、でも!」
確かに私なんかより、イングリードの方がしっかりしている。
スルーすべきかと思ったが、さっき見たイングリードの固く握られたこぶしを思い出し、そうも言ってられなくなった。
『あの意地悪コンビ、いつか拳で打ち据えたいものです』
ある日の軽口が頭をよぎる。もちろん冗談のはず。だけどもし切羽詰まった彼女が実力行使に出ちゃったら……。
「ダメよ!!!!! イングリード!」
私はアッシュの手を振りほどき、ダンスの輪から抜け出すとバチバチのバトルトライアングルに割りこんでいく。
イングリードは、私に気が付くと両目を丸くした。
「何してるんですか。フロアに戻ってください!」
「あなた、殴るつもりだったでしょう。絶対にダメだからね! メイドが貴族に手を出したら……最悪、死刑なんだから!」
「ほっといてください。ターゲットはすぐそこなのですよ……!」
「これが解決したらスタンバイするわよ。人のことより自分のことを心配してよ」
イングリードはむう、と黙り込む。
ごめんね。イングリード。私のせいで面倒に巻き込んでしまって。
でもこの世界は貴族に優しい世界なの……。
なので、今は耐え忍ぶのよ、忍耐は私とアッシュが散々やってきたことだからね!
私はイングリードにテレパシーを送りつつ、作り笑いを浮かべながら、継母姉に向かい合った。
「あのね、これには深い事情が……」
なぜお前もここにいるのだと詰められるのを覚悟した。
ところが意外な展開が待っていた。
「あなた誰?」
「私たちの会話に口を挟まないでちょうだい」
二人は私にそんな事を言ってきたのだ。
「え……」
あまりの事に対応できずにいたら、イングリードに肩をつつかれた。
「エラ様だと気がついていないようですね」
「えええええええっ」
「アホかもしれません。この三日月たち」
「お願いだから、黙ってて」
とはいえ、正直かなり驚いた。
(別人級の美女になったイングリードが判別できるのに、大して代わり映えのしない私がわからないなんて、どういう基準よ!)
背後からアッシュの声が聞こえてきた。
「正体がバレていないのはラッキーだ」
(きゃあああああ、アッシュ!!!!!)
(アッシュ様!!!)
私とイングリードは心の中で歓声をあげる。
心強い味方アッシュが、私たちを庇うように継母姉コンビの目前に立つ。
「ごきげんよう。サマンサ様にメアリー様」
アッシュが名前を呼ぶと、二人は虚を突かれたような表情を浮かべた。
「まあ、素敵な人……女神みたい」
「どこかでお会いしましたっけ?」
母娘がうわずったような声で言う。
「ええ。アイマス男爵のパーティーでご挨拶をさせていただきましたわ」
しれっとした顔でアッシュは言う。
さあ、どんな言い訳をするのだろう、と固唾を飲んでいたら、
「先ほど、イングリードに招待状の事をお聞きになっていたでしょう? 実は彼女は命の恩人でして。ヒグマに食べられそうになっていたところを助けてもらったのです。そのお礼に付き添いを頼んだのですわ。大切なメイドを許可なく連れ出して申し訳ございませんでした」
いかにも嘘っぽい理由を繰り出してきた。
「ちょっと、さすがに無理があるわよ」
「ええ。いくらアホ二人でも、この言い訳で納得するわけがありませんね」
私とイングリードは絶望していたのに、母姉はにっこりほほ笑んだ。
「なるほど。そういうことだったのですか」
「最初からそう言えばよかったのに。イングリード。楽しみなさいね」
さっきとは打って変わった、にこやかな態度で去っていく。
「信じた……!」
案外継母コンビは、御しやすい人たちなのかもしれない。
まあ、ただアッシュのオーラに圧倒された可能性が高いけれど。
イングリードは柱時計を見ながら早口で言った。
「ったく、エラ様、私の事など放っておいても良かったのに。とりあえず、ダンスフロアに戻ってください!」
「そ、そうね」
ドレスをたくし上げて私は元いた場所に戻ろうとした。
ところが突然音楽が止んだ。
「え?」
王が立ち上がり両手をパンパンと叩いている。
おごそかな声でこう言った。
「王子のお妃が決定した。皆の者、静粛に!」
「ええええええええ」
私は唖然としてしまった。
「げ、マジか」
隣にいるアッシュも口をポカンと開けている。
「そんなっ……くっ……三日月コンビのせいで!」
イングリードは悔しがっている。
「大変よ。絶対に私じゃない自信があるわ」
私は頭を抱えてしまった。
王子の視界に入ることすら出来なかった。
お相手が決まってしまったら、私の出る幕はなくなってしまう。
物語が……終わってしまう。
あたりが真っ暗になった気がした。
アッシュは?
イングリードはどうなるの?
私のために、こんなに……こんなに頑張ってくれたのに!
「ああああ、こんなに人がいっぱいなのによりによって鉢合わせしちゃうなんて……」
慌てる私にアッシュが言う。
「彼女に任せておけばいい。自分のことに集中しろ」
「でも……」
「見ろ」
アッシュの視線を辿り、ドキッとした。
いつの間にか私たちは玉座の真下へ到着していた。
さっきは豆粒だった王子が、ほんの10メートルほど先に迫っている。
(う、う、嘘……いつの間に……!)
なんたることだ。
「アピールしなきゃ……どうやるの!?」
「エラ、落ち着け」
「あああ、でも、でも!」
確かに私なんかより、イングリードの方がしっかりしている。
スルーすべきかと思ったが、さっき見たイングリードの固く握られたこぶしを思い出し、そうも言ってられなくなった。
『あの意地悪コンビ、いつか拳で打ち据えたいものです』
ある日の軽口が頭をよぎる。もちろん冗談のはず。だけどもし切羽詰まった彼女が実力行使に出ちゃったら……。
「ダメよ!!!!! イングリード!」
私はアッシュの手を振りほどき、ダンスの輪から抜け出すとバチバチのバトルトライアングルに割りこんでいく。
イングリードは、私に気が付くと両目を丸くした。
「何してるんですか。フロアに戻ってください!」
「あなた、殴るつもりだったでしょう。絶対にダメだからね! メイドが貴族に手を出したら……最悪、死刑なんだから!」
「ほっといてください。ターゲットはすぐそこなのですよ……!」
「これが解決したらスタンバイするわよ。人のことより自分のことを心配してよ」
イングリードはむう、と黙り込む。
ごめんね。イングリード。私のせいで面倒に巻き込んでしまって。
でもこの世界は貴族に優しい世界なの……。
なので、今は耐え忍ぶのよ、忍耐は私とアッシュが散々やってきたことだからね!
私はイングリードにテレパシーを送りつつ、作り笑いを浮かべながら、継母姉に向かい合った。
「あのね、これには深い事情が……」
なぜお前もここにいるのだと詰められるのを覚悟した。
ところが意外な展開が待っていた。
「あなた誰?」
「私たちの会話に口を挟まないでちょうだい」
二人は私にそんな事を言ってきたのだ。
「え……」
あまりの事に対応できずにいたら、イングリードに肩をつつかれた。
「エラ様だと気がついていないようですね」
「えええええええっ」
「アホかもしれません。この三日月たち」
「お願いだから、黙ってて」
とはいえ、正直かなり驚いた。
(別人級の美女になったイングリードが判別できるのに、大して代わり映えのしない私がわからないなんて、どういう基準よ!)
背後からアッシュの声が聞こえてきた。
「正体がバレていないのはラッキーだ」
(きゃあああああ、アッシュ!!!!!)
(アッシュ様!!!)
私とイングリードは心の中で歓声をあげる。
心強い味方アッシュが、私たちを庇うように継母姉コンビの目前に立つ。
「ごきげんよう。サマンサ様にメアリー様」
アッシュが名前を呼ぶと、二人は虚を突かれたような表情を浮かべた。
「まあ、素敵な人……女神みたい」
「どこかでお会いしましたっけ?」
母娘がうわずったような声で言う。
「ええ。アイマス男爵のパーティーでご挨拶をさせていただきましたわ」
しれっとした顔でアッシュは言う。
さあ、どんな言い訳をするのだろう、と固唾を飲んでいたら、
「先ほど、イングリードに招待状の事をお聞きになっていたでしょう? 実は彼女は命の恩人でして。ヒグマに食べられそうになっていたところを助けてもらったのです。そのお礼に付き添いを頼んだのですわ。大切なメイドを許可なく連れ出して申し訳ございませんでした」
いかにも嘘っぽい理由を繰り出してきた。
「ちょっと、さすがに無理があるわよ」
「ええ。いくらアホ二人でも、この言い訳で納得するわけがありませんね」
私とイングリードは絶望していたのに、母姉はにっこりほほ笑んだ。
「なるほど。そういうことだったのですか」
「最初からそう言えばよかったのに。イングリード。楽しみなさいね」
さっきとは打って変わった、にこやかな態度で去っていく。
「信じた……!」
案外継母コンビは、御しやすい人たちなのかもしれない。
まあ、ただアッシュのオーラに圧倒された可能性が高いけれど。
イングリードは柱時計を見ながら早口で言った。
「ったく、エラ様、私の事など放っておいても良かったのに。とりあえず、ダンスフロアに戻ってください!」
「そ、そうね」
ドレスをたくし上げて私は元いた場所に戻ろうとした。
ところが突然音楽が止んだ。
「え?」
王が立ち上がり両手をパンパンと叩いている。
おごそかな声でこう言った。
「王子のお妃が決定した。皆の者、静粛に!」
「ええええええええ」
私は唖然としてしまった。
「げ、マジか」
隣にいるアッシュも口をポカンと開けている。
「そんなっ……くっ……三日月コンビのせいで!」
イングリードは悔しがっている。
「大変よ。絶対に私じゃない自信があるわ」
私は頭を抱えてしまった。
王子の視界に入ることすら出来なかった。
お相手が決まってしまったら、私の出る幕はなくなってしまう。
物語が……終わってしまう。
あたりが真っ暗になった気がした。
アッシュは?
イングリードはどうなるの?
私のために、こんなに……こんなに頑張ってくれたのに!