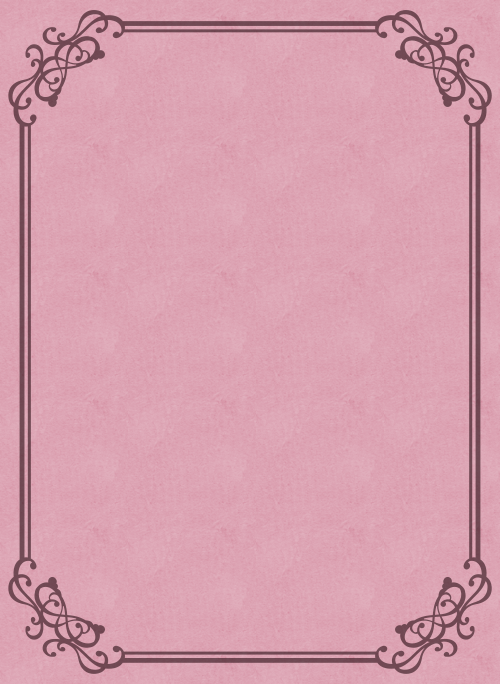イングリードが頑張ったおかげで、あっという間に丘の上の王宮に到着した。
「とうとう来たわ! シンデレラ城!」
私はぎゅっと目を閉じた。
セミの幼虫みたく、土に潜ったような8年間。
全てはこの時のためだった。
「エラ様。頑張ってください」
「大丈夫。今の君は最高に綺麗だ」
セミのイメトレに励んでいた私に、イングリードとアッシュが声をかけてくる。
「うん。頑張る! 二人ともありがとう……! ところで……」
私は傍らにいるイングリードを見た。
「イングリードも舞踏会に参加するのね」
「ええ。エラ様が心配ですし」
「……他にも理由があるわよね」
「ええ。馬だとまだ存在感が薄いでしょう。オリジナルキャラとしてレギュラー化を狙っています」
「凄いわね。その粘り強さ……っていうか、イングリードって超絶美女だったのね」
私はマジマジと彼女を見た。
スレンダーでボーイッシュな魅力のあるアッシュと比べて、イングリードはダークな大人の魅力だ。いつもはきっちりまとめている髪の毛が長く垂らされており、並ぶとイングリードの方が魔女っぽい。
(なんだか気後れ……ずっとオシャレをサボってたからなあ)
ヒロイン補正を当てにして、ビジュアル方面を一切磨いてこなかった。
でも……。
「美しい二人を見ると、もっと頑張っておけば良かったって思うわ……」
しみじみと呟く。
なんていうか、見た目もだけれど、立ち姿が素敵なのだ。
アッシュはうんと背が高く、イングリードもスラリとしている。
かっこいいとはこのことだ。
はあああ。ずっと見ていたい。眼福眼福。
「何を言ってるんだ(んですか)」
2人が同時に叫んだ。
「エラ様には畑を耕して培った強い筋肉があるでしょう。それに、付け焼き刃とはいえ、最高に似合うドレスと装い……きっと誰にも負けませんよ」
「その通り。俺の魔法とセンスを舐めんな。それから、君自身の素材もな」
素材……それを言われると「しょぼい」としか言えなくなるが……。
確かに当初望んでいたように、金髪碧眼で来て居たら、なんだか借り物の自分みたいで絶対に落ち着けなかっただろう。
これできっと良かったのだ。
「どうしてそんなに優しいの? さっきはお説教モードだったのに」
「もう本番だ。今さら四の五の言っても仕方ない」
「その通りです」
イングリードが言った。
「エラ様。あなたにはいい人です。でも、それは初見で伝わりにくいものなのですよ。でも、一度目に留まりさえすればこっちのもんです!」
「そ、そ、そうよね!」
的外れな努力だったかもしれないけれど、自分なりに頑張ってきた。
シンデレラとしての自信は0でも自覚はある。
この物語をハッピーエンドに導きたい。
それが、自分の意志でもあるし、協力してくれた二人に報いることだもの。
「それじゃ行くわね!」
私は一声そう言うと、傍らに美女二人を従えて、ゆっくりとカーペットの上を歩き出した。
◇◇◇◇
会場に入った瞬間、あまりの人の多さに眩暈がしそうになった。
とんでもなく広いフロアに、紳士淑女たちがひしめいている。
「お、王子発見」
双眼鏡を覗いていたアッシュが指さす先を見る。
100メートルほど先の遠い舞台上に玉座が3つあり、その中の1人がそうらしかった。
肉眼では豆粒ほどにしか見えない距離である。
「どうぞ」
アッシュに双眼鏡を渡され覗き込む。
中央にいる青年が、玉座の肘掛けに片肘をつき、つまらなさそうな表情を浮かべている。
王子をはさむように座っているのが王と王妃なのだろう。
「私にも見せてください。まあ、ハンサム」
イングリ―ドが言う。
「そ、そう?」
もう一度双眼鏡を渡される。
ハンサム……なのかな?
多分そうよね。
私は男性のビジュアルの良し悪しが昔から全然ピンとこないのだ。
女子高生時代、100年に1人の美貌とかいうイケメンの同級生が学校にいたが、どんなに目をこらして見ても、他のクラスメイトとの差を感じることができなかった。
男生の顔の差なんて、丸いか四角いか長いか小さいかくらいしかわからない。
(王子は丸ね。覚えておこう)
「とはいえ、アッシュ様には負けますね」
「だろ? 女装してきてよかったわー」
「また除草の話なの? アッシュ、どんなところに住んでるの?」
「……エラ様……」
「何、その憐れむような目は!」
まあいい。
二人には何か一瞬でできた絆があるみたい。
仲間に入れない私は、運命の相手をもっとちゃんと観察しようと目を凝らした。
王子は給仕の者が差し出した、恐らくカクテルの入ったグラスを億劫そうに受け取ると、一気に飲み干し無造作にまた給仕の者に突き返した。
とてつもなく不機嫌そうな、いや、不機嫌を見せつけているかのような態度だ。
(この人が私の夫になるの?)
正直なところ全然ピンとこない。
運命の鐘が鳴ることも胸がキュンとする事も想像していた感情の動きは全くなかった。
「王子、ずいぶん物憂げですね」
イングリードが腕を組む。
「ああ。今すぐここから退散したいけど、仕方なくここにいてやるんだバカやろう……とでも言いたそうな顔だな」
アッシュも頷いた
「まあ、億劫になるかもなあ。この人数だもんな」
「確かに……彼はストーリーを知らないんですもんね」
「早く安心させてやらなきゃな。エラ」
「ええ。でも……」
私は金髪の美男美女でごった返しているダンスフロアを見てため息をついた。
「どうやって玉座の間に行けばいいんだろう……不安になってきたわ」
「ああ、それならば私にお任せを」
イングリードが髪の毛をかきあげ、すっ、とフロアへと進み出た。
「ちょっと、見て。綺麗な人」
「わあ、本当ね」
たちまち、ざーっと注目がイングリードに集まる。
なぜか、彼女を中心にフロアのスペースが空いた。
それはまっすぐ、王子のいる場所まで広がっていく。
「海が割れたみたい……モーゼの十戒……」
それはまさしく古い映画のシーンを連想させる動きだった。
何千という男女がひしめく中、ほぼ全員の目がイングリードに向けられている気がした。
「もしかしてイングリードも魔法が使えるの?」
「いや。彼女は魔性の女だからな。そのオーラが人を圧倒するんだろう」
「知らなかったわ。そんな凄い人だったのね!」
「適当に言った。ま、チャンスだ」
アッシュが私に片手を差し出した。
「行こうぜ エラ」
「え? 踊るの?」
「そ」
「えっ、でもでも」
女同士なのに……という言葉は強引に手をとられ、ダンスの輪の中に引き入れられた瞬間にかき消えた。
たくみなリード。周りの人たちが、私たちを見てる。
視線のほとんどが、アッシュに向けられている。
綺麗で優雅でダンスも上手で。そりゃ注目されるよね。
でも一番うっとりしてるのは、きっと私だ。
(だ、だ、だ、だ、ダメだ。心臓がバクバクする!!!)
もともと人との距離感を詰めるのが苦手な私。
たとえ女性とはいえ、こんな至近距離に、こんな美しい顔があるとドキドキする。
「ん? どうした? 顔が赤いけど」
アッシュが私の顔を覗き込む。
「あああ、やめて。これ以上近づかないで。ドキドキしてるのばれちゃう」
「ははっ。変な奴」
アッシュは笑う。
ううん、確かに私はちょっぴり変かもしれないけれど、君とこんなシチュエーションに遭遇したら誰だって、こんな感じになると思うよ。
私はアッシュの視線を避けるため俯きがちに踊った。
ガラスの靴が、とっても綺麗。
なんだか、この先がクライマックスだなんて信じられないくらい、甘い気持ちで満たされる。
怖いくらいに楽しいなあ。こんなに楽しいの……生まれて初めてかも。
そうか。彼女って現世で私が夢ノートに書きつけていた、理想のヒロインそっくりだ。
そりゃ、憧れるに決まってる。強くて優しくて面倒見がいいとなったら余計に、そう。
「もっと胸を張って。君はヒロインなんだから」
囁かれて、ハッとする。
「そうだった。私には使命があったんだ」
私は慌てて顔を上げた。
「ほら、皆が注目してるの、わかるだろ?」
アッシュが再びそう言った。
確かに数人の男性と目が合っているけれど。
「皆アッシュを見てるのよ」
「いいや。君だよ」
「そんなまさか……」
「君はシンデレラなんだから。注目されて当然。だろ?」
「今さらだけどプレッシャーだわ……」
私は頬を赤らめた。
本当にイングリードやアッシュの言う通り、もっと場数を踏むべきだった。
初めての舞踏会が本番だなんて。
あっけないにも程がある。
「何もかもアッシュのおかげよ。あなたがいなかったらどうなっていたことか……」
私は心の底からそう言った。
「もし最初に甘いと叱ってくれなかったら……気楽な感じでここに来ていたと思う。そして後悔したと思うの。どうして万全の準備をしなかったのって。アッシュとイングリードが似合うドレスを選んでくれたおかげで後悔なく本番に挑めたわ」
私はしみじみとこう言った。
「運命って切り開くものなのね……待ってるだけじゃ、幸せは落ちてこない」
そう。
当初の予定通り、地上から這い出たセミのイメージで、ただそのへんにある木につかまって鳴いているだけだったとしたら。
私は森でイングリードともども、ヒグマに食べられていたかもしれなかった。
「結局、二人に助けられてばかりだけどね……もっと早く運命は自分で選べるってわかってたら……私シンデレラを降りてた。そしてあなたと立場を交換したわ」
なぜ思いつかなかったんだろう。それが可能かもしれないってことを。
「私が魔法使い、あなたがシンデレラだったらもっと素敵な物語になったと思わない? もちろん夢物語だけど」
そういうとアッシュはふっ、と笑った。
「分かってねえな。俺やイングリードが何の理由もなく、君に協力すると思う?」
ワルツのテンポが速まった。
「どういうこと?」
「君だから見てた。君だから助けた。イングリードだってそうだろう」
くるりと体が回される。
足に羽が生えたみたい。
「だから、どういう……」
尋ねようとした私の声を遮るように、聞きなれた声がした。
「なんでここにいるの?!」
「まさか、招待状を盗んだの?」
こ、こ、この声は。
(継母姉コンビ!)
もしかして見つかった?!
恐る恐る視線を向けると、案の定二人が立っていた。
そして。
「あーら、サマンサ様にメアリー様。偶然ですこと」
対峙しているのはイングリードだった。
「とうとう来たわ! シンデレラ城!」
私はぎゅっと目を閉じた。
セミの幼虫みたく、土に潜ったような8年間。
全てはこの時のためだった。
「エラ様。頑張ってください」
「大丈夫。今の君は最高に綺麗だ」
セミのイメトレに励んでいた私に、イングリードとアッシュが声をかけてくる。
「うん。頑張る! 二人ともありがとう……! ところで……」
私は傍らにいるイングリードを見た。
「イングリードも舞踏会に参加するのね」
「ええ。エラ様が心配ですし」
「……他にも理由があるわよね」
「ええ。馬だとまだ存在感が薄いでしょう。オリジナルキャラとしてレギュラー化を狙っています」
「凄いわね。その粘り強さ……っていうか、イングリードって超絶美女だったのね」
私はマジマジと彼女を見た。
スレンダーでボーイッシュな魅力のあるアッシュと比べて、イングリードはダークな大人の魅力だ。いつもはきっちりまとめている髪の毛が長く垂らされており、並ぶとイングリードの方が魔女っぽい。
(なんだか気後れ……ずっとオシャレをサボってたからなあ)
ヒロイン補正を当てにして、ビジュアル方面を一切磨いてこなかった。
でも……。
「美しい二人を見ると、もっと頑張っておけば良かったって思うわ……」
しみじみと呟く。
なんていうか、見た目もだけれど、立ち姿が素敵なのだ。
アッシュはうんと背が高く、イングリードもスラリとしている。
かっこいいとはこのことだ。
はあああ。ずっと見ていたい。眼福眼福。
「何を言ってるんだ(んですか)」
2人が同時に叫んだ。
「エラ様には畑を耕して培った強い筋肉があるでしょう。それに、付け焼き刃とはいえ、最高に似合うドレスと装い……きっと誰にも負けませんよ」
「その通り。俺の魔法とセンスを舐めんな。それから、君自身の素材もな」
素材……それを言われると「しょぼい」としか言えなくなるが……。
確かに当初望んでいたように、金髪碧眼で来て居たら、なんだか借り物の自分みたいで絶対に落ち着けなかっただろう。
これできっと良かったのだ。
「どうしてそんなに優しいの? さっきはお説教モードだったのに」
「もう本番だ。今さら四の五の言っても仕方ない」
「その通りです」
イングリードが言った。
「エラ様。あなたにはいい人です。でも、それは初見で伝わりにくいものなのですよ。でも、一度目に留まりさえすればこっちのもんです!」
「そ、そ、そうよね!」
的外れな努力だったかもしれないけれど、自分なりに頑張ってきた。
シンデレラとしての自信は0でも自覚はある。
この物語をハッピーエンドに導きたい。
それが、自分の意志でもあるし、協力してくれた二人に報いることだもの。
「それじゃ行くわね!」
私は一声そう言うと、傍らに美女二人を従えて、ゆっくりとカーペットの上を歩き出した。
◇◇◇◇
会場に入った瞬間、あまりの人の多さに眩暈がしそうになった。
とんでもなく広いフロアに、紳士淑女たちがひしめいている。
「お、王子発見」
双眼鏡を覗いていたアッシュが指さす先を見る。
100メートルほど先の遠い舞台上に玉座が3つあり、その中の1人がそうらしかった。
肉眼では豆粒ほどにしか見えない距離である。
「どうぞ」
アッシュに双眼鏡を渡され覗き込む。
中央にいる青年が、玉座の肘掛けに片肘をつき、つまらなさそうな表情を浮かべている。
王子をはさむように座っているのが王と王妃なのだろう。
「私にも見せてください。まあ、ハンサム」
イングリ―ドが言う。
「そ、そう?」
もう一度双眼鏡を渡される。
ハンサム……なのかな?
多分そうよね。
私は男性のビジュアルの良し悪しが昔から全然ピンとこないのだ。
女子高生時代、100年に1人の美貌とかいうイケメンの同級生が学校にいたが、どんなに目をこらして見ても、他のクラスメイトとの差を感じることができなかった。
男生の顔の差なんて、丸いか四角いか長いか小さいかくらいしかわからない。
(王子は丸ね。覚えておこう)
「とはいえ、アッシュ様には負けますね」
「だろ? 女装してきてよかったわー」
「また除草の話なの? アッシュ、どんなところに住んでるの?」
「……エラ様……」
「何、その憐れむような目は!」
まあいい。
二人には何か一瞬でできた絆があるみたい。
仲間に入れない私は、運命の相手をもっとちゃんと観察しようと目を凝らした。
王子は給仕の者が差し出した、恐らくカクテルの入ったグラスを億劫そうに受け取ると、一気に飲み干し無造作にまた給仕の者に突き返した。
とてつもなく不機嫌そうな、いや、不機嫌を見せつけているかのような態度だ。
(この人が私の夫になるの?)
正直なところ全然ピンとこない。
運命の鐘が鳴ることも胸がキュンとする事も想像していた感情の動きは全くなかった。
「王子、ずいぶん物憂げですね」
イングリードが腕を組む。
「ああ。今すぐここから退散したいけど、仕方なくここにいてやるんだバカやろう……とでも言いたそうな顔だな」
アッシュも頷いた
「まあ、億劫になるかもなあ。この人数だもんな」
「確かに……彼はストーリーを知らないんですもんね」
「早く安心させてやらなきゃな。エラ」
「ええ。でも……」
私は金髪の美男美女でごった返しているダンスフロアを見てため息をついた。
「どうやって玉座の間に行けばいいんだろう……不安になってきたわ」
「ああ、それならば私にお任せを」
イングリードが髪の毛をかきあげ、すっ、とフロアへと進み出た。
「ちょっと、見て。綺麗な人」
「わあ、本当ね」
たちまち、ざーっと注目がイングリードに集まる。
なぜか、彼女を中心にフロアのスペースが空いた。
それはまっすぐ、王子のいる場所まで広がっていく。
「海が割れたみたい……モーゼの十戒……」
それはまさしく古い映画のシーンを連想させる動きだった。
何千という男女がひしめく中、ほぼ全員の目がイングリードに向けられている気がした。
「もしかしてイングリードも魔法が使えるの?」
「いや。彼女は魔性の女だからな。そのオーラが人を圧倒するんだろう」
「知らなかったわ。そんな凄い人だったのね!」
「適当に言った。ま、チャンスだ」
アッシュが私に片手を差し出した。
「行こうぜ エラ」
「え? 踊るの?」
「そ」
「えっ、でもでも」
女同士なのに……という言葉は強引に手をとられ、ダンスの輪の中に引き入れられた瞬間にかき消えた。
たくみなリード。周りの人たちが、私たちを見てる。
視線のほとんどが、アッシュに向けられている。
綺麗で優雅でダンスも上手で。そりゃ注目されるよね。
でも一番うっとりしてるのは、きっと私だ。
(だ、だ、だ、だ、ダメだ。心臓がバクバクする!!!)
もともと人との距離感を詰めるのが苦手な私。
たとえ女性とはいえ、こんな至近距離に、こんな美しい顔があるとドキドキする。
「ん? どうした? 顔が赤いけど」
アッシュが私の顔を覗き込む。
「あああ、やめて。これ以上近づかないで。ドキドキしてるのばれちゃう」
「ははっ。変な奴」
アッシュは笑う。
ううん、確かに私はちょっぴり変かもしれないけれど、君とこんなシチュエーションに遭遇したら誰だって、こんな感じになると思うよ。
私はアッシュの視線を避けるため俯きがちに踊った。
ガラスの靴が、とっても綺麗。
なんだか、この先がクライマックスだなんて信じられないくらい、甘い気持ちで満たされる。
怖いくらいに楽しいなあ。こんなに楽しいの……生まれて初めてかも。
そうか。彼女って現世で私が夢ノートに書きつけていた、理想のヒロインそっくりだ。
そりゃ、憧れるに決まってる。強くて優しくて面倒見がいいとなったら余計に、そう。
「もっと胸を張って。君はヒロインなんだから」
囁かれて、ハッとする。
「そうだった。私には使命があったんだ」
私は慌てて顔を上げた。
「ほら、皆が注目してるの、わかるだろ?」
アッシュが再びそう言った。
確かに数人の男性と目が合っているけれど。
「皆アッシュを見てるのよ」
「いいや。君だよ」
「そんなまさか……」
「君はシンデレラなんだから。注目されて当然。だろ?」
「今さらだけどプレッシャーだわ……」
私は頬を赤らめた。
本当にイングリードやアッシュの言う通り、もっと場数を踏むべきだった。
初めての舞踏会が本番だなんて。
あっけないにも程がある。
「何もかもアッシュのおかげよ。あなたがいなかったらどうなっていたことか……」
私は心の底からそう言った。
「もし最初に甘いと叱ってくれなかったら……気楽な感じでここに来ていたと思う。そして後悔したと思うの。どうして万全の準備をしなかったのって。アッシュとイングリードが似合うドレスを選んでくれたおかげで後悔なく本番に挑めたわ」
私はしみじみとこう言った。
「運命って切り開くものなのね……待ってるだけじゃ、幸せは落ちてこない」
そう。
当初の予定通り、地上から這い出たセミのイメージで、ただそのへんにある木につかまって鳴いているだけだったとしたら。
私は森でイングリードともども、ヒグマに食べられていたかもしれなかった。
「結局、二人に助けられてばかりだけどね……もっと早く運命は自分で選べるってわかってたら……私シンデレラを降りてた。そしてあなたと立場を交換したわ」
なぜ思いつかなかったんだろう。それが可能かもしれないってことを。
「私が魔法使い、あなたがシンデレラだったらもっと素敵な物語になったと思わない? もちろん夢物語だけど」
そういうとアッシュはふっ、と笑った。
「分かってねえな。俺やイングリードが何の理由もなく、君に協力すると思う?」
ワルツのテンポが速まった。
「どういうこと?」
「君だから見てた。君だから助けた。イングリードだってそうだろう」
くるりと体が回される。
足に羽が生えたみたい。
「だから、どういう……」
尋ねようとした私の声を遮るように、聞きなれた声がした。
「なんでここにいるの?!」
「まさか、招待状を盗んだの?」
こ、こ、この声は。
(継母姉コンビ!)
もしかして見つかった?!
恐る恐る視線を向けると、案の定二人が立っていた。
そして。
「あーら、サマンサ様にメアリー様。偶然ですこと」
対峙しているのはイングリードだった。