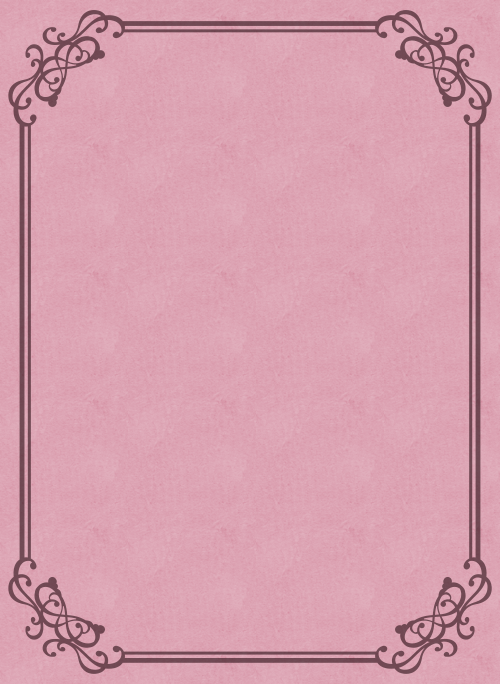シンデレラにおける魔法使いとは王子に次ぐ主要人物だ。
彼女の協力がなければ、私はそもそも舞踏会という舞台にすら立てない。
ずっと彼女を待ち望んでいた。
でも……。
原作では高年齢女性のはずだった。
しかし目の前にいるこの人は。
「こんな綺麗な人だったなんて……」
アッシュはオタク女子高生だった頃、書いたり読んだりしていたファンタジー小説ヒロインのビジュアルイメージそのものだった。
女性なのに「俺」呼びだし、いきなりキスはしてくるし、まごうことなき変人である。
だけどそれを忘れてしまうほど、彼女の美貌に圧倒される。
毎日同じメンツと似たようなルーティンを繰り返していた私は、イレギュラーな出来事にとことん耐性がないらしい。
「あはは。ありがとう。でも、俺は君の目的を叶えるモブキャラだ。君の幸せのために全力を尽くすよ」
私はハッとした。
「ちょっと待って。今、モブキャラ、って言った?」
「ああ。言ったよ」
「えっと、じゃあ、もしかして……」
「ここはシンデレラの世界で、君がヒロインだ。俺たちは物語の世界を生きている。最初からその前提で話してるだろ」
「えええええ! これ、墓場まで持っていくはずの秘密じゃなかったの……!?」
「おいおい、気づくの遅すぎだろ」
アッシュは心底呆れたような顔をした。
「あなたがキスなんかするから……それどころじゃなくて……!」
「人工呼吸だって。まあ、知ってるのは俺だけだよ。つまり君と俺とはこの世界の本質を知っている、運命の双子みたいな関係、ってわけ」
そしてアッシュはクスリと笑った。
「そう言えば君さ、ここ数日、ずっとこの日のシミュレーションしてただろ。あの小芝居、目の前で見れなかったのは残念だな。爆笑できたのに」
「小芝居……?」
「泣き真似の練習だよ。『私も舞踏会に行きたいのにぃぃぃ』ってやつ。しかしなー君、稀に見る大根なんだわ。セリフが全部棒読みだろ。あれじゃあ、俺を騙すのは無理だわ」
「嘘! アカデミー賞ものじゃなかった? 私、眠っていた才能を掘り起こしてしまったかと思ったのに」
「逆にすごいな。その自惚れ」
「って言うか、なんで知ってるの? そんな事!」
「そりゃ、水晶玉で見てたからだよ。暇だったから四六時中」
アッシュは、にやっと笑いながら言った。
「君のことなら何でも知ってるぜ。自作鼻歌が得意だとか。1人になると大抵謎の踊りを踊ってるとか。全部笑えるほど下手だけど」
「もしかしてあなたってストーカー?!?!」
私はざざっと後ずさる。
「バーカ。俺は君の目的を達成させるために存在してるんだぞ。君を知るための情報収集だよ」
「いやいやいやいや、情報収集なんて必要あるの?! 全ては運命で決まってるのに」
「は?」
アッシュの表情が一気に変わった。
「君は運命が決まっていたら本気にならないのか? 流されるままでいいのか? それでも物語のヒロインか?」
どうしよう。
イングリードたちだけじゃなく、お説教好きがまたここにも……。
適切なアドバイスだったら聞く気になるけど、私だって考えてるから、なんだかげっそりしてしまうのよね……。
ここはボソボソと反論しておく。
「本気も本気、めちゃくちゃ本気よ。シンデレラって大人しくて健気で優しい心の美しい女の子が人格をひたすら磨いていたら、ご褒美のように幸せになれる話じゃない。私、家事ならなんでもできるようになったわ。畑仕事だって。家具だって作れるし瞑想もしたしお祈りもしたし羊の世話もしたし牛の世話もしたし、犬猫の世話もしたし筋トレもしたし腹筋は毎日100回したし継母姉たちの意地悪にも耐えてひたすら徳を積んできたの。どう? これ以上ない完璧なヒロインだと思わない?」
えっへん、と胸をはったけど、アッシュはますます難しい顔になってしまった。
「あー、偉い偉い。君の努力は認めるよ。ずっと見てたからな。水晶玉で」
ストーカー魔法使いは開き直ったように言うとこう続けた。
「けどそれってさあ、王子も見てたと思う?」
「え? 何を言ってるの? 見てるわけないでしょ。まだ会ったこともないのに」
そもそもアッシュだって水晶玉がなければ知らないはずの情報だ。
「じゃあ、どうやって君のその善行を知るんだよ」
「えっ。えっ、そんなの自然に伝わるんじゃない? だって私はシンデレラなんだし」
「んなわけねーだろ」
アッシュは少し声を荒らげた※。
「あのな、心の中なんて、一番見えにくいものなんだよ……それにな、善人だから好かれるわけでもない。君さー、初めて会った人に毎日畑を耕してます! とかドヤ顔で言われて好きになる?」
「ええ……最高だと思うんだけど。だって畑よ? 太陽の下、汗をかくのよ? 好感度アップの可能性しかなくない??」
「マジか……」
アッシュは頭を抱えている。どうやら会話が噛みあっていないみたい。
どうしよう。
目の前で魔法使いのモチベーションがぐんぐん下がっていくのがわかる。
「アッシュ、お願い。見捨てないで」
「ああ……そんなつもりはない。俺は君の目的を叶えるためのサポートキャラだから」
アッシュは義務感だけで踏ん張ってくれているようだった。
それでもほっとする。ここで見捨てられたら、そもそも方向音痴の私は王宮にたどり着けない。
「とりあえず君の武器はなんだ? アピールポイントを言って見ろ」
アッシュは即席のコンサルタントになったようだった。
「えっと……その……無害なところ……?」
「論外だ。ったく、こんなノープランで、どうやって王子を惚れさすつもりなんだ」
「それは……目と目があえばビビビッと……」
「甘すぎる。原作のシンデレラは絶世の美女だぞ? 君が同じことをして同じ成果があげられると思う?」
「原作と私のスペック差!」
初めて、アッシュの苦言が脳に突き刺さった。
「確かに……!」
私は己の肩を両手で抱いた。
確かに、シンデレラが黒髪黒目のままだったり、おばあさんのはずの魔法使いが美女だったり、お屋敷にメイドたちがいたり、原本とかなりのズレがある。
つまり、王子が私を好きになるかどうかも、わからないのだ。
なんてことだろう。
当然あると思っていたヒロインへの優遇措置が、もしかしたら、ない可能性があるなんて。
「どうしよう。急に不安になってきたわ!」
そしてアッシュに尋ねる。
「教えて。今まで本当はどうすれば良かったのか。そうしたら出来る範囲で立て直すから」
私のヒロインスイッチがかちりと入った。
なんだかんだ言っても私は前向きな人間だもの。
「メイクやファッションを頑張ること、だな。それからちょっとしたパーティーに参加して男に慣れることだ」
「わああああ、さっきイングリードに同じことを言われたばかりじゃない!」
あの時は、またまた、事情を知らないイングリードは、悲観的になるのも仕方ないわねえ、なんて、余裕綽々に流してしまったが、結局彼女の言うことが正しかった。
何故なら、アッシュは私と同じでここが物語の世界だと知っている。
その上で、イングリードと同じことを言うのだから、多数決で、私の負け。
「例えばな、俺のこのドレスを見てみろ。一年かけてデザインした」
「ええっ」
「俺にとっては、この日がそれほど大切だったからだ。君に好かれたかったからな」
「私に好かれたかった……?」
「そう。ファッションとは、相手への思いやりだ。そして相手を動かすものでもある」
「なるほど! 新しい視点だわ!」
暑ければ脱ぎ、寒ければ重ね着する。
体を締め付けられるのは大嫌い。動きやすいのがベスト。
そんな私の認識は大間違いだったというわけだ。
後悔。
私の一番嫌いな言葉だ。
なのにその言葉が私の頭を満たしかけていた。
しかし。
「ん? でもちょっと待って」
ざわついていた心が落ち着いてきた。
「アッシュ。あなた魔法使いよね?」
「そうだ」
「私をプリンセスに変身させてくれるのよね」
「その通り」
「なーんだ。じゃあ、簡単じゃない。私を魔法でちゃっちゃと金髪ロングの美人シンデレラにしてくれたらいいのよ……って、アッシュ、どうしたの?」
眉根を寄せ、いかにも怒った表情へと変わっていく彼を見て、私はうろたえる。
「君は魔法は何だと思ってる!」
「え? できないの? ごめん。デリカシーがなかったわね……」
「変身魔法なんて簡単だよ! 特にテンプレな美女なんてお手の物さ」
「だったら、何を怒ってるの?」
「自分の素材を生かさず勝負してたとえ勝っても、それが嬉しいか? 嫌だろう? そんなハッピーエンド!」
「え、いや、私は別にそれでも全然問題ないんだけど」
「だめだめ! 君は黒髪黒目、寸胴体型のそのまんまで舞踏会へ行く。それは俺のこだわりだ!」
「やめてよう。無駄な職人気質……」
と、そこに
「エラ様! アッシュ様の言う通りです!」
ばん、と大きな音と共にドアがあき、入ってきたのはイングリードだった。
「わあああああっ! 部屋に来ちゃダメって言ってたのに!」
「話は全部聞きました。ここは物語の世界でエラ様はヒロインのシンデレラ。魔法の力でハッピーエンドを迎えること」
ちょっと待って。
ひた隠していた真実まで知られてしまったじゃないの。
最悪すぎる。
「だから三日月コンビに何を言われても平気だったんですね。納得です。いいじゃないですか。素材勝負。エラ様は素のままで魅力があります。私もお手伝いさせていただきます!」
ぱちぱちと私は両目を瞬かせた。
「協力……してくれるの?」
「当然です」
「ずっと、秘密を黙っていたのに?」
「ええ」
「それに私、あなたの言うことを無視してメイクもオシャレもサボってたのよ……」
「大切なのは過去じゃなくて今です。その気になった時から頑張ればいいのですよ」
イングリードの言葉は胸にしみた。
「そうよね。大切なのは過去じゃなくて今よ」
愚かな私は、善行をつみ大人しくさえしていれば、順当にハッピーエンドを迎えられると信じていた。
でも、本番前に、それが甘いと知れたのはいいことだ。
「運命は待つものじゃなく、自ら掴むもの……今こそ私は地中から這い出すわ。大切なのはこれから。思い立ったが吉日。軌道修正よ!」
私はアッシュをしっかりと見つめた。
「というわけで、私を金髪碧眼の美少女に……!」
「だからそれはないって言ってるだろ」
あえなく却下されてしまった。
彼女の協力がなければ、私はそもそも舞踏会という舞台にすら立てない。
ずっと彼女を待ち望んでいた。
でも……。
原作では高年齢女性のはずだった。
しかし目の前にいるこの人は。
「こんな綺麗な人だったなんて……」
アッシュはオタク女子高生だった頃、書いたり読んだりしていたファンタジー小説ヒロインのビジュアルイメージそのものだった。
女性なのに「俺」呼びだし、いきなりキスはしてくるし、まごうことなき変人である。
だけどそれを忘れてしまうほど、彼女の美貌に圧倒される。
毎日同じメンツと似たようなルーティンを繰り返していた私は、イレギュラーな出来事にとことん耐性がないらしい。
「あはは。ありがとう。でも、俺は君の目的を叶えるモブキャラだ。君の幸せのために全力を尽くすよ」
私はハッとした。
「ちょっと待って。今、モブキャラ、って言った?」
「ああ。言ったよ」
「えっと、じゃあ、もしかして……」
「ここはシンデレラの世界で、君がヒロインだ。俺たちは物語の世界を生きている。最初からその前提で話してるだろ」
「えええええ! これ、墓場まで持っていくはずの秘密じゃなかったの……!?」
「おいおい、気づくの遅すぎだろ」
アッシュは心底呆れたような顔をした。
「あなたがキスなんかするから……それどころじゃなくて……!」
「人工呼吸だって。まあ、知ってるのは俺だけだよ。つまり君と俺とはこの世界の本質を知っている、運命の双子みたいな関係、ってわけ」
そしてアッシュはクスリと笑った。
「そう言えば君さ、ここ数日、ずっとこの日のシミュレーションしてただろ。あの小芝居、目の前で見れなかったのは残念だな。爆笑できたのに」
「小芝居……?」
「泣き真似の練習だよ。『私も舞踏会に行きたいのにぃぃぃ』ってやつ。しかしなー君、稀に見る大根なんだわ。セリフが全部棒読みだろ。あれじゃあ、俺を騙すのは無理だわ」
「嘘! アカデミー賞ものじゃなかった? 私、眠っていた才能を掘り起こしてしまったかと思ったのに」
「逆にすごいな。その自惚れ」
「って言うか、なんで知ってるの? そんな事!」
「そりゃ、水晶玉で見てたからだよ。暇だったから四六時中」
アッシュは、にやっと笑いながら言った。
「君のことなら何でも知ってるぜ。自作鼻歌が得意だとか。1人になると大抵謎の踊りを踊ってるとか。全部笑えるほど下手だけど」
「もしかしてあなたってストーカー?!?!」
私はざざっと後ずさる。
「バーカ。俺は君の目的を達成させるために存在してるんだぞ。君を知るための情報収集だよ」
「いやいやいやいや、情報収集なんて必要あるの?! 全ては運命で決まってるのに」
「は?」
アッシュの表情が一気に変わった。
「君は運命が決まっていたら本気にならないのか? 流されるままでいいのか? それでも物語のヒロインか?」
どうしよう。
イングリードたちだけじゃなく、お説教好きがまたここにも……。
適切なアドバイスだったら聞く気になるけど、私だって考えてるから、なんだかげっそりしてしまうのよね……。
ここはボソボソと反論しておく。
「本気も本気、めちゃくちゃ本気よ。シンデレラって大人しくて健気で優しい心の美しい女の子が人格をひたすら磨いていたら、ご褒美のように幸せになれる話じゃない。私、家事ならなんでもできるようになったわ。畑仕事だって。家具だって作れるし瞑想もしたしお祈りもしたし羊の世話もしたし牛の世話もしたし、犬猫の世話もしたし筋トレもしたし腹筋は毎日100回したし継母姉たちの意地悪にも耐えてひたすら徳を積んできたの。どう? これ以上ない完璧なヒロインだと思わない?」
えっへん、と胸をはったけど、アッシュはますます難しい顔になってしまった。
「あー、偉い偉い。君の努力は認めるよ。ずっと見てたからな。水晶玉で」
ストーカー魔法使いは開き直ったように言うとこう続けた。
「けどそれってさあ、王子も見てたと思う?」
「え? 何を言ってるの? 見てるわけないでしょ。まだ会ったこともないのに」
そもそもアッシュだって水晶玉がなければ知らないはずの情報だ。
「じゃあ、どうやって君のその善行を知るんだよ」
「えっ。えっ、そんなの自然に伝わるんじゃない? だって私はシンデレラなんだし」
「んなわけねーだろ」
アッシュは少し声を荒らげた※。
「あのな、心の中なんて、一番見えにくいものなんだよ……それにな、善人だから好かれるわけでもない。君さー、初めて会った人に毎日畑を耕してます! とかドヤ顔で言われて好きになる?」
「ええ……最高だと思うんだけど。だって畑よ? 太陽の下、汗をかくのよ? 好感度アップの可能性しかなくない??」
「マジか……」
アッシュは頭を抱えている。どうやら会話が噛みあっていないみたい。
どうしよう。
目の前で魔法使いのモチベーションがぐんぐん下がっていくのがわかる。
「アッシュ、お願い。見捨てないで」
「ああ……そんなつもりはない。俺は君の目的を叶えるためのサポートキャラだから」
アッシュは義務感だけで踏ん張ってくれているようだった。
それでもほっとする。ここで見捨てられたら、そもそも方向音痴の私は王宮にたどり着けない。
「とりあえず君の武器はなんだ? アピールポイントを言って見ろ」
アッシュは即席のコンサルタントになったようだった。
「えっと……その……無害なところ……?」
「論外だ。ったく、こんなノープランで、どうやって王子を惚れさすつもりなんだ」
「それは……目と目があえばビビビッと……」
「甘すぎる。原作のシンデレラは絶世の美女だぞ? 君が同じことをして同じ成果があげられると思う?」
「原作と私のスペック差!」
初めて、アッシュの苦言が脳に突き刺さった。
「確かに……!」
私は己の肩を両手で抱いた。
確かに、シンデレラが黒髪黒目のままだったり、おばあさんのはずの魔法使いが美女だったり、お屋敷にメイドたちがいたり、原本とかなりのズレがある。
つまり、王子が私を好きになるかどうかも、わからないのだ。
なんてことだろう。
当然あると思っていたヒロインへの優遇措置が、もしかしたら、ない可能性があるなんて。
「どうしよう。急に不安になってきたわ!」
そしてアッシュに尋ねる。
「教えて。今まで本当はどうすれば良かったのか。そうしたら出来る範囲で立て直すから」
私のヒロインスイッチがかちりと入った。
なんだかんだ言っても私は前向きな人間だもの。
「メイクやファッションを頑張ること、だな。それからちょっとしたパーティーに参加して男に慣れることだ」
「わああああ、さっきイングリードに同じことを言われたばかりじゃない!」
あの時は、またまた、事情を知らないイングリードは、悲観的になるのも仕方ないわねえ、なんて、余裕綽々に流してしまったが、結局彼女の言うことが正しかった。
何故なら、アッシュは私と同じでここが物語の世界だと知っている。
その上で、イングリードと同じことを言うのだから、多数決で、私の負け。
「例えばな、俺のこのドレスを見てみろ。一年かけてデザインした」
「ええっ」
「俺にとっては、この日がそれほど大切だったからだ。君に好かれたかったからな」
「私に好かれたかった……?」
「そう。ファッションとは、相手への思いやりだ。そして相手を動かすものでもある」
「なるほど! 新しい視点だわ!」
暑ければ脱ぎ、寒ければ重ね着する。
体を締め付けられるのは大嫌い。動きやすいのがベスト。
そんな私の認識は大間違いだったというわけだ。
後悔。
私の一番嫌いな言葉だ。
なのにその言葉が私の頭を満たしかけていた。
しかし。
「ん? でもちょっと待って」
ざわついていた心が落ち着いてきた。
「アッシュ。あなた魔法使いよね?」
「そうだ」
「私をプリンセスに変身させてくれるのよね」
「その通り」
「なーんだ。じゃあ、簡単じゃない。私を魔法でちゃっちゃと金髪ロングの美人シンデレラにしてくれたらいいのよ……って、アッシュ、どうしたの?」
眉根を寄せ、いかにも怒った表情へと変わっていく彼を見て、私はうろたえる。
「君は魔法は何だと思ってる!」
「え? できないの? ごめん。デリカシーがなかったわね……」
「変身魔法なんて簡単だよ! 特にテンプレな美女なんてお手の物さ」
「だったら、何を怒ってるの?」
「自分の素材を生かさず勝負してたとえ勝っても、それが嬉しいか? 嫌だろう? そんなハッピーエンド!」
「え、いや、私は別にそれでも全然問題ないんだけど」
「だめだめ! 君は黒髪黒目、寸胴体型のそのまんまで舞踏会へ行く。それは俺のこだわりだ!」
「やめてよう。無駄な職人気質……」
と、そこに
「エラ様! アッシュ様の言う通りです!」
ばん、と大きな音と共にドアがあき、入ってきたのはイングリードだった。
「わあああああっ! 部屋に来ちゃダメって言ってたのに!」
「話は全部聞きました。ここは物語の世界でエラ様はヒロインのシンデレラ。魔法の力でハッピーエンドを迎えること」
ちょっと待って。
ひた隠していた真実まで知られてしまったじゃないの。
最悪すぎる。
「だから三日月コンビに何を言われても平気だったんですね。納得です。いいじゃないですか。素材勝負。エラ様は素のままで魅力があります。私もお手伝いさせていただきます!」
ぱちぱちと私は両目を瞬かせた。
「協力……してくれるの?」
「当然です」
「ずっと、秘密を黙っていたのに?」
「ええ」
「それに私、あなたの言うことを無視してメイクもオシャレもサボってたのよ……」
「大切なのは過去じゃなくて今です。その気になった時から頑張ればいいのですよ」
イングリードの言葉は胸にしみた。
「そうよね。大切なのは過去じゃなくて今よ」
愚かな私は、善行をつみ大人しくさえしていれば、順当にハッピーエンドを迎えられると信じていた。
でも、本番前に、それが甘いと知れたのはいいことだ。
「運命は待つものじゃなく、自ら掴むもの……今こそ私は地中から這い出すわ。大切なのはこれから。思い立ったが吉日。軌道修正よ!」
私はアッシュをしっかりと見つめた。
「というわけで、私を金髪碧眼の美少女に……!」
「だからそれはないって言ってるだろ」
あえなく却下されてしまった。