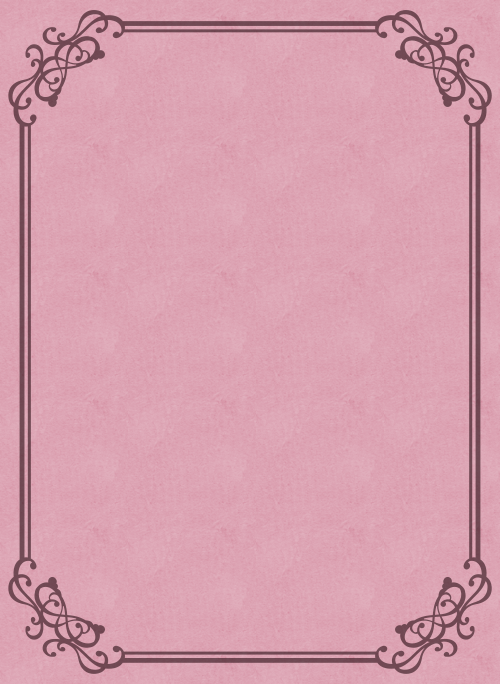着飾った母娘を見送った後、台所で夕ごはんの下ごしらえをしていたら、メイドのイングリードがだん、と両拳で作業台を叩いた。
私はびくっと肩をすくめる。
「どうしてあのバカ母娘が舞踏会に行き、エラ様がここで私たちと豆の皮を剥いているのですか。私は不思議でなりません」
メイドのバーサも同意する。
「馬車に雷でも落ちてくれればねえ」
「無理でしょう。憎まれっ子世に憚るとはよく言ったものですよ」
二人は物心ついた頃から私の味方だ。
気分の浮き沈みが激しい義母たちから理不尽な仕打ちを受けても受け流せていたのは、苦境は期間限定だという救いがあったのと、彼女たちの存在が大きい。
しかしそんな二人にさえ、この先の展開を言えない罪悪感で私の胸はちくりと痛む。
「まあまあ、仕方ないのよ。招待状が来なかったんだから」
「これの事ですか?」
イングリードがくしゃくしゃに丸められた紙を台の上に置いた。
「えっ? 来てたの?」
「ゴミ箱から回収しました。サマンサ様が捨てたのです。まさか気が付いてなかったんですか? お茶会に貴族が開く小さな舞踏会など、殿方との出会いが望めるイベントはことごとく握りつぶされてきたことを」
「そうだったのね……」
私は両目を丸くした。
鈍感にもほどがある。
理不尽に耐えることと、舞踏会を無事迎えること、その二つに全振りしていたから、それ以外の社交イベントに全然目が向かなかった。
「まあ、別にいいわ。過ぎたことだし」
私の発言に、二人はますます渋い表情になった。
「随分余裕があるんですね。エラ様。もっと真剣にご自分の人生を考えてみてはどうですか?」
「え? 考えてるわよ?」
「そうは見えません」
イングリードは怖い目になった。
「この年になるまで、ろくに男性と話したこともないでしょう? お化粧もおしゃれにも興味なし。サマンサ様たちの理不尽にも受け流すまま。一体エラ様は何を楽しみに生きてるんですか?」
うううう。イングリードはお説教モードだ。
面倒くさいことになってしまった。
「楽しいことなんていっぱいあるわよ」
「何がです?」
「そんな、気の毒な人を見るような目で見ないで!」
私は言った。
「例えば、今、みんなとこうやって夕食の支度をしてるだけでも、私結構楽しいんだけど」
ぽっと頬が赤らむのが自分でもわかる。
現世の私はオタクが行き過ぎていて、他人とのコミュニケーションを怠っていた。
だから、イングリードたちとの会話は新鮮で楽しかった。
(でも、直接本人たちに伝えるのって照れくさいのよね……)
そう言いながらも少しは喜んでくれるかと思いきや、
「はああああああ」
イングリードは喜ぶどころか呆れ顔になった。
バーサもやれやれ、と言いたげに肩をすくめている。
「私たちと豆剥いて何が楽しいんですか。エラ様の気が知れません」
「えっ? イングリードは楽しくないの?」
「全然」
きっぱりと言われて私はそこそこのショックを受けていた。
「私が働くのはお金の為です。でないといきていけませんのでね」
「お願い……少しはオブラートに包んでよ!」
「それに、そのうち私は嫁にいきますよ。そうしたらここにはいられません」
イングリードの指先が、ピシリと私に向けられる。
「私はもっとエラ様に運命に抗ってほしいのです。このままでは奴隷として孤独死する未来が待っていますよ!」
孤独死……。
それは嫌だ……。
でも……。
「大げさねえ。イングリードったら」
私は余裕たっぷりにその予言を退けた。
未来を知る私には、それに怯える必要は一切なかった。
「これでも控え目な未来予想図ですよ。もっともっと悲惨かも」
あまりにもしつこいイングリードに、私は口を尖らせる。
「運命にに抗えば物語が破綻するじゃない……」
「ん? どういうことです?」
「いや、なんでもない。あのね、イングリード」
予言者イングリードに私は言った。
「大丈夫。私はきっと幸せになるから。今は言えないけれどそういう運命なのよ。それはそれは腰が抜けるほどのハッピーよ。きっとあと数日したら私の言ってることがわかるわ。だから今は黙って見守って」
本当は、私の味方たちに真実を告げたい。
私の本番はすぐそこに来ているのだという真実を。確かに受け身に見えていたかもしれないけれどそれは本番に合わせてスタンバイしていただけの話。
心配しなくても私は王子の妃になる。魔法使いの手によって、プリンセスにしてもらえるのだ。
私はぐっと唇を噛みしめる。
「いっけない。部屋に戻ってなくちゃ」
私は立ち上がると、イングリードたちにこう言い含めた。
「朝が来るまで部屋に来ちゃだめよ」
◇
「ううううう、しくしく。私だけ舞踏会に行けないなんて……」
私はベッドに突っ伏して泣きまねをしていた。
物語の展開的に必要なムーブである。
(置き去りにされて泣いていなきゃ、魔法使いのおばあさんが、助けてくれないからね)
私は頑張った。
熱演だった。
アカデミー賞を受賞しそうなほどの勢いだった。
とはいえ、いつまでやってても、誰も来ない。
「疲れちゃったな」
そう独りごちて目を閉じる。
もうすぐこの世界での本番が幕をあける。
最高のハッピーエンドを迎えたら、その先はどうなるのだろう。
物語は終わって、私は元の世界に戻れる?
それとも……。
ううん。
それは考えても仕方がない。
とにかく大舞台を成功させなきゃ。
私はそう心に誓った。
◇
薄暗い部屋の中、ゆるゆると眠りからさめていく。そして感じた、唇に触れる温かい感触。
頬に当てられた掌が、優しくて……気持ちがいい。
「んんん」
声が甘くなっていく。なんだ、まだ夢なの?
私は思わず両手を突き出し、そこにあるものへと絡ませた。
と、唐突にぬくもりが離れていき
「あ、生きてた」
澄んだ声が鼓膜に響く。
一気に意識が覚醒した。こんな声、知らない。
ここは物語の世界。予定調和な人物以外、登場してくるわけがないんですけど!?
「うわわああああああ」
私は転がるようにベッドから降りた。
部屋の隅っこにたち、ベッドの上の不審者を睨む。女性だった。長い金髪で黒いドレスを着ている。
「あなた、今、私に、き、き、き……」
唇に触れる。濡れた感触が指先に伝わってきた。絶対私、キスされたよね? だとしたらファーストキスを見ず知らずの女性に奪われた、ってことなんですけど!
「人工呼吸だ。死んでるのかと思ったから」
女性は信じがたい言い訳をしながら素早くベッドから降りてきた。ハイヒールをはいたままらしく2メートルはあろうかと思える長身。高い位置にある小さな顔は例えようもないほど美しい。私を見下ろしてにっこりと笑う。バラの花が一斉に開いたような華やかな笑顔。不審者なのに、ダメだ。つい見とれてしまう。それくらい彼女の美貌は際立っていた。
「誰……?」
震える声で私は尋ねる。
美女はすくっと背中を伸ばし、挨拶をした。
「俺の名前はアッシュ」
「アッシュ……?」
「お、呼び捨ていいね!」
アッシュと名乗った美女は嬉しそうに言った。
「別に……っこれは……ただオウム返ししただけで……っていうか何者?」
私の警戒心はマックスになる。
今夜はとても大切な日だ。
なのになぜこう、予定外なことが起きるかな。
「俺? ああ、魔法使いだ」
アッシュは凛とした声でそう言った。
「……魔法使い? 誰が?」
「俺が」
彼女が微笑むたびに白い歯がきらりと光る。
え?
「えええええっ!」
私は驚きの声をあげた。
私はびくっと肩をすくめる。
「どうしてあのバカ母娘が舞踏会に行き、エラ様がここで私たちと豆の皮を剥いているのですか。私は不思議でなりません」
メイドのバーサも同意する。
「馬車に雷でも落ちてくれればねえ」
「無理でしょう。憎まれっ子世に憚るとはよく言ったものですよ」
二人は物心ついた頃から私の味方だ。
気分の浮き沈みが激しい義母たちから理不尽な仕打ちを受けても受け流せていたのは、苦境は期間限定だという救いがあったのと、彼女たちの存在が大きい。
しかしそんな二人にさえ、この先の展開を言えない罪悪感で私の胸はちくりと痛む。
「まあまあ、仕方ないのよ。招待状が来なかったんだから」
「これの事ですか?」
イングリードがくしゃくしゃに丸められた紙を台の上に置いた。
「えっ? 来てたの?」
「ゴミ箱から回収しました。サマンサ様が捨てたのです。まさか気が付いてなかったんですか? お茶会に貴族が開く小さな舞踏会など、殿方との出会いが望めるイベントはことごとく握りつぶされてきたことを」
「そうだったのね……」
私は両目を丸くした。
鈍感にもほどがある。
理不尽に耐えることと、舞踏会を無事迎えること、その二つに全振りしていたから、それ以外の社交イベントに全然目が向かなかった。
「まあ、別にいいわ。過ぎたことだし」
私の発言に、二人はますます渋い表情になった。
「随分余裕があるんですね。エラ様。もっと真剣にご自分の人生を考えてみてはどうですか?」
「え? 考えてるわよ?」
「そうは見えません」
イングリードは怖い目になった。
「この年になるまで、ろくに男性と話したこともないでしょう? お化粧もおしゃれにも興味なし。サマンサ様たちの理不尽にも受け流すまま。一体エラ様は何を楽しみに生きてるんですか?」
うううう。イングリードはお説教モードだ。
面倒くさいことになってしまった。
「楽しいことなんていっぱいあるわよ」
「何がです?」
「そんな、気の毒な人を見るような目で見ないで!」
私は言った。
「例えば、今、みんなとこうやって夕食の支度をしてるだけでも、私結構楽しいんだけど」
ぽっと頬が赤らむのが自分でもわかる。
現世の私はオタクが行き過ぎていて、他人とのコミュニケーションを怠っていた。
だから、イングリードたちとの会話は新鮮で楽しかった。
(でも、直接本人たちに伝えるのって照れくさいのよね……)
そう言いながらも少しは喜んでくれるかと思いきや、
「はああああああ」
イングリードは喜ぶどころか呆れ顔になった。
バーサもやれやれ、と言いたげに肩をすくめている。
「私たちと豆剥いて何が楽しいんですか。エラ様の気が知れません」
「えっ? イングリードは楽しくないの?」
「全然」
きっぱりと言われて私はそこそこのショックを受けていた。
「私が働くのはお金の為です。でないといきていけませんのでね」
「お願い……少しはオブラートに包んでよ!」
「それに、そのうち私は嫁にいきますよ。そうしたらここにはいられません」
イングリードの指先が、ピシリと私に向けられる。
「私はもっとエラ様に運命に抗ってほしいのです。このままでは奴隷として孤独死する未来が待っていますよ!」
孤独死……。
それは嫌だ……。
でも……。
「大げさねえ。イングリードったら」
私は余裕たっぷりにその予言を退けた。
未来を知る私には、それに怯える必要は一切なかった。
「これでも控え目な未来予想図ですよ。もっともっと悲惨かも」
あまりにもしつこいイングリードに、私は口を尖らせる。
「運命にに抗えば物語が破綻するじゃない……」
「ん? どういうことです?」
「いや、なんでもない。あのね、イングリード」
予言者イングリードに私は言った。
「大丈夫。私はきっと幸せになるから。今は言えないけれどそういう運命なのよ。それはそれは腰が抜けるほどのハッピーよ。きっとあと数日したら私の言ってることがわかるわ。だから今は黙って見守って」
本当は、私の味方たちに真実を告げたい。
私の本番はすぐそこに来ているのだという真実を。確かに受け身に見えていたかもしれないけれどそれは本番に合わせてスタンバイしていただけの話。
心配しなくても私は王子の妃になる。魔法使いの手によって、プリンセスにしてもらえるのだ。
私はぐっと唇を噛みしめる。
「いっけない。部屋に戻ってなくちゃ」
私は立ち上がると、イングリードたちにこう言い含めた。
「朝が来るまで部屋に来ちゃだめよ」
◇
「ううううう、しくしく。私だけ舞踏会に行けないなんて……」
私はベッドに突っ伏して泣きまねをしていた。
物語の展開的に必要なムーブである。
(置き去りにされて泣いていなきゃ、魔法使いのおばあさんが、助けてくれないからね)
私は頑張った。
熱演だった。
アカデミー賞を受賞しそうなほどの勢いだった。
とはいえ、いつまでやってても、誰も来ない。
「疲れちゃったな」
そう独りごちて目を閉じる。
もうすぐこの世界での本番が幕をあける。
最高のハッピーエンドを迎えたら、その先はどうなるのだろう。
物語は終わって、私は元の世界に戻れる?
それとも……。
ううん。
それは考えても仕方がない。
とにかく大舞台を成功させなきゃ。
私はそう心に誓った。
◇
薄暗い部屋の中、ゆるゆると眠りからさめていく。そして感じた、唇に触れる温かい感触。
頬に当てられた掌が、優しくて……気持ちがいい。
「んんん」
声が甘くなっていく。なんだ、まだ夢なの?
私は思わず両手を突き出し、そこにあるものへと絡ませた。
と、唐突にぬくもりが離れていき
「あ、生きてた」
澄んだ声が鼓膜に響く。
一気に意識が覚醒した。こんな声、知らない。
ここは物語の世界。予定調和な人物以外、登場してくるわけがないんですけど!?
「うわわああああああ」
私は転がるようにベッドから降りた。
部屋の隅っこにたち、ベッドの上の不審者を睨む。女性だった。長い金髪で黒いドレスを着ている。
「あなた、今、私に、き、き、き……」
唇に触れる。濡れた感触が指先に伝わってきた。絶対私、キスされたよね? だとしたらファーストキスを見ず知らずの女性に奪われた、ってことなんですけど!
「人工呼吸だ。死んでるのかと思ったから」
女性は信じがたい言い訳をしながら素早くベッドから降りてきた。ハイヒールをはいたままらしく2メートルはあろうかと思える長身。高い位置にある小さな顔は例えようもないほど美しい。私を見下ろしてにっこりと笑う。バラの花が一斉に開いたような華やかな笑顔。不審者なのに、ダメだ。つい見とれてしまう。それくらい彼女の美貌は際立っていた。
「誰……?」
震える声で私は尋ねる。
美女はすくっと背中を伸ばし、挨拶をした。
「俺の名前はアッシュ」
「アッシュ……?」
「お、呼び捨ていいね!」
アッシュと名乗った美女は嬉しそうに言った。
「別に……っこれは……ただオウム返ししただけで……っていうか何者?」
私の警戒心はマックスになる。
今夜はとても大切な日だ。
なのになぜこう、予定外なことが起きるかな。
「俺? ああ、魔法使いだ」
アッシュは凛とした声でそう言った。
「……魔法使い? 誰が?」
「俺が」
彼女が微笑むたびに白い歯がきらりと光る。
え?
「えええええっ!」
私は驚きの声をあげた。